小泉信三「わが文芸談」読了。
本書は、1965年(昭和40年)10月から1966年(翌41年)にかけて行われた小泉信三による講義録である。
慶応義塾大学では、久保田万太郎の著作権寄付による資金で、昭和39年から「詩学」に関する連続講義を行っており、その四人目の講師として壇上に上がったのが、かつて慶應義塾で学長を務めた小泉信三だった。
最初に小泉信三は「三田文学」創設の経緯に触れて、明治43年、永井荷風が慶應義塾の教授に着任したときの様子を紹介している。
永井荷風が創設した「三田文学」は、やがて、水上滝太郎や久保田万太郎、佐藤春夫、西脇順三郎、小島政次郎、石坂洋二郎などの文学者を輩出することになる。
小泉信三が、日本の近代文学史上の巨人として挙げているのは、森鴎外、夏目漱石、幸田露伴の三人で、このうち、最もポピュラルティを擁するのが漱石であり、次に鷗外、幸田露伴はいずれ消えてしまう作家になってしまうだろうと、小泉は指摘している。
森鷗外で読んでおくべきものは「即興詩人」「舞姫」などの初期の作品で、鷗外独特の文章は最初は読みにくいが、すぐに慣れて、美しい文章だということが理解できるようになる。
そもそも読みにくいものを敬遠していては、いつまでも自分の国に伝えられているトレジュア知らずに終わることになってしまうだろう。
次に、夏目漱石で読んでおくべきものは、やはり「吾輩は猫である」と「坊つちゃん」であって、「道草」は哲学がうるさすぎるし、「虞美人草」はわざとらしくて嫌味、凝りに凝っていて筋も低俗。
「行人」は良い作品で、この中で、小泉信三は、漱石は兄嫁に恋心を抱いていたのではないかという持論を紹介している。
我が国で漱石に異常の人気があるのは、彼のモラル・バックボーンに依るところがあるのではないかと、小泉は語る。
漱石は、とにかく道義的に行動する人で、文部大臣から文学博士の学位を贈られるという話があったときには、断固として、これを辞退しているし、総理大臣の西園寺公望の食事会に招待されたときも「ほととぎず厠半ばに出かねたり」と返事をしてこれを断った。
あなた方が世の中に出られて、いろんな境遇に出会われるでしょうが、やはり、諸君の生活というものは大事ですから、生活のためということになると、なかなか進退に窮する事態が起こり得る。金はきらいだという顔はしなくてもいいけれども、道理のない、筋の通らないものをとらないということは、是非心がけておいてもらいたい。(小泉信三「わが文芸談」)
幸田露伴に人気がないのは、我々が無識・無学になっているためで、露伴の文学はあまりに偉すぎるので読まれなくなってしまった。
今の国語教育は、無学を奨励するようなやり方をしていて、人が間違えるから正しく教えるというのではなく、間違った方を正しいとしてしまう。
泉鏡花の作品も、そんな理由でだんだんと読みづらくなっていく。
昭和40年当時、慶応大学の学生は、幸田露伴も泉鏡花も読んでいないということが印象的である(文学に関心のある学生たちが集まっているはずなのに)。
生き方に問題のあった人が久保田万太郎である
水上滝太郎は、小泉信三の子どものときからの友人で、小泉は滝太郎の妹を嫁にしているから、滝太郎は義理の兄ということにもなる。
滝太郎の作品としては、小説では「大阪の宿」と「果樹」、評論では「貝殻追放」がいい。
滝太郎は正義感の強い人間だったから、少数派であっても、自分が正しいと思う方の味方をした。
水上が死んだとき、「三田文学」は水上滝太郎先生記念号を出して、慶應義塾内外の多数の人の追憶談を掲載したが、水上の作品で何が傑作かと言えば、この記念号が傑作なのではないか。
水上という人間が多くの人間に尊敬されていたという、その生涯を伝える記念号こそが、良い作品なのではないかと、小泉は語っている。
対して、生き方に問題のあった人が久保田万太郎である。
万太郎の作品には、古い人情とか義理堅い人間とかが登場するが、作者本人はその点非常にルーズで、会合には必ず遅刻する、酒のための借金も返さない、嫁の他に女を作って子どもまで生ませ、嫁は睡眠薬を飲んで自殺してしまう。
万太郎の最大の理解者で、私生活の上でも援助をしていた水上滝太郎は激怒して、酒を断つよう激しくせまり、万太郎も約束をするが、すぐに約束を破って酒を出してしまった。
滝太郎が万太郎を見放して、絶交という状態になったのは、この時からである。
万太郎が死んだとき、後輩の小島政次郎は「小説新潮」に「久保田万太郎」という小説を書いて、腹の中に溜まっていたものを一気に吐き出しているが、政次郎にしてみると、万太郎にはかなり辛い思いをさせられたものらしい。
万太郎は肩書に弱い人間で、自身も「芸術院会員 久保田万太郎」という名刺を持って歩いていたが、当時、このような文学者は少なかったのではないか。
もっとも、文学作品ということで比較をすると、滝太郎よりも万太郎の方が、やはり優れた作品を残したことには間違いがない。
万太郎の作品は、どこまでもリアリスティックでありながら、そこにいつでも漂うさびしさとか、侘びしさとか、残り惜しさとかいう気持が現れている。
四年間、そのグループにいたってことが一生財産になる
本書は、大学での講義を記録したものなので、全編が話し言葉であり、一部には学生との会話の形も収録されているが、昭和40年当時、慶応の学生にとって、鷗外も露伴も鏡花も滝太郎も、既に遠い時代の文人になっていることが分かる。
かろうじて漱石だけが読まれているところは、令和の現代と大きく違っていないのではないか。
そういう意味で、小泉信三の予測は外れていない。
この日、小泉は、学校の持つ意義について、文学体験を通してこんなことを言っている。
わたしは通信教育の必要を認めていますけど、(大学では)通信教育だけでは得られないものを得ると思います。学校でろくに講義を覚えなくとも、四年間、そのグループにいたってことが一生財産になると思いますね。(小泉信三「わが文芸談」)
大学生にとって、心に残る講義だったのではないか。
自分も学生として、こんな講義を聴いてみたかった。
書名:わが文芸談
著者:小泉信三
発行:1994/5/10
出版社:講談社文芸文庫



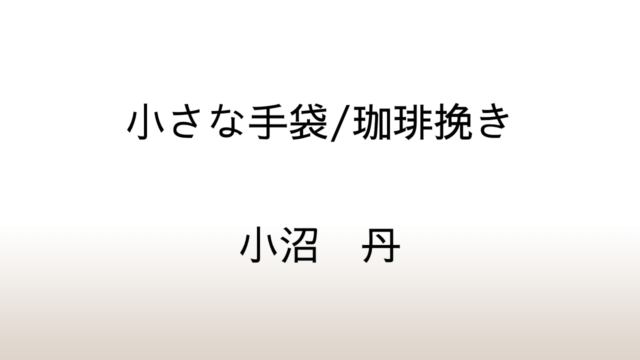


-150x150.jpg)









