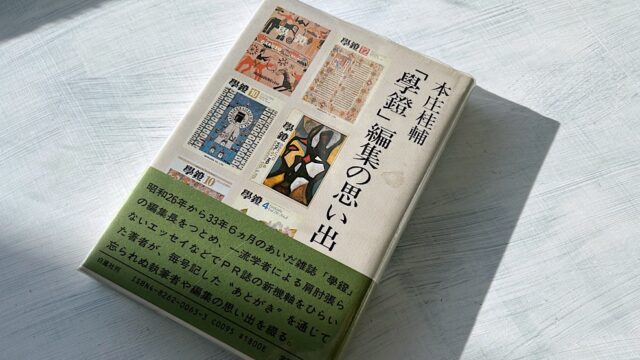夏目漱石「吾輩は猫である」読了。
本作「吾輩は猫である」は、1905年(明治38年)1月から1906年(明治39年)8月まで『ホトトギス』に連載された長編小説である。
連載開始の年、著者は38歳だった。
単行本は、1905年(明治38年)から1907年(明治40年)にかけて、大倉書店と服部書店から刊行されている。
浮世離れしているインテリ集団の物語
本作「吾輩は猫である」は、猫の視点から人間社会を風刺的に描いた長編小説だが、あまり難しいことを考えずに読んだ方が楽しい。
最大の見所は、主人公の英語教師・苦沙弥先生と、苦沙弥先生の家に集まる仲間たちとの丁々発止のやり取りである。
苦沙弥先生と親友の美学者・迷亭君、現在は実業家として活躍している鈴木籐十郎君とは、学生時代に小石川の寺で自炊生活をしていたときの仲間たちで、彼らは学校を卒業して九年目になる。
年齢で言うと30歳過ぎのアラサー男子たちが、この物語の牽引役だ。
「曾呂崎と云えば死んだそうだな。気の毒だねえ、いい頭の男だったが惜しい事をした」と鈴木君が云うと、迷亭は直ちに引き受けて「頭は善かったが、飯を焚く事は一番下手だったぜ。曾呂崎の当番の時には、僕あいつでも外出をして蕎麦で凌いでいた」(夏目漱石「吾輩は猫である」)
学生時代の仲間が3人集まって昔話をする場面は、しみじみとして楽しい。
そこに、苦沙弥先生の教え子である水島寒月君や、友人の越智東風君、元書生の多々良三平君など、20代の若者たちが加わって話を盛り上げていくのだが、それぞれのキャラクター設定が実にいい。
偏屈で頑固者の苦沙弥先生、人を食ったようなデタラメばかり言う迷亭君、世間離れした理学者の寒月君、実業家を目指す多々良君など、どの登場人物も生き生きとしている。
そして、このインテリ集団の高尚な会話は、どこか浮世離れしていて、互いにすれ違っているところなど、読み物として「猫」の完成度の高さを感じさせてくれる。
一番笑ったのは、寒月君がヴァイオリンを買いに行くくだり。
「みんな食ったら日も暮れたろう」「ところがそう行かないので、私が最後の甘干しを食って、もうよかろうと首を出して見ると、相変らず烈しい秋の日が六尺の障子へ一面にあたって……」「僕あ、もう御免だ。いつまで行っても果てしがない」(夏目漱石「吾輩は猫である」)
寒月君の話は、どこまで真面目で、どこから冗談なのか分からないが、話を聞いている仲間たちの自由な態度も楽しい(なにしろ、真面目に聞いていない)。
苦沙弥先生の「書を読むや躍るや猫の春一日」という俳句のほか、「秋淋しつづらにかくすヴァイオリン」「シャンパンの三々九度や春の宵」などと、会話の中で突然に挿入される迷亭君の俳句も悪くない。
掲載誌が俳句雑誌『ホトトギス』だからか、作品全体に(ちょっぴりだけど)俳句の薫りが漂っている。
願わくば明治の代に生まれて、こんな連中の仲間入りをしてみたかったなあと、本気で思う。
自分たちの暮らしを客観視したメタ認知の物語
本作「吾輩は猫である」のストーリー上の主軸は、近所の金持ち金田家の娘・富子と、苦沙弥先生の若き弟子たちとの結婚物語である。
富子の母親は、苦沙弥先生のところへやってきて、花婿候補者・寒月君の評判を集めていくが、もとより実業家を憎んでいる苦沙弥先生のことだから、話がまとまるはずもない。
富子の結婚話は、金田一家と苦沙弥先生との対立の物語へと発展し、金田家は政治力を使って近所の庶民連中に、苦沙弥先生へ散々の嫌がらせをさせる。
するとまた垣根のそばで三四人が「ワハハハハハ」と云う声がする。一人が「高慢ちきな唐変木だ」と云うと一人が「もっと大きな家へ這入りてえだろう」と云う。また一人が「御気の毒だが、いくら威張ったって蔭弁慶だ」と大きな声をする。主人は縁側へ出て負けないような声で「やかましい、何だわざわざそんな塀の下へ来て」と怒鳴る。「ワハハハハハサヴェジ・チーだ、サヴェジ・チーだ」と口々に罵る。(夏目漱石「吾輩は猫である」)
文化人と実業家との対立は、本作で大きなテーマの一つとなっていて、最終的に富子が、学者ではなく実業家の卵と結婚するあたり、「吾輩は猫である」の一つの結論だと感じた。
もっとも、漱石は、自分たち文化人の中に潜む憂鬱を自ら指摘してもいる。
呑気と見える人々も、心の底を叩いて見ると、どこか悲しい音がする。悟ったようでも独仙君の足はやはり地面のほかは踏まぬ。気楽かも知れないが迷亭君の世の中は絵にかいた世の中ではない。寒月君は珠磨りをやめてとうとうお国から奥さんを連れて来た。これが順当だ。しかし順当が永く続くと定めし退屈だろう。(夏目漱石「吾輩は猫である」)
「吾輩は猫である」は、猫に自身を投影して、自分たちの暮らしを客観視しようとした、メタ認知の物語である。
そして、夏目漱石の小説世界は、すべてここから始まっていくのだ。
物語を読み終えたとき、懐かしい同窓会が解散したような、祭りの後の寂しさを感じた。
自分は何より、明治の若者たちの前向きで逞しい情熱が羨ましかったのかもしれない。
どうでもいいけど、文春文庫の「現代日本文学館」で読む『吾輩は猫である』は、とても読みやすくて良かった。
注釈の分かりやすいところがすごくいいね。
書名:吾輩は猫である
著者:夏目漱石
発行:2011/11/10
出版社:文春文庫・現代日本文学館