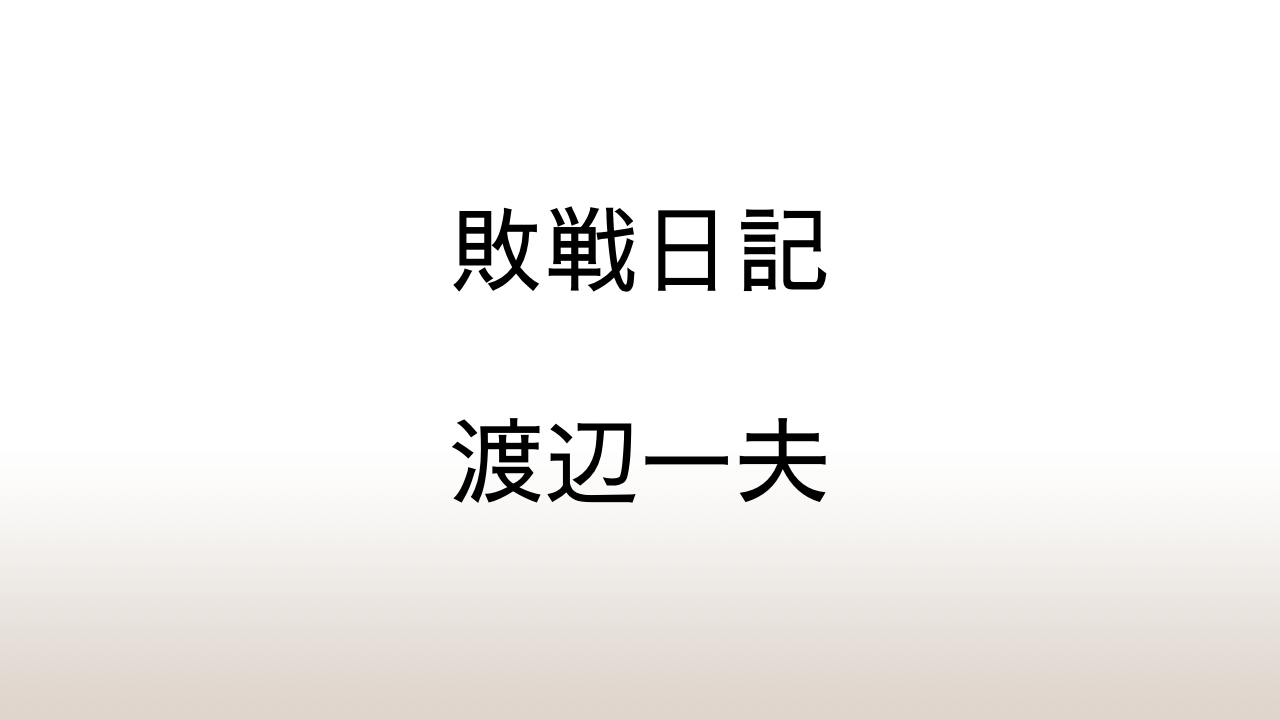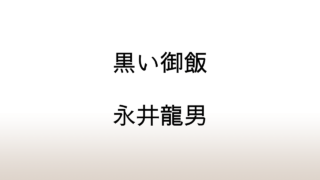渡辺一夫「敗戦日記」読了。
本書は、1995年(平成7年)に刊行された戦中日記である。
なお、終戦の年、著者は44歳だった。
強い反戦感情と、政府への激しい憤り
渡辺一夫は、東京大学のフランス文学者である。
1964年(昭和39年)、フランソワ・ラブレーの『ガルガンチュワとパンタグリュエル物語』の翻訳によって、読第16回読売文学賞(研究・翻訳賞)を受賞するなどの業績を残している。
本作は、まだ東京帝国大学だった東大の助教授として活動していた頃の著者が遺した戦争日記を出版したものである。
さすがに、大学教授だからなのか、いくら日記とはいえ、戦時中というのに過激な文章が並んでいる。
(1945/3/15)本郷の廃跡を見て思ふ。こんな薄ぺらな文化国は燃えてもかまひはせぬ。滅亡してもよいのだ。生れ出るものが残ったら必ず生れ出る。(渡辺一夫「敗戦日記」)
歴史に残る大惨劇となった東京大空襲は、1945年(昭和20年)3月10日の午前0時過ぎから始まった。
3月11日の日記で、著者は「三月九日の夜間爆撃によって、懐しきわが「本郷」界隈は壊滅した」と綴っている。
15日の日記は、焼け跡の本郷を見て書かれたものだが、「こんな薄ぺらな文化国は燃えてもかまひはせぬ。滅亡してもよいのだ」からは、苦しいくらいの愛国心が伝わってくる。
日本が大好きだったからこそ、「こんな薄ぺらな文化国は燃えてもかまひはせぬ」という強い言葉になったのだろう。
日本という国に対する著者の強い愛情は、日記全般を通して感じられるものだ。
(1945/6/12)我国は死ぬべきだ。その上で生れ変らねばならぬ。(渡辺一夫「敗戦日記」)
6月12日の日記にある「我国は死ぬべきだ。その上で生れ変らねばならぬ」も、同じように、日本を愛するが故の言葉だろう。
壊滅の向こうにある再生を、著者はずっと信じていたのだ。
日記全体を通して伝わってくるのは、強い反戦感情と、政府への激しい憤りである。
万が一、戦時中に、こんな日記が発見されたら、大変なことになっていただろうことは、容易に予測できる。
しかし、それでも、書かなければならなかったのだ。
安易に「カタルシス」という言葉を使いたくはないが、著者は、この日記を書くことによって、終戦まで生き延びることができたのかもしれない。
戦時を生きるインテリの生身の言葉
強い反戦意識は、同業者への批判へとつながっていく。
(1945/7/16)辰野、鈴木の両氏、想像力に欠け、かつエゴイスト。それぞれ違うが共に浅ましきエゴイストなり。辰野さん曰く、「今や松本で読書研究三昧の時ではない」鈴木さん曰く、「僕は焼け落ちるまで我家を守るね」前者は祖国のために生き残らんと願う弟子たちの身の上を顧慮せず、後者は万人にとって貴重なる書物の損失を敢て考えず。ただ己が生活の静謐をのみ思う。(渡辺一夫「敗戦日記」)
「辰野」とあるのは、東京帝国大学仏文科の教授だった「辰野隆」で、「鈴木」とあるのは同じく東大でフランス文学を教えていた「鈴木信太郎」のこと。
鈴木信太郎の名前は、7月5日の日記にも見える。
川村君来談。鈴木さんに言われたそうだ、「見苦しい死にざまを見せぬようにしたまえ。死ぬべき時には死なねばならん」(渡辺一夫「敗戦日記」)
抵抗感なく戦争を受け入れている文化人への激しい怒りが、そこからは感じられる(当然、日記以外の実生活で、このような発言をすることはなかっただろうが)。
戦時を生きるインテリにとって、太平洋戦争とは何だったのか。
この日記は、生身の言葉で、その答えを教えてくれるかのようだ。
書名:敗戦日記
著者:渡辺一夫
編者:串田孫一、二宮敬
発行:1995/11/12
出版社:博文館新社