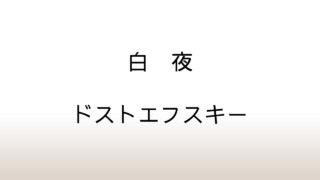庄野潤三「山の上に憩いあり」読了。
本作「山の上に憩いあり」は、1984年(昭和59年)11月に新潮社から刊行された随筆集である。
この年、著者は63歳だった。
河上徹太郎夫妻と庄野潤三一家との交流
全部で9篇の随筆と1篇の対談が収録されている。
作品タイトルとなっている「山の上に憩いあり」は、1984年(昭和59年)5月『新潮』に発表されたもので、河上徹太郎との交友の記録が綴られている。
次の「河上さんの心境」は、1980年(昭和55年)2月号『波』に発表された随筆で、以上の二篇が、河上徹太郎に関する作品となっている。
残り8篇は、庄野さんが敬愛する福原麟太郎に関する随筆(と対談)である。
「御縁のあった年長のお二人との交遊の思い出だけで一冊の本を編むめぐり合せになったのは、大きな喜びである」と、庄野さんは「あとがき」に記している。
本書中で、最もボリュームがあり、内容的にも注目すべきものは、河上徹太郎夫妻と庄野一家との交遊を回想した「山の上に憩いあり──都築ヶ丘年中行事」だろう。
河上家と庄野家との交遊は、1961年(昭和36年)の4月、庄野一家が、石神井公園から生田の山の上の家へと引っ越したときから始まっている。
たまたま生田の山の上に私たちの家を建ててくれた建築家の広瀬三郎さんが柿生の河上さんのお宅と荻窪の井伏さんのお宅を手がけた方であったという御縁で、四月の末の家びらきに来て下さっている。(庄野潤三「山の上に憩いあり」)
この家びらきには、井伏鱒二や村上菊一郎、横田瑞穂、小沼丹など、親交のあった仲間が集まっているが、先着組が近辺の散策を終わった頃に、河上徹太郎は到着した。
そろそろ日が傾きかけた頃、縁側の硝子障子を開け放したら、何も木の植わっていない庭に目をやった河上さんが、「なんだ。『禿山の一夜』じゃないか」と叫んだ。(庄野潤三「山の上に憩いあり」)
家びらきに来てもらったお礼として、この夏、庄野夫妻は、柿生にある河上徹太郎邸を訪ねるが、これが、柿生と生田との交流の、実質的な始まりだった。
この年、庄野さんは40歳、河上徹太郎は59歳。
19歳の年齢差を越えた交遊の始まりである。
翌年(1962年)の夏にも、柿生での夕食に招かれた庄野夫妻は、「今度は生田でお月見をする」約束をして、9月30日、河上徹太郎夫妻を生田の山の上へ招待する。
庄野一家の賑やかな歓待を受けて、河上夫妻は、さぞかしびっくりしたことだろう。
「逝きしユーラリ」と中学三年の長女が学校で習った「アンボンの船」(アンボン島土人の旋律より。高木東六編曲)の二曲。食事が終ってから小学五年の長男と一年の次男がそれぞれ大きさの違う「松のたんこぶ」を持って現れ、お二人の肩をそれで叩いた。(庄野潤三「山の上に憩いあり」)
当時の庄野家の生活を伝えるため、庄野さんは「お月見の翌週の日曜日(十月七日)」の日記を引用している。
遅く起きて、龍也、和也とシバ(生田へ来てから貰った雑種の日本犬)を散歩に連れて行く。朝食はおじや。「群像」書く。一時半にパン。夏子の靴を買ってやるため、妻と二人で東京へ行かせる。(庄野潤三「山の上に憩いあり」)
夏子が、新宿アメリカ屋で買った千四百円の靴を、書斎でスカートを脱いだシミーズという恰好で履いてみたり、龍也と和也が、紐で足を縛って二人三脚をして現れたり、笑いの絶えない庄野家の日常が伝わってくる。
翌年(1963年)1月3日の午後、庄野夫妻は、柿生の河上邸を年始に訪れるが、河上夫人の勧めで、子どもたちを呼び寄せて、夕食をご馳走になる。
暖炉のそばの腰かけに火の面倒を見てくれる河上さんをいちばん奥にして坐り、薪の火ででびらがれいを焼き、ハムを焙りながらビールを頂く。(庄野潤三「山の上に憩いあり」)
「でびらがれい」は、福原麟太郎から送られた郷里の瀬戸内のものだったが、このとき、庄野さんは、龍也に「燈台守」を歌わせ、「夜ふけの森に響くコヨーテの鳴き声」を四回も出させている。
さらに、長女と妻が「逝きしユーラリ」を、庄野さん自身も英語で「いとしのクレメンタイン」を歌うと、河上徹太郎がピアノの演奏を披露してくれた(このときの曲が「山の上には憩いがある」という曲名だった)。
続けて、河上夫婦の連弾でモーツァルトの「メヌエット」が演奏されるという、かなり豪華な夕食会となったらしい。
「河上と連弾をしたのは何十年ぶりで、本当に珍しいことです」と河上夫人が言ったくらいだから、本当に貴重なことだったのだろう。
翌年(1964年)の正月は、最初から一家五人で柿生を訪れ、暖炉の火で「でびらがれい」を焙って食べているが、このときの様子は、「週刊読書人」に連載された河上徹太郎の『文学的回想録』にも綴られている。
この年の夏に、庄野夫婦を夕食に招待したとき、河上徹太郎は「遊びに来て下さい。おれは淋しいんだよ」を言って、何度も握手をしたという。
クリスマスに、河上夫妻を招待するようになったのは、この年(1964年)からで、12月25日に、生田の山の上で、クリスマスの会が催されている。
河上さんは酔って来られると、よく、「おい! たつ! かず! なんだ面白い顔をして」といったり、二人が返事をすると、「しっかりしろ」といってからかっておられたけど、お母さんや私に対しては口調を変えて(声が高くなる)、「奥さま」とか「夏子さん」というふうに決して怒鳴ったりなさらず、飽くまでジェントルマンでいらっしゃいました。(庄野潤三「山の上に憩いあり」)
本作「山の上に憩いあり」には、南足柄市在住の長女が書いた「てっちゃんメモ」が随所に織り込まれていて、子どもたちの目から見た庄野潤三と河上徹太郎の交遊を知ることができる。
相当酔ったてっちゃんが、お父さんに、「おい! 庄野」と怒鳴って、握手してから急に真面目な声になって、「お互いにいいものを書きましょう」とおっしゃったことがあります。お父さんがそれに対して、本当に是非お互いに元気でいい仕事を残したいという意味のことをいっていると、今度は私たちの方を向いて、「何かもしょもしょいってるよ」といわれて、おかしかったです。(庄野潤三「山の上に憩いあり」)
こうして、「柿生」の河上夫妻と、「生田」の庄野一家との交流(つまり「都築ヶ丘年中行事」)は続いていくが、あるとき、井伏鱒二は庄野さんに、「河上が、いい友達を紹介してくれたといって喜んでいた。河上はあんなふうに素直にいう男じゃないが、こんなことは初めてだ」と言ったという。
庄野家のフィレ・ステーキを楽しみにしていて、一口食べると必ず「おいちい!」と言ったり、酔うと必ず「お勘定!」と叫んだり、河上さんは庄野一家に囲まれて、本当に心を許していたのだろう。
最後のクリスマス会が、生田の山の上で開かれたのは、1975年(昭和50年)12月。
河上夫人が病に倒れ、やがて、河上徹太郎も国立がんセンターへ入院するようになる。
「新潮」の「退屈」よかったです。あの蚊がはいって来て刺すところはどきんとしました。よくあれだけお書きになりました。そういうと、「庄野さんが誉めてくれりゃ、もうそれでいいや」と喜ばれる。(庄野潤三「山の上に憩いあり」)
最後に、次男(和也)の書いた「山歩きのこと」が掲載されている(今村夏子の文章は、いくつかあるが、庄野和也の文章は珍しい)。
河上徹太郎が亡くなったとき、次男は「昨夜はひと晩中、てっちゃんの夢を見ていた」とつぶやいたという。
河上徹太郎との交遊を通して、庄野家の三人の子どもたちの成長ぶりを知ることができる、貴重な交友録だ。
福原麟太郎へのリスペクト
本書の後半には、庄野さんが敬愛する英文学者・福原麟太郎に関する随筆が収録されている。
二人の交流は、1959年(昭和34年)、庄野潤三が著作『ガンビア滞在記』を福原麟太郎へ贈ったことから始まっている。
実際に対面したのは、河盛好蔵『フランス文壇史』の出版記念会の夕べだった。
三十六年五月十日の日記をみると、「東京駅地下の食堂で生ビール二杯、ステーション・ホテルへ十五分前に着く。福原麟太郎氏にはじめてお会いし、向い合って会が始まるまで三十分ほど話をする」とある。(庄野潤三「治水」)
このとき、庄野さんは、福原さんに「『治水』をおもしろく読みました」と言うと、福原さんは「あれを読んで貰ったのはうれしい」と喜んだという。
もっとも福原さんの随筆には、数え上げればいくらでも傑作が出て来る。夜空にきらめく星の中からどれがいちばんよく光るか、くらべようというようなものではないか。(略)シェイクスピアの云った言葉でもラムの云った言葉でも、この人の身体を通って出て来ると、もう福原さんの魅力となる。(庄野潤三「治水」)
実際、庄野さんの作品には、至るところに福原麟太郎の影響が見られる。
福原麟太郎は、庄野文学に大きな影響を与えた人物でもあったのだ。
上野の西洋美術館は何の展覧会であったか思い出せない。招待日で、入口の近くで開場を待っていたら、雑誌のカメラマンに附き添われた福原さんが来た。グラビアの写真を撮るためだと分ったが、福原さんは、僕はまだあなたと一緒の写真を一枚も持っていない、ここで撮って貰いましょうといわれた。(庄野潤三「福原さんを偲ぶ」)
このときの記念写真は、『現代日本の文学44 小島信夫・庄野潤三』(1971年、学習研究社)に掲載されている(ただし、二人とも笑ってはいないようだが)。
福原麟太郎の「今日の運勢」という随筆に、庄野潤三が登場している。
そこには、近代日本文学館設立のための色紙展を覗いたところ、「驚いたことに庄野潤三さんが入口のところへ受付みたいに坐っている」と書かれていたが、実際には「佐藤春夫展の出口」だったらしい。
佐藤先生の生前、毎年、桜の花の咲く頃に誕生日を祝う「春の日の会」が開かれたが、それに出席していた者の中から指名された何人かが交替で会場に詰め、自分の本を買ったお客さんのために署名をすることになった。ひとりだけ嫌だというわけにはゆかないから、不似合いなのは承知で引受けた。(庄野潤三「福原さんの思い出」)
福原麟太郎と庄野潤三に共通する大きなテーマは、チャールズ・ラムに代表される英国の随筆文学を、日本でも定着させることだった。
小説よりも随筆の地位が低くてはいけないんだ。それは決して健康なことではないんだ。おそらく福原さんには固い信念がおありになったに違いない。たとえ四百字詰原稿用紙で僅か二枚、三枚の原稿であっても(もっと少なくて何百字というのもある)、あるいは短ければ短いほど、心をこめ、言葉を選んでお書きになった。(庄野潤三「『随想全集』のあとに」)
「小説よりも随筆の地位が低くてはいけないんだ。それは決して健康なことではないんだ」とあるのは、きっと、庄野さん自身の言葉でもあったのだろう。
随筆(エッセイ)だから簡単に書けるでしょ?という風潮を、福原さんも庄野さんも、かなり苦々しく感じていた様子が伝わってくる。
最後の「対談 瑣末事の文学」にも、その姿勢は鮮明に現れている。
【福原】「庄野さんもよく悩まされていらっしゃるに相違ないけれども、軽いものでいいと言っても、軽いっていうわけにはいかない。たかが三枚でもね」【庄野】「そうです。短ければ短いほど、それだけ努力をして、集中して書かなきゃできないものなんですね」(福原麟太郎・庄野潤三「対談 瑣末事の文学」)
随筆に続けて、福原さんが主張するのは、日常の何気ないことを描いた「瑣末事の文学」の重要性だ。
【福原】「そこで、言いたいことはね、そういう瑣末事の文学が、われわれ人間としては重大事なんですよね。そこんところを突いて、庄野さんの小説がこんなに重なってくるというのは、前に言ったような意味でも大事ですけどね。そういうものを読む読者をこさえたのは、庄野さん自身であるということね。これはちょっと言いたい」(福原麟太郎・庄野潤三「対談 瑣末事の文学」)
福原麟太郎は、庄野文学の本質を、しっかりと把握していた。
庄野潤三の小説が「随筆みたいだ」とか「日記みたいだ」なとと言って騒ぐことが、そもそも庄野文学を理解していないことであると、福原さんは伝えたかったのではないだろうか。
河上徹太郎と福原麟太郎という二人の先輩に対する愛情が、たっぷりと詰まった一冊。
その愛は重いけれども、同時に、それは、年齢を越えた爽やかな友情でもある。
そんな友情を育むことができる人の作品が、面白くないはずがない。
つまり、本作『山の上に憩いあり』は、庄野文学の再評価へと繋がる重要な随筆集だったのだ。
書名:山の上に憩いあり──都築ヶ丘年中行事
著者:庄野潤三
発行:1984/11/05
出版社:新潮社