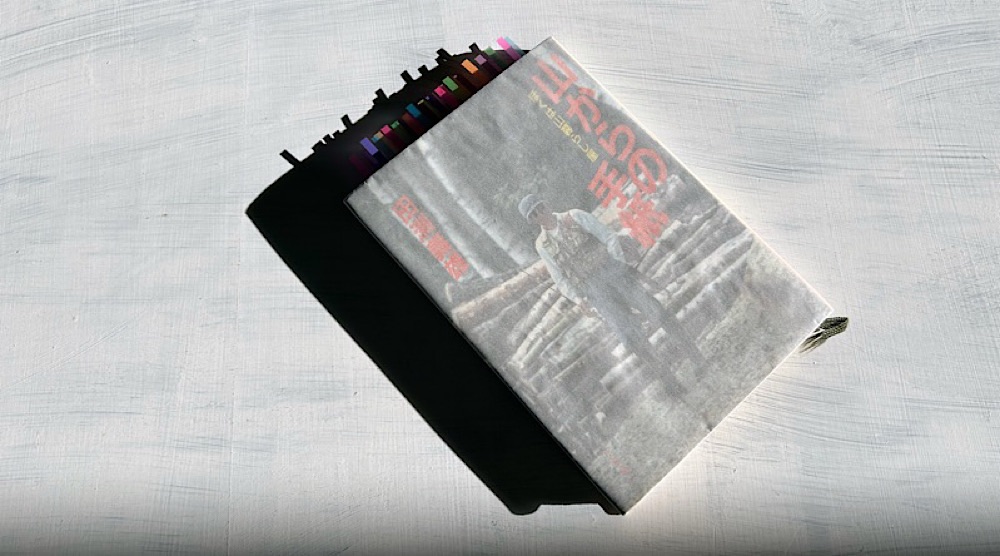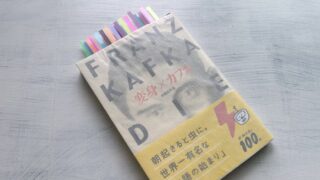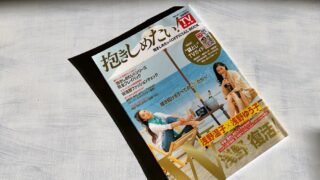田渕義雄「山からの手紙」読了。
本作「山からの手紙」は、1988年(昭和63年)12月に小学館から刊行されたエッセイ集である。
この年、著者は44歳だった。
山の暮らしを通して人生を語る
本作『山からの手紙』は、80年代版『森の生活』である。
都会を棄てて、山で暮らし始めた男の生活が、そこに描かれている。
人や人の社会や人が造った物から学べることには限りがある。だから、自然生活が必要だ。山で暮らしていても、アウト・オブ・ドアー・ライフがなければリクリエーションがない。(田渕義雄「山からの手紙」)
80年代には飽和状態となっていた物質文明社会に対するアンチテーゼ、と言ったら安易すぎるだろうか。
著者の生きる姿勢の向かい側には、常に「80年代」という現代社会があった。
豊かな暮らしって何だろう? どうすりゃいいんだろう。オレにはわからない。でも、貯金ある奴が、いい暮らししてるってことはないのだと思う。幻想だよ。イリュージョンだ。(田渕義雄「山からの手紙」)
山暮らしの作者は「貯金ある奴は、金の奴隷やってるだけじゃないのか」と、バブル景気に沸く日本社会を笑い飛ばしてしまう。
トレンディじゃないのだ、全然。
ノリキもタモツもユウ子ちゃんもヤスエも、それから井原君も、みんながんばれ、愚痴をいうな。ブーだれるな。金持ちを笑え。ハシャギすぎの街の娘を笑え。評論家を笑え。時代を笑え。みんな笑ってしまえ。(田渕義雄「山からの手紙」)
作者が笑い飛ばしているもの、それは「80年代」という時代そのものだった。
山の中にいて、作者は「80年代」という時代と対峙している。
戦争ごっこやって、本当の戦争も少しだけやりあって、何が平和会議だ、軍縮だ、エイズだ。オレには関係ない。全然関係ない。そんなことオレの知ったことじゃない。この地球も人類も滅びたりするものか。(田渕義雄「山からの手紙」)
舞台を離れたからこそ見えてくる物語というものがあるかもしれない。
作者にとって、それが「東京」であり、「日本」であり、「80年代」という現代社会だった。
ぼくはゴルフはやらない。身近な自然のよさに目を向けないで、なにがグリーンだ芝生だ。想像力が欠如している人たちがゴルフやりたがる。(田渕義雄「山からの手紙」)
徹底的なアンチ80年代というライフスタイルが導いたものは、山の中での生活だった。
街の暮らしが好きな人が街の暮らしをやっている。原発やりたい人が原発やって、自動販売機のための電気おこしてる。山で淡々と暮らすことが、本当にあなたの人生の夢なら、どうして今すぐにそうしないのだろう。みんな好きにやってるんだもの。ぼくたちだって好きにやりましょう。(田渕義雄「山からの手紙」)
当時、「田渕義雄」というライフスタイルに影響を受けた若者たちが、どれほど生まれただろうか。
都会の生活を見棄てた若者たちは、「田渕義雄」の提唱するアウトドア・ライフに新しい生き方を発見した。
人生は勝った負けたのコンペティションじゃない。フライ・フィッシングや山登りやハング・グライディングみたいな競争のないアウトドア・スポーツのほうが、技術の優秀を争いあう競技スポーツよりも男らしいし、奥の深いスポーツなのだとおもう、ぼくは。(田渕義雄「山からの手紙」)
この本には、生きることに関する考察がたくさん書かれている。
山での暮らしというのは、常に生きることと向き合っていたからかもしれない。
軽い気持ちでまじめにやろう。下品なこと考えるより、まじめでいたほうが楽だよ。人生は楽でいたほうがいい。なぜなら楽しいということは楽ということだから。ねえーきみ、そうでしょ。(田渕義雄「山からの手紙」)
「軽い気持ちでまじめにやろう」というライフスタイルに、我々は惹かれた。
窮屈な都会の生活に、誰もが飽き飽きしていたのだ。
人生は自己満足的であればそれでいい。他人の視線や他人の価値観のなかでしか生きられない人は不幸であり、厄介である。ひとつの時代も社会も、ひとつの国家のあり方もまたそうなのだとおもう。(田渕義雄「山からの手紙」)
木を切り倒し、薪を割り、ストーブで火を焚く。
山での暮らしは、ひとつひとつの行為に意味がある。
哲学的にならないわけがない。
えー、そうですとも。わたしは文学部で哲学の勉強をしました。実存主義が流行ってた時代で、カミュとかサルトルとかハイデッカーをよく読みました。(田渕義雄「山からの手紙」)
哲学以上に作者が惹かれたもの、それが文学(詩)だった。
本作『山からの手紙』は、それ自体が、ひとつの「詩」となっている。
「四月は残酷な月だ。冬はぼくらを温かくしておいてくれた。大地を忘却の雪でおおって──」そういう詩を書いたのはセント・ルイス生まれのT・S・エリオットという詩人だったが、いかがお暮らしですか。(田渕義雄「山からの手紙」)
野外生活(アウトドア・ライフ)の本だからといって、馬鹿にする必要はない。
この本は、アウトドア・ライフを通して現代社会を語り、人生を語っているのだ。
自然生活(アウトドア・ライフ)はいい。自然はいつも気持ちいい。自然のよさに比べれば、娑婆のざわめきなんか、テレビジョンの退屈ドラマみたいなもんだろう。(田渕義雄「山からの手紙」)
山暮らしを語り、フライ・フィッシングを語り、焚き火を語り、人生を語る。
生きるということの意味を、我々は、山暮らし(アウトドア・ライフ)の中に見つけることができる。
金はないけど、三年分のいい薪がある。薪があればね、山暮らしなんか楽なもんさ。(田渕義雄「山からの手紙」)
ヘンリー・デイヴィッド・ソローは『ウォールデン 森の生活』(1985)で、森に生きる暮らしを描いた。
田渕義雄は『山からの手紙』の中で、山の暮らしについて綴っている。
その「手紙」は『BE-PAL』という雑誌を通して、全国に散らばっている読者という名の友だちのところへと届けられた。
友達を大切に。新しい友達、古い友達がいる。でも、昔からの友達はやっぱりいい。同じ時代を一緒に生きてきた者同志でなければわかりあえないことが、どうしてもある。(田渕義雄「山からの手紙」)
あの時代、『BE-PAL』には『山からの手紙』があった。
我々は毎月山から届く「手紙」を楽しみにして、都会の暮らしを生きていたのだ。
それでは、精神的に豊かな生活とは、いったい、どのような生活だったのだろうか?
でも、みんな一緒に年をとっていくのだね。僕は一〇年前も今も、ニール・ヤングのレコードを聴いている。(略)朝はニールのカントリー・ミュージックかけて、夕方になったら古いバロック聴いて、もう何も私をかえない。(田渕義雄「山からの手紙」)
豊かな生活から音楽を欠くことはできない。
流行に左右される音楽ではなく、時代を越えて愛される音楽だ。
薪ストーブがあったかい。とても気持ちがいい。いい気分。気持ちがいいことはいいことである。薪ストーブもイワナ釣りもロック・クライミングも家具作りも、そしてセックスも。(田渕義雄「山からの手紙」)
おそらく、豊かな生活の本質とは、気持ちいいことだった。
だから、山暮らしの作者は、気持ちいいことにしか興味がない。
耐え忍ぶために山暮らしをしているわけではない、というところに、豊かな生活の意味がある。
テレビも映らない。ラジオもロクに聴こえない。土地は狭くて畑は借地。家の屋根は近頃めずらしいトタン屋根。冬はひどく寒い土地で何もない山の上。たっぷりあるのは木々の緑と薪ぐらいのもの。でも、オレはこの山暮らしが気に入っている。(田渕義雄「山からの手紙」)
大切なことは、必要ではないものは何もない、ということだ。
私たちの幸せは、今いろいろですね。シティ・リビングに憧れる人もいれば、うんざりしている人もいる。ぼくは電気のない生活を夢みているし、きみは完全電化のエレクトロニクス・ライフをエンジョイしているかもしれない。(田渕義雄「山からの手紙」)
裏を返すと、自分に必要なものはたくさんある、ということでもある。
難しいのは、本当に自分に必要なものを、自分自身で取捨選択するということだろう。
それにしてもフライ・フィッシングはいいなあー。やめられない。やめなくていい。今にしておもえば、フライ・フィッシングとの出合いがぼくの人生を変えたのだと感じる。人の世に金と雑事の悩みはつきないもの。どうせそうなら、川の畔に住んで夏を陽気に釣り暮らすのがいい。そう考えて、ぼくはここに移動してきた。(田渕義雄「山からの手紙」)
作者(田渕義雄)は、イワナ釣りをして暮らすために、金峰山北麓の山里へ移り住んだという。
沢野ひとしの対談集『僕はやっぱり山と人が好き』(1987)でも、田渕義雄は語っている。
「今年は三〇〇匹くらい釣ったかな。夏場は文字どおり貴重なたん白源になるし、まあ、飽きるから人が思ってるほどは食べないんですけども、やっぱり僕にとってはイワナの釣れる川が、しかも村のなかにあるってことはすごく重要だったんです」(沢野ひとし「僕はやっぱり山と人が好き」)
生活の軸としてフライ・フィッシングがある。
豊かなモノに囲まれて生きることが当たり前となった1980年代において、それは、決して簡単ではない生き方だった。
それにしても、ソフトハウスはいいなあー。ぼくは今、ティピーも含めて、全部で五つのテントを持っている。でももっと欲しい。テントは、コストの安い小さな家なのだ。(田渕義雄「山からの手紙」)
ソフトハウス(テント)は、人間が自然の中へ還ることのできる重要なツールだ。
明るいドームの床に腹ばいになってテント屋さんのカタログのページをめくる。去年オレゴンのセーレムの自転車屋さんでもらってきた、モス・テンツの1984年版のカタログ。(田渕義雄「山からの手紙」)
当時、ビル・モスのテントを日本で入手することは、まだ難しい時代だった。
だから、作者はアメリカまで、ビル・モスへ会いに行く。
ポートランド・メインでは、ビル・モスのデザイン事務所を訪ねた。ビルは有名なテント・デザイナー。芸術とテントの関係と、それからフライ・フィッシングの話をぼくたちはした。(田渕義雄「山からの手紙」)
精神的に豊かな生活とは、モノにこだわらない生活のことではない。
自分に必要なモノについては、徹底的にこだわること。
それが、精神的に豊かな生活ということだ。
ムラタのフライ・ロッド(9万円)を購入したのも、つまりは、豊かな生活のためだった。
バンブー・ロッドはやっぱりいいなあーと、最近はそう思うようになった。なぜって、素材が自然だし、手作りのよさが伝わってくるから。千葉の臼井に住んで、一人でバンブー・ロッド作ってる村田孝二郎兄、ガンバレ!(田渕義雄「山からの手紙」)
L.L.ビーンの柳のクリールも、やはり、山での暮らしには必要なものだった。
なにしろ、フライ・フィッシングをやるために、作者は都会を棄てて山に入ったのだから。
フライ・フィッシングは優雅に楽しむべし。自信があろうとなかろうと、いつも特大のビクを肩から下げて、川へ行くのがいい。(田渕義雄「山からの手紙」)
夏は釣りを楽しみ、冬は薪ストーブで暖まる。
都会を離れることで、作者は、そんな生活を手に入れた。
ぼくは何もしなかった。何も考えなかった。ぼくはただ黙々と山暮らしをやっていただけだった。(田渕義雄「山からの手紙」)
気負いのようなものは、どこにも感じられない。
好きだから、山で暮らす。
ただ、それだけだ。
わたしたちの山暮らしは旅。ひとつづきの長い旅。この道は、ぼくたちが思っていたよりも、ずっと遠くまでつづいているらしい。(田渕義雄「山からの手紙」)
結局、1982年(昭和57年)からのすべての人生を、作者は山で過ごした。
きっと、今も田渕義雄さんの魂は、金峰山北麓の山里に生き続けていることだろう。
書名:山からの手紙
著者:田渕義雄
発行:1988/12/01
出版社:小学館(BE-PAL BOOKS)