吉行淳之介の「札幌夫人」は、昭和37年10月号の「小説・中央公論」に掲載された短編小説である。
当時、38歳だった著者(吉行淳之介)は、「札幌夫人」を執筆するために、現地で取材を行ったらしい。
「薄野の高級キャバレーの並んでいる一郭を歩み抜けたすぐ眼の前に、薄暗い横丁がある。その横丁では、片側は貧相な旅館が軒を並べ、片側は寺院の土塀がつづいている。その塀の前に、板囲いの四角い小屋が幾つも並んでいる。板の横腹には四角く窓が開かれ、ガラスの替りに透明なビニールが貼りつけてある」などといった、当時のススキノの具体的な描写が随所に登場しているのは、現地取材の成果だろう。
主人公の「東野」は「Z商事会社」の社員で30歳、新たに設置された北海道支社に配属されて札幌まで単身赴任でやってきた。
「サッチョン」(札幌へ単身赴任している男性のこと。札幌チョンガーの略)はもてると期待していたが、実際にもてるのは金や地位のある支店長・部長級の男性であって、若い世代は、つぶ焼小屋で商売女を買って用を済ませているというのが、現実だった。
やがて、東野は、バーのホステス「エミ子」へ、毎月一万円のお小遣いを支払う代わりに、月4回の肉体関係を持つことができるという、大人の契約を結ぶことに成功し、現地妻を手に入れる。
ライバル社のサッチョン「西田」から助言をもらいながら、バーのマダムとその元・愛人「A氏」の行く末を見守りながら、「東野」は「札幌夫人」なる言葉の意味を、少しずつ理解していくことになるのだが、、、
貧しいつぶ焼小屋が並ぶススキノ
札幌に転勤になって一ヵ月目の夏の夜、東野はキャバレー街を素通りして、この一郭に歩み込んだ。同じ道幅だが、この横丁の入口までで舗装は尽き、雨上りの道はひどくぬかる。小屋を覗くと、五十年配の女が金網の上に小さな買を並べて焼いている。蠟燭の灯と、金網の下の赤い炭火とが、その女の薄化粧した顔を薄い明るく照し出している。(吉行淳之介「札幌夫人」)
「札幌夫人」の特徴は、札幌の繁華街である「ススキノ」風景、それも、貧しいつぶ焼小屋が並ぶ未舗装地域の描写に詳しいということである。
昭和30年代後半とはいえ、戦後の闇市の名残りを引きずっているかのようなつぶ焼小屋の描写は、非常に貴重な記録とも言える。
一方で、ススキノの他に登場するのは、ホステスの「エミ子」と初めて関係を持つときに連れていった、支笏湖くらいのもので、札幌らしい札幌はほとんど登場しないから、著者の取材はススキノと支笏湖に集中していたのかもしれない。
寺町「すすきの」の一郭にある、寺院周りの風景ばかりが粘り強く描写されていて、読者に強い印象を残すだろう。
サッチョンと札幌夫人
湖心からの展望は、さすがに北の国の風物を強く感じさせた。札幌界隈の風景は、それほど特殊ではない。近畿地方の盆地をおもわせる山並がみえたりする。しかし、東野にとって、最も印象深かったものは、そのような風景ではなかった。それは支笏湖の底に沈んでいた、柄の取れたアルミニュームの鍋である。(吉行淳之介「札幌夫人」)
初デートで訪れた支笏湖で、「東野」は「エミ子」から、ひとつの心中伝説を聞く。
それは、あるサッチョンと札幌夫人が心中を計画して支笏湖へやって来るのだが、湖の底に沈んでいる「アルミニュームの鍋」を見つけた瞬間、ロマンチックな気持ちが吹き飛ばされて、結局死ぬのをやめて別れてしまうという話だった。
東京や大阪に本社のある企業の支社が、次々と札幌へ進出していた時代、「サッチョン」や「札幌夫人」は、札幌の近代的な発展を示す、ひとつのキーワードだったのかもしれない。
ススキノを中心に、様々な伝説や噂が生まれては消えていったに違いない。
「札幌夫人」は、そんな時代の伝説をしたためた、昭和のお伽噺である。
本書を片手に、現代のススキノを歩いてみるのも悪くないだろう。
書名:札幌夫人
著者:吉行淳之介
発行:1986/1/25
出版社:集英社文庫


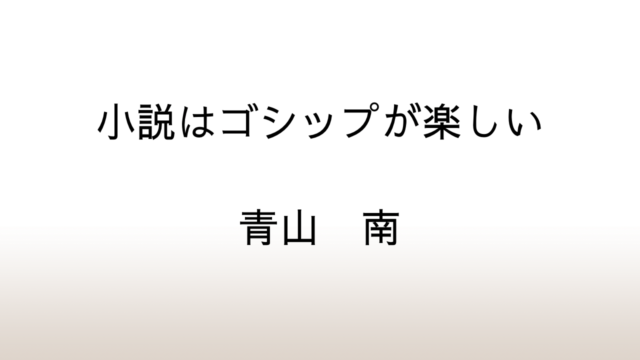



-150x150.jpg)









