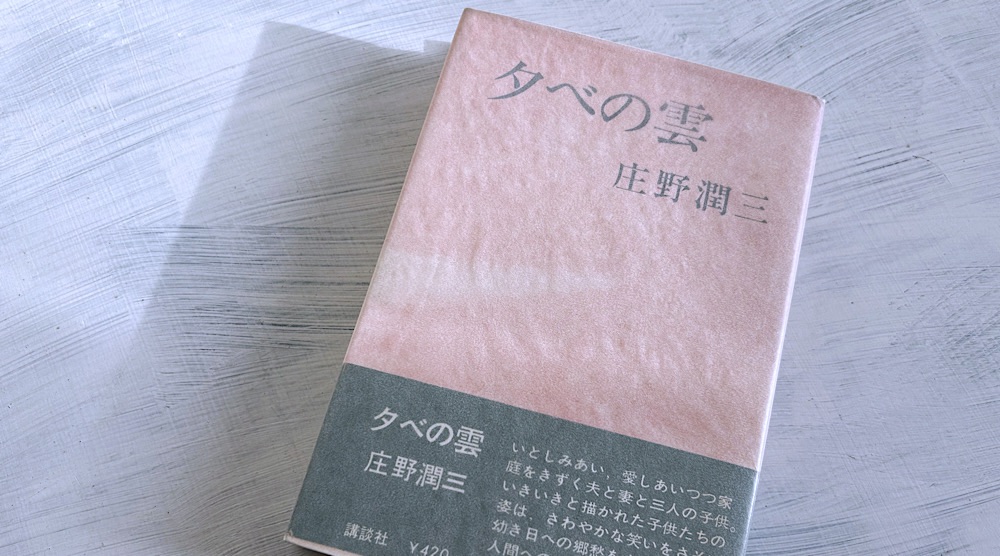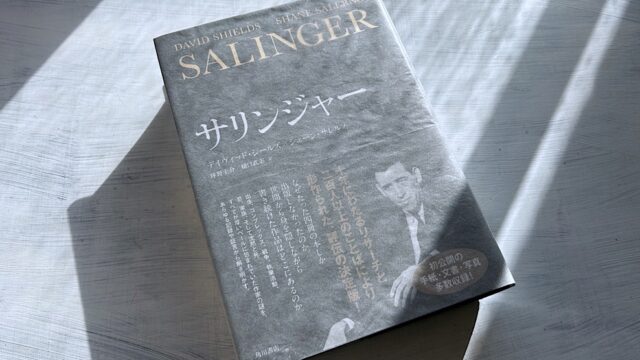庄野潤三「夕べの雲」読了。
本作「夕べの雲」は、1964年(昭和39年)9月から1965年(昭和40年)1月まで『日本経済新聞』に連載された長篇小説である。
連載開始の年、著者は43歳だった。
単行本は、1965年(昭和40年)3月に講談社から刊行されている。
1966年(昭和41年)、第17回読売文学賞(小説賞)受賞。
故郷を離れた中年男性の郷愁
1996年(平成8年)から2006年(平成18年)まで10年間(計11作)続いた「夫婦の晩年シリーズ」の最終作『星に願いを』。
その最終話の最後の場面で、大阪の実家から株分けした浜木綿と、武井武雄の『赤ノッポ青ノッポ』のエピソードが出てくるところは、『夕べの雲』から40年以上も続いた家族物語のフィナーレを飾るに素晴らしい演出だった。
なぜなら、浜木綿も赤ノッポ・青ノッポも、庄野文学の原点を象徴するキーワードとなっているからだ。
浜木綿を株分けする話は、『夕べの雲』の中の「雷」という章で登場する。
体調の悪い母親を見舞って帰省した折に、主人公<大浦>は、実家の庭から浜木綿を持って帰る。
シャベルで掘っている時、大浦は不思議な感じがした。自分がいま株分けしているのは浜木綿であるが、それは何かの生命に違いない。向うの部屋では、母が眠っている。何度も危なくなって、まだ続いている母の生命がある。この「畑」の浜木綿の一株を掘って、東京へ持って帰って、庭に植えるのは、眠っている母の生命を分けて、向うの土につぐようなものではないか。(庄野潤三「夕べの雲」)
武井武雄の『赤ノッポ青ノッポ』が出てくるのも、同じく「雷」の章だ。
安雄が大きな声で、「ただいま、けえりやした」というと、みんな笑った。関西生れの東京育ちがいま帰りました、という意味である。(庄野潤三「夕べの雲」)
子どもが、漫画の登場人物を真似て「ただいま、けえりやした」と現れる場面はユーモラスであり、母親の危篤に際して、実家の浜木綿を株分けする話は、生命の世代間継承を伝える感動的なエピソードだが、浜木綿の株分けには、家族の継承という意味のほかに、関西の人間が、東京郊外に根を下ろしたという、もう一つの特別な意味を孕んでいる。
そもそも『夕べの雲』は、二年前に植えた萩の話から始まっている。
この萩を近くの山から取って来て、ここに植えたのは、二年前のことだ。それは随分ちっぽけな萩であった。見つけたのは上の男の子の安雄で、あの時は小学五年生であったが、その膝よりもまだ小さかった。(庄野潤三「夕べの雲」)
大浦家が、生田の山の上に新築した住宅に引っ越してきたのは、それからさらに一年前の春だから、もう三年半も昔のことになるが、この新しい町で、彼らはまだ余所から転入してきた一家族に過ぎない。
いつの間に大きくなった萩のエピソードは、彼ら家族が、この地に根づき始めていたという、重要な意味を持っている。
こうした視点で読み進めていくと、本作『夕べの雲』は、大阪出身の人間が故郷を離れて、遠く東京郊外の山の上で暮らし始める場面を描いた、移住の物語であることが分かる。
大阪から東京へ引っ越してきたときの「上京物語」は、同じ日経新聞の連載小説『ザボンの花』(1955)に描かれているから、この『夕べの雲』は、さしずめ「生田移住物語」である。

株分けした浜木綿が根付いていく過程は、大浦が生田の山の上に定着していく過程を象徴するものであり、だからこそ、最晩年の作品『星に願いを』の最終場面で、浜木綿の株分けの話が出てくるところは、庄野文学の家族物語を総括する上で、極めて象徴的な場面だった。
そして、その原点とも言える作品こそ、庄野潤三自身が代表作と呼んで憚らなかった、この『夕べの雲』である。
この物語が、懐かしい響きを持って読まれているのは、その根底のところで、故郷を離れた中年男性の郷愁が描かれているからだろう。
失われていく「いま」を描く
同時に、『夕べの雲』は、過去から現在、現在から未来へとつながる時の流れを、鮮明に描いた作品でもある。
講談社文芸文庫のあとがき「『夕べの雲』の思い出」で、庄野さんは「『いま』を書いてみようと思っている」と、当時の気持ちを披露している。
その「いま」というのは、いまのいままでそこにあって、たちまち無くなってしまうものである。その、いまそこに在り、いつまでも同じ状態で続きそうに見えていたものが、次の瞬間にはこの世から無くなってしまっている具合を書いてみたい。(庄野潤三「夕べの雲」「著者から読者へ『夕べの雲』の思い出」)
庄野一家が生田へやってきたのは、日本住宅公団による大マンションプロジェクト「西三田団地」の造成が始まるのと、ほぼ同じ頃だった(1961年4月)。
主人公の大浦は、削られつつある山と向き合いながら、「いま」を見つめ続けている。
だから、いつから工事が始まるのか、知らない。いずれ近いうちに始まることは確からしいが、少なくとも今すぐということはない。それなら、この山がこのままの姿をしている間にうんと楽しもうじゃないか。彼はそう考えた。(庄野潤三「夕べの雲」)
過去から未来へと続く、時の流れを認めているからこそ、大浦は「いま」にこだわろうとしていたのだろう。
「コヨーテの歌」の章では、日の暮れかかる谷間で遊ぶ子どもたちの声を聴きながら、遠い未来へと思いを馳せる。
「ここにこんな谷間があって、日の暮れかかる頃にいつまでも子供たちが帰らないで、声ばかり聞こえて来たことを、先でどんな風に思いだすだろうか」すると、彼の眼の前で暗くなりかけてゆく谷間がいったい現実のものなのか、もうこの世には無いものを思い出そうとした時に彼の心に浮ぶ幻の景色なのか、分らなくなるのであった。(庄野潤三「夕べの雲」)
「過去の大浦」へ思いを寄せる「未来の大浦」は、実は「現在の大浦」である。
同じような表現は「ムカデ」にもある。
このようにして彼等はムカデ馴れのした夫婦になり、次第に年を取って行く。子供はみんな大人になって、家にいなくなり、昔、テレビの西部劇をみていた時、知らぬ間に壁の真中あたりでツイストのような身振りをしていた大ムカデがいて、びっくり仰天したことも、とっくに記憶の彼方に沈んでしまっていることだろう。(庄野潤三「夕べの雲」)
『夕べの雲』では、こうした時の流れが、物語上の大きな柱となっている。
あるいは、大阪から東京郊外への移住という地理的な移動さえも、庄野文学の中では、過去から現在へと続く時間的な移動の中に飲み込まれてしまうのかもしれない。
ここにも『夕べの雲』の懐かしさの理由がある。
一家を背負う父親の覚悟の物語
この作品最大の特徴は、移住や時の流れといった大きな主題が、五人家族の日常生活を通して語られている、というところにある。
『夕べの雲』の登場人物は、大浦夫妻と晴子(高校二年生)・安雄(中学生一年生)・正次郎(小学三年生)という五人家族。
庄野一家をモデルにした、この大浦一家の物語は、特別のストーリーこそないものの、生きることの味わい深さを、丹念に浮かび上がらせている。
例えば「コヨーテの歌」には、「進めラビット」という子ども向けのテレビ番組を息子たちと一緒に楽しんでいる父親が、テレビアニメの登場人物に、自分の人生を重ね合わせてみる場面がある。
中年に達した大浦のような男が、ラビットとタイガーの運命に一喜一憂するのは、漫画の世界の出来事でありながら彼等がいつも旅をしているという一点で、どこかわれわれの送っている尋常な人生に似ているところがあるからであった。(庄野潤三「夕べの雲」)
おそらく、大浦の頭の中にあったのは、大阪から東京までやってきた自分の人生だろう。
外房州へ海水浴に行ったときの思い出は「終りと始まり」に出てくるものだ。
いま「海草しらべ」をやっている正次郎は、三つの年にここへ来たが、最初の晩に、「さあ、もうお家へ帰ろう」といい出した。「ここへ泊るのよ」といわれても、この子にはその意味が分らなくて、「帰ろう。帰ろう」という声が、だんだん泣き声になって来た。(庄野潤三「夕べの雲」)
このエピソードは、短篇小説「蟹」(『静物』所収)にも登場するものだが、子どもの泣き声を聞きながら、大浦は「自分たちはどこにも住む家がなくて、この町からあの町へ、あの町からこの村へと旅を続けている宿無しの一家のような気がして来るのであった」と回想する。
あるいは、子どもの「帰ろう。帰ろう」という声は、生田の山に棲み始めたばかりの頃の、庄野さんの気持ちを投影したものではなかっただろうか。
一家の責任者として家族を背負い、山の上の一軒家で暮らす中年男性の不安が、ここにはある。
「大きな甕」に現われてるのも、新しい土地で暮らす主人公の不安だ。
しかし、そんな家にいる人は、どこかへ引越すことなんか、一度も考えずに、心静かに暮している筈であった。人が家に住むというのは、もともとそういうものではないか。年月とともに屋根の瓦も柱の色も古びてゆくように、住む人も古びてゆく。(庄野潤三「夕べの雲」)
結局のところ、僕は『夕べの雲』という小説を、中年男性の覚悟の物語として読んだ。
それは、故郷を離れて、東京郊外の山の上で暮らし始めた男の覚悟であり、会社員を辞めて、作家として食べていかなければならない男の覚悟である。
退路を断って生きようとする男の覚悟が、この『夕べの雲』という物語であって、そういう文脈の上で、僕は、江藤淳の言った「父性の文学」という言葉の意味を理解することができたような気がする。
「前のひげ根のことは思わず、ここで少しでも早くひげ根を下すことを考えた方がいい」と、大浦は考えている(「萩」)。
『夕べの雲』で頻繁に登場する庭木の話は、やはり、山の上での定着を目指す主人公の投影であって、庭木の不安は、そのまま大浦自身の不安でもある。
庭木が根付いたときこそ、大浦がこの地に根付いたことを意味するのだとしたら、株分けされた浜木綿は、生田の山の家を象徴する存在ということだったのだろう。
井伏鱒二や河上徹太郎の思い出
この『夕べの雲』という長篇小説くらい、広がりを持つ作品は珍しい。
例えば、「コヨーテの歌」は、庄野さんが河上徹太郎の思い出を語る時、頻繁に引用されたもので、庄野一家が河上家を訪れたとき、楽しい夕餉の団欒の中で、庄野さんは上の子に命じて「コヨーテの鳴き声」を出させたという。
小学五年生の上の子に命じて「燈台守」を歌わせ、夜ふけの森にひびくコヨーテの鳴き声を四回も出させた上に、長女と妻には「逝きしユーラリ」などの二重唱をさせ、自分も学校時代に覚えた英語の「いとしのクレメンタイン」を久しぶりに歌った。(庄野潤三「山の上に憩いあり」)
日本テレビ系列『ディズニーランド』の「コヨーテの腹ぺこ物語」は、1962年(昭和37年)10月19日に放送された。
庄野さん41歳、長男・龍也は小学四年生、次男・和也が小学一年生のときである。
「若いころから外国の一流の演奏家に接して来た河上さんも、コヨーテの鳴き声を聞かされるのははじめてだから、さぞかし面喰ったに違いない」と、庄野さんは当時を楽しく回想している。
コヨーテの鳴き声で大いに盛り上がった河上さんは、アヤ夫人と二人でピアノの連弾を始めるのだが、「河上と連弾をしたのは何十年ぶりです。この家始まって以来のことです」という夫人の言葉が、この夜の賑わいぶりを表していると言えるだろう。
「大きな甕」に登場する<飯沼さん>は、もちろん井伏鱒二だ。
井伏さんが、庄野夫人に「すり鉢のかけら」を贈る話は、井伏さんの名随筆「庄野君と古備前」に詳しく紹介されている。
それから数日たって、庄野君の奥さんから丁重な手紙が来た。先日は珍しい半地上窯の擂鉢の破片を頂戴して有難いという前文で、「しかし庄野はあの破片をよこしません。あれを机の上に置いて原稿を書き、夕食のときには、あれを洗ってレタスにヌタを盛ったのを置いてお酒を飲みます」と云ってあった。(井伏鱒二「庄野君と古備前」)
大きな甕を入手する経緯が、庄野さんの受けとめと少々異なっているところも楽しい。
「松のたんこぶ」に出てくる中国の昔話(蛇使いのこと)は、『エイヴォン記』(1989)で詳しく語られていて、庄野さんの読んだ本は、新日本少年少女文庫の『志那文学選』(佐藤春夫編、新潮社)だったことが分かる。

実際の体験を素材としているから、どこかで聞いたような話が、別の話の中に突然飛び出してくることも珍しくないが、生田時代の原点を綴った『夕べの雲』には、後年まで繰り返し語られるエピソードが多かった。
まだanan増刊だった頃の『クウネル』のインタビューで、庄野さんは、『夕べの雲』について触れている。
「たぶん、『夕べの雲』というのがね、私の大きな転換点だと思うんですけどもね。ここに引っ越してきて、家のまわりの木がつぶされていくのを、子供たちと一緒に惜しんで、眺めてきたのがこの本のいちばん大きなモチーフだったんです」(『クウネル』(2002/11/15))
不安を抱えながら始まった山の上の生活は、やがて生田の地に根付き、多くの花を咲かせた。
なにしろ「細君にとっては二十分なんていうものではない」山の上である。
「行けども行けども、まだ現れない」というこの土地で彼らが根付くまでに、どれだけの苦労があっただろうか。
庄野さんは、その苦心を、おもしろおかしい話として『夕べの雲』に綴った。
雷が落ちたことも、大きなムカデに刺されたことも、安雄が学校で大怪我をしたことも、すべては懐かしい思い出だ。
そして、いつか懐かしい思い出になるだろうことを踏まえた上で、庄野さんは1964年の「いま」を描いていたのである。
多くの書評がある『夕べの雲』の中で、忘れることができないものが、小沼丹の書いた文章だ。
「夕べの雲」が大浦一家の幸福な家庭生活を描きながら、静かな感銘を残すのはそのためかもしれない。いまあるひとときを、喜び生きている家族の姿が美しい余韻を残す。「夕べの雲」は静かな作品である。夕暮、どこからか、静かな合唱の声が聞えて来る。そんな感じがある。それは敬虔でつつましい人生讃歌のようでもある。(小沼丹「夕べの雲」あとがき・講談社文庫)
庄野さんの歌う人生讃歌は、山の上に生きていくことを覚悟した男の開き直りである。
『夕べの雲』は、決して、ただ平穏で楽しいだけの物語ではない。
男の開き直りを、こんなにも柔らかくて温もりのある物語として描くことのできるところにこそ、庄野潤三という作家の価値があるのだ。
書名:夕べの雲
著者:庄野潤三
発行:1988/04/10
出版社:講談社文芸文庫