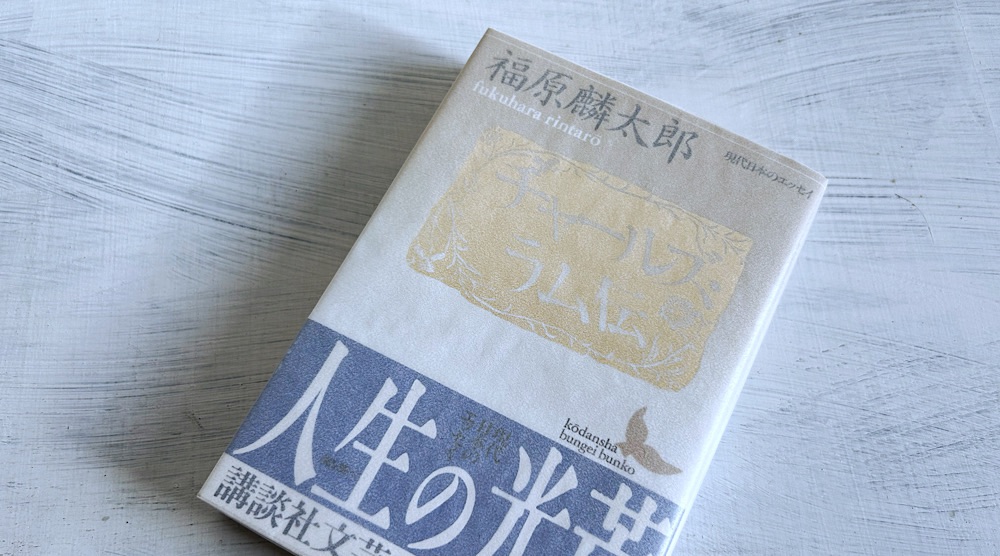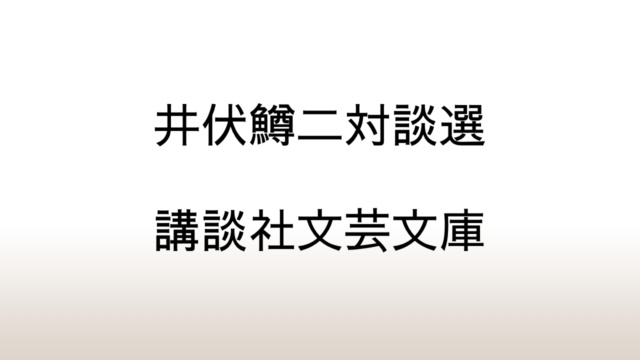福原麟太郎「チャールズ・ラム伝」読了。
本作「チャールズ・ラム伝」は、1959年(昭和34年)4月から1964年(昭和39年)5月にかけて『声』及び『学燈』に連載された人物評伝である。
単行本は、1964年(昭和39年)10月に垂水書房から刊行されている。
この年、著者は70歳だった。
1964年(昭和39年)、読売文学賞受賞。
「古なじみの顔」と「われ愚人を愛す」
英文学者でもあった小沼丹の小説では、チャールズ・ラムが引用されることが多い。
栗拾いは中止して、家に這入って新聞を見ると、林さんの写真が載っていた。眼が細くて、笑っている顔だなと思う。新聞を読んで、ぼんやり庭の方を見ながら、いろいろ昔のことを想い出していたら、四十雀が一羽飛んで来て、木蓮の枝にちょんと止った。(略)不意に、「──みんなみんな、いなくなった」と云う悉皆忘れていた懐かしい詩句が甦ったから不思議である。四十雀がその一行を咥えて来たのかしらん?(小沼丹「四十雀」)
鎌倉文士・林房雄の思い出を綴った「四十雀」では、チャールズ・ラムの「古なじみの顔」という詩が引用されている。

福原麟太郎の『チャールズ・ラム伝』によると、「古なじみの顔」は、ロイドと共同で作った詩集『無韻詩集』(1798年)に発表されたものだった。
どこへ行ってしまったのだ。あの古なじみの顔は。
遊び友達があった。仲間がいた。
子供の頃の話だ。楽しい学校の日々だった。
みんな、みんな、いなくなった。古なじみの顔が。
チャールズ・ラム「古なじみの顔」
このとき、チャールズ・ラムは22歳で、まだ文学者と呼ばれるほどの業績もなく、東印度会社の会計係として働く、文学好きの一人の青年に過ぎなかった。
ただし、彼の周囲には、サミュエル・テイラー・コールリッジやウィリアム・ワーズワスといった若き詩人たちが登場し始めていたから、彼の文学的環境は整い始めていたということができる。
1775年生まれのチャールズ・ラムは、1770年生まれのワーズワスや1772年生まれのコールリッジ(『クーブラ・カーン』)、1774年生まれのロバート・サウジー、1775年生まれのジェイン・オースティン(『高慢と偏見』)などと同時代に活躍した、イギリスの作家だった。
1771年にはトマス・グレイ(『墓畔の哀歌』)が他界し、ラムやオースティンの生まれた1775年には、オリヴァー・ゴールドスミス(『ウェイクフィールドの牧師』)が亡くなっている。
少し先の世代には、1757年生まれのウィリアム・ブレイク(『ミルトン』)がいて、少し後の世代には、1788年生まれのジョージ・ゴードン・バイロン(1824年に36歳で逝去)や、1795年生まれのジョン・キーツがいた(1821年に25歳で逝去)。
ラムはキーツを買っている。そして「聖アグネスの前夜」をほめ、ワーズワスに次ぐ詩人だと言っている。しかしキーツはラムの悪洒落や地口に閉口している。(福原麟太郎「チャールズ・ラム伝」)
ちなみに、ラムの実兄が脚を怪我したときに診療した医師は、1784年にサミュエル・ジョンソン(『英語辞典』)の臨終を看取ったクルークシャンク先生だったという。
そんな時代に生きたチャールズ・ラムは、決して、現代的な作家とは言えないかもしれないが、姉メアリー(11歳上だった)と共同で執筆した『シェイクスピア物語』(1807年)は、現在も岩波少年文庫から入手可能だし、ラムの代表作である『エリア随筆』も、岩波文庫で読むことができる(2022年に南條竹則の新訳が出た)。

メジャーな人気作家とは言えないまでも、チャールズ・ラムは、我が日本にも、しっかりと根を下ろした実力派の作家と言っていいわけだ。
本作『チャールズ・ラム伝』は、そんなチャールズ・ラムの生涯を、日記や手紙などから綴った、本格的な人物評伝である。
特徴的なのは、作品解説のほかに、著者(福原麟太郎)の思い出なども交えた、評伝エッセイとも言うべき充実した内容となっていることだろう。
無味無臭のいわゆる偉人伝とは違って、この『ラム伝』は、福原麟太郎のエッセイ集として読むことができる、味のある作家評伝なのだ。
福原さんのチャールズ・ラム観は、「われ愚人を愛す」という一語に象徴されることが多い。
しかし、「私はバカが好きなのです」という。それは「萬愚節」という随筆だ。人間はおろかなるこそ人間らしけれ、という。おそらくラムの思想はここに極まっているであろう。そういう愚の哲学がラムのエピキュリアニズムとストイシズムとを包んでいる。(福原麟太郎「チャールズ・ラム伝」)
「萬愚節」は、ラムの代表作『エリア随筆』に収録されたエッセイである。
人間の弱小感を押しつめてゆくと、弱小なるところに人間同士の同情が沸く。(略)人はみな死ぬものであるという、諸行無常の思想に到達してしまうこともできる。そのような無常観をうしろにして、人はみな馬鹿であるという見方が成立する。(福原麟太郎「チャールズ・ラム伝」)
「それは悲しむべきではなく、だから人間はお互いにいとしいものである」というのが、この「萬愚節」の趣旨だった。
ちなみに「萬愚節(ばんぐせつ)」は「エイプリルフール(4月1日)」のことで、チャールズ・ラムの人間肯定の姿勢が、そこには示されている。
「われ愚人を愛す」のフレーズは、福原麟太郎の晩年を代表する座右の銘ともなった。
はかない人生への慈しみ
「エリア氏によって書かれたエッセイ」という意味を持つ「エリア随筆」を、創刊間もない『ロンドン雑誌』に連載し始めたとき、チャールズ・ラムは45歳だった。
エリアという筆名は、かつて南海会社で同僚だったイタリア人の名前を勝手に使ったものだが、この「Ellia」は、「エライア」とか「イーリア」「イライア」などと発音すべきものであったかもしれないという指摘もあるらしい。
福原麟太郎が師・岡倉由三郎の随筆集を編纂したときのタイトルは『イーリア随筆』だった。
その手紙には「誰にもエリアは全く謎の人で、あらゆるところで話題になり、みんなが正体を見つけてやろうと思っていながら解らなかったものです」と書いてある。エリアは今われわれが想像する以上に世上の評判に上っていたらしい。(福原麟太郎「チャールズ・ラム伝」)
ラムの「エリア随筆」は、「身辺に起こった何かを材料にしていた」もので、こうした手法は、明治時代の日本文壇にも影響を与えたという。
むかし平田禿木氏が、ラムがね、エリア随筆に書いたと同じような材料を使って、わたしの思い出にある身辺のことを書いてみたらと思っているのです、と言われたことを想起するのである。事実、禿木氏はその幾つかの随筆にその方法を使われたのであった。(福原麟太郎「チャールズ・ラム伝」)
当時、日本では、岡倉由三郎や平田禿木、戸川秋骨などの英文学者たちが『エリア随筆』の邦訳に取り組んでいて、本作『チャールズ・ラム伝』においても、彼らの翻訳による『エリア随筆』を引用の形で読むことができる。
ちなみに、若き日の平田禿木と戸川秋骨は、島崎藤村の親友であり、藤村の自伝的小説『春』にも登場しているところが興味深い(福原さんも『春』を愛読していたと、エッセイに書いている)。
https://gentle-land.com/shimazaki-toson-haru/
「除夜」で「年も取らず、友達も変らず、若返らず、富まず、品良くもならず、ただこのままに生きたい」と綴ったラムは、1834年、59歳の年に、転んだ怪我が元で急死した。
墓碑文のために書かれたワーズワスの詩は長すぎたために、教会内の円形浮彫像(メダリヨン)の下の銘中に刻まれたという。
やさしきエリア、沙翁物語の著者、チャールズ・ラムを記念す。(略)善人世にありとすれば彼こそはその人。(福原麟太郎「チャールズ・ラム伝」)
ラムが亡くなる少し前に、学生時代からの親友コールリッジが他界している(62歳)。
ラムは葬式にはゆかなかったが、後日コウルリッヂの住んでいたハイゲートの家へ弔問に出かけた。その淋しさは忘れられず、時々不意に、談話の間にも「コウルリッヂは死んだ」と独語するようになった。(福原麟太郎「チャールズ・ラム伝」)
一つの時代の終わりを告げるようなエピソードだと思う。
チャールズ・ラムの評伝を中心に据えながら、一つの時代のイギリス文壇を描いているとも言えるかもしれない。
親友のランドル・ノリスが死んだとき(1827年)、その悲しみをラムは、クラッブ・ロビンソンに宛てた手紙に綴っている。
僕も老いて来たけれど、ノリスの眼には僕など昔なじみの子供なのだ。彼は一生僕をチャーリーと呼んだ。もう僕をチャーリーと言ってくれる人はいない。(福原麟太郎「チャールズ・ラム伝」)
「もう僕をチャーリーと言ってくれる人はいない」と綴った感性は、名詩「古なじみの顔」にも通じるものであり、こうしたはかない人生への慈しみの思いは、小沼丹の小説に書かれている主題と、同様のものだと言うことができるだろう。
これは、チャールズ・ラムの評伝的紀行『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』(1984)をまとめた庄野潤三にも共通するところである。

結局のところ、庄野潤三や小沼丹の読者は、チャールズ・ラムを避けて通ることはできないし、そのためにも、福原麟太郎の『チャールズ・ラム伝』は必携の書ということになるんだろうな。
庄野潤三や小沼丹の作品を読んだ後で、この『チャールズ・ラム伝』を読んでみると、理解の深まる部分が多いのでおすすめ。
作品名:チャールズ・ラム伝
著者:福原麟太郎
書名:福原麟太郎著作集4「評伝チャールズ・ラム」
発行:1968/12/25
出版社:研究社