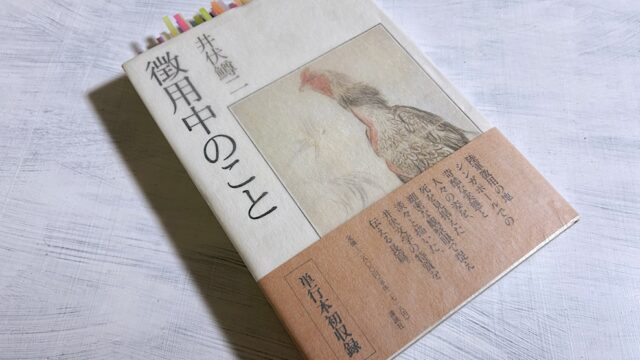庄野潤三「相客」読了。
本作「相客」は、1957年(昭和32年)10月『群像』に発表された短篇小説である。
この年、著者は36歳だった。
作品集としては、1960年(昭和35年)に講談社から刊行された『静物』に収録されている。
講談社文芸文庫では、富岡多恵子編集『大阪文学名作選』にも収録された。

戦犯の容疑者となった庄野英二
1957年(昭和32年)8月、庄野さんは夫人とともに横浜港を出発した。
『ガンビア滞在記』の舞台となるアメリカのオハイオ州ガンビアへ向かうためである。

だから、この「相客」は、出発直前に執筆された作品ということになるらしい(その直後の『群像』に掲載されているので)。
主人公は、次兄の庄野英二(と思われる男性)である。
兄は童話や童話劇の原稿を書いていた。その方面の仕事に兄は情熱を持っていた。私は今でも兄に対して悪かったと思うが、この時期の兄を捉えていた情熱に対して理解が少なかった。(庄野潤三「相客」)
次兄がレバノン島から復員したのは、その前の年の初夏だった。
南方の孤島で俘虜生活を送っていた次兄は、乏しい食事とマラリヤのため、ひどく痩せて帰ってきたのだ。
兄が帰って来た時、家には長兄夫婦と私の夫婦とがいた。私は二番目の兄が帰って来る半年前に結婚していた。妹と弟がいたが、二人は父と母が住んでいる、大して遠くはない疎開先の家にいて、時々こちらにも来た。(庄野潤三「相客」)
庄野さんが、浜生千壽子と結婚したのは、1946年(昭和21年)1月のことだから、この物語は、終戦の翌年(1946年)の初夏の頃の庄野家を舞台にしたものだと考えていい。
長兄は会社勤めをしていて、物語の語り手である<私>も学校勤めをしていたが、二番目の兄は定職に就かず、童話の原稿などを書いて暮らしていたという。
1945年(昭和20年)10月、復員した庄野さんは、大阪府今宮中学校の歴史教師として就職している。
そんな生活が一年近く続いた頃、次兄が警察に連れて行かれるという事件が起こった。
ジャワのチラチャップにある俘虜収容所で副官をしていた次兄は、戦犯の容疑者として取り調べを受けるために、東京の巣鴨拘置所へ入ることとなったのだ。
父の知人の交渉によって、家族のうちの一人が、特別に巣鴨まで見送りに行けることになった。
この物語は、<私>(つまり庄野潤三だろう)が、刑事に連行された次兄に付き添って、巣鴨まで同行したときの体験を素材として描かれた作品である。
大阪発東京行の急行列車には、次兄と一緒に見知らぬ男が、刑事に連れられて乗車していた。
命令を出したのは自分でないことが立証されればいいがと云う風に云った。私はその話を聞いた時、「大変なことに関わり合ったものだ。この人は何という運の悪い人だろう」と思わずには居られなかった。(庄野潤三「相客」)
物語は、東京へ向かって走る列車の中で、食事をしている場面で終わる。
ここに登場する次兄は、後の庄野文学では「英二伯父ちゃんの薔薇」の贈り主として親しまれることになるが、戦後間もない頃の庄野家には、こんな事件もあったのだ。
悲しみの中のユーモアを描く
作品タイトルの「相客」は、次兄と一緒に同乗している男性のことを示しているが、このタイトルは同時に、イギリスの作家ガーディナーが書いたエッセイ「ア・フェロー・トラヴェラー」に対するオマージュともなっている。
その時、彼は誰もいないと思っていた箱の中に、一人だけ客がいたのを発見する。その相客というのは、一匹の蚊だ。(庄野潤三「相客」)
庄野さんは、学校時代に教科書で読んだ、このイギリスのエッセイに、生涯に渡って大きな影響を受けることになったらしい。
そのことを顕著に示す文章が、冒頭にある。
本人が真面目であるのに、物事がちぐはぐにうまい具合に行かないのを見る時には、滑稽な感じを伴うものである。それにそういうことは、貧乏な人間と金持とでは、貧乏な人間の方に起りやすいように思われる。(庄野潤三「相客」)
「真面目な中にある滑稽な感じ」は、やがて、庄野文学の大きなテーマとなった。
イギリス文学では、それをヒューマーと呼ぶ。
例えば、戦地から復員してきたときに、次兄がこんな話をした。
ラジオで、毎朝、女の人が「グッド・モーニング・ツー・ユー」という歌をうたっていた。兄は何かの時にそのことを知って、「そうか。雲に露、というのは、変った歌だなあと思っていた」と私に云った。(庄野潤三「相客」)
この話を聞いて<私>は笑うが、兄が外地で俘虜として生活していたことを考えるとき、この笑い話には、滑稽なだけではない悲しみが付きまとう。
物語の冒頭で、本編とはまったく関わりのないオールナイト食堂の話が出てくるのも、こうした悲しみの中のユーモアを予兆させるものだ。
オールナイト食堂で弟が聞いた話は、同じ好き嫌いでも、違った印象を与える。私はそれを聞いた時、悲しい気持がしたが、悲しい気持だけではなかった。(庄野潤三「相客」)
本作「相客」で大きなテーマとなっているのは、悲しみの中にあるユーモアである。
巣鴨へ向かう列車に同乗している相客は、軍隊にいる間に、飯を肴にして酒を飲む習慣が付いてしまったという。
「もっとウィスキーを上って下さい」飛行場大隊長をしていた人がいくらも飲まないうちに飯の方に箸をつけ出したのを見て、私は云った。すると、その人は、「いや、頂きます」と云って、私のついだグラスを受け取ってから、「私は軍隊にいる間に、メシをさかなにして酒を飲むくせがついてしまいましてね」そう云いながら、ちょっと恥ずかしそうに笑った。(庄野潤三「相客」)
「メシをさかなに酒を飲む」というのは、男にとって笑い話のつもりだったのかもしれない。
しかし、彼らが今、戦犯の容疑者として護送されている途中であることを考えるとき、この笑い話には滑稽なだけではない悲しみがある。
おそらく、庄野さんは、次兄の戦犯事件を、正面から描くことはできなかったのだろう(それは、庄野家にとって、あまりにも辛すぎる体験だったから)。
相客にピントを合わせつつ、描かれているのは、東京へ向かう次兄の不安であり、大阪に残されている家族の不安である。
「英二伯父ちゃんの薔薇」とは、作風がすっかりと異なっているが、この頃の庄野文学のレベルの高さは凄い。
何か、他人を寄せ付けない才能といったようなものを感じさせる鋭さがある。
結局のところ、こういう時期を通ってきたからこそ、晩年の庄野文学があるということなんだろうな。
作品名:相客
著者:庄野潤三
書名:プールサイド小景・静物
発行:2002/05/25 改版
出版社:新潮文庫