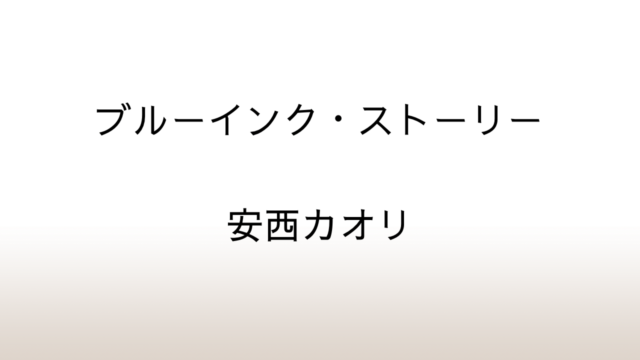森恭三「滞欧六年」読了。
本書「滞欧六年」は、1959年(昭和34年)に刊行されたエッセイ集である。
この年、著者は52歳だった。
1959年(昭和34年)4月から『朝日ジャーナル』に連載されたものが中心となっている。
戦後昭和のヨーロッパ見聞録
タイトルから分かるように、本書は、朝日新聞のヨーロッパ総局長だった著者が、6年を超えるヨーロッパ勤務によって得られた知見を綴ったものである。
海外旅行がまだ難しかった時代の、ヨーロッパ見聞録と言っていい。
例えば、イギリスのロンドンで、著者は貧民街を訪れている。
最初のロンドン滞在は、1939年(昭和14年)秋から1940年(昭和15年)春までで、貧民街であるイースト・エンドを訪ねる日本人は、ほとんどいなかったという。
そこへ行ってみると、人々は、レストランともいえないような屋台店のようなところで、ジャガイモを油であげたのを(ポテト・チップスという)新聞紙にのっけて食べていた。フィッシュ・アンド・チップスは、いまでも最も安い、最も代表的なイギリス大衆の食物だが(今日では、食物を新聞紙につつむことは絶対にしない)、そのころイースト・エンドでは、こんな安い屋台店でも、魚を食う人はわりにすくなかったように思う。(森恭三「滞欧六年」)
ところが、1952年(昭和27年)にロンドンを再訪したとき、イースト・エンドは、四階から八階くらいの労働者住宅が続々と建つ街へと変貌していた。
第二次世界大戦を経て、イギリスも大きな変化の中にあったのだろう。
街の光景だけではなく、日本とイギリスとの文化の比較もある。
読書に対する日英の違いはおもしろい。
わたくしが接したイギリスのインテリは、びっくりするほど読書している。だが、かれらの家庭にまねかれて、気がつくのは、蔵書がすくないことだ。それでは、いったい、どうして読書するのか? 答は簡単だ。第一の方法は、図書館から本を借り出すことである。(森恭三「滞欧六年」)
日本のインテリは経済力に比例しないような、大きな蔵書を持っている(そのくせ、読まずにツンドク)。
書籍を所有することよりも、読書を重視する。
どちらが大人の文化と言えるかは言うまでもない。
古いエッセイ集から見えてくるもの
イギリスでは、夏の休暇が重要である。
夏、休暇をとって陽にあたることが、健康を保持するのに、絶対に必要なのだ。クリスマスが終ると、たいていの人ははやくも夏の休暇の計画をたてる。ホテルなど何カ月も前に予約してしまう。仕事のために旅行するといっても、汽車や飛行機など特別の便宜をはかってくれないが、休暇だというと、優先してくれる。休暇といえば旅行であり、目的地に着くと、朝から晩までなにもしないで、日なたぼっこする人が多い。(森恭三「滞欧六年」)
これは、1959年のエッセイ集だから、60年以上前に書かれたものということになるが、60年経っても、日本はイギリスに追いついていない。
文化というよりも、もはや国民性の違いということなのかもしれない。
売春婦の存在についての考察もおもしろい。
ロンドンは、世界でももっとも売笑婦の多い町である。といって悪ければ目につく町だ。マルクスがそこに住んで、毎日、大英博物館の図書室に通ったというソホーとよばれる一帯は、ピカデリーに近いが、大げさにいえばロンドンの暗黒街で、この町角に立つ女たちは一番安いとされている。(森恭三「滞欧六年」)
こうした娼婦には、アイルランド出身者が多かったらしい。
一方で、客の大部分がイギリス紳士だというところが、いかにも皮肉である。
古いエッセイ集を読むと、古い時代の文化を知ることができる。
そこから大切なものが見つかるということもあるのではないだろうか。
書名:滞欧六年
著者:森恭三
発行:1959/11/15
出版社:朝日新聞社