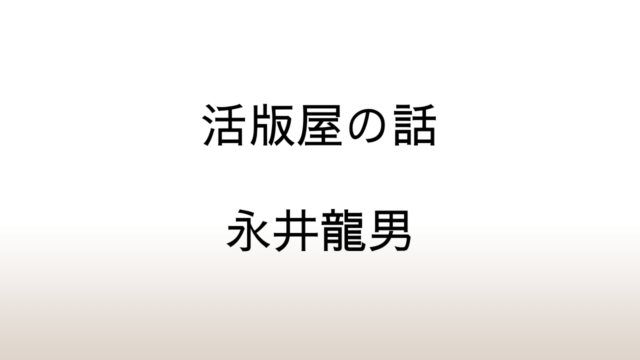フョードル・ドストエフスキー『悪霊』読了。
本作『悪霊』は、1873年(明治6年)に刊行された長編小説である。
この年、著者は52歳だった。
初出は、1871年(明治4年)~1872年(明治5年)『ロシア報知』(連載、一部休載あり)。
ドストエフスキーの五大長編の1つで、3番目に書かれた作品である(『罪と罰』『白痴』『悪霊』『未成年』『カラマーゾフの兄弟』)。

革命思想を徹底的に否定する物語
村上春樹は、ドストエフスキーの『悪霊』を高く評価している。
この前、久し振りにドストエフスキーの『悪霊』を読み返してみたんです。いやぁ、やっぱりいいですね。小説としては、そんなに完全な小説ではないというか、『カラマーゾフの兄弟』に比べれば、構成としてはいくぶん落ちる小説だと思うんですが、読んでいて、この振り回され方というのはやはりすさまじいものだなと思いました。(インタビュー「『海辺のカフカを中心に』」/村上春樹『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』所収)
ドストエフスキーの中でも、『カラマーゾフの兄弟』と『悪霊』は、特別な存在だったらしい。
『白痴』や『罪と罰』なんかは作品にまだ、ちょっと書き残しているところはありますけど、『悪霊』とか『カラマーゾフ』になると、もうそんな範疇じゃないですもんね。もともと連載小説として書かれたものだから、ところどころバランスは悪いところはあるし、完璧な作品とは言えないかもしれないけど、作品総体としては、もう言うことないですよね。(インタビュー「るつぼのような小説を書きたい」/村上春樹『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』所収)
『悪霊』や『カラマーゾフの兄弟』の魅力は「総合小説」であること。
それで、僕はそういう小説に、仮の名前として「総合小説」という呼び名を付けてみたんです。総合小説って言葉は、人それぞれずいぶん違うコンセプトで使っているので、あるいは誤解されるかもしれないけど、僕の考える「総合小説」っていうのは、とにかく長いこと、とにかく重いこと。そしていろんな人物が、特異な人から普通の人まで次々に登場してきて、いろんな異なったパースペクティブが有機的に重ね合わされていく小説であること。(インタビュー「るつぼのような小説を書きたい」/村上春樹『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』所収)
「長くて重い」ということは、ともかく、ポイントは「いろんな人物が、特異な人から普通の人まで次々に登場してきて、いろんな異なったパースペクティブが有機的に重ね合わされていく小説である」ということだろう。
なぜなら、これは、本作『悪霊』を読むときの、ひとつのヒントになっていると言えるからだ(特に「いろんな異なったパースペクティブが有機的に重ね合わされていく」という部分に注目)。
本作『悪霊』のストーリーの中心になっているのは、革命思想に憑りつかれた若者たちのグループが、仲間割れを起こして崩壊していく過程を描いた「自滅の物語」である。
シャートフはとつぜん、短い、絶望的な叫び声をあげた。だが、叫びは言葉にならなかった。ピョートルは、彼の額にじかに、正確にしっかりと拳銃をあて、ぐいと強く押しつけるようにして引き金を引いた。(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
革命思想から距離を置こうとした被害者(シャートフ)は、見せしめのために殺された(「シャートフ、そんなことをするとあなたのためになりませんよ!」)。
正確に言うと、一人の裏切り者を共謀して殺すことで、首謀者(ピョートル)は、仲間たちの結束を計ろうとしたのだ(「あなたは、血を膏薬がわりにしてグループを一つにくっつけようとしている」)。
狂った若者たち(五人組)は、悪霊に憑りつかれていたと言えるし、仲間たちを先導する首謀者(ピョートル)は、彼自身が悪霊であったとも言える。
小説『悪霊』誕生の直接のきっかけとなったネチャーエフ事件は、先の皇帝暗殺未遂事件から二年後の一八六九年十一月にモスクワで起こりました。この事件は、ネチャーエフという革命家を指導者とする、とある革命結社から脱退を申し出た大学生が、残った同志たちに殺される事件で、大学生の遺体は、彼が学んでいた農業大学の構内にある池から発見されました。(亀山郁夫「『悪霊』神になりたかった男」)
ドストエフスキーは『悪霊』のエピグラフに、聖書(「ルカによる福音書」)を引用した。
悪霊どもは豚の中に入った。すると、豚の群れは崖を下って湖になだれ込み、おぼれ死んだ。(フョードル・ドストエフスキー『悪霊1』亀山郁夫・訳)
おぼれ死んだ「豚」を、革命思想や無神論に憑りつかれた若者たちだとすると、「悪霊」は(反社会的な)革命思想そのものである。
つまり、本作『悪霊』は、激化する革命思想を否定する物語となっているのだ。
実際、スターリンの時代、『悪霊』は発禁扱いを受けている。
【サラスキナ】ソビエト時代に『悪霊』を個別に出版しようとの唯一の試みは(略)悲しい結果となりました。第一巻のみが出版され、第二巻は、破棄されました。出版は禁止され、すでに印刷された第一巻もほとんどが破棄され、偶然に、何冊かが無事に残ったというのが経緯です。(亀山郁夫、リュドミラ・サラスキナ「ドストエフスキー『悪霊』の衝撃」)
若者たちを洗脳し、民衆を扇動する首謀者(ピョートル)は、「政治的詐欺師」である(「で、ね、ほんとうの真実っていうのは、つねにどこか嘘っぽいところがあるもんなんですよ」)。
村上春樹が「いろんな人物が、特異な人から普通の人まで次々に登場してきて」と言った、「特異な人」の一人が、ピョートルだったとも言える。
彼らの活動によって、街は大混乱となり、次々と人が死んでいく。
これは、まさしく、革命思想がもたらした「社会の崩壊」だったが、彼らの野望が成就することはなかった。
仲間(シャートフ)を殺した後、彼らは、それぞれに自滅の道をたどるからだ。
五人組の一人であるリプーチンは、売春宿でひどく酔っているところを逮捕された。
しばらくのあいだ、彼はスタヴローギンとピョートル・ヴェルホヴェンスキーの行方を追っていたが、とつぜん酒を飲みだし、ありとあらゆる限度を超えたすさまじい放蕩にのめり込んだ。いっさいの常識と自分の立場についての理解を、完全に喪失した男のようであった。(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
秘密結社(五人組)の若者たちは、急進的な思想に溺れやすい「人間の弱さ」を象徴した存在として読むことができる。
同時に、それは「社会の弱さ」でもあり、現代社会にも通じる普遍性の原動力となっている。
石が結わえられ、ピョートルが起きあがると、ヴィルギンスキーはとつぜん全身を小刻みにふるわせ、両手をぱんと叩いて、悲し気に声を張りあげて叫んだ。「こんなはずじゃない、こんなはずじゃない、全然ちがう!」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
シャートフの死体の前で、ヴィルギンスキーは「こんなはずじゃない、こんなはずじゃない、全然ちがう!」と叫んだ。
ヴィルギンスキーの叫びは、本作『悪霊』のひとつの主題として聞こえてくるが、しかし、本作『悪霊』において、真の主人公は、彼ら革命家たちではなかった。
絶望しかないカリスマ
首謀者(ピョートル)に大きな精神的影響を与えた青年(スタヴローギン)こそ、この物語の主人公である。
ところが彼は、それとは正反対に、わたしがかつて出会っただれにもまして優雅なジェントルマンで、身につけているものはとびきり上等、その身のこなしも、洗練のかぎりをつくし、上流社会の交際に慣れている紳士でなければとうてい真似のできない、みごとなものだった。(フョードル・ドストエフスキー『悪霊1』亀山郁夫・訳)
裕福な地主(ワルワーラ夫人)の息子であるスタヴローギンは「たいへんな美青年」で、つまり、財産にも美貌にも恵まれた完璧な若者だったが、彼は、人生と真摯に向き合って生きていくことができない。
彼は、自分自身を傷つけることに喜びを見出すという、自己破滅型の若者だったのだ。
スタヴローギンは、自分を辱めるために、足の悪い女(マリヤ・レビャートキナ)と結婚する(「かのスタヴローギンが、こんな屑みたいな女と結婚するというアイデアが神経をくすぐった」)。
「ほんとうですの? この、足の悪い不幸せな女の方が、ほら、あの方ですよ、あそこにいます、あの方をご覧なさい! あの方が……あなたの正式の妻だというのは、ほんとうですの?」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊1』亀山郁夫・訳)
しかし、スタヴローギンの目的は、自分を貶めることだったから、もちろん、マリヤは幸せな生活を送ることができない。
スタヴローギンは、友人(シャートフ)の嫁(マリヤ・シャートワ)を妊娠させる。
彼女の唇はふるえ、こらえていたが、ふいに体を起こすと、目をぎらぎらさせてこう言い放った。「ニコライ・スタヴローギンは人でなしよ!」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
マリヤ・レビャートキナは、兄(レビャートキン)とともに、脱走囚(フェージナ)に殺され、マリヤ・シャートワは、生まれたばかりの赤ん坊とともに病死してしまう。
正妻(マリヤ・レビャートキナ)が殺された夜、スタヴローギンは、マヴリーキーの嫁(リザヴェータ)と一緒だった。
そのとき、誰かが叫んだ。「そいつだぜ、スタヴローギンの女は!」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
レビャートキン兄妹の殺害現場を訪れたリーザは、狂った群衆に殺されてしまう。
スタヴローギンと関わった若者たちは、次々と死んでいった(「だいたいです、あのお方にとっちゃ、高潔きわまりない娘さんを凌辱したり、他人の奥さんを寝取ったりすることぐらい朝飯前なんですから」)。
修道院で隠居暮らしをしているチーホン主教を訪ねた彼は、自分の罪を告白する(「スタヴローギンの告白」)。
ある女性にはもっとひどい仕打ちをし、そのためにその女性は死んでしまった。目の前で、罪のない二人の命を決闘でうばったこともある。(略)私には一度毒殺の経験がある──意図したもので、まんまと成功し、だれにも知られていない。(フョードル・ドストエフスキー『悪霊2』亀山郁夫・訳)
しかし、スタヴローギン最大の罪は、少女(マトリョーシャ)の首吊り自殺に象徴されていた(「まだ分別もできていない、無力で、十歳の生きもののみじめな絶望!」)。
こんな小さな子どものくせに、と思い、憐れみの念から不快でたまらなくなったのだ。しかし私は、ふいに襲ってきた恐怖の感情をおさえ、その場に留まった。いっさいが終わったとき、彼女はもじもじしていた。(フョードル・ドストエフスキー『悪霊2』亀山郁夫・訳)
やがて、スタヴローギンは、少女(マトリョーシャ)の亡霊(悪霊)につきまとわれるようになる。
「いや、何もかもばかばかしい、ほんとうにばかばかしい話だ。なにしろ、これはいろんな形をしたぼく自身で、それ以外の何ものでもないんですからね」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊2』亀山郁夫・訳)
マトリョーシャの亡霊は、スタヴローギンの中に潜む「悪霊」を具現化した存在だ。
「ひとつまじめに、堂々と申しあげておきますがね、僕は悪霊を信じているんですよ、完全に信じています、個人的実在としてね」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊2』亀山郁夫・訳)
このとき、チーホン主教が示したフレーズ(黙示録からの引用)は、本作『悪霊』の根幹をなす重要なモチーフとなっている(「ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ」)。
「あなたは、冷たくもなく熱くもない。むしろ、冷たいか熱いか、どちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく、なまぬるいので、わたしはあなたを口から吐き出そうとしている」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊2』亀山郁夫・訳)
このフレーズは、後に、旅に出たピョートルの父親(ステパン・ヴェルホヴェンスキー)と福音書売りの女(ソフィヤ)との間でも繰り返されるものだ(ヴェルホヴェンスキーは「信仰の冷めた人間=なまぬるい人間」として描かれている)。
高い知性と裕福な財産を持つスタヴローギンが、同世代の若者たちへと与える影響は大きい。
「もっとうまい手段があります。つまり、サークルのメンバー四人をそそのかし、残りの一人のメンバーを、密告の怖れありとかなんとか言って殺させるんです。そうしたら、あなたは、たちまち四人をがっちり結束させられる、流された血で縛るんですよ。連中はあなたの奴隷になって、反抗するどころか、説明すら求めなくなる。は、は、は!」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊2』亀山郁夫・訳)
秘密結社(五人組)の首謀者(ピョートル)には、スタヴローギンの影がある。
ピョートルは、その事実を憎々しく思いながら、彼の存在を否定することができなかった(ここに「ピョートルの弱さ=スタヴローギンの強さ」がある)。
「ぼくは殺してはいません、そのことに反対していました。でも彼らが殺されることはわかっていました。それでも、人殺しどもを止めようとしなかった。ぼくから離れてください、リーザ」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
すべての破滅こそ、スタヴローギンの求めるところだった。
ここに、スタヴローギンという若者が憑りつかれた「悪霊」(=ニヒリズム・虚無主義)がある。
「ああ、見える…目に見える…」チーホンは悲痛な表情を浮かべ、魂をつらぬくような声で叫んだ。「かわいそうに、破滅した若者よ、あなたは、いまこの瞬間ほど、そら怖ろしい犯罪の近くに、立っておられたことはありません!」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊2』亀山郁夫・訳)
修道院を訪ねたスタヴローギンは、チーホン主教に許しを求める(「ぼくを苦しめてくれ、ぼくを罰してくれ、ぼくに憎しみをぶちまけてくれ」)。
「聞いてください、チーホン神父、ぼくですよ、自分で自分を許したいんです。これが最大の目的、目的のすべてです!」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊2』亀山郁夫・訳)
生きていることの葛藤が、スタヴローギンにはある。
自分の中に巣くう「悪霊」に、スタヴローギンもまた抗うことができなかったのだ。
ウリー州の市民は、ドアの真うしろにぶらさがっていた。テーブルには、鉛筆でしたためた紙きれが載っていた。『だれも責めてはならない、ぼく、自身だ』(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
凌辱した少女(マトリョーシャ)と同じように、彼自身もまた、首吊り自殺をして死んだ(「ぼくにはわかっているのです、自分を殺さなくてはならない、卑しい虫けらみたいに」)。
彼の中の「悪霊」を絶つために、スタヴローギンには自殺以外の選択肢は残されていなかったのだ(「どうして、きみは自分で自分を破滅させてしまった? それもこんな醜い、ばかげたやり方で」)。
「そう、これはまさしくぼくたちのロシアそのままじゃないかって。病人から出て、豚のなかに入る悪霊ども、これはね、何世紀、そう、何世紀にもわたって、ぼくたちの偉大な愛すべき病人、つまり、ぼくたちロシアに積もりつもったすべての疫病、すべての病毒だし、ありとあらゆる不浄の輩だし、ありとあらゆる悪霊どもだし、その子鬼でもあるんです!」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
スタヴローギンだけではない。
ロシアという世界に巣くう悪霊を絶つため、作者(ドストエフスキー)は、多くの登場人物を、次から次へと葬らざるを得なかった。
そこに、本作『悪霊』という長編小説が持つ悲劇がある(なにしろ「救い」がない)。
あるいは、彼らの死そのものが、近代ロシアへと捧げる希望のようなものだったのだろうか。
「ぜんぶ放火だ! こいつはニヒリズムなんだ! 燃えているものがあれば、そいつはニヒリズムだ!」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
この長大な物語の底に流れているものは、生まれ変わりつつある祖国ロシアを脅かそうとする、すべての危険思想に対する憎悪だ。
それは、裏を返すと、祖国ロシアに対する深い愛情ということでもある。
「いいや! ぼくらの時代はそんなふうじゃなかった、ぼくらにしても、そんなことをめざしていたわけじゃない。ほんとうにそう、けっしてそんなことをめざしたわけじゃない」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊1』亀山郁夫・訳)
彼らが目指していたものは、ただ、祖国ロシアの幸福だけだったのだ。
『悪霊』の「救い」は『悪霊』という小説そのものだった
本作『悪霊』は、カリスマ的ニヒリスト(スタヴローギン)の影響を背景に、政治的詐欺師(ピョートル)を中心とする革命家たちの自滅を描いた物語だが、そこに付随して、多くのモチーフが語られている。
村上春樹の言葉を使うと「いろんな人物が、特異な人から普通の人まで次々に登場してきて、いろんな異なったパースペクティブが有機的に重ね合わされていく小説である」ということになる。
実際、『悪霊』に登場するキャラクターは、誰もみな魅力的で、一つ一つのエピソードも興味深いものばかりである。
例えば、ピョートルの父親(ステパン・ヴェルホヴェンスキー)は、スタヴローギンの母親(ワルワーラ夫人)に、プラトニックな愛情を抱き続けていた(20年間も)。
「あなたを愛していました!」やがて彼の口をついて言葉が出た。夫人はこれまでいちども、彼の口からこんな言葉が、こんなふうにほとばしり出るのを聞いたことがなかった。(略)「これまでずっと、あなたを愛してきました……二十年間!」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
スタヴローギンの安っぽい恋愛ドラマに比べて、父親世代の愛は高貴で尊い。
死に際の言葉が、ヴェルホヴェンスキーの人生を総括したとき、読者は、物語の冒頭に出てきた、ヴェルホヴェンスキーとワルワーラ夫人との昔話を思い出す(「さっきのあなたの仕打ち、わたし、ぜったいに忘れませんから!」)。
スタヴローギンを崇拝する二人の青年(シャートフとキリーロフ)もいい(彼らはアメリカで一緒に暮らしていたことがある)。
内ゲバ殺人で殺されるシャートフは、この物語で最も人間らしい登場人物だ。
「キリーロフ、ぼくらは、アメリカでいっしょに横になっていたね……じつは、妻がもどってきたんだ……ぼくは……お茶をください……湯沸かし器も必要なんだ」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
シャートフには祖国ロシアの未来が見えるが、そのシャートフが殺されるところに、本作『悪霊』の悲劇がある。
「スタヴローギンの不利になるようなまねは、何もさせませんからね」客を見送りながら、キリーロフがそうつぶやいた。ピョートルは驚いて彼のほうをふり返ったが、なにも答えなかった。(フョードル・ドストエフスキー『悪霊2』亀山郁夫・訳)
同世代の若者たちの価値観は多様で、「なんとか世代」という言葉で安易にくくることができるほどの統一感はない。
その中で、とりわけ自己投影することができた登場人物が、この物語の語り手となっている「わたし」(アントン・ラヴレンチエヴィチ・G)である。
物語を語っているのは、記者のアントン・ラヴレンチエヴィチです。彼は観察者であり、傍観者でもありますが、じつに多くのことを知っていますし、多くのものごとに関心を持っている、いってみれば、作者の腹心の友です。(亀山郁夫、リュドミラ・サラスキナ「ドストエフスキー『悪霊』の衝撃」)
G氏は、ピョートルを中心とする過激な革命家たちとも、ニヒリストのスタヴローギンとも距離を置きながら、事件の推移を(回想的に)綴っていく。
どちらかといえば、彼の視点は、父親世代であるヴェルホヴェンスキー先生に近かったのかもしれない(つまり、祖国ロシアに)。
「だいたい、ぼくたちのあとに出てきた連中が、自分の口からどんな新しいことが言えるっていうんです? それにしても、ああ、何もかも、なんという表現だろう、すべてがゆがめられ、ぐしゃぐしゃになっている!」指で本をこんこんと叩きながら、彼は叫んだ。「ぼくたちが、めざしていたのが、こんな結論だっていうんですか?」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊2』亀山郁夫・訳)
語り手(G君)は、ステパン・ヴェルホヴェンスキーの良き理解者であり、伝記作家としての機能も果たしている。
つまり、この物語は、ステパン・ヴェルホヴェンスキーの評伝を下敷きとした事件小説として読むことも可能なのだ。
「ああ、ほんとうにもういちど生きたい!」異常なほどの生命力をみなぎらせて、彼は叫んだ。「人生の一分一分、一刻一刻が、人間にとって至福の時でなくちゃならない……そうでなくちゃ、ぜひともそうでなくちゃ!」(フョードル・ドストエフスキー『悪霊3』亀山郁夫・訳)
もしも、この物語に「救い」があるとしたら、それは、ステパン・ヴェルホヴェンスキーのが残した言葉の中にあるのではないだろうか。
つまり、「救い」のない物語『悪霊』の「救い」は、『悪霊』という小説そのものにあった、ということである。
訳者(亀山郁夫)は、本作『悪霊』に関わり、いくつもの解説本を出版しているが、『「悪霊」神になりたかった男』(2005)は、基本講義として楽しめるものだ。
『謎とき「悪霊」』(2012)は、マニアックな研究者向けの探究書となっている。
ちなみにドストエフスキーは、『悪霊』の創作ノートで、「オナニー、自慰」に「ルカブルーツトヴォ」のロシア語をあてた。もっとも、ルソーの『告白』に見られる「悪徳」は、自慰だけに限られていたわけではない。(亀山郁夫「謎とき『悪霊』」)
ドストエフスキーの執筆背景まで含めてディープに、『悪霊』の世界に浸りたいと考える人は、『謎とき「悪霊」』を読むべきである(小説を読むのと同じくらい消耗するかもしれないが)。
初心者におすすめは、ロシアのドストエフスキー研究者(リュドミラ・サラスキナ)との共著『ドストエフスキー「悪霊」の衝撃』(2012)である。
日本人翻訳者とロシア人研究者との議論は、作品理解に大きく貢献してくれるものとなるだろう(なにしろ、読みやすい)。
長く失われて未発表となっていた「スタヴローギンの告白」は、1906年(明治39年)になって発表された(『ドストエフスキー作品集』)。
全集から独立したかたちで、『悪霊』が単行本として出されるようになったのは、ソ連末期、検閲が弱体化した一九八九年になってからのことである。(フョードル・ドストエフスキー『悪霊 別巻』亀山郁夫・訳)
作品としての不幸な成り立ちは、そのまま「ロシア」(ソビエト連邦)という国の不安定な情勢を予告しているかのようだ。
本作『悪霊』は、変わりゆく祖国(ロシア)に捧げられた、ひとつの黙示録だったのかもしれない。
書名:悪霊
著者:フョードル・ドストエフスキー
訳者:亀山郁夫
発行:2010/09/20-2012/02/20
出版社:光文社古典新訳文庫