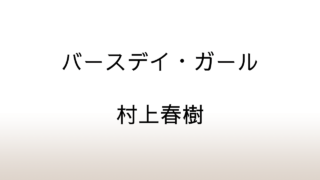庄野潤三「曠野」読了。
「曠野」は、学生時代の満州旅行を素材にした短篇小説で、「群像」1964年(昭和39年)7月号に掲載された。
この年、庄野さんは43歳だった。
なお、作品集では『丘の明り』に収録されている。
鏡泊湖へ向かう満州旅行
昭和18年(1943年)9月、庄野さんは満州旅行へ出かけた。
そのとき、庄野さんは九州帝国大学法文学部の学生で、福岡で下宿暮らしをしていたが、専攻する東洋史の研究に必要だからという理由で、両親に旅費を工面してもらう。
庄野さんが満州を旅するのは、これが二度目で、最初の満州旅行は、昭和17年(1942年)7月のことだった。
二度目の満州旅行で、庄野さんは、汽車に乗って京城から東京城へと向かうが、折からの大雨のために汽車が不通となっていて、北鮮の城津という駅で降ろされてしまう。
城津で、庄野さんは、道連れになった人たちと三日間を過ごし、再び汽車に乗って、どうにか東京城へ到着することができた。
京城大学の鳥山教授に紹介してもらった富士屋旅館に落ち着いた後、庄野さんは、鳥山教授からの紹介者である牛島氏を訪ねる。
牛島氏は食堂を経営していて、もう十年前からここへ来て住みついているということだった。
上海にいた時も南方にいた時も、私は白人に随分いじめられたり馬鹿にされたりした。上海で公園のベンチに座ってポルトガル人の音楽を聞いて居ったら、イギリス人の夫婦が来て、ベンチが広いのに退けと云って、ステッキで叩く。私を叩くんではなくてベンチの上を叩くんですが、そこに坐っている私は自分が叩かれるのも同じ気持です。口惜しい思いをしました。(庄野潤三「曠野」)
「曠野」という短篇小説では、この牛島老人の回想が、重要な役割を果たしている。
庄野さん得意の聞き書き小説である。
それから庄野さんは、鏡泊湖を訪ねるために、開拓団のトラックに乗せてもらう。
鏡泊湖までの旅は過酷なもので、庄野さんは、日本を出てきたことを後悔してしまうほどだった。
先ず私が心配したことは、こんなに遅く(夕食の時間をとっくに過ぎて)前ぶれもなしに訪ねて行って、学園の向井先生という人は私に晩御飯を食べさせてくれるだろうかという問題であった。私はそのことを真剣に考えた。(庄野潤三「曠野」)
結局、道連れになった義勇隊の人が心配してくれて、自分の部屋に泊めてくれた上に、夕食と朝食まで一緒に食べることができた。
翌日、庄野さんは、義勇隊の人たちに例を言って、鏡泊湖へと出発する。
満州旅行へなんか来なければよかったという後悔の気持ちは、もうなくなっていた。
竜宮城のモデルは渤海国だった?
「曠野」では、東京城で知り合った牛島老人の回想がおもしろい。
とりわけ、昔話「浦島太郎」の舞台は渤海だという自説は興味深い。
浦島太郎が、日本海に面した海岸に住んでいた漁師だとすると、船が難破して遭難したときに流れ着くのは、朝鮮の羅南か清津のあたりである。
そこから、渤海の首都である東京城へ送られた浦島太郎は、渤海の人々に日本の漁業技術を教えて、厚くもてなされる。
乙姫というのは、日本から渤海国へ送られてきていた舞姫で、久しぶりに同郷の男性に会った舞姫は、いたく感激したことだろう。
これは無論、一人ではない。浦島の方も一人ではない。一緒に漂流した漁師の仲間がいたでしょう。乙姫と浦島というのは、どちらも複数と考える方がいいかも知れん。ともあれ、舞姫たちは、遠い異国で日本人に会ったのですから嬉しい。あんたを帰したくないと云うたに違いない。男がホームシックを起した時、胸が張りさける思いがしただろうと思う。(庄野潤三「曠野」)
牛島老人の説によると、玉手箱というのは、東京城の名産品であった鏡のことで、日本に戻った浦島太郎は、鏡に映った自分の姿が、あまりに老け込んでいるのを見て驚いた、という話である。
意外と、牛島老人あたりを主人公にして長編小説がひとつ書けそうな気がするが、そうはならなかった。
戦争中の満州の話というと古くさい感じがするが、実際に読んでみると、古くも何ともない、むしろ、おもしろい旅行小説である。
庄野さんの小説の懐の深さを感じた。
作品名:曠野
書名:丘の明り
著者:庄野潤三
発行:1979/4/25
出版社:筑摩書房




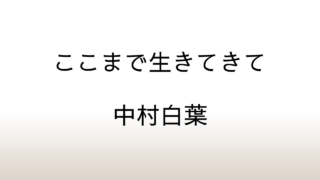

-150x150.jpg)