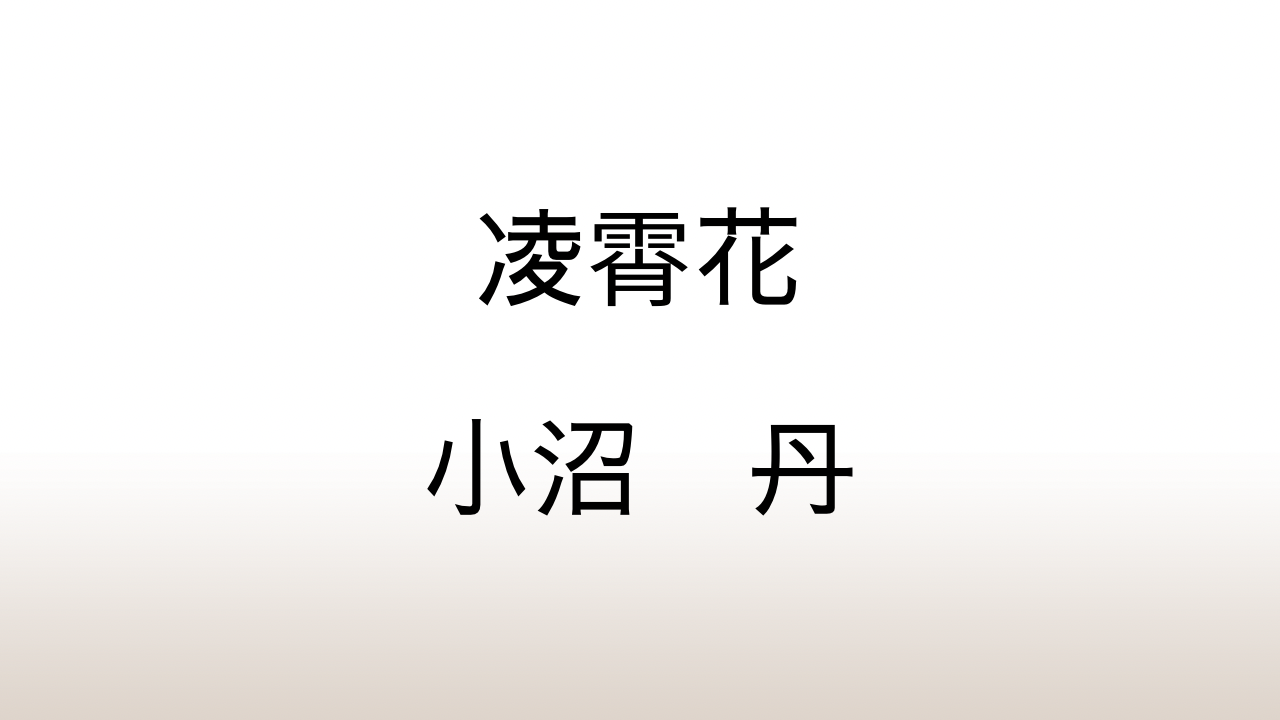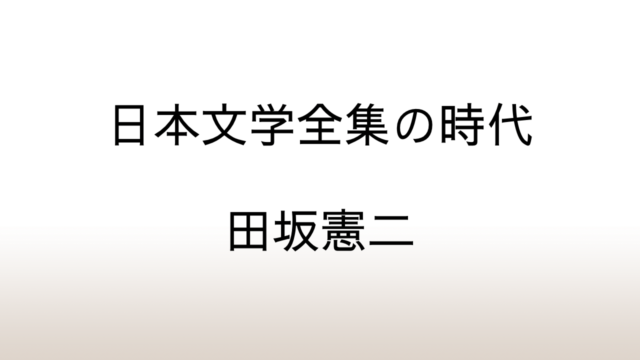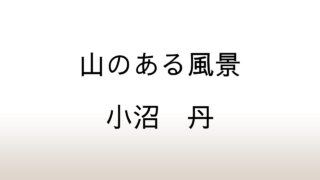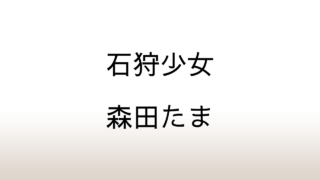小沼丹「凌霄花」読了。
本作「凌霄花」は、1978年(昭和53年)12月『昴』に発表された短篇小説である。
この年、著者は60歳だった。
作品集としては、1980年(昭和50年)9月に河出書房新社から刊行された『山鳩』に収録されている。
井伏鱒二や吉岡達夫と波高島を旅した思い出
本作「凌霄花(ノウゼンカズラ)」は、ノウゼンカズラの花に関する思い出で構成された短篇小説である。
ノウゼンカズラの花は、ずっと昔に清水町先生たちと旅をした波高島(はだかじま)の思い出から始まる。
凌霄花の花の咲く宿屋へ行ったのは、もう二十数年前のことで、友人と二人、清水町先生に随いて行った。何でも最初は下部へ行く予定で身延線の下部で下車したが、宿が混んでいたかどうかして波高島に行ったのだと思う。下部から波高島迄歩いて行くことにして、その前に茶店で一服した。(小沼丹「凌霄花」)
年譜では、1952年(昭和27年)7月のところに「井伏鱒二・吉岡達夫と御坂峠を越え、甲府、波高島に遊ぶ」と記されている。
小山清を加えて、井伏さんや吉岡さんと一緒に、太宰治文学碑建設予定地の下見に出かけるのは、この翌年のことだ(短篇小説「連翹」に詳しい)。
波高島の宿屋で見た凌霄花が、小沼さんの強い印象として残ったらしく、「窓近くには松が枝を張っていて、その枝で凌霄花の朱色の花が風に吹かれていた」と綴られている。
もっとも、田舎の一軒家だから風が吹き通っていて、「原稿用紙を飛ばされないようにインク瓶を載せて置いたら、そのインク瓶が飛ばされてしまったと先生が驚いていた」らしい。
このエピソードは「断片」(『小さな手袋』所収)でも紹介されていて、清水町先生は「──佐藤さんの所に凌霄花がある」と言ったという。
朱い花が激しく風に揺れているのを見ていると「風と揺れる花と共に遠い記憶が甦りそうになって消えて行く」とあるところがいい。
夢を見て、眼が醒めたら悉皆忘れている、そんなことが偶にある。何の夢か判らないが、いい夢を見たらしいと云う記憶だけが何となく残っていて、想い出せそうで一向に想い出せない。ちょうどそんな感じで、風に揺れる凌霄花の花をぼんやり見ていた記憶がある。(小沼丹「凌霄花」)
この短篇小説の中で、この部分は印象深い文章のひとつだ。
昔の思い出の中にも「想い出せそうで一向に想い出せない」何かがあって、それが「風に揺れる凌霄花の花」の記憶と、強く結びついている。
記憶を小説として描いてきた小沼丹らしい表現ということだろうか。
どのくらい騒いでいたか知らないが、連中がまたどやどやと帰って行ったら、途端に辺りがしいんと静まり返って、今迄の騒が嘘のように思われる。何となく不意の静寂に聴き入る格好になったら、どこか遠くでひょろ・ひょろと云うような声が聞えた。「──ああ、河鹿だ……」先生の言葉に、友人と二人、暫く耳を澄していたのを思い出す。(小沼丹「凌霄花」)
ノウゼンカズラの花は、思い出の物語を進行する役を務めているのであって、決して主役ではない。
井伏さんや吉岡さんと過ごした波高島の思い出が、この物語のひとつのメインテーマとなっているのだ。
埼玉県の安行で凌霄花を買った日のこと
本作「凌霄花」のもう一つのテーマは、埼玉県の安行(あんぎょう)へ出かけたときの思い出である。
この凌霄花は昔、埼玉県の安行に行ったとき買った。知人の車に乗せて貰って、植物の好きな人間が三、四人で行ったのだが、もう十年以上前のことだから詳細は忘れている。同行の友人の一人は植物の知識が豊富で、「──植物辞典なんて当にならないよ」と云う程の物識博士だが、この物識博士が安行行を提案したのだと思う。(小沼丹「凌霄花」)
物識博士の友人は、花梨の木を入手するのが目的だった。
短篇小説「落葉」(『銀色の鈴』所収)の中で、「森君は前に安行に一緒に行ったとき、花梨の木を買った」とあるから、「物識博士の友人」は森君(室淳介のこと)だったのかもしれない。
ちなみに「栗の木」(『福寿草』所収)には、「凌霄花は昔仏文科の村上さんや室さんと安行に行ったとき購めたもので」と綴られている。
このとき、小沼さんは、安行の植木屋で凌霄花を買い求めている。
一軒の植木屋に寄ったとき、何の弾みかひょっこり凌霄花を想い出して、「──凌霄花は無いかしら?」と訊いたら、「──ああ、ありますよ」と云う返事で、その家で、四、五十糎ばかりの丈の細い苗木を三、四本購めた。(小沼丹「凌霄花」)
「それ迄凌霄花は全然念頭に無かったのに、その店に這入ったら不意に頭に浮んだのだから何だか面白かった」とあるが、この凌霄花が、波高島を旅したときの思い出へと、主人を案内していくことになる。
「落葉」では、波高島で見た凌霄花の思い出話に続いて、「このときの印象が強かったので、安行に行ったとき凌霄花の苗を探したのだと思う」という一文がある。
思い出から思い出へとつながっていく構成は、まさしく追憶文学という一つのジャンルだと言っていいのではないだろうか。
物語の最後に、凌霄花を離れて「梨の実」で締めくくられるところも、小沼丹らしい。
思い出に浸りすぎない適度な距離感こそが、小沼文学の肝だからだ。
落ちていた実を一個拾って、皆の後に随いて小径を上って行くと、「──それは無しの実だ」と云う声が聞えた。誰が云ったのかしらん? 何だか歯の無い顔が笑ったように思う。(小沼丹「凌霄花」)
得意の「~かしらん?」が最後に出て、追憶の物語は唐突に終わりを告げる。
これ以上の回想は、もはや不要だとでも言うかのように。
こういう追憶の文学を書くことのできる人間は、豊かな人生を送ってきた人間だけだろう。
人生の滋味が、そのまま小説のテーマとなってしまうからだ。
小沼さんの小説を読むと、「大人の文学」ということの意味が分かるような気がする。
そして、自分もようやく「大人の文学」の味わいが、分かるようになってきたのかもしれない。
作品名:凌霄花
著者:小沼丹
書名:山鳩
発行:1980/09/19
出版社:河出書房新社