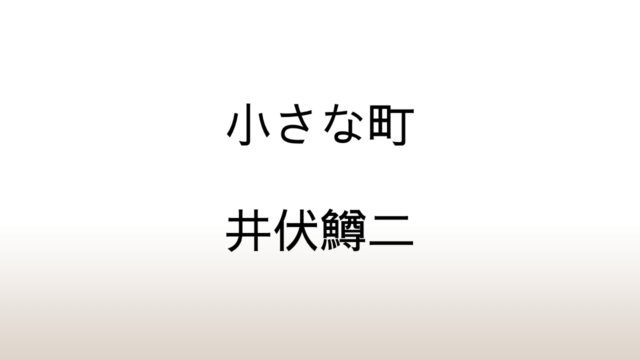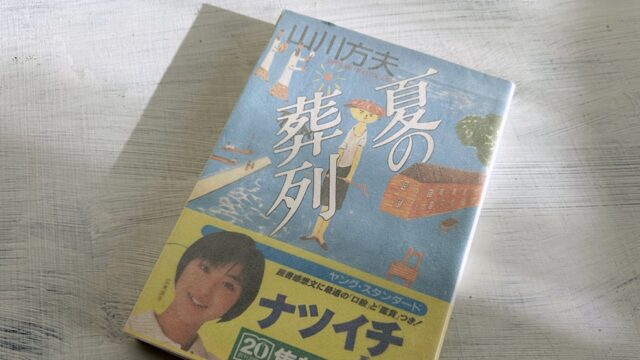フョードル・ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』は、1879年(明治12年)1月から1880年(明治13年)11月まで『ロシア報知』に連載された長篇小説である。
連載終了の年、著者は59歳だった(1881年1月、59歳で他界)。
単行本は、1880年(明治13年)12月に刊行されている。
村上文学に登場した『カラマーゾフ』
村上春樹の作品には『カラマーゾフの兄弟』が頻繁に登場する。
デビュー作『風の歌を聴け』(1979)では、主人公の親友(鼠)のエピソードとして登場した。
鼠はまだ小説を書き続けている。(略)昨年のは精神病院の食堂に勤めるコックの話で、一昨年のは「カラマーゾフの兄弟」を下敷きにしたコミック・バンドの話だった。(村上春樹「風の歌を聴け」)
『羊をめぐる冒険』(1982)では、主人公の愛読書として登場している。
彼らは僕を笑うだろうか? 僕は「カラマーゾフの兄弟」と「静かなドン」を三回ずつ読んだ。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)
『ねじまき鳥クロニクル』(1994)の主人公も、「カラマーゾフの兄弟」を愛読していた。
もちろん僕に特徴がないというわけではない。失業していて、『カラマーゾフの兄弟』の兄弟の名前を全部覚えている。(村上春樹「ねじまき鳥クロニクル」)
『1Q84』では、ヒロイン(青豆)と宗教団体「さきがけ」のリーダーの会話に、この物語が登場している。
「たしか『カラマーゾフの兄弟』に悪魔とキリストの話が出てきます」と青豆は言った。(略)「知っているよ。わたしも『カラマーゾフの兄弟』は読んだ」(村上春樹「1Q84」)
物語の中で『カラマーゾフの兄弟』が重要な役割を持っているのが、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985)である。
「『カラマーゾフの兄弟』を読んだことは?」と私は訊いた。「あるわ。ずっと昔に一度だけだけど」「もう一度読むといいよ。あの本にはいろんなことが書いてある。小説の終りの方でアリョーシャがコーリャ・クラソートキンという若い学生にこう言うんだ。ねえ、コーリャ、君は将来とても不幸な人間になるよ。しかしぜんたいとしては人生を祝福しなさい」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
「とても不幸な人生を総体として祝福することは可能だろうか」と、主人公は考える。
私は眼を閉じて『カラマーゾフの兄弟』の三兄弟の名前を思いだしてみた。ミーチャ、イヴァン、アリョーシャ、それに腹違いのスメルジャコフ。『カラマーゾフの兄弟』の兄弟の名前をぜんぶ言える人間がいったい世間に何人いるだろう?(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
『世界の終り』の中で、『カラマーゾフ』は最終章の、ほぼラストシーンで登場している。
つまり、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』という長篇小説にとって、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』は、かなり重要な役割を果たしているということだ。
私はアリョーシャ・カラマーゾフの気持がほんの少しだけわかるような気がした。おそらく限定された人生には限定された祝福が与えられるのだ。私はついでに博士と太った孫娘と図書館の女の子にも私なりの祝福を与えた。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
主人公のセリフの出典は、『カラマーゾフの兄弟(第10編・少年たち)』である。
「でも、いいですか、コーリャ、きみは将来、とても不幸な人になります」アリョーシャはなぜかふいに口走った。「わかってます、わかってます。あなたはそう、先々のことが何でもわかってしまうんです!」コーリャは即座に相槌をうった。「でも、全体としては、やっぱり、人生を祝福してくださいね」(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
アリョーシャの言葉は、謎の予言である。
そして、アリョーシャの予言の背景には、アリョーシャ自身がゾシマ長老から与えられたメッセージがあった。
「多くの敵を持つことになっても、その敵たちさえ、おまえを愛するようになる。人生は多くの不幸をおまえにもたらすが、それらの不幸によっておまえは幸せになり、人生を祝福し、ほかの人々にも人生を祝福させるようになる。これがなにより大事なのです」(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
おそらく、アリョーシャもコーリャも、いずれ、自身の身を社会のために投げ出すことになる。
彼ら自身がたとえ不幸になろうとも、世の中を変えることができるのであれば、それは祝福される人生であっていい(「大きな悲しみを見ることがあっても、その悲しみのなかでおまえは幸せだろう」)。
アリョーシャの予言は、ゾシマ長老のメッセージ(自己犠牲の尊厳)を、アリョーシャがしっかりと受け取っていたことの証明である。
早熟な少年コーリャ(13)の言葉から、アリョーシャは不吉なものを嗅ぎ取ることができていたのだ(作者の急死により、続編が書かれることはなかったが)。
『世界の終り』の主人公は、太った孫娘に「もう一度読むといいよ。あの本にはいろんなことが書いてある」と言った。
「あの本にはいろんなことが書いてある」という言葉は、そのまま『カラマーゾフの兄弟』という長篇小説の性格を表していると言っていい。
実際、この物語には、実にいろいろなことが書かれている(書かれ過ぎているくらいに)。
本作『カラマーゾフの兄弟』は、基本的には、ロシアの田舎町に暮らす20代の若者たちの苦悩を描いた青春群像劇である。
時代設定は1870年(明治3年)前後で、日本流に言うと、明治初期のロシア社会を描いた物語ということになる。
日本の文学作品では、島崎藤村『夜明け前』(1929)とほぼ同時代の設定だが、『カラマーゾフの兄弟』は、フョードル・カラマーゾフ殺人事件の起きるまでの三日間に第三部までが充てられていて、最後の第四部・エピローグも、事件から二か月後の裁判の模様を描いたものである。
主な登場人物は、ドミートリー・カラマーゾフ(28)、イワン・カラマーゾフ(24)、アレクセイ・カラマーゾフ(20)というカラマーゾフ三兄弟で、とりわけ、三男のアレクセイ(愛称アリョーシャ)が、この物語の主人公として設定されている。
ここに、腹違いの兄弟ではないかと噂される下男(スメルジャコフ、24~25)が、ストーリー上の重要な役割を担って加わることになる(「賢い人とはちょっと話すだけでも面白い」)。
ドミートリー(愛称ミーチャ)とイワンは、カテリーナ(愛称カーチャ)という美女をめぐって三角関係となり、さらにミーチャは、アグラフェーナ(愛称グルーシェニカ、22歳)というセクシーな女性とも関係を持ってしまう。
二十歳のアリョーシャは、リザヴェータ(愛称リーザまたはリーズ)という14歳の女の子と恋仲になるが、やがて、リーザはイワンへと心変わりしてしまう。
「人間って、時によると、罪を好きになる瞬間があるものなんです」アリョーシャはもの思わしげに言った。(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
若者たちの恋愛模様が重要なモチーフになっていることを考えると、『カラマーゾフの兄弟』は恋愛小説として読むことができるし、リーザに焦点を当てると、成長の苦悩を描いた思春期小説という側面を見つけることもできる(「ああ、わたしって、なんていやらしい、なんていやらしい、いやらしい、いやらしい、いやらしい!」)。
ところが、セクシーなグルーシェンカにイカレた父親(フョードル・カラマーゾフ、55歳)が、長男ミーチャとドロドロの三角関係になったことで、「父殺し」という、『カラマーゾフ』を象徴する事件が発生することになる。
フョードルを殺したのは、ミーチャか? スメルジャコフか?(「みなさん、これはスメルジャコフのしわざです!」)
犯人探しの展開はミステリー小説であり、裁判における検事と弁護士のやり取りは、もはや「法廷小説」と言っていい(「神と、おそろしい最後の審判にかけて誓います、父の血にかんして、ぼくは無実です!」)。
「ぼくが知っているのは、ひとつ」と、アリョーシャは、あいかわらずほとんどささやくような声で言った。「父を殺したのは、あなたじゃないってことだけです」(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
そもそも、長男ミーチャは、次男イワン・三男アリョーシャとは、別々の母親から生まれた腹違いの兄弟である。
女にダラしない父フョードルは、暴力的な夫であり(ドメスティック・バイオレンス)、生まれた子どもたちには、まったく関心を寄せなかった(育児放棄、児童虐待)。
不遇な境遇のもとで育てられた三兄弟は、誰もが父親を憎んでいるのであり、父と子という観点から読めば、この物語は、ひとつの家族小説として読むこともできる。
しかし、金にも女にもだらしがない、クズのような成金地主フョードルを、ロシア社会の象徴と見たとき、『カラマーゾフの兄弟』は、現代ロシア社会を痛切に批判した社会小説へと変身する。
現代ロシア社会の重要な背景となっているのは、市民の思想的土壌を成す宗教問題である(神はいるのか? いないのか?)。
この物語で、宗教論争が多くを占めているのは、宗教問題を考えることが、そのまま現代ロシア社会を考えることであり、ロシアに生きる人々を解き明かす鍵となったからだ。
つまり、『カラマーゾフの兄弟』は、若者たちの恋愛や複雑な家庭環境、社会的格差、宗教問題など、大小様々なモチーフが複雑に絡み合った、壮大でスペクタクルな大物語なのである。
研究者でもない限り、全容を解明することは、ほぼ不可能で(研究者にだって難しいだろうが)、多くの読者は、理解できるところを理解しながら、この小説を何度も読み返すことになる。
【村上】「十四歳か十五歳のときは一晩中、ロシアの古典文学を読んで過ごしました。(略)今までに『カラマーゾフの兄弟』は四回読みました。僕は大長篇が大好きです。長大な物語は嫌でも長いことその世界に浸らせてくれる。そういうわくわくさせてくれる小説が、何より好きなのです」(村上春樹『夢を見るため毎朝僕は目覚めるのです』所収「ハルキ・ムラカミ あるいは、どうやって不可思議な井戸から抜け出すか」)
2008年(平成20年)のインタビューで、村上春樹は「今までに『カラマーゾフの兄弟』は四回読みました」と語っている。
「世の中には二種類の人間がいる。『カラマーゾフの兄弟』を読破したことのある人と、読破したことのない人だ」というほど、村上春樹は『カラマーゾフ』に心酔していたらしい(ジム・フリージ『ペット・サウンズ』訳者あとがき)。
もし「これまでの人生で巡り会ったもっとも重要な本を三冊あげろ」と言われたら、考えるまでもなく答えは決まっている。この『グレート・ギャツビー』と、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』と、レイモンド・チャンドラー『ロング・グッドバイ』である。(スコット・フィッツジェラルド「グレート・ギャツビー」訳者・あとがき)
至るところに『カラマーゾフ』が登場している(ただし、一冊だけ選ぶとしたら『ギャツビー』になるが)。
【村上】「ドストエフスキーが僕のアイドルで理想です。彼は六十歳近くになってから『カラマーゾフの兄弟』という最高傑作を書いています。僕もそのようになりたいと思っています。(村上春樹『夢を見るため毎朝僕は目覚めるのです』所収「ハルキ・ムラカミ あるいは、どうやって不可思議な井戸から抜け出すか」)
ちなみに、この年、村上春樹は59歳だった(ドストエフスキーが死んだ年齢と同じ)。
細部を構成するエピソードを楽しむ
村上春樹が、ここまで『カラマーゾフの兄弟』に惚れ込んだ理由は、やはり、この作品が「総合小説」だったからだろう。
つまり、「あの本にはいろんなことが書いてある」ということだ(『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』)。
人生や世の中の、明るい部分から暗い部分まで、この物語には様々なエピソードが登場する。
『カラマーゾフ』を楽しむコツは、細部を構成するひとつひとつのエピソードを楽しむということに尽きる。
例えば、「第5編 プロとコントラ」で、アリョーシャと議論したイワンが、おかしな恰好で去っていく場面がある。
そこで彼はなぜかふと、兄のイワンが妙に体を揺らしながら歩き、後ろから見ると右肩が左肩よりもいくぶん下がっているのに気づいた。以前それに気づいたことはなかった。(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
『大審問官』なる物語詩で無神論を展開する次男(イワン)には、ゲーテ『ファウスト』に登場する悪魔(メフィストフェレス)の姿が重ねられている。
この悪魔は、やがて「第11編 兄イワン」で、イワンの見る幻覚として、具体的な形を伴って登場する。
「で、やつはな、アリョーシャ、おれなのさ、おれ自身なんだ。おれがもっている全部の下劣な部分、いやらしい部分、軽蔑すべき部分なんだよ!」(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
イワンの言葉は、神(良心)と悪魔(卑劣)は、一人の人間の中に併存する存在であることに気づかせてくれる(自己葛藤)。
そして、イワンの中の悪魔を実体化した存在こそ、腹違いの兄弟(スメルジャコフ)だった。
細かいひとつひとつのエピソードは、壮大な物語を構成するパズルの一片である。
無関係と思われる無数のエピソードが繋がっていったとき、『カラマーゾフの兄弟』という長大な物語を完成させているのである。
イワンの中の葛藤は、実の父を激しく憎悪した「人でなしの人殺し」ミーチャの中にも描かれているものだ。
「餓鬼(がきんこ)ですものねえ」と御者が彼に答える。「餓鬼だから泣いてるんですよ」(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
焼け跡のそばにたたずむ若い母親と乳飲み子の姿は、ミーチャに再生を促す(「おれは、自分のなかに新しい人間を感じているんだ。新しい人間がおれのなかで甦ったんだよ!」)。
餓鬼(がきんこ)の話は、「第11編 兄イワン」でも繰り返される。
「ただ、あの人、いきなり餓鬼のことを口にするようになったの。つまりどこかの子どものことね。『どうして餓鬼はああも貧しいんだ?』とか、『これからおれがシベリアに行くのも、あの餓鬼のかわりなんだ、人殺しなんかやってない、でも、おれはシベリアに行かなくちゃだめなんだ!』とか。ねえ、これって何なの、この餓鬼って、何のことなの……」(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
気になるモチーフは、必ずと言っていいくらい繰り返されているのは、本作『カラマーゾフ』の特徴だろう(つまり、バラバラのエピソードが繋がっている)。
グルーシェニカの「一本の葱」は、芥川龍之介「蜘蛛の糸」を思い出させる。
「ぼくが何をしてあげられたっていうんです?」アリョーシャは彼女のほうにかがみこみ、優しく彼女の両手をとると、感に堪えないという面持ちで微笑みながら答えた。「あなたに一本の葱をあげました。ほんとうに小さな葱をね。それだけです。それだけのことです……」(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
芥川の「蜘蛛の糸」は、ポール・ケーラス『カルマ』の日本語訳『因果の小車』に収録されている「蜘蛛の糸」が引用元と言われているが、グルーシェニカの中の良心をすくい上げたアリョーシャの言葉には響くものがある。
引用として忘れらないのは、ゴーゴリ『死せる魂』だろう。
ひと時代前の大作家ゴーゴリは、彼のもっとも偉大な作品のフィナーレで、ロシア全土を、未知の目的に向かって突っ走る勇ましいロシアのトロイカ(三頭馬車)になぞらえ、こう叫びました。『ああ、トロイカよ、鳥のようなトロイカよ、だれがおまえを考え出したのだ!』(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
『カラマーゾフの兄弟』という大長編では、シラー『群盗』(1782)やゲーテ『ファウスト』(1808)、ゴーゴリ『死せる魂』(1842)などが下敷きとなって、「人間とは何か?」「社会とは何か?」という文学の根源的なテーマを掘り起こす仕掛けとなっている。
ちなみに、ゴーゴリでは『ディカーニカ近郷夜話』や『査察官』も登場している(『ディカーニカ近郷夜話』は、フョードルがスメルジャコフに貸したものだが、スメルジャコフは満足できなかった)。
『カラマーゾフ』というと、メインストーリーである「父親殺し」に注目しがちだが、アリョーシャと小悪魔(リーズ)との幼い恋愛劇や、ゾシマ長老の「遺体腐臭事件」で傷付いたアリョーシャが、「ガラリヤのカナ」の婚礼を夢に見て力を取り戻す復活再生劇など、サイドストーリーにも読むべきところが多い。
彼は、地面に倒れたときにはひよわな青年だったが、立ち上がったときには、もう生涯かわらない、確固とした戦士に生まれ変わっていた。(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
「確固とした戦士」の意味は謎だが(おそらく続編への伏線)、本作『カラマーゾフの兄弟』においては、余分なサイドストーリーなどなく、すべてがメインストーリーと言うべきなのかもしれない。
ひとつひとつの編を短篇小説のように読み重ねていくことで、やがて、『カラマーゾフの兄弟』という物語の全体像が明らかになる。
おキツネさんだった母親、六本指の赤ん坊、風呂場で赤ん坊を産み落として死んだ神がかりの女、世渡り上手なラキーチンのホフラコーワ夫人への告白、小役人ペルホーチンの活躍(殺人事件の発覚に一役買った)、ポーランド人たちのイカサマなカードゲーム、モークロエにあるトリフォーンの旅籠屋での大宴会(ジプシー女たちの踊り)と貧しいマクシーモフ老人(『死せる魂』に出てくる地主と同じ名前だった)、、、
全容解明に挑むよりも、細部のエピソードを読み込んでいくことこそ『カラマーゾフの兄弟』という大長編の醍醐味だと言っていい。
いずれ、すべての物語はつながっていくし、すべてに通底しているのは、作品中で「地上的なカラマーゾフ力」と呼ばれる、現代ロシア社会が持つ世界観なのだ。
とりわけ、ラストシーン、イリューシャの葬儀の場面は胸を打つ。
「そう、かわいい子どもたち、かわいい友人たち、どうか人生を恐れないで! なにか良いことや、正しいことをしたとき、人生ってほんとうにすばらしいって、思えるんです!」「そうです、そうです」少年たちは、感激して繰り返した。(略)「カラマーゾフ万歳!」コーリャが歓喜の声をあげた。(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
イリューシャの死を受け容れて、少年たちは前を向いて生きていくことを誓う。
ここにあるのは、将来への誓いだ(おそらくは続編を意識して)。
「永遠に、死ぬまで、こうして手をとりあって生きていきましょう! カラマーゾフ万歳!」(フョードル・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』亀山郁夫・訳)
少年たちが、永遠に手をとりあって生きていくことができたのかどうか、それは分からない。
しかし、「父親殺し」の事件を経て、多くの若者たちが自分の存在を確認し、自分の歩いていく道を見つけた。
クズのような父親フョードル・カラマーゾフは、現代ロシア社会の象徴であり、「父親殺し」は、若者たちが生きていく苦悩の未来を暗示している(息子イリューシャの死を嘆き悲しむ二等大尉(スネギリョフ)の姿は、フョードル・カラマーゾフに対する強烈な反論となっている)。
有罪判決を受けて、なお、青年ミーチャが「おれはロシアを愛しているんだ!」「おれ自身はたとえ卑怯者でも、ロシアの神を愛しているんだよ!」と叫んだように、誰もが、自分なりの方法で、祖国ロシアを愛していた。
愛しているからこそ、殺したいものもあるのだ。
ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』は、すべてを理解できる小説ではない。
人生経験を重ねながら、何度も何度も繰り返し読むことによって、「カラマーゾフ」という謎が、少しずつ明らかになっていくものだからだ。
20代には20代の、60代には60代の『カラマーゾフ』がある。
村上春樹の小説は、もしかすると、そんなことを教えてくれているのではないだろうか。
書名:カラマーゾフの兄弟(全五巻)
著者:フョードル・ドストエフスキー
訳者:亀山郁夫
発行:2007/07/20
出版社:光文社古典新訳文庫