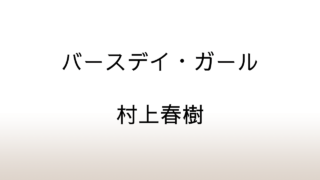井伏鱒二「徴用中のこと」読了。
本作「徴用中のこと」は、1996年(平成8年)7月に講談社から刊行された長篇随筆である。
著者は、1993年(平成5年)7月10日に他界している。
初出は、1977年(昭和52年)9月~1980年(昭和55年)1月『海』(連載)。
厭戦観に支えられた戦記
庄野潤三の随筆中『野菜賛歌』に「井伏さんの『徴用中のこと』」という随筆がある。
この夏は七月に講談社から出た井伏鱒二『徴用中のこと』をひまさえあればとり出して読んだ。はじめ頁を繰っていて途中から読み出し、大分読み進んでから最初に戻って読み返した。面白くて、やめられなかった。(庄野潤三「井伏さんの『徴用中のこと』」)
「はじめ頁を繰っていて途中から読み出し、大分読み進んでから最初に戻って読み返した」とあるところが、なんとなく庄野さんっぽい。
井伏鱒二が陸軍に徴用されて、シンガポールへ出発したときのことは、小沼丹の作品に描かれている。
清水町先生が徴用で仏印に行くことになって、東京駅へ見送に行った。(略)東京駅の乗車口だったか降車口だったか忘れたが、行って見ると向うに太宰さんの顔が見えるが、其方へ行くと清水町先生がつまらなそうな顔をして立っていて、傍に矢張り見送に来た亀井さんがいた。(小沼丹「翡翠」)
東京駅には、井伏鱒二と一緒に徴用された中村地平や高見順などもいたが、見送人の数は多くなかった(太宰治や亀井勝一郎の名前がある)。
先生に挨拶して、どうぞ、お元気で、と云ったら、「──うん、有難う」と先生は点頭いてから、小さな声で、「──厭だね、こんなの。本当に厭だね」と云った。(小沼丹「翡翠」)
「──厭だね、こんなの。本当に厭だね」という言葉に、戦争に対する井伏鱒二の気持ちが象徴されている。

本作『徴用中のこと』は、徴用でシンガポールに派遣された井伏鱒二の「厭だね、こんなの。本当に厭だね」という気持ちを現地での出来事とともに綴った、ひとつの戦記である。
ひとつの戦記ではあるが、そこには戦争に対する高揚感や感動的なドラマは、ほとんど出てこない。
実は私たち、みんな心の底では戦争をきらっているが、せっかく猫をかぶって、ここまで来て殊勝な顔をしているわけだ。どうかお手柔らかにやってもらいたかった。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
「心の底では戦争をきらっているが、せっかく猫をかぶって、ここまで来て殊勝な顔をしている」というのが、戦地における井伏鱒二の姿勢である。
山下司令官が宣伝事務所を訪問したときには、うっかり挨拶を忘れ、「軍人は礼儀が大事だ。こんなものは、内地へ追い返してしまえ」と叱られる(井伏さんは咄嗟に「はい」と答えた)。
瞬間、本当に内地へ帰してくれるのだろうかと思った。それより先に、「はい」と云った自分の声を情けなく思った。それは私が自分の家庭で中学一年生の長男を叱るとき、「はい」と答える長男の声そっくりであった。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
宣伝班の井伏鱒二が、山下将軍に叱り飛ばされた事件は、一種のスキャンダルだった。
多くの兵隊たちは「あんた、それでもう出世できませんな」と同情したが、「羨ましいなあ。わしもたった一度でよいが、司令官閣下に叱られてみたいなあ」とつぶやいた上等兵もいたという。
戦地の生活で、軍隊の人間と一緒に暮らしながら、井伏さんも少しずつ、戦争に馴染んでいく。
イポー経由で、前線タバの鉄道修理の状況を確認するよう命じられた際は「もう観念したと云いたいような気持になっていた」とある。
いよいよ危険な場所へ行かされることになった。私はそれに対処する覚悟のようなものは出来ていなかったが、自分が戦地へ持って来られたことで、不平をこぼすのはもう止すつもりにはなっていた。(略)もう観念したと云いたいような気持になっていた。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
それは、前向きな戦争肯定ではなく、ある種の諦念にすぎない。
私はクルーアンを出発する頃には、自分の徴用されたことに対する不満など、決して表に出さないようにしてみせると心に決めていた。平凡な一兵卒の性根を早く身につけたいと思うようになっていた。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
自我を奪うところが軍隊という場所だったと言えば、それまでかもしれない。
命令だから否応ないだろう。それが戦争だという答しかないから怖ろしい。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
「命令だから否応ないだろう」という軍隊生活の中で、井伏さんは、どんどんと消耗していく。
私は昭南タイムスを退社するとき、自分が殆ど三日に一度の割で鼻血を出していると古山君に証人になってもらい、自分は新聞社の激務を止して神保光太郎が校長をしている昭南日本学園に勤めるようにしたいと班長の阿野中佐に申し出た。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
シンガポールに派遣された井伏鱒二が配置されたのは、宣伝班である。
シンガポール陥落後に昭南市が誕生したときは、英字新聞『昭南タイムズ』の編集責任者を命じられた。
「僕は英語が出来ないから駄目です。お断りします」と井伏さんは辞退するが、「軍隊では、上官の命令を拒むことは許されない」と一蹴される。
「殆ど三日に一度の割で鼻血を出している」のには、不向きな仕事に対するストレスも大きかったのだろう。
もちろん、こうした厭戦観は、井伏鱒二に固有のものではなく、多くの兵隊に共通するものだった。
石井亀次郎と斉田愛子が慰問にやってきたとき、「遺骨を抱いて」という歌を歌った。
シンガポール攻略戦で負傷した兵隊は、「遺骨を抱いて」の歌のとき、「まだ進撃はこれからだ……」というところに来ると、わっと泣き伏してしまうのがある。(略)日本軍がシンガポールを陥落さえすれば、戦争は終ると思い込んでいた兵が多かったからだろう。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
歴史書によると、シンガポールにおけるイギリス軍との戦いは、1942年(昭和17年)2月8日から15日までとある。
イギリス連邦軍が降伏したとき、多くの兵隊は「これで戦争が終わった」と安堵したのかもしれない。
「遺骨を抱いて」の歌詞は、シンガポールが陥落したとき、一人の下士官(辻原実)が持ってきたものだという。
一番乗りを やるんだと
力んで死んだ 戦友の
遺骨を抱いて 今入る
シンガポールの 街の朝
シンガポールを 陥しても
まだ進撃は これからだ
遺骨を抱いて 俺は行く
護ってくれよ 戦友よ
(「戦友の遺骨を抱いて」)
本作『徴用中のこと』にBGMがあるとしたら、それは「戦友の遺骨を抱いて」だったかもしれない。
「遺骨を抱いて」の舞踊では、江口が踊り、石井亀次郎と斉田愛子が交る交る歌った。斉田愛子は声を出す前から、もう兵隊たちを涙もろくさしてしまった。絶唱であった。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
本作『徴用中のこと』は、「厭だね、こんなの。本当に厭だね」と思いながら戦地を生きた男による、シンガポール陥落の記録である。
戦時シンガポールの風俗誌
本作『徴用中のこと』には、魅力的な登場人物と魅力的なエピソードが、次々と登場する。
サイゴン河の岸壁につけた船から、酔った海音寺潮五郎が落ちた。
みんなほっとして、わいわい騒いだので、海音寺は隊長に知られては拙いと思い、岸壁にすがりつくと同時に「みんな騒ぐな」と注意した。(略)マレー宣伝班員たちのゴシップとして、海音寺さんは岸壁にすがりついたとき、わいわい騒ぐ人たちを叱って「ものども騒ぐな」と云ったと伝えられていた。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
時代小説で人気の海音寺潮五郎だったから、「ものども騒ぐな」という名台詞が伝えられたのかもしれない。
庄野潤三は、「華僑少年リン・カナン」が好きだった。
「ここは、日本人には物騒なところのようだ。日本人が軍装で歩いたら拙いだろうか」とリンに訊くと、「軍曹は不可(ノー・グッド)である。貴官(トアン)は白シャツに白ズボンをはいているから宜しい。タイ国人そっくりに見える」と云った。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
井伏さんは、昭南タイムズの社会部記者レンベルガンと市内電車に乗ったときも、タイ国人に間違えられた。
やがて電車を降りて、「あの車掌、どうして僕に切符を買わせたんだろう」と訊くと、「彼は貴官(トアン)を、タイランド・ピープルと思ったのだ」と云った。私が意外な気がして反っぽを向くと、「ことに貴官は、うしろから見るとタイランドのピプン首相にそっくりだ」と云った。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
ナッシム・ロードの宿舎に近い映画館では『秀子の車掌さん』を観た。
高峰秀子主演『秀子の車掌さん』(1941)は、井伏鱒二の小説『おこまさん』(1941)を原作とする映画である。
映画『秀子の車掌さん』の撮影現場に、井伏さんは偶然に立ち会ったことがある。
夏川は甲府盆地の蒸暑いさなか、セルの着物を着てセルの袴をはいていた。「セルの着物なんか着て、どこへ行くのかね」と訊くと、「あなた知らないんですか。この先の、酒折の山崎の踏切のところで、あなたの「おこまさん」の映画の一駒を撮っているんです。セルの着物にセルの袴は、あなた自身と思しき少女小説家の服装です」と云った。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
もっとも、『秀子の車掌さん』は、兵隊の慰問用として不向きな映画であったため、間もなく上映禁止になってしまった。

ナッシム・ロードの宿舎では、第二次徴用の中島健三と一緒になった。
私は古参兵のような立場の徴員として、夜、中島、神保を案内して(六人の報道小隊の)堺君たちの宿舎に連れて行った。ここでも中島は「何ぶんともに宜しく頼む」と堺君に云った。今日でも中島は、私が「何ぶんともに宜しく頼む」と口真似をすると、「こら、もうそれを云うな」と苦笑いをする。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
中島健三は、井伏鱒二の訳詩に登場している。
ケンチコヒシヤヨサムノバンニ
アチラコチラデブンガクカタル
サビシイ庭ニマツカサオチテ
トテモオマエハ寝ニクウゴザロ
井伏鱒二「秋夜寄丘二十二員外」
「ケンチコヒシヤ(ケンチ恋しや)」の「ケンチ」とあるのが、中島健三のこと。
『建設戦』に北川冬彦のポエチカルな詩(「昭南島風物詩二篇」)が掲載されたときは、山下司令官が激怒した。
「こんな文章を、軍人のための詩と云われるか。敗戦国の住民が、草を摘んで朝飯に混ぜて食う。それがどうしたと云うのだ。草でも木の実でも、何でもいい。食べられるものを食べる。そこに何の不思議があるか」(井伏鱒二「徴用中のこと」)
井伏鱒二が、山下司令官に叱り飛ばされるのは、この直後のことである(「こりゃまずい。どうも俺は運が悪い」)。
立花軍属の「転落の詩集です」という言葉もおもしろい。
その頃、兵隊たちの間に、何か困ったことがあると「処置ないです」という言葉が流行っていた。立花君は「処置ないです」という成語と、「転落の詩集です」という成語を混ぜこぜに使っていた。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
戦記というより、戦地における風俗誌といった趣がある。
庄野さんが「面白くて、やめられなかった」と書いているのは、そうした部分を指摘しているのだろう。
イポーの町はずれの道端では、野生のザボンを採った。
私はゲートルを脱ぎ靴も靴下も脱ぎ、木登りをしてザボンを取った。それを一つずつ運転兵が下から受取って栗石の上に並べた。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
植物好きの井伏さんだったから、随所に現地の植物に関する記述が散見される。
そういう意味で、これは、戦時中のシンガポールを描いた風土記とも言える。
少し早いが昼食をすませ、一線へ進出する準備をしていると、後方の予備隊から狐色に焼いた餅を持って来てくれた。持って来る予備隊も決死の覚悟であったろう。一人に一個ずつの餅だが、苦戦中とは云いながらも、謹賀新年の餅でも食って戦ってくれというわけである。思いやりが有難い。その思召しに、ほろりとさせられた。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
作家の目は、イギリス軍の降伏によるシンガポール陥落からシンガポール華僑粛清事件へと続く非常時の外地を、庶民の目線から観察している。
井伏鱒二の戦争文学というと『黒い雨』が有名だが、本書もまた、井伏鱒二による貴重な戦争文学作品だ。
そして、取材に基づく『黒い雨』と異なり、本書『徴用中のこと』は、作家自身の体験を綴った見聞録である。
シンガポールが日本だった時代のリアルな現実が、この作品の中にはある。
『井伏鱒二自選全集』には収録されなかった作品が収録されているのも貴重。
書名:徴用中のこと
著者:井伏鱒二
発行:1996/07/10
出版社:講談社



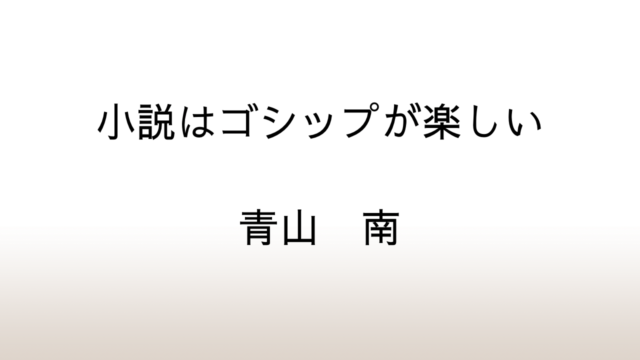



-150x150.jpg)