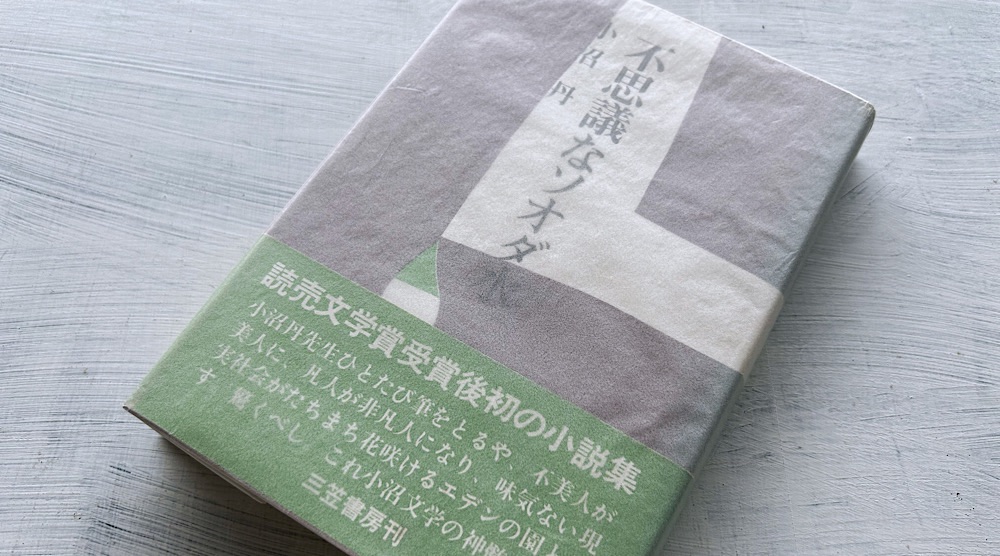小沼丹「不思議なソオダ水」読了。
本作「不思議なソオダ水」は、1969年(昭和45年)11月に三笠書房から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は51歳だった。
収録作品及び初出は次のとおり。
「不思議なソオダ水」
・1956年(昭和31年)6月『オール小説』
「マダムの階段」
・1956年(昭和31年)1月『小説公園』
「赤い帽子」
・1956年(昭和31年)11月『文芸春秋』
「木犀」
・1962年(昭和36年)7月『オール読物』
「遠い顔」
・1956年(昭和31年)10月『新女苑』
「女雛」
・1955年(昭和30年)『別冊文芸春秋』
「乾杯」
・1956年(昭和31年)7月『小説公園』
「二人の男」
・1956年(昭和31年)10月『オール読物』
「不可侵条約」
・1959年(昭和34年)8月『オール読物』
「焼餅やきの幽霊」
・1957年(昭和32年)7月『オール読物』
1969年(昭和44年)に『懐中時計』が読売文学賞を受賞したことを受けて、急遽、旧作による作品集を出版することになったものと思われる。
男と女の戯れを酒場の中から描く
作品集のタイトルにもなった「不思議なソオダ水」とは、バーで飲むハイボールのことらしい。
そこへ女が水の這入ったコップを持って来た。水には氷が這入っていて、御丁寧にレモンまで浮いていた。マノ氏はそのコップを受けとると、勢いよく飲み干そうとして、急に激しく咳こんだ。「──何だね、これは?」とマノ氏は怒った。水をくれと云ったじゃないか。「──あら」と女が云った。ソオダ水の方がいいと思ったものですから。(小沼丹「不思議なソオダ水」)
謹厳実直で真面目なマノ氏は、酒にも煙草にも女にも縁がない。
しかし、友人(アキヤマ)の息子(カンタロオ)に謀られて、酒場へ通ううちに、いつの間にか「不思議なソオダ水」の虜になり、バーの女とも仲良しになってしまう。
酒場と酒の効能を、楽しい物語で説いているような、これは「酒場文学」と言うものだろう。
酒場に対する愛情がなければ、このような小説は書けない。
「マダムの階段」も、酒場シャノワアルの女主人(ランコ)を主人公とする酒場文学の作品だ。
常連客の素敵な男性(タキタ氏)と恋愛をするため、ランコはダイエットを始める(店の最寄り駅の階段を上ったり下りたりする)。
……その夕刻、ランコは店の支度をすませると、鏡に向って化粧を始めた。多分、タキタ氏とタンノ氏は来るだろう。いつ来るか? それは判らない。彼女は眉を引きながら、例の歌を想い出した。……なお宵宵に眉つくるあわれ。「──あたしは、合歓の葉だわ」と、彼女は呟いた。(小沼丹「マダムの階段」)
酒場の女の失恋を、和歌に託して描いている。
高尚なエンターテインメント小説といった趣が感じられていい。
「乾杯」は、酒場の女と結婚をした男の物語。
彼女は空っぽの棚から瓶を降す恰好をした。更にハイボオルをつくる恰好をすると、タカギ氏の前において笑い出した。「──何だか、昔と同じみたいね。ときどき来て下さるわね?」「──そうも行かないぜ」とタカギ氏は云った。(小沼丹「乾杯」)
離婚した後も、タカギ氏は、前妻と妙な交流を強いられることになる。
微笑ましくも切ない酒場の物語だ。
「二人の男」は、見た目そっくりな二人の男が、酒場で出会う場面から始まる。
ある晩のこと、若くてあまり売れぬ画家のシマが一軒のバアでウイスキイを舐めていると、彼の隣の止り木に坐っていた一人の男がシマに話しかけた。シマはそのバア──と云ってもあまり上等じゃない──の常連みたいになっていた。(小沼丹「二人の男」)
小沼丹の酒場文学は「あまり上等じゃない」というところにこだわりがあるようだ。
男と入れ替わったシマは、一人の若い女性と知り合うことになる(お見合いの代理だった)。
「不可侵条約」も、酒場の女と三人の常連客との交流を描いた、酒場文学の作品だ。
コロ、と云うちっぽけな酒場が店を開いたばかりのところへ、中折帽を被って河の鞄を提げた一人の若い男が這入って来た。店のなかにはマダムが一人いて、スタンドの上を拭いていた。(小沼丹「不可侵条約」)
三人の男たちは、田舎から出てきたばかりの女の子をエスコートするため、週替わりでデートすることになった。
彼女は次第に垢ぬけていくが、意外などんでん返しが、結末に待っている。
これらの酒場物語は、いずれも昭和30年代に発表されたものだが、これは、トリスバー(サントリーバー)の隆盛と、ほぼ同じ時期である。
庶民的なバーは、トリスウイスキーをソーダで割ったハイボールで評判となり、サラリーマンの憩いの場となった。
洋酒の時代、ハイボールの時代、バーの時代。
小沼丹は、そんな時代の日本社会を、酒場の中から描いて見せた。
作者本人が、よほどお酒好きでなければ、こんな物語は生まれて来なかっただろう。
人生への激しい好奇心を物語で描く
一方で、酒場を離れた作品も、本作『不思議なソオダ水』には収録されている。
「赤い帽子」は、赤いトルコ帽みたいな帽子がトレードマークとなっている若い画家(ゴロオ)が、不思議なカップルと知り合いになる。
翌日の二時、ゴロオはA物産株式会社の受附で社長に面会したいと申し出た。二分ばかりすると、応接間に通るように云われた。ビルの三階にある応接間の窓から下の往来を見降していると、ドアが開いた。「──やあ、お待たせしました」(小沼丹「赤い帽子」)
ユーモアたっぷりに、男と女の関係を綴ったエンタメ小説である。
「木犀」は、かつて結婚していた女性と再会する物語で、本作収録作の中では、最も後の小沼丹を想像させる作品となっている。
彼は扉を開いて外へ出た。「──……?」木犀の甘い匂いがした。そんな筈はなかった。季節は春で、木犀の咲いている筈はなかった。それに、どこにも樹木らしいものは見当らなかった。しかし、彼はその香を嗅いだのである。あちこち、壁の剥がれ落ちた、古ぼけたアパアトが見える気がした。(小沼丹「木犀」)
別れた妻と木犀の匂いが、主人公の意識の中でつながっている。
「あちこち、壁の剥がれ落ちた、古ぼけたアパアト」は、新婚時代のイメージの残像だ。
後期の小沼丹は、こうした物語を、余韻ある叙情的な小説に仕立てる作風へと変化するが、本作「木犀」には、小沼丹のそうした才能が、明らかに顔を覗かせている。
本作『不思議なソオダ水』の中で、最もおすすめしたい作品。
「遠い顔」は、少年の目から、大人の男と女の微妙な綾を描いている。
「──何故、自殺なんかするのかしら?」私は母が呟くのを聞きました。「──あてつけにすぎないわ。莫迦な女」(小沼丹「遠い顔」)
ユーモア小説の多い本作の中では、シリアスな作風が目立つ作品である。
変わった作風という意味では、フォークロアな「女雛」も独特の雰囲気を持っている。
「──もし、もし」そのとき、呼びかける声がした。振返ると見知らぬ若い美しい女が立っていて、彼女に訊ねた。「──明石町にはどう参ったらよろしいのでしょうか?」(小沼丹「女雛」)
地方の風習に従い、生理を迎えた少女は、一番大切にしている女雛人形を川へ流す。
帰り道に現れた若い美しい女は、もちろん、大切な女雛の化身だったのだろう。
民話的な要素の強い作品である。
最後の「焼餅やきの幽霊」は、死んだ嫁が幽霊になって現れるユーモア小説である。
細君はカキ・カツオに、もし自分が先に死んだら、カキ・カツオもすぐあとから死んでくれるか、と訊ねたと云うのである。「──われまた何をか云わんや」と、AはBに嘆かわし気に云った。しかし、Bの方はうっかり訊ねた。「──それで君は何と答えたんだい?」「──むろん、すぐ死ぬと答えたよ」(小沼丹「焼餅やきの幽霊」)
どんなにおしどり夫婦であっても、嫁が先に死んでしまっては、話が別である。
主人公が、新しい恋愛を楽しもうとすると、死んだ嫁の幽霊が現れて、様々に妨害を企てる。
笑いたいけれど笑えない切なさが、この物語には含まれている。
小沼丹の先妻(和子)が急死するのは、1963年(昭和38年)のことで、本作「焼餅やきの幽霊」の発表は、1957年(昭和32年)である。
まさか、六年後になって、本当に女房が死ぬとは思っていないだろうから、この作品は、小沼丹にとって、不吉な前兆となった。
先妻亡き後、小沼丹は、ユーモア溢れるエンタメ小説を離れて、「大寺さんもの」に代表される人間ドラマを、淡々と綴っていくことになる(そうした作品群が『懐中時計』となって読売文学賞の受賞に至った)。
しかし、作風の違いはあれど、小沼丹が描き続けたものは、不思議な人間の営みだった。
そこには、人生への激しい好奇心が感じられる。
そして、男と女の関係は、壮年期を迎えつつあった作家にとって、大きな関心の対象となっていたのかもしれない。
昭和30年代、多くのサラリーマンが、小沼丹の物語に癒されて、高度成長時代の日本を生きていた。
本作『不思議なソオダ水』は、まだ若かった時代の日本を物語る戦後文学遺産として、後世まで受け継がれていくべき作品集だろう。
書名:不思議なソオダ水
著者:小沼丹
発行:1969/11/15
出版社:三笠書房