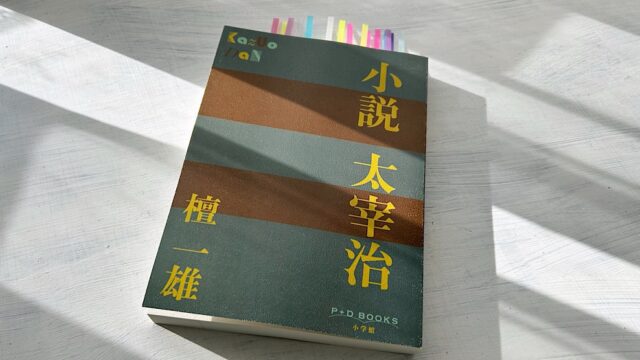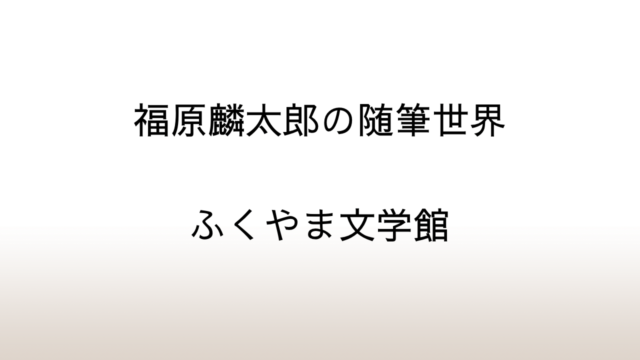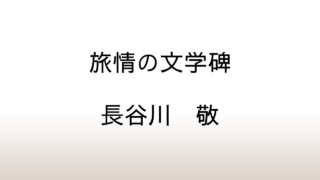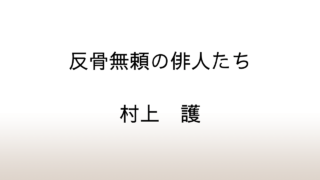高橋揆一郎「観音力疾走」読了。
本作「観音力疾走」は、1977年(昭和52年)冬号の『季刊藝術』に発表された短編小説である。
この年、著者は49歳だった。
本作は、1977年(昭和52年)の北海道文学賞を受賞するとともに、第77回(1977年・上半期)の芥川賞候補にもなっている。
ちなみに、このとき、芥川賞を受賞したのは、三田誠広「僕って何」と池田満寿夫「エーゲ海に捧ぐ」。同時受賞だった。
なお、単行本では、1978年(昭和53年)に刊行された『観音力疾走・木偶おがみ』に収録されている。
生きづらさを抱えた大人と知的障害児との心の交流
本作「観音力疾走」は、炭鉱文学の名作として知られている。
それだけに、炭鉱文化を背景とした特殊な状況設定下の物語と受け取られやすいが、ここで描かれているのは、根源的な人間同士の交流である。
その象徴とも言えるのが、コミュニケーション障害を抱えた二人目の夫<傅吉>と、知的障害を有する息子<青治>との心の交流だろう。
最初の夫に棄てられた<ふさ>は、山の中で傅吉にレイプされる。
その後も、傅吉はふさを何度も犯し、その都度、ふさに金を与えるようになるが、暴力と金は、不器用な傅吉流の愛情表現だったのかもしれない。
結局、ふさは傅吉と結婚し、前夫との間にできた3人の子どもたちと一緒に、家族5人で暮らすようになるが、長男の青治は知的障害を抱えていた。
ふさは、短気な傅吉が、青治に暴力を振るうことを極端に恐れるが、傅吉は青治に暴力を振るったりしない。
小賢しい理屈を振り回す人間を嫌っていた傅吉にとって、嘘も本当も言わない青治が、純粋な人間のように見えていたのかもしれない。
だからまじめもふまじめもないです。あのひとは子供のころからだまされてきて変人のようになったけど、青治は嘘もつかないし、はじめっからまじめもふまじめもないのだから、いってみれば動物のようですから、あの人は自分の心と合っているように思うんでないだろうか。(高橋揆一郎「観音力疾走」)
青治が肺炎で死んだ後、傅吉は炭鉱事故で植物人間のようになってしまう。
ふさの中で、死んだ青治と傅吉が同化していく場面は、家族の強い繋がりを感じさせる。
生きづらさを抱えた大人と知的障害児との心の交流。
この小説の本質的なテーマは、そんなところにあるのかもしれない。
生き生きとした炭鉱町の方言
貧しく教養もない女性<ふさ>の言葉によって語られる、この物語は、炭鉱文化を背景として描かれることによって、高橋揆一郎的な文学世界を構築している。
つまり、どれだけ普遍的な人間物語であっても、炭鉱なくして「観音力疾走」は成立しないのだ。
とりわけ印象に残るのは、生き生きとした炭鉱町の方言である。
一つの時代の炭鉱町の文化を克明に記録したものとして、この作品の文化的意義は大きい。
小説としては、特に後半部分で説明的な語りが多くなって、むしろ理屈っぽい印象さえ与えるけれど、炭鉱町の言葉が、作品としての欠点をうまくフォローしている。
ネイティブでなければ使いこなすことの難しい方言を採り入れることによって、独自の文学世界を構築したことが、この作品の最大の特徴なのかもしれない。
タイトルの「観音力疾走」もいい。
この言葉は、フサが切羽詰まったときに口走る祈りの言葉「みっしょうかなりき」の由来となっているが、「観音力疾走」が「みっしょうかなりき」に変換されて、フサの中で定着していたという細部の設定も、巧みなものだと感じた。
難を言えば、小説としてできすぎている部分は、確かにあるとしても。
高橋揆一郎の作品の中でも、特に好きな作品であることに間違いはない。
作品名:観音力疾走
著者:高橋揆一郎
書名:観音力疾走・木偶おがみ
発行:1978/7/25
出版社:東京新聞出版局