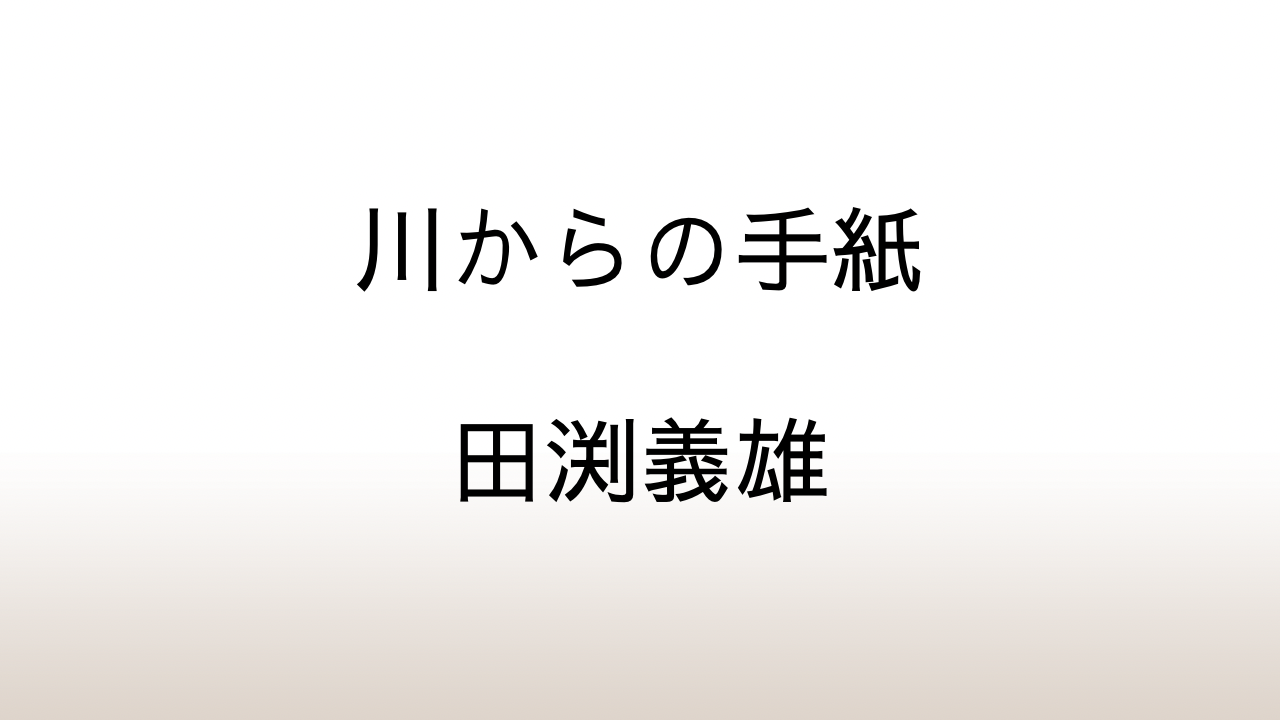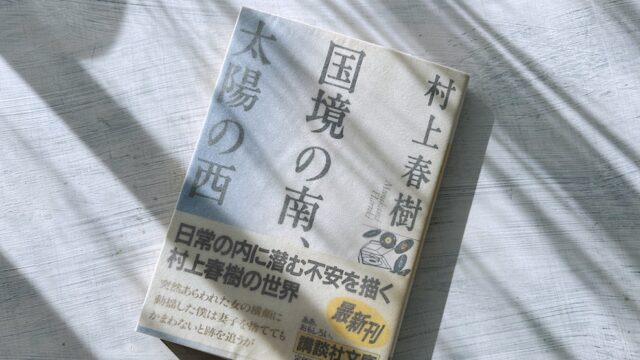田渕義雄「川からの手紙」読了。
本作「川からの手紙」は、1998年(平成10年)1月に小学館文庫から刊行されたエッセイ集である。
この年、著者は54歳だった。
魚釣りとは、人生そのものだった
本作「川からの手紙」は、フライフィッシングを中心的なテーマとしたアウトドア・エッセイ集である。
アウトドア・エッセイなのだが、読みながら、まるで哲学書を読んでいるかのような気持ちになった。
なぜなら、文章の至るところに、人生とか生きることについての警句が登場するからだ。
つまり、著者にとって魚釣りとは、人生そのものだったのだろう。
ぼくは二十八歳の秋に会社勤めをあきらめた。それから一〇年間、なんとか飯を食うためと魚釣りをするためだけの金を稼いできた。ライター(物書き)と呼ばれる職業で。しかし、ぼくはライターではない。ぼくはぼくだ。(田渕義雄「岩魚釣りのためのカルテット」)
魚釣りは孤独な遊びだ。
渓流と向き合いながら、自分自身と向き合っている。
ひたすらに自分自身と会話を続けていれば、誰だって哲学者になってしまうのではないだろうか。
釣りをしながら、あるいはキャンプをしながら、著者は一つずつ自分自身というものを見つけていく。
もしかすると、このエッセイ集は、一人の青年がフライフィッシングを通して、自我を手に入れるまでの経過を綴った哲学書なのかもしれない。
そして、わたしはリーディング・グラス(老眼鏡)なしではリーダー・ティペットにフライが上手に結べない年になった。けれども、夕暮れ時にもリーダー・ティペットを素早く結ぶことのできる若い釣り人を羨ましいとは思わない。二〇代には二〇代の釣りがあり、三〇代には三〇代の、四〇代には四〇代の、そして五〇代には五〇代の釣りの楽しみ方がある。(田渕義雄「九月の岩魚」)
「君もできるだけ早く年を取りたまえ」と、著者は若い読者に呼びかけている。
まるで、英文学者・福原麟太郎のように。
シティ・ボーイが魚釣りをする時代
もちろん、本書は紛れもないアウトドア・エッセイ集である。
わたしの趣味は、フライフィッシング。西欧スタイルの毛鉤釣りである。何事をなすにつけ、スタイルを気にするシティ・ボーイであってみれば、やっぱりカッコイイ釣りがいい。フライフィッシングは高尚な趣味なのである。(田渕義雄「千曲川源流ガイド」)
この文章が書かれた1987年(昭和62年)、日本ではアウトドアブームが始まりつつあった。
著者は、アウトドアブームというブームの到来を、不思議な気持ちで迎えている。
アウトドアがブームになる日が来るなんて、昔は誰も考えていなかったからだ。
シティ・ボーイが魚釣りをする時代。
それが、1980年代のアウトドアブームという時代だった。
本書では、アウトドアやフライフィッシングについての技術論というよりは、精神論的な部分からのアプローチが多い。
フライフィッシングという釣りはいつも、”絶対に釣れない鱒がいるのだろうか?”と考えつづけている釣りだったのだ。今までには絶対に釣れなかったはずの魚が、二〇番や二二番のミッジのウェット・フライで釣れることがわかった時、この釣りの魅力といやらしさを思わずにはいられなかった。(田渕義雄「川を渡って」)
フライフィッシングのテクニックについて解説している本ならいくらでもあるだろう。
けれども、釣りをすることによって得られる精神的効能について、ここまで深く考察している本は、そんなにはないはずだ。
著者は、やっぱり哲学者だったのだろうか?
この本を読んでいるうちに、心は渓流へと飛び、フライロッドを握りしめ、ヤマメと向かい合っている。
冷たい水しぶき、懐かしい川の匂い、吹き抜ける風の薫り。
ここは森の中だ。
そして、そんなとき、僕は、いつになく安らいでいる自分の心に気が付いていた。
書名:川からの手紙
著者:田渕義雄
発行:1998/01/01
出版社:小学館文庫