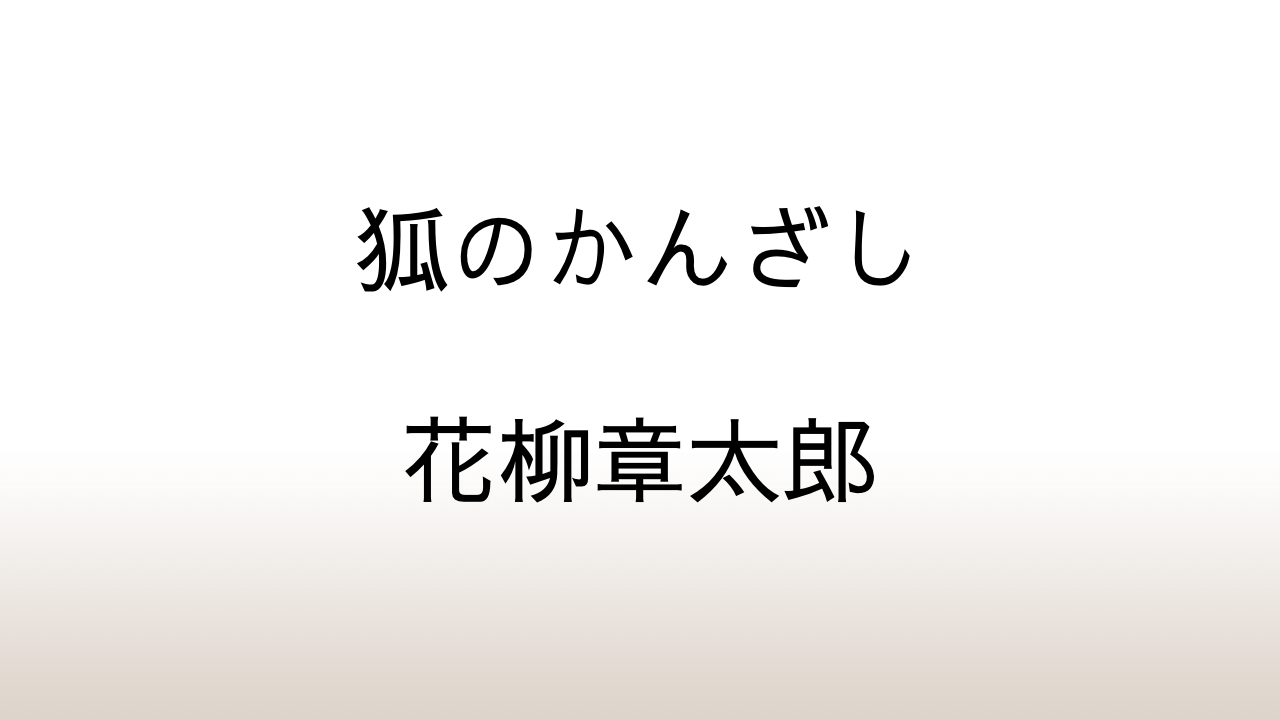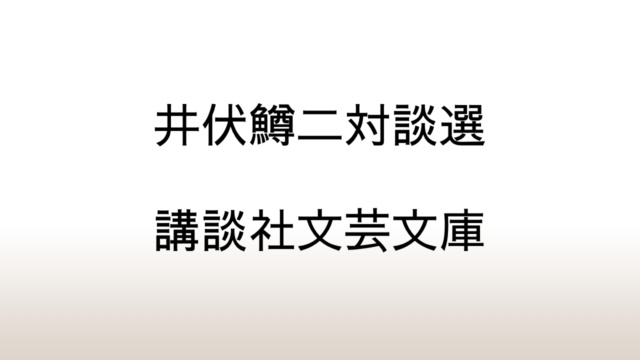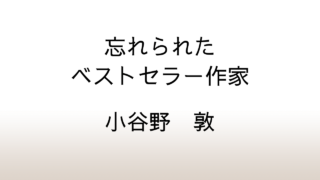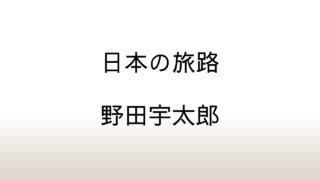花柳章太郎「狐のかんざし」読了。
本書「狐のかんざし」は、2008年(平成20年)に刊行された随筆集である。
この年は新派120年の節目の年だった。
著者の花柳章太郎は、1965年(昭和40年)、70歳で病死している。
消えゆく明治・大正の匂いを追いかけて
本書の中に「一つずつ名所消えゆく春の雪」という俳句が出てくる。
著者の花柳章太郎は、消えゆく明治・大正の匂いを追い続けた役者だったらしい。
「東京恋慕帖」は、『婦人之友』1960年(昭和35年)1月号から12月号に連載されたエッセイである。
三四郎池で出るまでに、三階建の煉瓦の洋館に沿って巴里馴染のマロニエの大木が四、五株あって、今を盛りに白い花を咲かせています。煉瓦の朱とマロニエの白との調和の妙が異国的で無聊を慰めてくれます。(花柳章太郎「狐のかんざし」)
本来、懐かしい東京風景をスケッチとエッセイで綴る「東京恋慕帖」だったが、連載中に交通事故に遭った花柳章太郎は東京病院へ入院。
思わぬ被災であったが、東京大学構内にも明治情緒はあったらしい。
久保田万太郎とともに俳句に親しんだ章太郎らしく、エッセイ中には自作の句も見える。
永井荷風『夢の女』を演じたときは、葛西あたりを散策して「秋晴れや荷風散人日和下駄」をモノにしているが、いかにも久保田万太郎流の作品である。
花柳夫妻は、谷崎潤一郎夫妻とも交流があり、和服一辺倒だった章太郎夫人が、谷崎夫人の勧めで、初めて洋装を作ったときのエピソードが綴られている。
谷崎潤一郎夫人は、うちの女房をトテモ親切に、ちょうどその頃、若い芦屋族の夫人たちは洋装が流行るはじめ、「貴方も若手の役者の細君なら、世間の流行並みに、洋服を着なさい、私がコーチをするから……」というので、三越あるいは、神戸の一流デザイナーの苦心に成る洋服が初めて調えられたわけでした。(花柳章太郎「狐のかんざし」)
「結婚して初めての夏」とあるので、大正末から昭和初期にかけての話だっただろう。
このとき、嫁の洋装づくりを全然知らされていなかった章太郎は、谷崎潤一郎のいたずらに「タチの悪い人ですよ……本当に谷崎オヤジという人は……」をグチをこぼしている。
花柳章太郎が牽引した新派は、旧派の歌舞伎に対し現代劇を演じるものだったから、流行作家との交流も盛んだったのだろう。
『あじさゐ』の永井荷風、『雪国』の駒子
1964年(昭和39年)の『毎日新聞』に連載された「新派十話」では、久保田万太郎が脚色した『あじさゐ』の原作者・永井荷風が登場している。
『あじさゐ』で毎日演劇賞を受賞した章太郎は、永井荷風を主賓に、久保田万太郎や木村荘八、川尻清潭、伊藤熹朔、中央公論社の嶋中社長らを、自宅に招いている。
永井先生は、終電車に間に合うように帰るとあって、愛用のバスケット(これには、いつも数十万円の現金がはいっていると評判だった)と古い洋傘を持ってこられたのだが、私の弟子の洋傘とそっくり同じであったため、まちがえてそれを持って帰られた。(花柳章太郎「狐のかんざし」)
市川菅野の永井荷風宅を訪問した時は、風呂へ行っていて留守だった。
そのときの模様は、毎日新聞の二行通信に「長湯荷風」(永井荷風のシャレ)と報じられたたというからおかしい。
川端康成の『雪国』を演じたときは、新潟(越後湯沢温泉)まで駒子(のモデルとなった芸者)を訪ねている。
炬燵のうえにならぶ、ひなびた田舎料理、野暮ったい大きい徳利。コタツのうえに置かれた四角塗盆の蒔絵も、何か東海道の、あの都会化してしまったさまとはちがい、床しさも感ぜられる風情でした。四、五人きた仲に、やがて目当の『駒子』が、あらわれました。(花柳章太郎「狐のかんざし」)
もっとも、このときの章太郎は、「理知的な、どこか高慢な感じのする」駒子に、あまり良い印象を持たなかったらしい。
随筆集全体からは、古き良き東京情緒への憧れが漂ってくる。
多くの作品は、高度経済成長期の昭和30年代後半に書かれたものだから、戦前東京が次々と消えてゆく時代であったことは確かである。
そして、僕は、この時代に書かれた随筆が、本当に好きなんだなあと思った。
書名:狐のかんざし
著者:花柳章太郎
発行:2008/06/01
出版社:三月書房