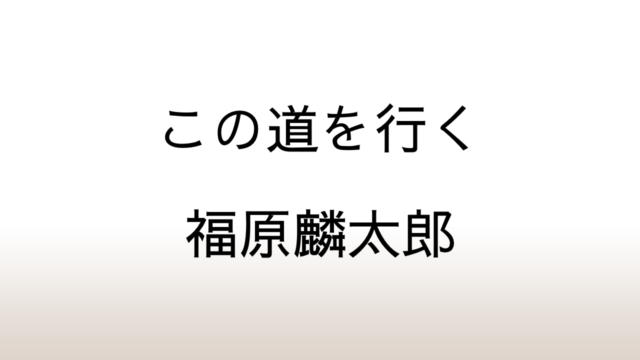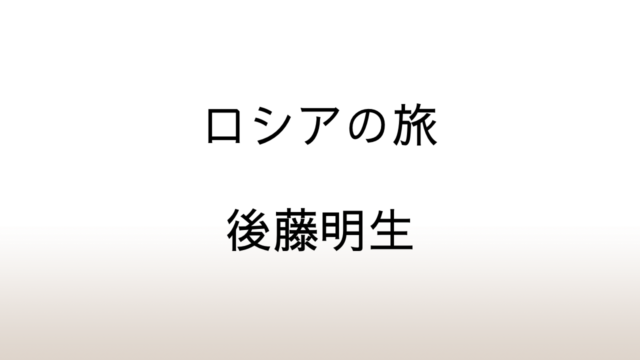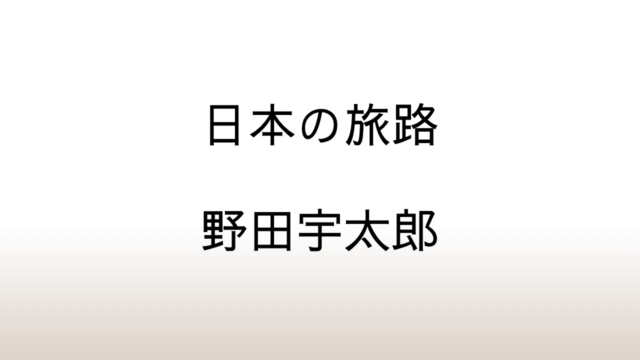庄野潤三「シェリー酒と楓の葉」読了。
本作「シェリー酒と楓の葉」は、1977年(昭和52年)1月から1978年(昭和53年)7月まで断続的(計10回)に『文学界』に発表された長篇小説である。
連載開始の年、著者は56歳だった。
単行本は、1978年(昭和53年)11月に文藝春秋から刊行されている。
ペトリとシュガー・メイプル
1957年(昭和32年)から1958年(昭和33年)までの一年間、アメリカ・オハイオ州のガンビア村に滞在した記録は、1959年(昭和34年)3月に『ガンビア滞在記』として発表されている。
それから約20年後の1977年(昭和52年)に、庄野さんは再びガンビア滞在記を書き始めた(それが、本作『シェリー酒と楓の葉』だ)。
ただし、今回のガンビア滞在記(『シェリー酒と楓の葉』)は、前回の『ガンビア滞在記』のように整理されたものではなく、アメリカでの暮らしを再現するかのような日記風に展開していく。
十月二十一日、月曜日の朝、ランサムさんが来て、一時四十五分にマウント・バーノン高校の校長に会いに行くことにしたからと知らせてくれる。(庄野潤三「シェリー酒と楓の葉」)
九月半ばに大陸横断の旅を終えてガンビアへ到着した庄野夫妻の生活は、深まりゆく秋からスタートしている。
庄野さんが、マウント・バーノン高校へ出かけたのは、大阪の帝塚山学院で校長をしている兄(庄野英二)から、「生徒と手紙の交換をする学校を見つけてほしい」という依頼を受けたからだ。
ランサムさんは「来年七十歳でケニオンを引退する詩人教授」で、汽車でコロンバスに着いた庄野夫妻を駅で迎えてくれたのも、この老詩人だった(オールドリッチ教授夫妻も一緒だった)。
ガンビアにおける庄野夫妻の暮らしは、「白塗りバラック」から始まる。
夕食前、お向いのエディノワラさんがペトリを飲みに来ないかと誘ってくれる。印度からイリノイ州のノースウェスタン大学に留学中に知り合って、二年前に結婚したアメリカ人の奥さんのジューンと、おむつをくっつけたまま家の中を這っているシリーンという女の子がいる。(庄野潤三「シェリー酒と楓の葉」)
政治学の講師であるミノー・エディノワラ夫妻との交流は、ガンビアにおける庄野夫妻の軸となるものだ。
練馬区立石神井公園ふるさと文学館『─生誕100年記念─作家 庄野潤三展』の図録にも、庄野さんとミノーの二人が写った写真が掲載されている。
ミノーと庄野さんは、一緒にペトリを飲んで友情を深めたのだろう。
ペトリは食料品店に置いてあるカリフォルニア産のシェリーの中でいちばん値段の安いものであるが、ケニオンの先生の中でまずいのを承知でこれを飲んでいる人がほかにもいることはもう少し日にちがたつと分って来る。(庄野潤三「シェリー酒と楓の葉」)
庄野さんにとってペトリ(シェリー酒)は、ガンビアの味だったのだ(だからタイトルにも入った)。
ミノーとペトリを飲んだ日、船便で着いた文芸雑誌に出発前に書いた短篇小説が載っていた。
「相客」というのはこうこういう意味で、はじめの方にA・G・ガーディナーの随筆のことがちょっと出て来るというと、エディノワラさんは、ガーディナーこそ自分の学生時代に最も愛読したエッセイストで、ああいう文章を書きたいと憧れていたといった。(庄野潤三「シェリー酒と楓の葉」)
「相客」は、1957年(昭和32年)10月『群像』に発表された短篇小説で、作品集としては『静物』に収録されている(新潮文庫『プールサイド小景・静物』で読むことが可能)。
ガーディナーが、二人の男性を深く結びつけたのかもしれない。
ガンビアへ来るにあたって、庄野さんは『ザボンの花』を持参していた。
トランクの中に一冊だけ「ザボンの花」を入れて来た。それは去年の夏に小さな出版社から出たもので、石神井公園の麦畑の畔の家での、春から夏までの日常生活を素材とした作品である。(庄野潤三「東部への旅」)
オールドリッチさんは「こちらにいる間に、自作の小説を翻訳してみたらどうか」と勧めてくれたが、これは、どうやら実現しなかったようだ。
そういえば「窓の燈」に読んだことのない作品がある。
その前、新女苑へ送る原稿を書いた。「ハローイーンの頃──アメリカの田舎町から」、四百字で九枚。横浜を出帆する前に向うへ着いたらそのうち何か送りますと約束したが、いままで気になりながら延び延びになっていた。(庄野潤三「窓の燈」)
庄野さんは、アメリカ滞在中にも、こうして日本へ向けて原稿を送っていたらしい。
「廃屋」にも「こちらでの生活風景を三十枚、書いて送るようにという出版社からの依頼の手紙が昨日、届いた」とある。
庄野さんが、日本の小説家であることは、ウイルソン食料品店の主人も知っていた。
「この土地のことを書いているのだろう。この前、ガンビアの家の数がいくらか聞いたので、そうだと思った」という。日本へ帰ってから本を出すというと、「私は読めない」そういいながら笑っている。(庄野潤三「除夜」)
オールドリッチさんから「日本の文学について何か話をしてもらえないか」と言われたときは、森鴎外「山椒大夫」「百物語」、佐藤春夫「西班牙犬の家」「田園の憂鬱」「自然の童話」「享楽論」を取り上げた。
サトクリッフさんから、いま聞いたのでは、短篇ではすべて劇的な事件を扱わず、出来事の無い話を書いているが、それは日本の作家の全体の特徴かという質問があった。私は、どちらかといえば日本の文学は劇的なものを表現するよりは静かで微妙なものを捉える方が巧みであると思うと答えた。(庄野潤三「船長の椅子」)
そのとき、名前を知らないファカルティが「ジュール・ルナアルを思い出した」と言ったので、庄野さんは「ルナアルは日本で好まれている、自分も愛読している」と答えている。
日本からの受け取った手紙に楓の話が出てくる。
植物の好きな年上の知人から来た返事の中に、私が手紙に入れて送った楓の葉が美しいので、植物図鑑で調べてみたところ、日本の楓の二十何種類のどれにも属していなかった、トキワカエデというのに形は似ているが、これは緑の葉で紅葉しないとある。(庄野潤三「シェリー酒と楓の葉」)
本屋で『アメリカの樹木』という本を買って調べると、その楓の名前はシュガー・メイプルだった。
シュガー・メイプル(楓の葉)は、庄野さんのガンビア生活を象徴する風物として、タイトルに入ることになったのだろう。
「植物の好きな年上の知人」とあるのは、あるいは井伏鱒二だっただろうか。
二時半ごろからテニスをしに出かけようとしたら、隣りのランドさん(というのはケニオンの会計の仕事をしている、年配の、いかにも温厚な人だが)の男の子が二人、家のまわりの落葉をかき集めていた。(庄野潤三「シェリー酒と楓の葉」)
サントリーの『洋酒天国29号』に、半外套を着ている二人の男の子が、大きな熊手を使って落ち葉をかき集めている写真が掲載されている(「四対一」)。
もしかすると、これが、ランドさんの男の子だったのかもしれない。
十一月一日の金曜日には、ニコディム夫人がコロンバスまで連れて行ってくれた。寒くなるのに冬物の用意をして来なかったので、私たちは気が気でなかったのだが、やっとオーバーを買うことが出来て、ほっとした。(庄野潤三「林の中」)
コロンバスで買ったツイードのコートは、『─生誕100年記念─作家 庄野潤三展』で写真を見ることができる。
アメリカで出会った人たちとの交流の記憶
エリオットさんの上の男の子のスティーブンがアジア風邪にかかったとき、庄野夫妻は、日本の『チャイルド・ブック』を持っていった。
それで明日の朝、クッキーでも買って見舞いに行こうと妻と話していたら、日本の留守宅から「チャイルド・ブック」が届いた。幼稚園で上の男の子が貰って来るのが溜っている。要らなくなったのを送ってくれるようにと妻が出紙を出しておいたら、ちょうどいいところへ着いた。(庄野潤三「ヨークシャーの茶碗」)
ちなみに、長男(龍也)は、翌年(昭和33年)4月に小学校へ入学している。
長女(夏子)は、この年(昭和32年)小学四年生で、次男(和也)は、前の年(昭和31年)の2月に生まれたばかりだった。
小学四年生の長女からは「ホームショックにならないように」という手紙も届いている(ちなみに、長女・夏子は、おかしな言葉を使うことで、庄野文学界隈では有名)。
クレスグで金髪の、髪も結えるし、服の着せ替えも出来る、いい人形が見つかった。小学四年生で、二人の弟の面倒をよくみている長女に買ってやることにする。櫛や口紅、頬紅の入った姿、石鹼とタオル、ミルクの壜の入った袋も買って、人形の箱へ入れて貰った。(庄野潤三「ヨークシャーの茶碗」)
庄野さんが買っているのはクリスマスのプレゼントで、本作『シェリー酒と楓の葉』では、秋から年末にかけてのアメリカの雰囲気を楽しむことができる。
マウント・バーノンの町はクリスマスの売出しで賑わっていた。いつも婆さんがいるクレスグにいい体格をした若い娘がアルバイトに来ている。クリスマス・カードを貼る紙と封筒、前から妻が欲しがっていた戸口に置くマット、灰皿を買い、飾り窓を眺めて歩く。(庄野潤三「廃屋」)
マウント・バーノンのビビイの家では、クリスマスのパーティーに参加した(12月上旬)。
ビビイの家の中は、賑やかにクリスマスの飾りつけをしてあった。暖炉には太い薪が燃えていて、一つのテーブルの上には葡萄酒の壜が四本とグラス、もう一つのテーブルの上には箱に入ったままのチョコレート、ボンボンその他甘いものがいっぱい並べてあった。(庄野潤三「廃屋」)
本作『シェリー酒と楓の葉』は、特別にアメリカを描いたものではないが、日常生活の中に、1950年代のアメリカの生活が登場するのは興味深い(アメリカの田舎町だが)。
クリスマス休暇には、学生の自動車に便乗して、ワシントンへ旅行に出かける。
空は少し曇って来た。前の席の、運転しない方の学生がラジオをかけてくれる。やがて「ホワイト・クリスマス」が流れ出すと、車の中の四人は一緒に歌い出した。(庄野潤三「東部への旅」)
ワシントンで別れるとき、トムは、クリスマス・プレゼントを渡してくれた。
その時、トムが、「これは僕らとジニイからのクリスマスの贈り物です」といって、紙に包んだものを二つ出して渡した。思いがけないことで、胸がつまりそうになった。(庄野潤三「東部への旅」)
庄野さんのアメリカ滞在記は、アメリカ観察の記録ではなく、アメリカで出会った人たちとの交流の記憶である。
庄野夫妻の住んでいる家にエディノワラ一家が入り、庄野夫妻は隣の狭い家へ引っ越すことになったとき、ミノーは、目に涙を浮かべて、悩ましい表情を見せたという。
庄野さんが励ますと、ようやくミノーは冗談を言って笑った。
そういって笑った、私の目から涙が出そうになったのは、ミノーがそんな冗談をいった時であった。(庄野潤三「移転計画」)
わずか三か月で、庄野夫妻が、ガンビアという大学町に溶け込んでいる様子が伝わってくる。
ニコディム夫人へのクリスマス・プレゼントとして、漆塗りのボンボン入れと箸を渡したとき、ニコディム夫人は目に涙を溜めていたという。
クリスマス・イブ、庄野夫妻は、エディノワラ夫妻と一緒に過ごした。
ジューンは黒のオーバーに黒いベレーをかぶって出て来た。「パリジェンヌだ」と口々にいう。車が走り出すと、ミノーもジューンも私も出任せの片ことのフランス語を叫び、そのうちに、「セ・シ・ボン」と四人は大きな声でうたい出した。(庄野潤三「除夜」)
エディノワラ夫妻がいなかったら、庄野夫妻のガンビア滞在は、さぞかし味気ないものになっていたかもしれない。
庄野さんのガンビア滞在記は、エディノワラ夫妻との交流記でもあったのだ。
大晦日の夜は、大学のパーティーに参加する。
十二時になった時、私はハーヴェイさんの奥さんと話をしていた。「この時、そばにいる人にキッスする習慣です」とハーヴェイ夫人がいったので、少々まごついた。(庄野潤三「除夜」)
初めてのアメリカ生活で、庄野夫妻は、まるで日本で暮らしていたときと同じように、地元の人たちとの交流を楽しんでいる。
そこには、アメリカも日本もなくて、人間同士の触れ合いがあるだけだ。
旅行から20年経って、なお、庄野さんが、当時の生活を書き残しておきたいと思った、その情熱が、『シェリー酒と楓の葉』という作品の大きな主題になっているのだろう。
書名:シェリー酒と楓の葉
著者:庄野潤三
発行:1978/11/15
出版社:文藝春秋