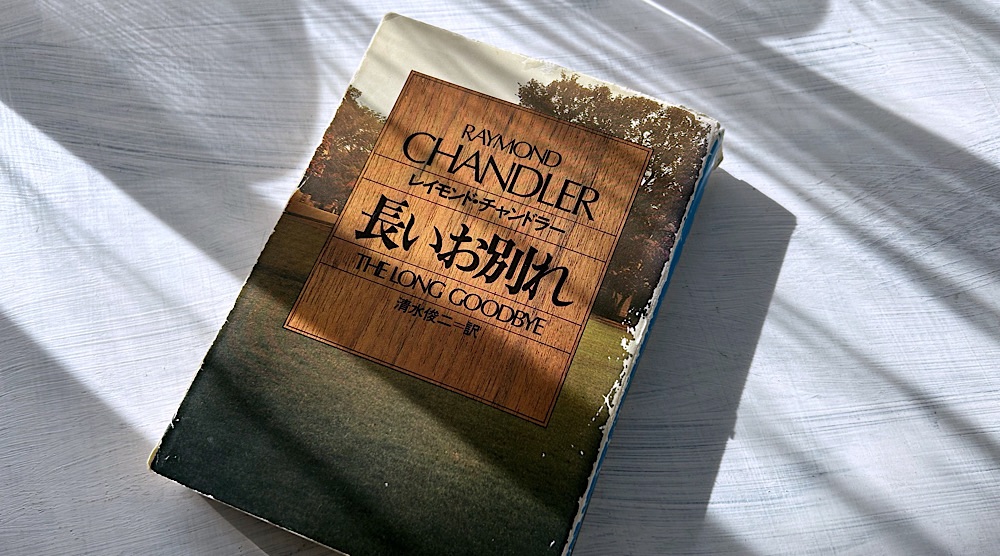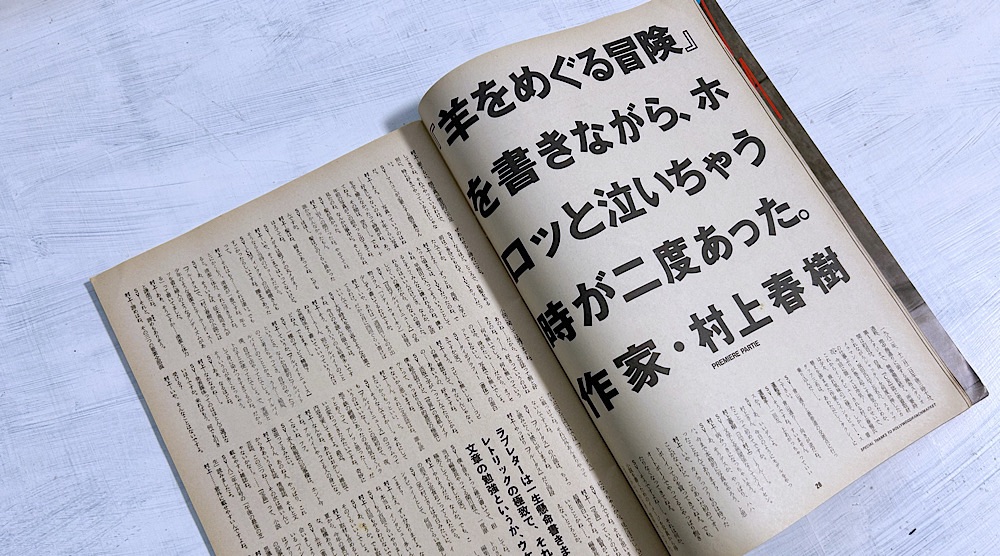レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」読了。
本作「長いお別れ」は、1953年(昭和28年)にハミッシュ・ハミルトン社(イギリス)から刊行された長篇小説である(本国アメリカでは1954年に刊行)。
原題は「The Long Goodbye」。
この年、著者は65歳だった。
1955年(昭和30年)、アメリカ探偵作家クラブのエドガー賞(MWA賞)最優秀長篇賞受賞。
村上春樹の愛読書『長いお別れ』
レイモンド・チャンドラーの『長いお別れ』は、村上春樹の愛読書として知られている。
1983年(昭和58年)にリクルートから刊行されたエッセイ集『ちょっと手の内拝見』で、村上春樹は、「僕はレイモンド・チャンドラーの『長いおわかれ』という本をこれまでに20回近く読んでいるので……」と綴っているくらいだ。
とにかく、村上春樹は、至るところで、レイモンド・チャンドラー好きをアピールしている。
【村上】結局、何か分かんなくなったら『長いお別れ』を読む、と。そうすると、あっ、小説はこういうふうに楽しんで書きゃいいんだな、と。(略)チャンドラーはいいですね、神様ですね。(村上春樹ロングインタビュー『スタジオ・ボイス』1983/Vol.87)
本作『長いお別れ』は、レイモンド・チャンドラー「フィリップ・マーロウ・シリーズ」の長篇小説全7作品の中で、最も有名で、最も長く、そして、最も人気のある作品である(つまり、レイモンド・チャンドラーの代表作ということになる)。
「ギムレットには早すぎる」や「さよならをいうのはわずかのあいだ死ぬことだ」など、実際に小説を読んだことがない人にも知られているような、いわゆる名言と呼ばれる有名な台詞も多い。
こんなとき、フランス語にはいい言葉がある。フランス人はどんなことにもうまい言葉を持っていて、その言葉はいつも正しかった。さよならをいうのはわずかのあいだ死ぬことだ。((レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」/清水俊二・訳)
この小説の根幹となっているのは、私立探偵フィリップ・マーロウと、「礼儀正しい酔っぱらい」テリー・レノックスとの、大人の友情である。
このとき、フィリップ・マーロウは42歳の独身男性で、酒場ダンサーズの駐車場で妻シルヴィアに置き去りにされたテリーを助けたことから、二人の友情は始まった。
私たちは<ヴィクター>のバーの隅に坐って、ギムレットを飲んだ。「ギムレットの作り方を知らないんだね」と、彼は言った。(レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」/清水俊二・訳)
「ジンとローズのライム・ジュースを半分ずつ、ほかには何も入れないんだ」という、テリーの「本当のギムレット」は、古谷三敏の酒コミック『BAR レモン・ハート』にも登場している。
しかし、シルヴィアの惨殺死体が発見されたとき、テリーはメキシコへ姿を消してしまう。
やがて、告白の手紙を遺して自殺したテリーの遺体が発見されて、シルヴィア殺人事件は幕を閉じるが、このエンディングは、マーロウの気に入らないものだった。
テリー&シルヴィアのレノックス夫妻の痛ましい死を外輪として、その内側に、酔っぱらいのベストセラー作家ロジャー・ウェイドと、絶世の美女アイリーン・ウェイドという、ウェイド夫妻の物語が挿まれる。
結果から見ると、ウェイド夫妻の物語は、レノックス夫妻の殺人事件を解決するための、一つの過程に過ぎないのだが、このウェイド夫妻の物語こそが、本作『長いお別れ』の主軸となっている。
やがて、レノックス夫妻とウェイド夫妻の物語が重なって、ひとつの輪となっていく構成は秀逸で、『長いお別れ』の人気は、探偵小説(推理小説)として優れたプロットによるところが大きい。
しかし、それ以上に素晴らしいのは、この作品が、ミステリー小説というジャンルを超え、ひとつの文学作品として完成されていることだろう。
君はぼくを買ったんだよ、テリー。なんとも言えない微笑や、ちょっと手を動かしたりするときの何気ない動作や、静かなバーで飲んだ何杯かの酒で買ったんだ。今でも楽しい想い出だと思っている。君との付き合いはこれで終わりだが、ここでさよならは言いたくない。本当のさよならは、もう言ってしまったんだ。本当のさよならは、悲しくて、さびしくて、切実な響きを持っているからね。(レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」/清水俊二・訳)
この物語のテーマは、大人の男性同士の友情である。
ひとつの友情が生まれ、そして終わるまでのストーリーが、美しくて示唆に富んだ文章で綴られている。
テリーが部屋を出ていった後で、マーロウは「ドアがしまるのをじっと見つめ」「模造大理石の廊下を歩いていく足音に耳をかたむけて」いる。
やがて、足音がかすかになり、ついに聞こえなくなってしまっても、まだ、マーロウは「耳をかたむけていた」。
もしかすると、マーロウは、テリーが引き返してきて、「もう一度、やりなおそう」と言うのを期待していたのかもしれない。
しかし、「彼は戻ってこなかった」。
ここに、寂しくて、はかない、大人の友情の余韻がある。
「むだだよ」と、私はいった。「テリー・レノックスはぼくの友だちだった。ぼくが彼が好きだった。警官に脅かされたからって、友情を裏切りたくはない」(レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」/清水俊二・訳)
この事件には、依頼人も報酬もない。
友情の終わりという「長いお別れ」を告げることが、マーロウには必要だったのだろう。
『グレート・ギャツビー』へのオマージュ
テリー・レノックスとの友情を取り巻くように描かれているのが、男女の恋愛模様である。
ロジャーの嫁アイリーンは、かつて、テリーと結婚していたが(元旦那)、戦争が二人を引き裂いた。
しかし、元夫テリーを忘れらないアイリーンは、テリーを裏切り続けている男好きの淫乱嫁シルヴィアを殺し、シルヴィアに寝取られた夫ロジャーをも殺してしまう(つまり、二人の男を寝取られたことが、アイリーンの殺人の動機となっている)。
「きっと戻ってきてくださると思っていたわ」と、彼女はしずかにいった。「たとえ、十年たっても」(レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」/清水俊二・訳)
一途に過去の恋愛に憧れ続けているアイリーンの姿は、F・スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』を思い出させるものだ(テリーがギャツビーで、アイリーンがディズィ)。
『ギャツビー』は、男性が別れた女性を求める物語だったが、『長いお別れ』は、女性が別れた男性を求める物語として読むことができるのではないだろうか。
かつて燃えた「一生に一度しか来ない、信じられないほどはげしい恋」の残像を求めた、人妻の物語。
もしかすると、レイモンド・チャンドラーの『長いお別れ』は、フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』へのアンサーソングだったのかもしれない(あるいはオマージュ作品)。
「私は自分を愛することに関心がなく、私が愛を感ずるものはすでに一人もいない。ロジャー(F・スコット・フィッツジェラルド)・ウェイド。追記。私が『最後の巨星(ラスト・タイクーン』)を完成できないのもそのためである」(レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」/清水俊二・訳)
ちなみに、村上春樹は、スコット・フィッツジェラルドを崇拝する酔っ払いの作家ロジャー・ウェイドに、晩年のフィッツジェラルド(『崩壊』)の姿を重ね合わせている(『ロング・グッドバイ』訳者あとがき「準古典小説としての『ロング・グッドバイ』」)。
そのように読んでいくと、『長いお別れ』は、実に奥の深い小説であることが分かる。
本作『長いお別れ』では、非常に心惹かれるサブキャラ(あるいはモブキャラ)が多い。
『長いおわかれ』におけるもっとも魅力的なキャラクターはもちろん主人公のフィリップ・マーロウだけど、その他にもこの小説には実にいろんなタイプの人物が次から次へと登場してくる。そしてまたそれぞれの人物が小説の中にとてもしっくりとなじんでいるのである。(村上春樹「何冊かに一冊はエヴァ・グリーンの小説を」/『ちょっと手の内拝見』所収)
村上春樹は、ヴァリンジャー(もぐり医者)とアール(イカれた青年)のコンビが好きだったようだが、僕は、ヴィクターのバーテンダーが好きだった(「ちかごろ、お友だちを見ませんね」)。
T・S・エリオットの詩集を愛するエイモス(リンダ・ローリングの運転手)もいい。
「”私はとしをとった……私はとしをとった……ズボンのすそをまるめあげて穿くことにしよう” これはどういう意味ですか、マーロウさま」「たいした意味はないね。気のきいた文句だというだけさ」(レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」/清水俊二・訳)
エイモスが引用するのは、エリオットの処女詩集の冒頭を飾った「J・アルフレッド・プルーフロックの恋唄」である(「”部屋では、女たちが出たり入ったりしている。ミケランジェロの話をしながら”」も同じ)。
一般に、このフレーズは、加齢で体が縮んできた中年男性のアイロニーとして解釈されているが、髪の毛の禿げた中年男性プルーフロックの姿は、ある意味で、42歳のフィリップ・マーロウを象徴するものではなかったか。
運転手エイモスの言葉は、これからリンダ・ローリング(36歳、バツイチ)とセックスをしようとしているマーロウの心境に、何らかの影響を及ぼしていると考えたくなる。
一時間ほどたって、彼女ははだかの腕をのばして私の耳をくすぐりながらいった。「私と結婚しようと思わない?」「六ヵ月とつづかないね」(レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」/清水俊二・訳)
結局、マーロウは、リンダ・ローリングと別れて、「さよならをいうのはわずかのあいだ死ぬことだ」という有名な台詞を呟くのだが、このとき、アイリーンの遺書を掲載した地元新聞『ジャーナル』が、シェイクスピア『ハムレット』にあるオフィーリアの「そなたは分別をこえて悲しみの衣をまとわねばならぬ」という言葉を引用していたことを思い出す(村上春樹の訳では「あなたは違うかたちの悲嘆を身にまとわなくてはね」)。
『ハムレット』には「結婚などというものは、もうこの世から消えてなくなれ」という有名な台詞があるからだ(福田恆存・訳)。
美しさと誠実さを兼ね備えた女性はいないというハムレットの台詞も、『長いお別れ』を読んでいると、何やら意味深なものに思えてくる(マーロウに「絶品」と言わせた美女アイリーンを示唆しているのか)。
犯罪を告白したアイリーンを放置したのも、不倫の母親には手を出さなかった『ハムレット』の教えかもしれない(「母の裁きは天に委ね、心に残る呵責のとげに責め苛ませるのだ」)。
そもそも、エイモスの好きなエリオット「プルーフロックの恋唄」は、シェイクスピアの『ハムレット』を引用した作品だから、この三つの作品は、きちんとつながっているということになる。
と言うよりも、エリオットやシェイクスピアを引用しながら、『長いお別れ』は、男女間の恋愛問題の難しさや、あるいは、人生のはかなさを伝えようとしているのかもしれない。
こうなってくると、ロジャー・ウェイドが殺される前に呟いていた「”苦痛なく夜半に消ゆるは”──それから、なんだっけ」という台詞の意味も気になるけれど(村上春樹の訳では「真夜中に苦痛もなく人生を終え」)出典が分からない。
たしかに「文学のことはむずかしすぎる」のだ(ロジャー・ウェイドの台詞)。
しかし、こうした文学的な引用が、『長いお別れ』を深みのある作品に仕立て上げていることは確かだ。
随所に登場する文学的な表現もいい。
彼女は私のすぐそばに立っていた。香水が匂っていた。匂ったと思えただけかもしれなかった。噴霧器でふりかけているはずはなかった。夏の日だからだったかもしれない。(レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」/清水俊二・訳)
完成まで、この作品は『アイドル・バレーの夏』と呼ばれていたそうである(『レイモンド・チャンドラーの生涯』)。
感傷的で繊細な表現は、大人のハードボイルドに似合っている。
もっとも、僕の一番好きなマーロウの台詞は、ダンサーズの駐車場で初めてテリー・レノックスを拾ったときの、駐車係との会話だ。
泥酔しているテリーを介抱するマーロウを見て、白服の駐車係は「お人よしですね」と、冷やかに笑う。
「あたしはこういう奴にはかかりあわない主義にしてるんです。油断のならねえ世の中なんだから、いざというときのために力をのこしておかなければなりませんからね」「なるほど、それでここまでになれたってわけか」(レイモンド・チャンドラー「長いお別れ」/清水俊二・訳)
いかした人生哲学を持っている人に出会うと、僕は心の中で呟くことにしている。
「なるほど、それでここまでになれたってわけか」──(笑)
素晴らしい小説を読むと、幸福な気持ちになることができる。
人生が豊かになる。
本作『長いお別れ』は、そんな小説の一つとして、一生読み続けていきたいと思える作品だ。
書名:長いお別れ
著者:レイモンド・チャンドラー
訳者:清水俊二
発行:1976/04/30
出版社:ハヤカワ文庫