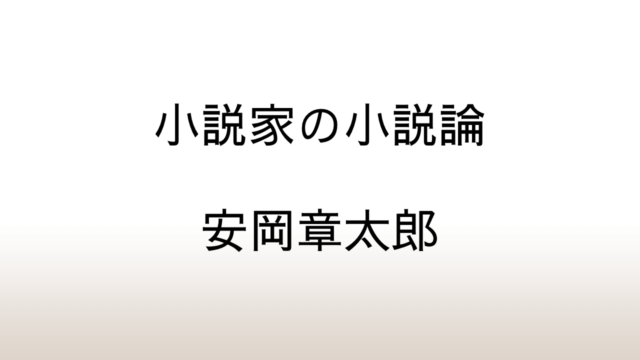太宰治「葉桜と魔笛」読了。
本作「葉桜と魔笛」は、1939年(昭和14年)6月『若草』に発表された短編小説である。
この年、著者は30歳だった。
作品集としては、1940年(昭和15年)4月に竹村書房から刊行された『皮膚と心』に収録されている。
恋愛経験なく死んでゆく青春の後悔
「はざくら と まてき」と読む。
最初、僕は、この作品を、少女小説の器を借りた反戦小説(厭戦小説)として読んだ。
この小説から伝わってくるものは、「死にたくない」という強烈なメッセージだったからだ。
「姉さん、あたしたち間違っていた。お悧巧すぎた。ああ、死ぬなんて、いやだ。あたしの手が、指先が、髪が、可哀そう。死ぬなんて、いやだ。いやだ」(太宰治「葉桜と魔笛」)
もちろん、これは、不治の病に冒されて死の病床にある妹の言葉であり、恋愛経験なく死んでゆく我が人生を後悔しているものとして描かれている。
だが、この可憐な少女小説の奥深くにあるものは、日本政府が推し進める戦争への批判ではなかったか。
当時の日本では、中国との戦争が激化する中、若者たちを取り巻く環境も、急速に厳しくなっていた。
日中戦争の開戦が1937年(昭和12年)7月で、日本軍による重慶爆撃が1939年(昭和14年)1月。
本作「葉桜と魔笛」は、このような時代に執筆された小説だから、巧妙に反戦思想が織り込まれていたとしても不思議ではない。
もっとも、太宰の嫁・津島美知子の『回想の太宰治』には、「昭和十五、六年頃はまだ戦争の影響もさほどではなく、太宰の身辺も平穏であった」という一文がある。
太宰治が、井伏鱒二の紹介で石原美知子と結婚したのは、1939年(昭和14年)1月で、「葉桜と魔笛」は、同じ年の春に書かれているから、間違いなく新婚当時の作品である。
四月太宰が書いた「葉桜と魔笛」は私の母から聞いた話がヒントになっている。私の実家は日露戦争の頃山陰に住んでいた。松江で母は日本海海戦の大砲の轟を聞いたのである。発表後この小説のことを井伏先生がほめてくださったそうで太宰はふしぎだ、意外だと言っていた。(津島美知子『回想の太宰治』)
当時の太宰に戦争への関心が高くなかったとすれば、この作品を反戦の観点から読む必要はないということになる。
もちろん、この「葉桜と魔笛」は、戦争を明瞭に扱った作品だ。
物語の舞台となっている葉桜の季節は、日露戦争の日本海海戦があったときで(5月27日)、「島根県の日本海に沿った人口二万人余りの或るお城下まち」では、日本海軍がバルチック艦隊を撃滅するための軍艦の大砲の音が、絶え間なく鳴り響いていたという(文春文庫の解説によると「或るお城下まち」のモデルは、島根県浜田市らしい)。
また、姉が偽装した手紙の中で、妹の恋人「M・T」は、病床の妹のために、毎日、庭先で口笛の軍歌(軍艦マーチ)を吹くことを約束している。
それから、毎日、毎日、あなたのお庭の塀のそとで、口笛吹いて、お聞かせしましょう。あしたの晩の六時には、さっそく口笛、軍艦マアチ吹いてあげます。僕の口笛は、うまいですよ。いまのところ、それだけが、僕の力で、わけなくできる奉仕です。お笑いになっては、いけません。いや、お笑いになって下さい。(太宰治「葉桜と魔笛」)
本作「葉桜と魔笛」は、随所で軍事色濃厚な少女小説となっているわけで、それだけに一層、戦争と少女小説との関わりについて考えたくなる。
「若草」は文学好きの若人を対象とする文芸誌で、今と違い娯楽の少なかった戦前なかなか人気があった。新進の太宰にとっては有難い発表の場であったから、「若草」の読者に向くような題材を選び、掲載誌の発表される葉桜の季節を考慮して爛漫の春にこのロマンを執筆したのである。(津島美知子『回想の太宰治』)
嫁の解釈によると、この作品はあくまでもロマンティックな少女小説ということになるらしい。
幸せな新婚時代に書かれた作品であることを考えると、物語作家としての太宰治の実力が発揮された技巧的な小説と解釈した方がスムーズで無理がないのだろう。
軍艦マーチの口笛を約束する手紙にの「お笑いになっては、いけません。いや、お笑いになって下さい」という言葉は、神聖な軍歌である軍艦マーチを「お笑いになって下さい」と皮肉っているように、つい読みたくなってしまうのだが(笑)
新しい自分への生まれ変わり
この物語の語り手である「老婦人」は、35年前の、さらに7年前に13歳だったとあるので、現在は55歳である。
先の「死ぬなんて、いやだ。いやだ」という妹の台詞の前に、「姉さん、あたしたち間違っていた。お悧巧すぎた」という言葉があるのは、処女性を重視する日本的な貞操観念を表しているものだ(そして、二人は、伝統に極めて従順な姉妹だったので、二人とも恋愛経験がない)。
作品のポイントは、「M・T」の手紙の中にある「僕たち、さびしく無力なのだから、せめて言葉だけでも、誠実こめてお贈りするのが、まことの、謙譲の美しい生きかたである」という、若者らしい生きる姿勢だろう。
僕たち、さびしく無力なのだから、他になんにもできないのだから、せめて言葉だけでも、誠実こめてお贈りするのが、まことの、謙譲の美しい生きかたである、と僕はいまでは信じています。つねに、自身にできる限りの範囲で、それを為し遂げるように努力すべきだと思います。(太宰治「葉桜と魔笛」)
当時の太宰治はまだ20代で(6月に30歳となった)、青春の日の情熱を引きずっていた、最後の時期だったと言うこともできる。
あるいは、この作品は、太宰治の青春の、最後の輝きだったのだろうか。
タンポポの花一輪の贈りものでも、決して恥じずに差し出すのが、最も勇気ある、男らしい態度であると信じます。僕は、もう逃げません。僕は、あなたを愛しています。(太宰治「葉桜と魔笛」)
「僕は、もう逃げません。僕は、あなたを愛しています」という言葉には、結婚して、新しい家庭を持った男の意欲が感じられる。
当時の女学生は、きゃーきゃー言ったかもしれない。
注目したいのは「待ち待ちて ことし咲きけり 桃の花 白と聞きつつ 花は紅なり」という、「思っていたのと違ったことの驚き」を、桃の花に託して詠んだ短歌である(白い花が咲くと聞いていたのに赤い花が咲いて驚いた)。
この歌には、「新しい自分」を期待する変身願望が感じられないだろうか。
肉体関係まで交わした女性を裏切って捨てた、過去の自分との決別。
愛のために生きる、新しい自分への生まれ変わり。
それは、結婚によって再生を願う太宰治自身の祈りとも読めて、意外と太宰は、この短歌を、最初から作品のオチで使おうと考えていたのかもしれない。
この男の手紙が、実は「姉の書いた偽物だった」というどんでん返しがあって、物語は収束に向かうが、最後にもうひとつ、謎の大どんでん返しがある。
姉が嘘の手紙で書いた「夕方六時の軍艦マーチ」が、本当に庭先から聞こえてきたのだ。
これが、作品タイトルの「魔笛」で、不可思議な口笛という意味を持つ。
あの口笛も、ひょっとしたら、父の仕業ではなかったろうかと、なんだかそんな疑いを持つこともございます。学校のおつとめからお帰りになって、隣りのお部屋で、私たちの話を立聞きして、ふびんに思い、厳酷の父としては一世一代の狂言したのではなかろうか、と思うこともございますが、まさかそんなこともないでしょうね。(太宰治「葉桜と魔笛」)
現実的な解釈をすると、魔笛は、やはり、姉妹を哀れに思う父が吹いた口笛だったのだろう。
しかし、大切なことは、主人公が、あの口笛を、「神様が吹いた魔笛だと信じていたい」と願っているという姿勢にある。
我々は、不可思議な現象に合理的な理由を付けて現実的に解釈しがちだが、世の中には、科学では証明のすることのできない神秘的なことが起こり得る。
主人公は、それを「信仰」と呼んで、物欲に惑わされる心を戒めようとしているのだ。
それは、不憫にも(恋愛経験なく)若くして死んでいった妹を弔う気持ちでもある。
そして、この世の奇跡を信じたいと願う祈りは、新たな生活を始めたばかりの、太宰治自身の祈りではなかったか。
本作「葉桜と魔笛」は、この世の奇跡(つまり神様)を信じる老婦人の祈りであるとともに、作者・太宰治自身の祈りを託した少女小説である。
新しい季節を迎えるに、ふさわしい作品ではないだろうか。
作品名:葉桜と魔笛
著者:太宰治
書名:斜陽 人間失格 桜桃 走れメロス 外七篇
発行:2000/10/10
出版社:文春文庫
日本の近代文学の世界をもっと深く知りたい方へ
日本の近代文学の世界をもっと知りたい!という方に、おすすめの記事を用意しました。
日本の近代文学のおすすめ 50選!
夏目漱石や島崎藤村、志賀直哉、小林多喜二、谷崎潤一郎、太宰治など、有名どころの名作を集めてみました。
詳細な考察記事へのリンク付きなので、作品解釈に迷ったときの参考にもなりますよ!
▶ 日本近代文学の名作おすすめ50選|中高生・初心者でも楽しめる傑作を徹底解説