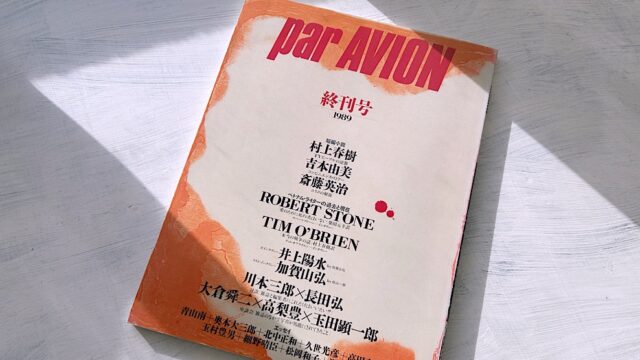福原麟太郎「書斎の無い家」読了。
本作「書斎の無い家」は、1964年(昭和39年)10月に文藝春秋から刊行された随筆集である。
この年、著者は70歳だった。
人間を愛し、人生を愛した福原麟太郎
最近は、どこの家でも書斎を作るのがブームらしい。
オシャレな部屋はともかく、小さくても狭くてもいいから、男の隠れ家とも言うべき書斎を持つことは、現代を生きる大人の男性にとって普遍的な憧れとなっているような感じすらある。
しかるに、英文学者の福原麟太郎は、書斎を持っていなかった。
それが、本書のタイトルの由来となっている。
私は書斎というものを持ったことがない。つまり本を読んだり、ものを書いたりするための部屋で、そのために便利なようにしつらえたものを書斎というとすると、私はいま半世紀ほどの間、本や机を置く部屋はいつでも持っていたが、それは同時に寝室であり、居間であり、あるいは客間であり、最上の場合でもせいぜい書庫であった。(福原麟太郎「書斎の無い家」あとがき)
偉大な学者の福原さんから「書斎を持ったことがない」という話を聞くと、何だか勇気づけられるような感じがする。
学者でも物書きでもない、一介のビジネスマンが書斎などという言葉を口にすることさえ、面はゆいような気持ちにさせられてしまう。
「一生の思い出に快適な書斎というものの中で勉強したいと思うが、まず大ていその望は適えられそうもない」と、福原さんは綴っている。
「快適な書斎というものの中で勉強したい」というところが、福原さんの本望であって、特に「勉強したい」という言葉に一番の力が入っている。
つまり、「勉強したい」という気持ちこそが、福原さんの読書の源であり、エッセイを書く原動力となっているのだ。
書斎を持たない福原さんは、人から訊ねられると「どこということもない家中が書斎なのです」と答えることにしている。
実際、あらゆる部屋に本があり、机みたいなものがあって、どこででも本を読み、ものを書いた。
これこそ、究極の書斎というものではないだろうか。
本作『書斎の無い家』という随筆集の中で、僕は、この「あとがき」が一番気に入っている。
それは、本を集めることが目的ではない、勉強することこそが、大人が生きる大きな目的なのだという戒めにもなるものだから。
もっとも、そんな福原さんであってさえ、すべての蔵書を読むことは不可能だったらしい。
しかしまあ、諸行無常だと思ってもいる。読みたくて買って来て、読まない本が、目の前に何十冊でも何百冊でもあって棚に並び卓に積み重ねてあれば、命のあるうちにこれを読んでしまうことは不可能だと、観念するのは当然である。(福原麟太郎「「鎮れ、鎮れ」」)
蔵書に対する福原さんの思い入れは深くて、「悲しき蔵書」では、師・岡倉由三郎の蔵書を処分したときのエピソードが綴られている。
なんでもない小冊子が、実は先生のロンドンやパリやベルリンのある日の記憶を濃く宿していたものに相違ないのである。生きていれば決して捨てないものが、一山三十円で処分されてしまう。実際、私は泣きたくなった。(福原麟太郎「悲しき蔵書」)
重要な書籍は文理大図書館で保存されることとなり、図書館に置けない本の中でも貴重なものについては、古本屋へ売り払うことになった。
それでも残った一山が「三十円」ということで、福原さんは「あれこそ先生の体臭を保存しているものであった」と悔しがっている。
本の価値と持ち主の思い入れとは、必ずしも一致するものではないが、「やっぱり学者は一代。本も一代のものか」という福原さんの嘆きが切ない。
なぜ、本を読むのかということについて、福原さんは「人はいかに生きるか、生きて来たか、を知り味うというのが、今日まで、私の、いわば一生の興味であった」と綴っている。
この年になると、伝記というものが面白くなった。一般的に伝記であって、文学者に限らない。ヴィクトリア女王でもチャーチルでもよい。いかに人間は生きて来たかという事実がそこにある。(福原麟太郎「老自由主義者」)
戸川秋骨も、晩年はもっぱら伝記文学を好んだと言われているが、さして有名ではない人の一生でさえも、福原さんにとっては、稗史小説より興味深いものであったらしい。
そう言えば、数年くらい前に、村上春樹も、伝記文学を好んで読んでいるというような話を聞いたような気がする。
文学のたどり着くところは、やはり、人はどのように生きるのかということになるのだろうか。
人間とか人生とかいうことを突き詰めていくと、福原さんの場合、「われ愚人を愛す」という愚人哲学に結論付けられる。
シェイクスピアの面白さとは、「人間の行為を愚に帰して、その愚かさを愛するということ」だと、福原さんは指摘する。
そういう人間観をシェイクスピアは持っていたのではあるまいか。二百年後に出たチャールズ・ラムという随筆家は、折りしも四月の随筆に「万愚節」(エイプリル・フールの日)という小品を書いて、その中で「われ愚人を愛す」という名句を残した。(福原麟太郎「四月はシェイクスピア」)
人間を愛し、人生を愛した福原麟太郎らしい言葉だと思わずにはいられない。
勉強したいという情熱
「ありし昔」は、現役だった頃の夢を見た話である。
眼をつむったままで、そういう時代があったのだ、ぼくにも、と思った。そして停年退職後の今の生活が、なんと違うことであろうと、しみじみ思った。(福原麟太郎「ありし昔」)
最近でこそ「セカンド・ライフ」などという言葉も定着したが、昭和時代まで、定年退職とは、すなわち人生からの引退であった。
「雑文を書くくらいがせきの山で、これがおれか、と何べんか歎いて来た」という文章からは、仕事(大学教授)にすべての情熱を傾けてきた男の凄まじさすら感じる。
つまり、福原さんたちの世代の人たちにとって、仕事というのは、人生のすべてだと言ってよかったのかもしれない。
ワーク・ライフ・バランスなどという言葉の広がる、何十年も昔の話である。
小品なのに「散歩」という作品は、まるで優れた短篇小説のような余韻を残した。
薄暗い住宅街の夜道、ところどころに街燈の立った淋しい道を、ぼんやりした老人の影法師が、犬をつれて、空を眺めながらゆるゆると散歩している。今夜も明日も。来年も再来年も。百年のさきにも、きっと。(福原麟太郎「散歩」)
福原麟太郎の随筆の魅力が、この作品には顕著である。
大仰な出来事の中ではなく、日常生活の一場面にこそ、人生は感じられるということではないだろうか。
久保田万太郎から俳句を書いてもらった話も印象に残る。
あれは小宮豊隆氏の金婚喜寿の会とかいう折であったろうか。久保田さんは私の隣の空いた椅子へ腰を下ろして、福原さんこういう句ができましたよ、と言われたのが、賑やかなパーティーであったので、すこし耳の遠くなった私にはよく聞きとれなかったのだが、問い返して、やっとわかったのが、「旧正やトーマスグレー墓畔吟」というのであった。(福原麟太郎「グレー墓畔吟」)
これは、昭和38年5月6日、久保田万太郎が急死したときの追悼文で、不慮の事故で死んだ久保田万太郎の死を悼んで、福原さんは「何という伏兵」と呟いている。
大きな病気ではなくて、寿司を喉に詰まらせて死んだという久保田万太郎の運命に、心臓病を患っている福原さんは、「死ぬときは心臓病ではなくて、とても思いがけぬ、いわゆる伏兵にやられるのではないか」と感じたらしい。
人生の幸福な思い出を描いたものでは、ロンドンでの暮らしを振り返った「街」がいい。
バス、自動車、トラック、ロンドンに特有なタクシー、それに、輝く街の燈火、薄く立ちこめた霧、そして歩道を行交う人の流れ、何とも知れぬ巷の雑音。そういう中をくぐっていると、何だか、幸福と淋しさに、私は胸が迫ってくる気がした。(福原麟太郎「街」)
結局のところ、人生にも光と影がある。
光と影の機微をすくい上げて表現するのが、つまり、文学というものだったのだろう。
庄野潤三に「山の上の家」があったように、福原麟太郎にも「野方の里」があった。
野方の里といっても、たいていの人にはわからない。東京都中野区野方町一丁目のことで、その五七六番地に、この筆者が住まっているのである。その野方の里だ。(福原麟太郎「野方の里」)
福原麟太郎の文学は、野方の里と切り離して考えることはできない。
その町はずれの小さな家を買って、昭和二十三年の夏、暑いさかりにこの町へ越して来たとき、書斎にした六畳の窓をあけると、生けがきの外にはすぐ麦畑が見渡すかぎり海のように続いており、涼風がそよそよと吹き込んで実に快適であった。(福原麟太郎「野方の里」)
チャールズ・ラムがロンドンの街を愛し、庄野潤三が生田の街を愛したように、福原麟太郎は野方の街を愛した。
福原さんの随筆を読んでいて、野方の街が出てくると、それだけでうれしい気持ちになってしまうのは、自分だけではないだろう。
福原さんの随筆は、ページの隅々にまで良い文章が隠されているから油断がならない。
結婚式の披露宴で「人生長いこと御苦労さまでございます」とスピーチしたこと(「愉快な驚き」)や、十九世紀の詩人ブラウニングの「われとともに老いよ」という言葉を気に入っていること(「古典と人間の知恵」)など、福原さんの言葉には、人生の深い味わいがある。
西川正身や吉田健一、庄野潤三とNHKラジオの座談会を録音している際中に、芸術院会員となった知らせが届けられた話は「その日のこと」に詳しい。
饗庭篁村(あえば・こうそん)、チャールズ・ラム、エドマンド・ブランデン、河上徹太郎、土居光知。
福原さんの文章に出てくる作家の作品は、どれも読んでみなければならないと思わせられるものばかりだ。
勉強したいという情熱。
それが、福原麟太郎という英文学者の、ほとんどすべてだったような気がする。
書名:書斎の無い家
著者:福原麟太郎
発行:1964/10/01
出版社:文藝春秋