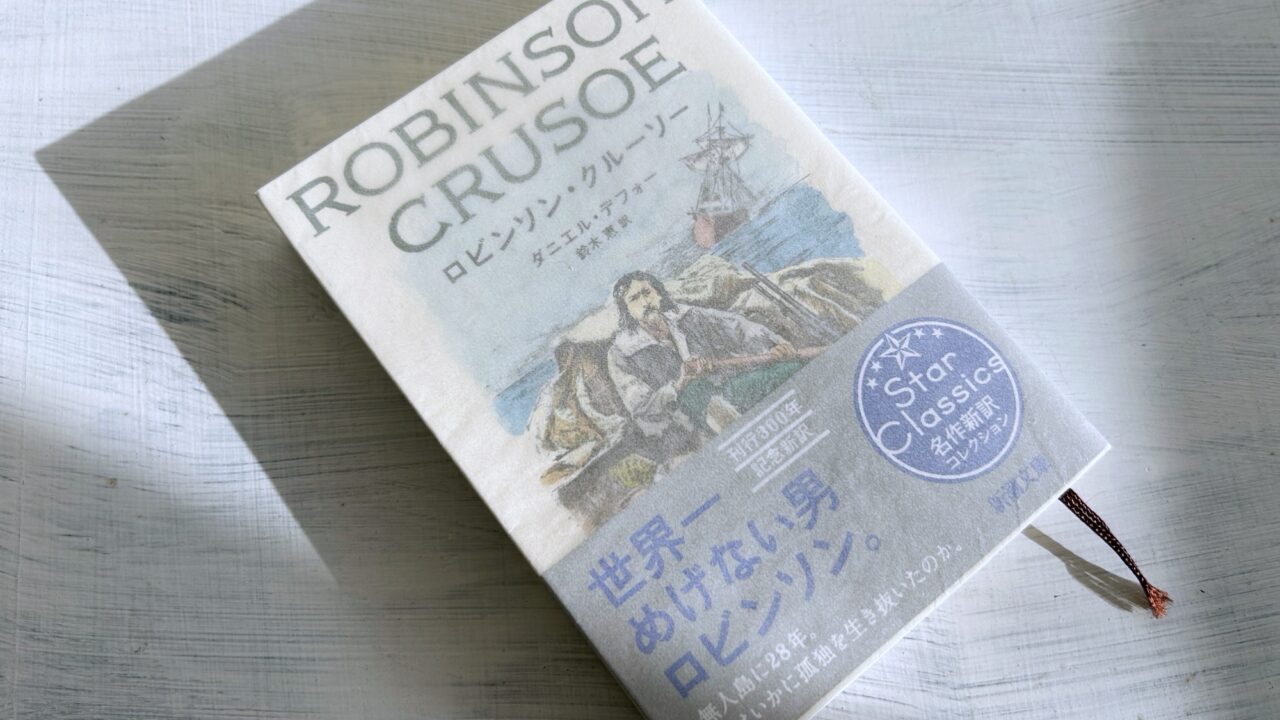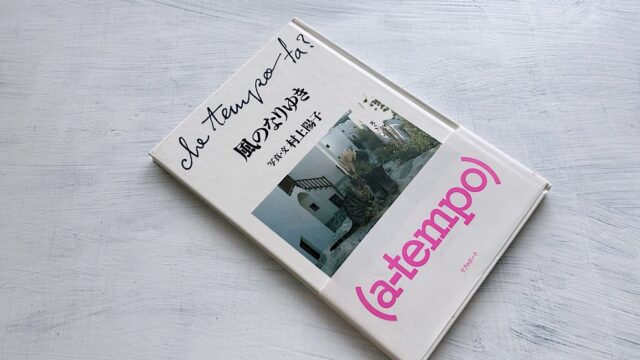ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」読了。
本作「ロビンソン・クルーソー」は、1719年に刊行された長篇小説である。
原題は「Robinson Crusoe」。
この年、著者は59歳だった。
人間の知恵を極限まで突き詰めた叡智の物語
村上春樹『ダンス・ダンス・ダンス』の中で、ユキの父親(牧村拓)の手伝いをしている男に、主人公は「書生のフライデー」というあだ名をつける。
東京に帰って以来どうも奇妙な人間にばかり会ってるな、と僕は思った。五反田君、二人のハイ・クラスの娼婦(一人は死んだ)、二人組のタフな刑事、牧村拓と書生のフライデー。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)
作家の従順な下僕である書生への皮肉を込めて、主人公は「フライデー」という言葉を引用しているのだが、その出典元は、イギリスの作家ダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』だった。
ロビンソン・クルーソーが無人島で孤独な生活を送っているときの従順な召使いの名前が「フライデー」だったのだ。
まず、彼の名前をフライデーにすることを理解させた。命を救ったのが金曜日だったので、それを憶えておくためにそう名づけたのである。(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
孤独な生活を送っているロビンソン・クルーソーに召使いがいたというのも不思議な感じがするが、フライデー(26)は、ロビンソンが無人島生活を始めてから24年目に出会った、最初の人間だったのである。
ロビンソンが漂着した無人島は、近隣の食人族が、人間を食うために利用していたらしく、フライデーも、敵の食人族に捕虜として連行されてきた男の一人だった。
危うく殺されるところを救出したロビンソンは、フライデーにとって命の恩人となり、以来、ロビンソンの従順な召使いとなったのである。
食人族の噂は、当時のイギリスの船乗りたちにも知られており、無人島へ漂着したとき、ロビンソンも、食人族との遭遇を極度に恐れている。
そのときの恐怖はとうてい言葉にできない。なんと海岸に、人の頭蓋や手足などの骨が散らばっていたのである。そればかりか火を焚いた跡と、地面を円形に彫った闘鶏場のような場所まであった。蛮人どもがそこに腰をおろして、同じ人間の肉を食うむごたらしい宴を張ったのだろう。(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
殺されるところを助けられたのだから、感謝も当然だが、地面に口づけをして「あなたの奴隷になるという誓い」まで立てるような従順ぶりを、『ダンス・ダンス・ダンス』の主人公は「書生のフライデー」に見たのかもしれない。
そこには、権力に従順な人間に対する嫌悪感が含まれていたことも、また間違いないだろう(『ロビンソン・クルーソー』を読むと理解できる)。
無人島でフライデーを手に入れた後のロビンソン・クルーソーは、島からの脱出を試みることになるのだが、そこまでの24年間は、完全に孤独な生活だった。
「ロビンソン漂流記」などという翻訳もあるが、ロビンソン・クルーソーの回想録は、そのほとんどが、無人島に漂着してからの生活の記録なので、「漂流記」などというものではない。
人間のいない島で、どのように生きたのか?というところにこそ、この物語の主題がある。
もっとも、無人島での生活などというと、我々は、素っ裸の男が、魚などを捕って生活している姿を想像しがちだが、ロビンソン・クルーソーの生活は、意外にも文化的なものだった。
まず、彼は、ちゃんと服を着ていた。
上着は山羊の毛皮でこしらえたもので、裾が太腿のなかばぐらいまであった。半ズボンも同じ材料でできていたが、こちらは老いた雄山羊の皮だったので、毛が両脇に長く垂れて、パンタロンのように脚のなかばまで届いていた。(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
頭には山羊の毛皮で作った帽子を被り、足下も半長靴のように脚にまとって両側からゲートルのように紐で締め上げたものを履いていた。
赤道に近い熱帯の無人島での暮らしは、裸で過ごすには向いていなかったのである。
食糧事情も、無人島生活が長引くにつれて充実していった。
朝食には、干し葡萄をひと房。正餐には、山羊か亀の肉をひと切れ。これはまことに残念なことに、器がなくて茹でることも煮ることもできなかったので、炙るほかなかった。そして、夕食には、亀の卵を二つか三つ食べた。(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
後に、ロビンソンは、土の器を焼くようになったばかりか、葡萄を栽培し、山羊を家畜として飼育するようになる。
ミルクを飲み、バターやチーズを生産し、いずれは、パンまで焼くようになるのだから凄い。
一般に、ロビンソン・クルーソーというと「冒険小説」のイメージがあるが、衣服を自作し、穀物を栽培し、家畜を飼育する生活は、「冒険」というジャンルを既に越えているのではないだろうか。
これは、人間の叡智に迫った物語である。
「およそこの世にある有意義なものとは、人が利用するかぎりにおいて有意義なのである」と、ロビンソン・クルーソーは言っている。
与えられた材料を使い、どのような工夫をして、生き残ることができるか。
ロビンソン・クルーソーが生きながらえた理由は、体力ではなく、知恵があったからだ。
本作『ロビンソン・クルーソー』は、人間の知恵を極限まで突き詰めた、叡智の物語なのである。
無人島でキリスト教に目覚めていく
一方で、『ロビンソン・クルーソー』は、宗教の意味を問い続けた小説でもあった。
無人島に漂着して以来、孤独なロビンソンは、自分自身との対話を繰り返す。
話し相手がいないのがつらくなると、よくこう自問したものだ──こうやって思索を通じて自分自身と対話し、さらにはこんな言い方が許されるならば、祈りを通じて神御自身と対話することのほうが、人との交わりからどんな楽しみを得るよりも、まさっているんじゃないか?(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
ロビンソンの自己対話は、まさしく、神との対話だった。
自分の不幸な境遇を呪ったロビンソンは、最後には必ず命を救ってくれた神に感謝する。
その繰り返しこそが『ロビンソン・クルーソー』という物語だったと言っていい。
早い話が、わたしの暮らしは不幸なものであると同時に、恵まれたものでもあった。その暮らしを安らかなものにするのに必要なのは、わが身に対する神の優しさと、このような境遇にあるおのれへの配慮とを感じ取り、それを日々の慰めにすることだけだった。(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
ロビンソンの自己正当化は、「酸っぱい葡萄を食べなくてよかった」と強がりを言うキツネに似ているが(『イソップ物語』)、孤独な生活における(内面の)自分自身との対話は、新しい自分を見つけるステップでもあった。
もとより、ロビンソンは、敬虔なキリスト教徒だったわけではない。
無人島に漂着した哀れな暮らしの中で、偶然手にした聖書に、魂を救われたというに過ぎない。
つまり、多くの物資と、人間の知恵と、神の教えが、無人島におけるロビンソン・クルーソーの生活を支えたということだ。
本作『ロビンソン・クルーソー』は、文明を切り開く男の物語であると同時に、キリスト教に目覚めていく男の物語でもあった。
考えてみると、『ロビンソン・クルーソー』は、主人公の若者が、旅に出るまでの過程に興味深いものがある。
おまえの境遇はそこまで下でもなければ、そこまで上でもない。その中間であり、言わば上流の庶民のようなものだ。自分は長年の経験からそれこそがこの世でいちばん望ましい、いちばん人の幸せにふさわしい身の上だと思っている。(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
船乗りを志す息子に対し、ロビンソンの父親は、中流の暮らしこそが、最も幸せな暮らしであると説いてみせる。
さらに、友人の誘いで乗った初めての船旅で遭難しかけた主人公に、船長は船乗りを諦めるよう忠告する。
「だからな」と彼は言った。「これは信じてほしいが、家に帰らないと、どこへ行っても出会うのは災いと失望ばかりで、最後にはお父さんの言葉どおりになるぞ」(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
「お父さんの言葉どおり」とあるのは、あのときの父の予言だ。
「おまえがその愚かな道へもし本当に踏み出したら、神はおまえを祝福なさらないはずだから、おまえは将来きっと、この父の忠告に耳を貸さなかったのを悔やむことになる。けれどもそのときにはもう、助けてくれる人は誰もいないかもしれないぞ」(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
結局、父の予言は的中して、ロビンソンは、父の忠告に従わなかったことを悔やむことになるのだが、こうした父への反発は、長い無人島生活の中で、幾度となくロビンソンによって反芻されることになる。
同時に、(精神的に)窮地のロビンソンを救ったのも、また、神様だった。
最初に眼にはいったのはこんな文句だった。”悩みの日にわれを呼べ、さらばわれ汝を救わん、しかして汝われをあがむべし”(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
病気で死にそうになっているロビンソンは、何げなく開いた聖書の「悩みの日にわれを呼べ、さらばわれ汝を救わん、しかして汝われをあがむべし」という言葉に心を救われ、やがて、少しずつ神との対話を繰り返すようになる。
これは、現実生活の厳しさに戸惑った人間の、普通によくある姿だったのではないだろうか。
もしかすると、デフォーは、無人島生活という舞台を借りて、迷える人間の物語を書きたかったのかもしれない。
父親の忠告に逆らい、道を踏み外した若者が、やがて、神の警告を受け容れて、人生をやり直していく物語を。
逆境にあって、”おれほど不幸な人間がいるだろうか!”とこぼしがちな人々に、ぜひともじっくり考えてほしいことである。世の中には自分よりもはるかに惨めな人間もいること、自分も神の御心しだいではそうなっていたかもしれないことに、思い至ってほしい。(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
考えてみると、我々の人生もまた、ひとつの「漂流記」みたいなものである。
過ちと後悔を繰り返しながら生きる、僕たちの漂流記。
キリスト教を知らないフライデーに、ロビンソンは、こんな言葉で神の教えを伝える。
「おれやおまえがここで悪いことをして神を怒らせたとき、神はなぜおれたちを殺さないのか。それはおれたちに罪を悔いさせ、許しをあたえるためなんだ」(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
難破船が漂着したとき、他の乗組員が全滅する中、ロビンソンだけが生き残った。
それは、自分に罪を悔いさせ、許しを与えるためだったと、ロビンソン・クルーソーは理解したのだ。
無人島(ロビンソンは「絶望島」と呼んだ)は、我々の人生そのものである。
1686年12月19日、ロビンソン・クルーソーは、召使いのフライデーとともに島を出た。
それは、この島に漂着した日から数えて、実に28年2か月19日ぶりのことだったという。
「ロビン、ロビン、ロビン・クルーソー、憐れなロビン・クルーソー、おまえはどこにいる、ロビン・クルーソー? おまえはどこにいる?」(ダニエル・デフォー「ロビンソン・クルーソー」鈴木恵・訳)
人は誰も、自分の居場所を探し続けているのだろう。
書名:ロビンソン・クルーソー
著者:ダニエル・デフォー
訳者:鈴木恵
発行:2019/08/01
出版社:新潮文庫