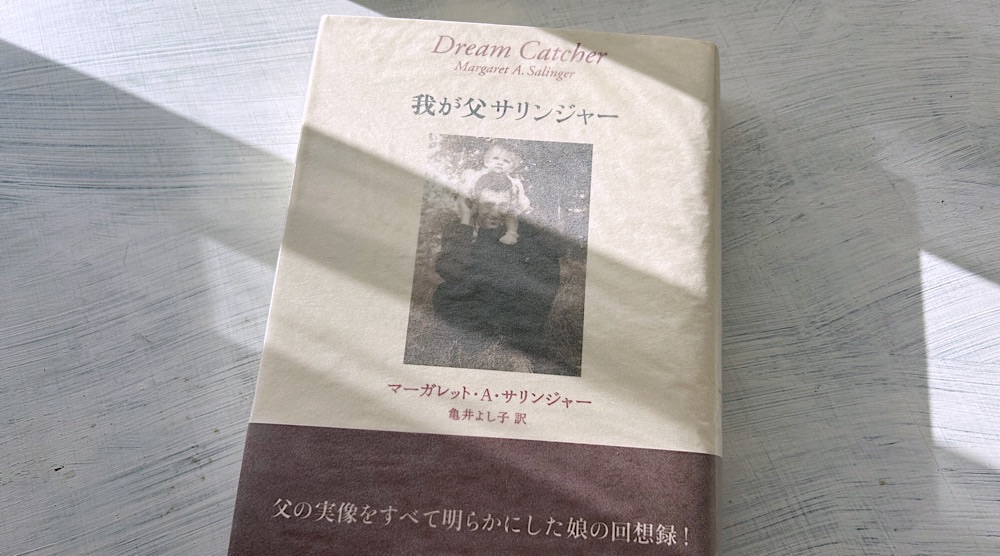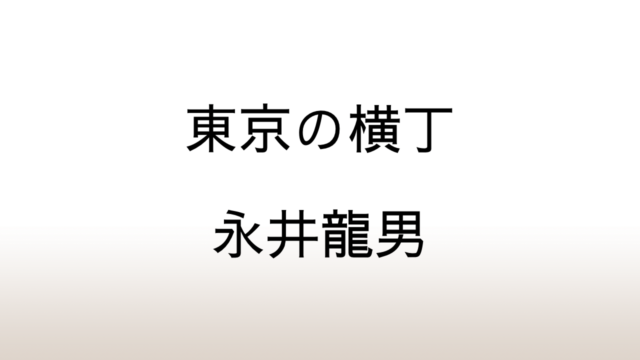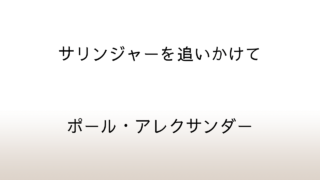マーガレット・A・サリンジャー「我が父サリンジャー」読了。
本書は、作家<J.D.サリンジャー>の長女が綴った自叙伝である。
原題は『Dream Catcher:A Memoir』(2000年刊行)。
この年、著者は45歳だった。
戦争体験と反ユダヤ主義というトラウマから逃れるためのカルト
本書『我が父サリンジャー』は、1960年代から1970年代にかけて青春期を過ごした一人の女性の、成長の過程を辿った自叙伝である。
多くの女性の成長過程で父親が関わっているのと同じように、著者<マーガレット・A・サリンジャー>にも父親がいた。
作家の<J.D.サリンジャー>である。
本書は、あくまで著者マーガレットの自叙伝であって、作家サリンジャーについての評伝ではない。
とは言え、マーガレットの成長過程を理解する上で、父サリンジャーを理解することは、極めて重要なことだ。
本書の前半部では、父サリンジャーの生き方と作品との関わりが、家族の(そして娘の)目から、かなり冷静に考察されている。
マーガレットが考えるサリンジャー文学のバックボーンは、反ユダヤ主義と戦争体験という二つのトラウマだった。
『ライ麦畑でつかまえて』では、戦争と死と混乱のトラウマが別のものと置きかえられている──敵としてのナチスが「まやかしども」あるいは「いんちき人間たち」に置きかえられている──が、人命を破壊し、生き残った人々を大混乱に陥れる彼らの力は、ナチス突撃隊の黒いユニフォームが教授たちのツイードのジャケットに置きかえられたときにも、少しも衰えてはいない。(マーガレット・A・サリンジャー「我が父サリンジャー」亀井よし子・訳)
苦しいトラウマから逃れるために、サリンジャーの求めたもの、それが「カルト」だった。
禅、ヴェーダンタ・ヒンドゥーイズム、クリヤ・ヨーガ、クリスチャン・サイエンス、ダイアネテックスと呼ばれたサイエントロジー、エドガー・ケイシー、ホメオパシー、鍼療法、マクロビオティクス、、、
1950年代、サリンジャーは、様々なカルトの本にのめり込んだ。
彼らは、ホールデン・コールフィールドのいうように、「どこかの危ない崖」の縁に立っていて、落ちそうになる自分をつかまえてくれる人を探している。自分がどんどん落ちる前にすがりつけるものを持っているランズマンを探している。カルトに入る者の多くはそこに「同じような心を持つ他人との緊密な関係」を見いだす。(マーガレット・A・サリンジャー「我が父サリンジャー」亀井よし子・訳)
戦争体験と反ユダヤ主義というトラウマから逃れるためのカルト、それがサリンジャー文学の本質だと、彼女は考えているのだ(カルトに関する分析が非常に多い)。
もっとも、ここで注目すべきは、「ライ麦畑でのキャッチャー」を探し求めながら、サリンジャー自身は、決して「キャッチャー」にはなれなかったということである。
わたしの父がどんな人物かはともかく、現実世界で彼があなた方のつかまえ屋になることはけっしてないだろう。彼の書いたものから、彼の作品から、得られるものを得てほしい。けれども作者自身は、たとえ子どもがあの恐ろしい崖に近づきすぎても、どこからともなく現れて彼らをつかまえようとはしない。(マーガレット・A・サリンジャー「我が父サリンジャー」亀井よし子・訳)
実際、何人もの若い女性たちが、サリンジャーに救いを求め、そして放り棄てられた。
マーガレットの母親<クレア>(二番目の妻)や、同棲相手<ジョイス・メイナード>(『ライ麦畑の迷路を抜けて』の著者)は、いずれも、心に闇を抱えた若い女性で、サリンジャーに救いを求め、最後には放り棄てられている。
サリンジャーが求めていたのは、「自分を救ってくれる女性」であり、「彼が救わなければならない女性」ではなかったのだ。
こうした一連の考察は、サリンジャー文学を理解する上で、非常に良い助けとなってくれるだろう。
強烈で境界性人格障害者的な要求の多さ
サリンジャーが求めた救済としてのカルトは、サリンジャーの文学作品の中でどんどん先鋭化していく。
父が特別にブレンドした「キリスト教化された」東洋神秘主義(必ずしも東洋神秘主義そのものでもないし、キリスト教でも禅でもヒンドゥーでも仏教でもない)は、自分の感情生活に圧倒される大人たちを救うために、十歳の子どもの感情生活と肉体の発達を生け贄として差しだすことを正当化する──実際には神聖化する。(マーガレット・A・サリンジャー「我が父サリンジャー」亀井よし子・訳)
「父の作品に登場するすべての善良で啓発されたキリスト的人物、すなわちテディやシーモアの背後には、女性性の断罪ないし悪魔化と、幼年期の犠牲が隠されている」と、マーガレットは考えている。
それは、男に価値を置き、女を誘惑者として位置付ける、偏った思想から生み出される文学だ。
サリンジャーの家族としての女性たちは、著者マーガレットを含めて誰もが、女性としての屈辱をサリンジャーによって与えられている。
彼に必要なのは十歳の少女であり、<フィービー>(『ライ麦畑でつかまえて』)や<マティ>(『最後の休暇の最後の一日』)は、永遠に少女のままのフィービーやマティであることを求められた。
わたしがようやく理解したのは、父は無関心であること、すなわち世俗の利害を離れて超然としていることの重要性をいやというほど説き、書き、公言しているにもかかわらず、そのじつこのうえなく要求の多い人だ、ということだった。(マーガレット・A・サリンジャー「我が父サリンジャー」亀井よし子・訳)
「父の作品のそうした面、断崖を歩く人のように強烈で境界性人格障害者的な要求の多さが、父の読者の心をあそこまで深く揺さぶるのだろう」と、マーガレットは続けている。
サリンジャー文学の熱狂的な読者は、サリンジャー教の熱狂的な信者でもあった。
サリンジャーの文学作品に触れていることで、心の傷を癒そうでもするかのように。
しかし、生身のサリンジャーは、誰も救わないし、誰もキャッチしない。
本書は、サリンジャーの実像と虚像との乖離を、娘としての立場から考察した、非常にアカデミックな内容の自叙伝である。
自己満足に終わっていないところに、この本の価値があるのでないだろうか(自己救済は多分にあるとしても)。
それにしても、本当に疲れることだったんだろうなあ。
──サリンジャーの家族であり続けるっていうことは。
書名:我が父サリンジャー
著者:マーガレット・A・サリンジャー
訳者:亀井よし子
発行:2003/04/25
出版社:新潮社