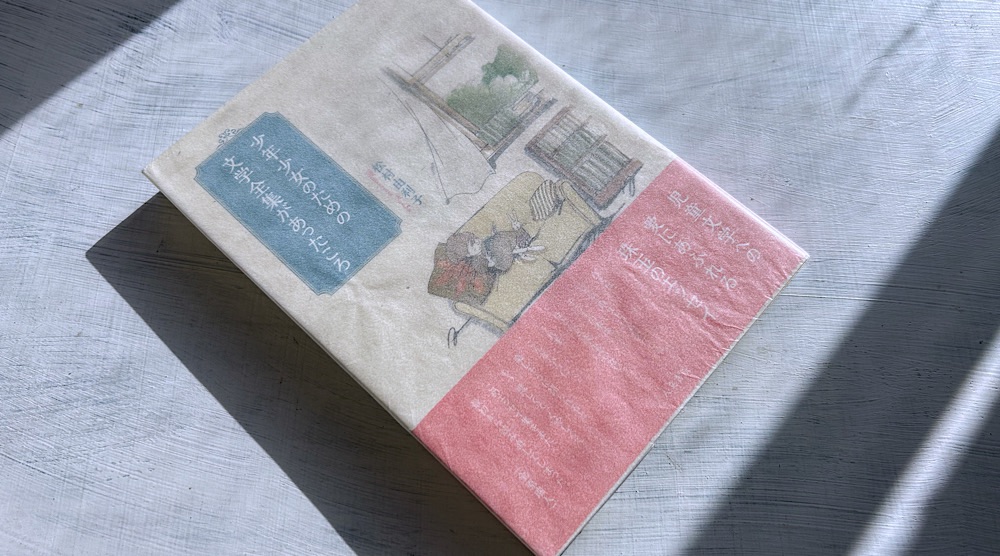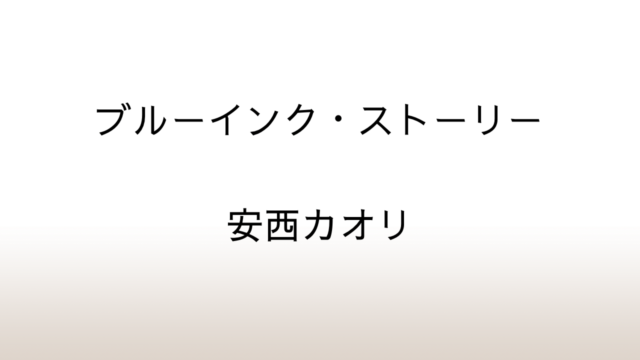松村由利子「少年少女のための文学全集があったころ」読了。
本書は、2016年(平成28年)に刊行されたエッセイ集である。
児童文学に対する深い知識と愛情
タイトルだけを見て、昭和中期に流行した少年少女文学全集の出版状況を解説している本だと勝手に思い込んで、ネットで注文した。
届いた本を読んでみると、児童文学に関する「普通の」エッセイ集である。
失敗したかな~と、ちょっと失望しつつ読み始めると、最初から面白い。
メロンを食べるときには、ルナール『にんじん』を思い出していたこと、ジャムパンやクリームパンを食べるときには、『くまのパディントン』を思い出していたこと。
カニグズバーグ『ベーグル・チームの作戦』が、松永ふみ子によって日本で最初に翻訳されたとき(1974年)は、『ロールパン・チームの作戦』というタイトルだったこと(ベーグルは日本では馴染みのない食べ物だった)。
1959年に村岡花子が訳した『アンの娘リラ』の中で、<シュークリーム>は<軽焼饅頭>と訳されていたことなど、子ども時代の思い出が、児童文学の翻訳事情へとつながっていく。
<うさこちゃん>は、いつから<ミッフィー>という名前のキャラクターになったのか。
オランダ生まれの<うさこちゃん>の本名は<ナインチェ・プラウス>(うさちゃん・ふわふわ)で、<ミッフィー>は英語版の名前だった。
明治期には、外国人の名前を日本風の名前に置き換えてしまうことも多かったらしい。
例えば、ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』の場合、1908年(明治41年)以降、西城八十や鈴木三重吉ら多くの文学者によって翻訳され、「アリス」は「愛ちゃん」「綾子さん」「美(みい)ちゃん」「あやちゃん」「まりちゃん」「すゞ子ちゃん」などさまざまな名に置き換えられた。アリスの「ア」にこだわるよりも、日本人に親しみのある名前にした方がよいと考えた訳者も多かったのだろう。(松村由利子「少年少女のための文学全集があったころ」)
ちなみに、1908年(明治41年)に日高柿軒が訳した『フランダースの犬』で、主人公<ネロ>は<清>、愛犬パトラッシュは<斑(ぶち)>、少女<アロア>は<綾子>と訳されている。
興味深かったのは、ルイス「ナルニア国ものがたり」シリーズの翻訳で知られる瀬田貞二のエピソードだ。
瀬田貞二は中村草田男に師事し、俳誌「萬緑」の初代編集長を務めた俳人だったが、「余寧金之助」という俳名で、「秋風やゴーシュのセロはゆるみがち」など、子ども向け読みものを素材にした句も多く作ったという。
おもしろいなあ。
児童文学に対する著者の深い知識と愛情が満遍なく散りばめられている。
息をもつかせぬ児童文学うんちく攻撃。
最初の数ページを読んで、やっぱり買って良かったと思った。
子ども時代に欲しかった本を「大人買い」する
子どもの頃に買ってもらえなかった本を、大人になって買うべきか。
著者は、子ども時代に憧れだった「岩波少年少女文学全集(全30巻)」が15,500円で出品されているのを、ネットオークションに見つける。
奇妙な葛藤の末、私はネットオークションで岩波少年少女文学全集を買い取った。前後して『海の見える窓』も手に入れた。所有できた喜びを感じつつ、「あのまま買わずにいてもよかったのに」という思いも抱く。自分はこれらの素晴らしい本を、ふさわしい価格で買わなかった──そんな悔恨である。また、所有したことによって、長年自分の中にあった本が失われたような気持ちにもなった。(松村由利子「少年少女のための文学全集があったころ」)
幼少期に読んだ本を大人になって読んだときに、同じ感動を再び得られるとは限らない。
楽しかった読書の記憶は勝手に自分の中で「思い出補正」されて、違う物語になってしまっている場合だってあり得る。
それでも、子ども時代に欲しかった本を、大人になって「大人買い」したくなる気持ちは、とてもよく分かるし、強く共感できると思った。
もっとも、古い本は、インターネットで探しても見つからない場合も多い(特に児童書の場合は難航する)。
だけど、子ども時代に読んだ本を入手できないからと言って、我々は極度に落胆する必要もないのだ。
あらすじも忘れ、印象的な場面だけが鮮やかに心に刻まれている本は、その人だけの一冊である。記憶違いがあっても構わない。手に残るクロス装の感触や背表紙の光沢、挿絵の印象なども含め、幼いころの自分を熱中させた本の記憶こそ、最良の宝物ではないかと思う。(松村由利子「少年少女のための文学全集があったころ」)
もしかすると、僕はこんな文章に出逢うために、この本を買ったのかもしれないな。
子ども時代の思い出探しの趣味はやめられないかもしれないけれどね。
書名:少年少女のための文学全集があったころ
著者:松村由利子
発行:2016/7/10
出版社:人文書院