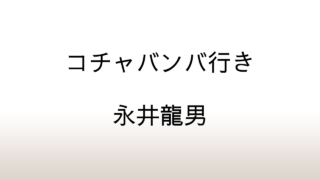永井龍男「活版屋の話」読了。
本作「活版屋の話」は、1920年(大正9年)9月、『サンエス』第二巻第九号に発表された処女短編小説である。
この年、著者は16才だった。
永井龍男にとって、初めての懸賞小説応募当選作品で、単行本未収録。
当時の筆名は「川崎龍男」だった(川崎は母方の姓)。
菊池寛が激賞したデビュー作
短編小説の名手として知られる永井龍男のデビュー作は、原稿用紙5枚の掌編小説だった。
原稿用紙5枚という短さも驚きだが、若干16歳でのデビューというのも驚きである。
永井龍男の言葉を引用すると「十六歳の少年が文房具屋で買ってきた一と綴り二十枚の原稿用紙というものに文字を書き込んだ、初めての経験」ということになるらしい。
選考にあたった菊池寛は、『サンエス』誌上で「この題材なら、選者自身も一寸短篇にかいてみたいと思う位である」と綴っている。
さらに、当時『サンエス』に作品を発表していた芥川龍之介や久米正雄、宇野浩二らに、この作品の話をしたところ、「みな会心の微笑を洩らした」そうである。
ストーリーは至ってシンプルである。
貧しい活版屋の職工と、その妻が、四つになる息子(良助)を連れて寄席へ出かけた。
五年間の勤勉を認められて、年末賞与を与えられたのである。
高座では、何かの芝居噺をやっていて、噺家が「音羽屋」とか「成駒屋」とかいった言葉を発し始める。
そのとき、四つになる良助が大きな声で「活版屋!」と言い放った。
お客の笑いがおさまると私の心はただもう自らの職業を嘲ける声に満ちて居りました。その頃活版屋の職工と一口に云われたらどんな程度までにさげすまれて居た事でしたろう! 私は何も忘れて手すりの下の灰はたきを見詰めて居ましたが、落語に笑ったお客の声に思わずびくっとしました。(永井龍男「活版屋の話」)
爆笑に包まれる会場。
いたたまれなくなった夫婦は、良助を連れて外に出る。
帰り道のさびれた縁日で、良助に玩具をねだられた主人公は、いつもなら驚くような上等のやつを買ってやった。
ただ、それだけの話ではあるが、貧しい暮らしの中に突然現れた笑いと悲しみが、この短い物語を支えている。
歴史に残る掌編小説の名作
この作品について著者は、『永井龍男全集(第一巻)』のあとがきで、こんなふうに触れている。
「活版屋の話」という小篇には、菊池寛の影響というものがなまなましく出ている。十六歳の少年が初めて原稿用紙に文字を書くに当たって意識しての模倣ではなく、菊池寛の作品に酔った一人の少年が菊池寛流に書いた、そういう内容であろうと思っている。(『永井龍男全集(第一巻)』あとがき)
菊池寛が、若い作家のための雑誌『文藝春秋』を創刊するのは、それから間もなくの1923年(大正12年)のことだった。
「活版屋の話」でデビューした永井龍男が、文藝春秋社への就職を希望して、社長(菊池寛)を訪ねるのは、それからさらに先の1927年(昭和2年)のことである。
1939年(昭和14年)、永井龍男は『文藝春秋』の編集長となり、終戦時には、文藝春秋社の専務取締役にまでなっていた。
こうした成功物語の最も最初の一滴が、「活版屋の話」という、原稿用紙わずか五枚の掌編小説であったということは、いかにも人生の妙味を感じさせる話である。
戦後、公職追放で出版業界を追われた永井龍男は、一人の作家として自立の道を歩き始め、やがて、日本を代表する「短編小説の名手」と呼ばれるようになっていく。
そんなことを考えると、「活版屋の話」は、習作には違いないかもしれないけれど、昭和文学愛好家として一度は読んでおきたい、掌編小説の名作だと思う。
作品名:活版屋の話
著者:永井龍男
書名:永井龍男全集(第一巻)
発行:1981/4/17
出版社:講談社