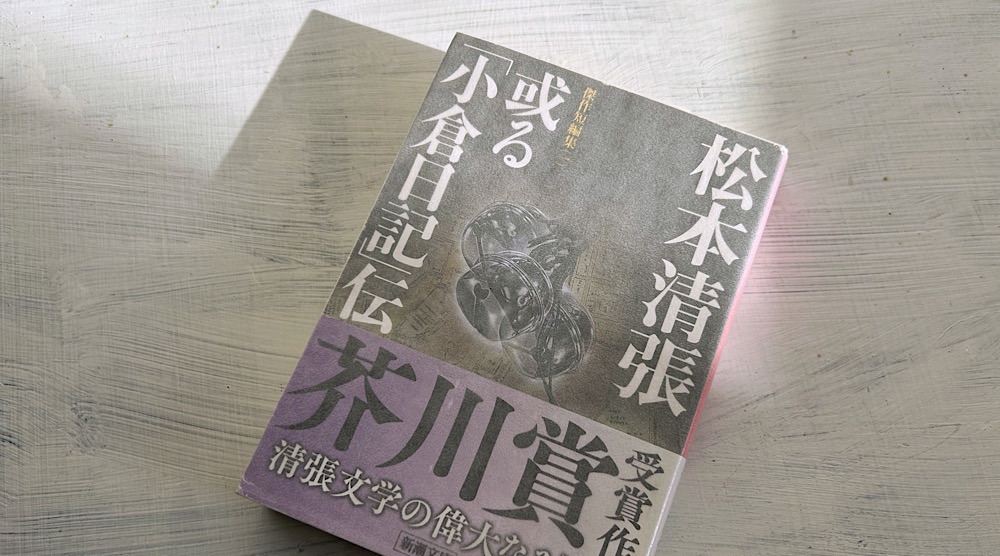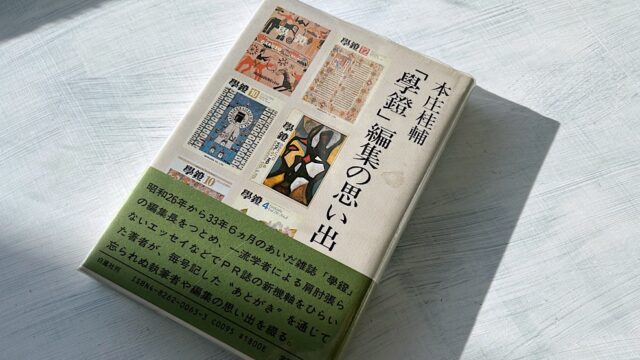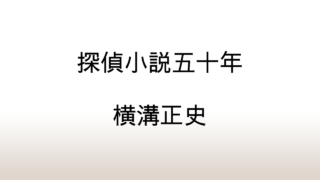松本清張「或る「小倉日記」伝」読了。
本作「或る「小倉日記」伝」は、『三田文学』1952年(昭和27年)9月号に発表された短編小説である。
この年、著者は43歳だった。
1953年(昭和28年)、第28回芥川賞受賞(同じく直木賞候補作)。
障害、シングルマザー、貧困家庭
短編小説だが、非常に読み応えのある物語だった。
ストーリーの骨格としては、北九州の小倉に住む若者が、森鷗外の『小倉日記』で空白となっている三年間の謎を追うという至ってシンプルなものだが、そこに肉付けされた物語が凄い。
主人公<田上耕作>の母親<ふじ>は、若い頃、皇族が嫁に欲しいと言ったくらいの美女だったが、家庭の事情から父親の甥と結婚する。
ところが、二人の間に生まれた子どもは、言葉と片足の不自由な障害者だった。
六尺近い長身で、顔の半分は歪み、口は絶えず閉じたことがない。だらりとたれた唇は、いつも涎で濡れて艶光りがしていた。これが片足を引きずって、肩を上下に揺すって歩くのだから、路で会った者は必ず振り向いた。(松本清張「或る「小倉日記」伝」)
耕作の父親は、彼が十歳のときに病死したから、以来、母親のふじは、シングルマザーとして障害のある息子を献身的に支え続ける。
しかし、戦後の食糧不足の中、耕作の障害はますますひどくなり、困窮する生活の末に耕作は母親を残し、41歳で亡くなった。
障害者、シングルマザー、貧困家庭という社会的弱者が、必死に生きる姿がそこに描かれているのは、果たして偶然だったのだろうか。
主人公の田上耕作も、母親の田上ふじも、そのキャラクター設定は非常に具体的で、この短編小説は、田上耕作という一人の障害者の生涯を、幼少期から丹念に辿った庶民伝とさえ言えるものとなっている。
そして、主人公の耕作が生涯をかけて探し続けていたのが、『小倉日記』の空白の三年間だった。
芥川賞の選考委員だった坂口安吾は、「この文章は実は殺人犯人をも追跡しうる自在な力があり」と、本作を評しているが、執拗に森鷗外の足跡を辿る耕作の生き様は、殺人犯人を追跡する私立探偵の執念そのものである。
実際、僕はこの作品を読みながら、何度も推理小説を読んでいるような気持ちになった。
そのくらいに世界観とプロットの設定が、しっかりと完成されている。
作中、耕作は、自分のやっている調査に、何度も疑問を持つ。
こんなことを調べまわって何になるのか。一体意味があるのだろうか。空疎な、他愛もないことを自分だけが物々しく考えて、愚劣な努力を繰り返しているのではないか。(松本清張「或る「小倉日記」伝」)
それは、この世に生きる者の誰もが、生涯に何度も出会う虚無感ではなかっただろうか。
この小説のテーマは、単刀直入に言って「生きることの意味」である。
人は何のために生きるのかということの謎が、『小倉日記』の空白を探し続ける障害者の姿によって描かれているのだ。
伝便の鈴の音が聞こえる
調査先で出会う様々な人間像が、この物語を一層深く味わい深いものにしてくれているのだが、耕作は、なぜ、それほどまでに『小倉日記』の空白に固執したのだろうか。
幼児の伝便の鈴の思い出が図らずも鷗外の文章で甦って以来、鷗外を読み、これに傾倒した。いま、『小倉日記』の散失を知ると、未見のこの日記に自分と同じ血が通うような憧憬さえ感じた。(松本清張「或る「小倉日記」伝」)
『小倉日記』の空白の三年間は、耕作にとって、自由にならない言葉や片足など、我が身の障害のようなものだったのかもしれない。
空白の三年間を補うことで、耕作は自身の障害を克服しようとしていたのだ。
まるで、祈りのように。
物語全体に通奏低音のように鳴り響いているのは、幼い日の耕作が聞いた「伝便屋の鈴の音」である。
「戸の外の静かな時、その伝便の鈴の音が、ちりん、ちりん、ちりんと急調に聞こえるのである」は、そのまま彼の幼児の実感であった。彼は枕に頭をつけて、じいさんの振る鈴の音を現実に聞く思いがした。(松本清張「或る「小倉日記」伝」)
鷗外の小説『独身』にも登場する、この伝便の鈴によって、耕作は鷗外研究に打ち込むことになるのだが、今際の際に彼がつぶやいた言葉が「鈴の音が聞こえる」だった。
あるいは、彼の生涯には、いつでも、あの鈴の音が鳴り続けていたのかもしれない。
最近読んだ小説の中では、圧倒的に一番おもしろいと思える作品だった。
作品名:或る「小倉日記」伝
著者:松本清張
書名:芥川賞全集(五)
発行:1982/06/25
出版社:文藝春秋