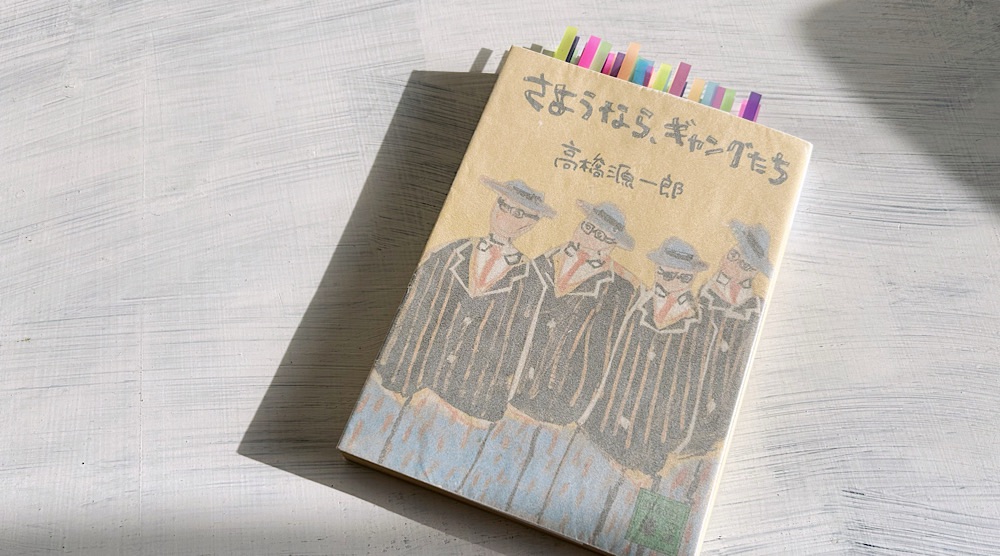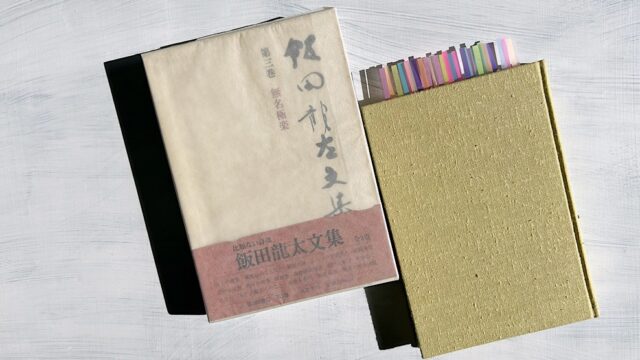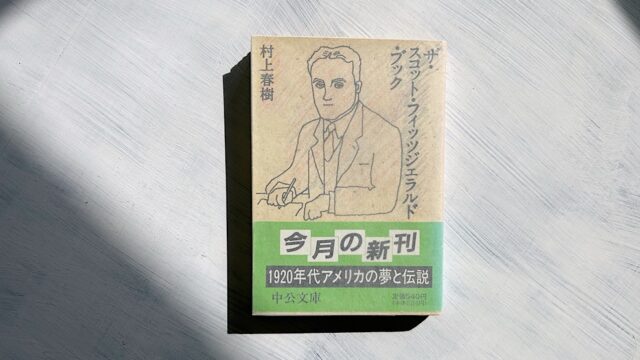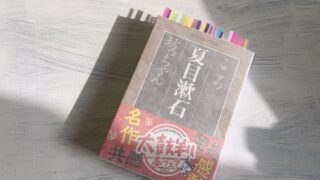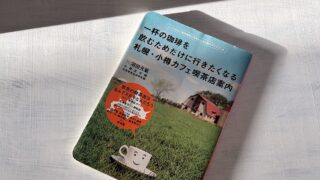高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」読了。
本作「さようなら、ギャングたち」は、1982年(昭和57年)10月に講談社から刊行された長篇小説である。
この年、著者は31歳だった。
初出は、1981年(昭和56年)12月『群像』。
1981年(昭和56年)、第4回「群像新人長篇(小説賞)」優秀作受賞。
青春に告げる「さようなら」
本作「さようなら、ギャングたち」は、青春の挫折を描いた自伝的長編小説である。
わたしはギャングだったんだ。わたしは詩人なんかではなかった。わたしは生まれてからずっとギャングだったんだ。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
青春の日の挫折を象徴する「びっこのギャング」は、「ナイスな今」に理解されることはない。
今、それがわかる。この、すごくナイスな今に。何よりもナイスな、ナイスな、ナイスなギャングであることが。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
時代は変わっていた。
もちろん、時代遅れのギャングが「ナイス」であるはずもない。
生まれる時代を間違えた主人公は、生まれたときからずっと、時代遅れのギャングだったのだ。
彼女は、時代遅れのギャングであることを否定しようとしていた。
「わたしはギャングだったから」とS・B(ソング・ブック)は言った。「今はギャングじゃないわ。もう、ギャングじゃ」とS・Bは言った。だからわたしの名前は「さようなら、ギャングたち」だ。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
ギャングであり続けることを否定する彼女の名前は「中島みゆきソング・ブック」だった。
わたしはいつかわたしが書く筈の詩集が、「中島みゆきソング・ブック」のようにすばらしい詩集であればいいと思ってきた。「中島みゆきソング・ブック」それがかの女の名前だ。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
1981年(昭和56年)、もちろん、中島みゆきは、現在のような大御所ではなかった。
この年、29歳の彼女は、「悪女」でシングルチャート1位を獲得する、流行のミュージシャンだったのだ。
人々は、時代に合わせるように名前を変えた。
古い名前は役人たちが、役所の裏の川にどんどん放りこんだ。何百万もの古い名前が川の表面をびっしり埋めて、しずしずと流れていった。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
目まぐるしく変わる戦後の価値観が、そこには投影されている。
この時代、人々は、ひとつの名前だけで生きていくことは、もはや困難でさえあったのだ。
「殺っちまおうぜ」とわたしに乗っているギャングが言った。「でも」とわたしは言った。「おれはがまんできねえ」(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
時代の転換期を恐れるかのように、ギャングは激しい抵抗を見せる。
自動車工場で、主人公は「ライン」のひとつとなった。
わたしはよくわからないものを運ぶ「ライン」を運ぶ「ライン」を運ぶ「ライン」を運ぶ「ライン」を観察しているわたしのわき腹をつっついた職長をのせて運ぶ「ライン」が流れていた。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
巨大な工場において、従業員は、もはや、自分が何を製造しているのかを知ることはない。
それは、ただの「ライン」であって、主人公も、ただの「ライン」にすぎない。
「ギャングたちの『ライン』はどんなのかな」はおしゃべりしているわたしたちの前から秒速7センチメートルで次の「ライン」へながれていった。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
世の中の仕組みは、ギャングたちには理解できないくらい、複雑になりつつあったのかもしれない。
複雑な社会では、「大観覧車」さえ生き延びることはできない。
わたしはブランコに腰かけて「大観覧車」が自殺するのをながめていた。「大観覧車」は円型のフレームを動かして観覧席をひとつずつ外していった。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
「大観覧車の自殺」は、ひとつの時代の終わりを象徴している。
問題は、主人公も、ただ、それを眺めているしかできなかったということだ。
ここに「さようなら、ギャングたち」という表題が持つ、無力感がある。
主人公には、独居房の中で、独居房の面積が持つ意味について考えることしかできない。
独居房の面積が、人格や犯罪の相違にかかわらず不変であるのは幾種類もの房をつくると看守がわからなくなってしまうからである。(略)わたしとドストエフスキーは実験的に考察した。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
著しいデフォルメの中に、青春の日の挫折が描かれている。
だからこそ、本作「さようなら、ギャングたち」は、悲しい青春物語として、読む者の胸を打つのだ。
わたしは詩人だけれど、自分がどうやって詩を書いているのか未だにわからない。詩を書く方法なんかないのだ、きっと。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
詩を書くことは、生きることでもある。
わたしは黙っていた。おばあさんは考えていた。「あばれとかげ」は静止していた。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
文学への不信は、そのまま、生きることへの不信でもあった。
「おい、ここはどこだ!」いきなり、その男は叫んだ。(略)「道に迷ったんだ! ここがどこだかわからないんだ!! 助けてくれ!」(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
そこでは、誰もが道に迷っていた。
誰もが「ここはどこだ!」と叫んでいた。
人々は、詩を通して、人生の道を切り開こうとしている。
「いいかい」とわたしは言った。「『自分で詩だと思ったものが詩なんだ。他人が詩だと思っても、自分が詩だと思わなければ詩ではない』これをぼくに教えてくれたのが誰かわかる?」(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
人生への不信は、文学への不信である。
文学への不信は、著しくデフォルメされた「物語」として具現化された。
つまり、本作「さようなら、ギャングたち」は、青春に挫折した主人公の、青春に別れを告げる物語だった、ということだ。
激しい怒りや激しい悔恨がそこにはある。
青春の日の痛みは、激しくデフォルメされながら、ポップ文学として生まれ変わったのである。
70年代の青春を葬る
本作「さようなら、ギャングたち」は、中島みゆきのアルバム『生きていてもいいですか』(1980)へのアンサーソングとして読むことができる。
「うらみ・ます」から始まる、このアルバムには「船を出すのなら九月」が収録されている(「♪船を出すのなら九月~、誰も皆、海を見飽きた頃の九月~」)。
二十世紀のおわり頃、日本語で書く詩人たちが沢山いた。わたしはその時代を「三人の偉大な詩人の時代」と呼んでいる。(略)そしてもう一人は「船を出すのなら九月」を書いた中島みゆきだ。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
谷川俊太郎、田村隆一と並んで、中島みゆきの名前がある。
それは、現代文学への不信を意味するものではなかっただろうか。
「何が起こっても、どんな激情のうちにあっても、それを統御できないようでは詩人とは言えない。詩人にとって、自分は最初の他人だ、ちがうかな?」そう言うと、冷蔵庫はにやりと笑った。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
人々は、様々に形を変えた(もちろん、名前も)。
「私は何なのでしょうか?」と「わけのわからないもの」は言った。そら来た、とわたしは思った。そんな予感がしていたのだ。この類は必ず「私は何なのだ」と質問するのだ。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
三田誠広に『僕って何?』(1977)という芥川賞受賞作がある。
時代は、まさに「私は何なのでしょうか?」と困惑していたのだ。
3号室からは煙がもくもく出ていた。(略)部屋のまん中でたき火をして、そのまわりに座ってギターを弾きながらフォーク・ソングを唄っている。<よあーけはちかい!! よあーけは、ちかい!!>(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
あれほどまでに感動的だった岡林信康の「友よ」も、今や、過ぎ去った時代の象徴でしかない(「♪夜明けは近~い、夜明けは近~い、友よ~」)。
彼らは、今の時代に歌うべき歌を、まだ知らなかったのだ。
なぜなら、彼らは、新しい時代に生きる「言葉」を失ってしまっていたから。
「おしのギャング」は自分の頭の中に書いてある言葉を探しはじめたが、どの頁もまっ白だった。まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。まっ白。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
言葉探しは、自分探しでもある。
「おしのギャング」は、「コーヒーとサンドイッチ」以外の言葉を自分の人生から見つけ出そうとしていた。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
かつて、生きることに、これほど苦しんだ時代があっただろうか?
それは、激しく生きた1960年代の残響のようにも聞こえてくる。
「私たちは、行動を終えた後、夜、机にむかっている時めまいがするほどの不安を感じます。それは私たちが、毎日少しずつこの世界から遠ざかってゆくという不安です」(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
大きく移り変わる時代の中で、彼らだけが、ギャングでいることを捨てきれないでいた。
「ギャングは何回殺されても生きかえります。ギャングを選択した者は殺されても殺されてもその度に、生きかえります。わたしたちは、顔がつぶされない限り、いつまでも、いつまでも、いつまでも、ギャングなんです」(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
「さようなら、ギャングたち」という名前の主人公は、結局、「ギャング」に別れを告げることはできない。
「S・B(ソング・ブック)」とわたしは言った。「『さようなら、ギャングたち』って、どんな意味なんだい?」(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
それは、挫折の青春ではあったけれど、その挫折を、主人公は否定することができなかった。
ここに、本作『さようなら、ギャングたち』という作品が持つ、大きな主題がある。
挫折を含めて、主人公は、自分の青春を受け容れようとしていたのだ。
わたしはトイレのドアを開けた。わたしは洗面所のタイルの床をびっこをひきながらぐるぐる回った。女の子はトイレのドアにもたれたままわたしを見ながら一生懸命オナニイをした。「もっと走って! もっと走って!」(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
若い男の子と若い女の子がいて、彼らはセックスをすることができない。
セックスよりもオナニーを愛する彼らは、他者と関わることができない、新しい時代の主人公たちだ。
「あんた、ギャングなの? 詩人なの?」(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
1970年代の終わりから、1980年代の初めにかけて、70年代の青春を愛しく葬るような作品が、いくつも登場した。
村上春樹『風の歌を聴け』(1979)や山川健一『鏡の中のガラスの船』(1977)などは、いずれも、青春の挫折を愛しく慰めるような物語であったと言っていい。

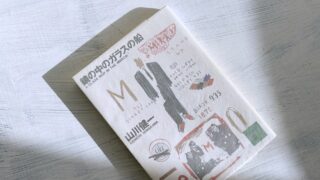
激しく燃えた炎の埋もれ火が、そこにまだ息づいていたのだ。
本作『さようなら、ギャングたち』は、長大な叙事詩である。
すこし、ナイスなきもちになってきたぞ。そうとも。ベリ・ナイス、ベリ・ナイス、ベリ・ナイスなきもちに。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
革命の時代は終わったかもしれないけれど、彼らの時代は、これからだった。
新しい時代へ進むためにも、70年代の青春を弔うことが、彼らには必要だったのかもしれない。
トーマス・マンという名前にふさわしい物語りを一つか二つ作るんだ、今すぐ。考えて、考えて、まず題名だ、何でもいい。「ジョン・レノン対火星人」それじゃだめだ、あんまりだな、まるでトーマス・マン的とはいえない。(高橋源一郎「さようなら、ギャングたち」)
新しい物語は、新しい人生の始まりを暗示している。
果たして、主人公は、新しい物語を完成させることができるのだろうか。
書名:さようなら、ギャングたち
著者:高橋源一郎
発行:1985/03/15
出版社:講談社文庫