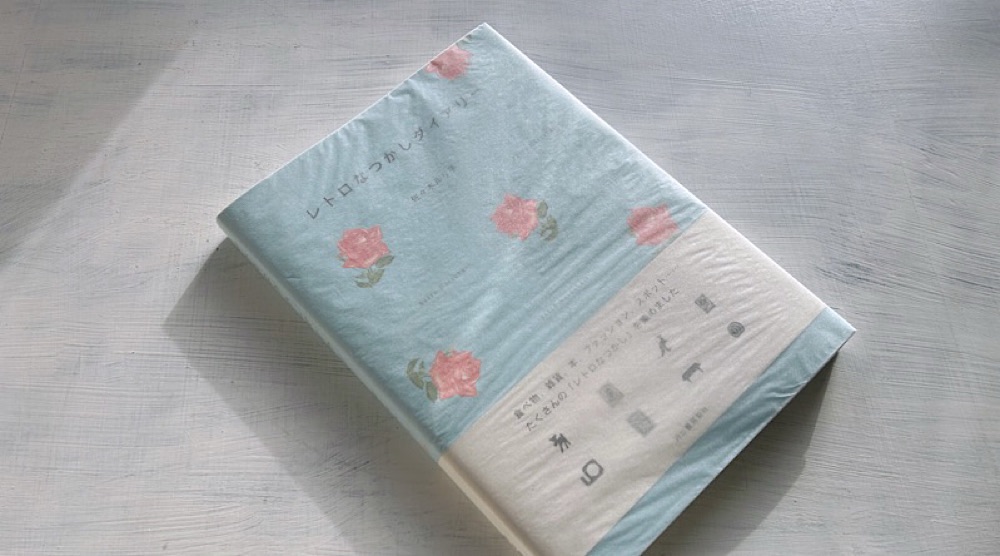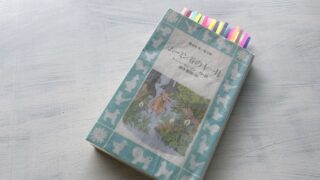佐々木ルリ子『レトロなつかしダイアリー』読了。
本作『レトロなつかしダイアリー』は、2005年(平成17年)12月に河出書房新社から刊行されたレトロ本である。
これは誌上インスタグラムだったのか?
札幌の街角から骨董店が少なくなったような気がする。
ゼロ年代の頃は、(小さいけれども)個性的なお店が、あちこちで頑張っていたのではなかったか。
その中には、骨董品とかアンティークとか格式張らずに、レトロで懐かしい気軽な雑貨を扱うお店も少なくなかった(「ほんのり横丁」とか「1番館」とか)。
『レトロなつかしダイアリー』を読んでいると、そんなレトロな空気に溢れていた懐かしいお店のことを思い出す。
本書『レトロなつかしダイアリー』は、決して骨董品やアンティークの解説書ではない。
「レトロ」で「懐かしい」「ダイアリー」という書名からも、それは伝わってくる。
ここにあるのは、ただただレトロで懐かしいだけのチープなモノたちだ。
この手の本をコレクター的な男性が作ると、スノッブな蘊蓄(うんちく)だけでページが埋まってしまうものだが、難しいコメントやマニアックな解説は、この本にはない(幸いなことに)。
あるのは、レトロで懐かしいアイテムの小さな写真と簡単なコメントだけ。
「ダイアリー」というよりは「カタログ」で、作者のアンテナがとらえたモノが、そこにはずらりと並んでいる。
本格的なアンティークにはあまり興味がなく、チープで親しみやすいものが好き。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
つまり、スローライフが日本中を席巻した、あのゼロ年代的に、作者はゆるゆるのレトロコレクターだったのだ。
ツイッターでつぶやく気軽さが、この本にはある。
というか、ツイッター(2006)やインスタグラム(2010)に先駆けて、本書では気軽な(写真付き)コメント投稿を実践していたと言っていい。
この本では、食べ物、雑貨、ファッション、スポット、言葉など、たくさんのジャンルの中から、わたしが懐かしいと感じるものを紹介しています。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
「懐かしいもの」が「古いもの」ばかりとは限らない。
昔からある定番商品、今はなくなってしまった昔のもの、そして、昔のものじゃなくても、どこかレトロでノスタルジックな雰囲気のあるものなら何でも!という気持ちで集めました。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
コンセプトが既にゆるい。
定義を定めてコレクションするのではなく、自分の直感を信じて集める。
これこそ、まさに、女性の柔軟性ではなかっただろうか(男性コレクターは定義付けが好きだ)。
チープで懐かしいモノたち
一番最初に「アイスのフタ」が出てくる(ゆるい)。
最近では、ペラッとはがすタイプや、パカッとはめるタイプのフタが主流で、1枚の丸い紙でできたフタは見かけなくなりました。ちょっと残念です。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
ツイッター的に気軽なコメントに、さらにオマケがついてくる。
フタについたアイスクリームを舌でペロッ。カップ入りアイスを食べるときのお約束でしたね。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
他愛ないようでいて、その時代を生きた者にしか分からない風俗描写。
今なら写真付きでX(旧ツイッター)へ投稿して、たくさんの「いいね」をもらっていたかもしれない。
そう、本書『レトロなつかしダイアリー』は、思わず「いいね」を押したくなるような、たくさんの共感性に満ちた「なつかし本」なのだ。
プレミアがつきそうなレア・アイテムというよりは、近所のコンビニで買えそうな商品が多い。
アクアフレッシュ
登場したのは、わたしが子どものころ。歯ブラシの上で、本当にトリコロールカラーのストライプになっているのを見たときの感動といったら!(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
いつの時代も、女子は乙女チックな「トリコロール」が大好き。
サンスター「アクアフレッシュ」の発売開始は1981年(昭和56年)で、当初は「白と青のストライプ」だった。
乙女チックといえば、洋菓子である(「スイーツ」ではない)。
アルプス洋菓子店のパルミエ
「洋菓子店」という名前がつくだけで、乙女な雰囲気が漂うから不思議です。駒込にある老舗の洋菓子店。ハート形のパルミエがお気に入りです。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
レトロで懐かしいものは、つまり、乙女な雰囲気が漂うものでもある、ということなのか。
駒込「アルプス洋菓子店」の包装紙は、東郷青児・作のレトロチックなデザインだったが、2019年(平成元年)3月に閉店、本当に懐かしいものとなってしまった。
何気に貴重なアイテムが「アメリカンクラッカー」。
アメリカンクラッカー
子どものころよく遊んだおもちゃ。わたしのまわりでは「カチカチ」、または「カチカチボール」と呼んでいました。リングを持って上下させると、玉がぶつかり合うというシンプルなものですが、かなり熱中していました。ほのぼのした時代だったんですね。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
日本におけるアメリカンクラッカーは、1971年(昭和46年)にアサヒ玩具から発売されたのが始まり(「アメリカで大流行のおもちゃ」)。
「バンバンボール」とか「フリスビー」とか「ヨーヨー」とか、当時はアメリカン・カルチャーが、日本の若者たちに大人気だった。
80年代の若者たちに指示されたものといえば「オサムグッズ」。
オサムグッズ
ミスタードーナツで有名な原田治さんのグッズ。昔は、ハンカチやペン、下敷き、レターセット、バッグ……、オサムグッズで統一していました。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
当時は、お気に入りのキャラクター・アイテムで、文房具を統一するのが流行していて、他人と異なる自分だけのキャラクターを確保するのが大変だった。
文房具以外にも、コーム(くし)や洋服ブラシなどを持ち歩いていたものである(中学生の分際で)。
階段で遊ぶスプリング
大好きでした、これ。階段などの段差を使って遊ぶおもちゃ。スプリングの動く様が楽しく、見ていて飽きません。百円ショップでは色つきを発見。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
正式名称は「スリンキー」。
日本では、1960年代に三光発条(現・サンコースプリング)が「トムボーイ」の名称で販売し、大ヒット商品となった。
「地球ゴマ」も同時期に流行った懐かしいオモチャである。
昭和40年代から50年代にかけて子ども時代を送った人には、懐かしいオモチャがたくさん出てくる。
怪獣消しゴム
20年くらい前に、ガチャガチャで友人の子どもたちが集めたもの。当時のヒーローや怪獣たちです。眺めていると、ほほえましい気分になります。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
消しゴムと言いながら実用性のない怪獣消しゴムは、『ウルトラ怪獣消しゴム図鑑』(2019)という本が出版されるほど、コレクターが多い(安くて子どもにも集めやすかったためか?)。
男性コレクターは「コンプリート」とか「分類」とか、やたら学術的に集めたがる。
ボードゲームも、昭和世代の子どもたちのスタンダードだった。
人生ゲーム「ハイ&ロー」
タカラが出した新タイプの人生ゲーム。パッケージがノスタルジックです。やっぱり、いちばんしっかりした人が「銀行」になって遊びます。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
「人生ゲームハイ&ロー」は、1979年(昭和54年)から1982年(昭和57年)にかけて、日本テレビで放映されていたクイズ番組(愛川欽也が司会)。
タカラのボードゲームは、1980年(昭和55年)に発売された。
ファミコン登場まで、子どもたちの遊びといえば「ボードゲーム」が主役だったのだ。
「ダイヤモンドゲーム」も懐かしい。
骨董市で見つけてきたような、正統派(?)のガラクタもある。
たんすのとっ手
たんすか戸棚、小さい物入れなどのとっ手だと思います。骨董市に行くと、こういった分解もの(と、勝手に呼んでいます)が、さまざまに売られています。使いみちは考えずに、きれいなので、可愛いので買ってきます。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
ガラクタのようで、意外と高値なガラスの取っ手は、女性に大人気らしい。
「分解もの」では、古民家の窓ガラスなども集めがいがある(ちょっと大きいけど)。
ガラクタには「実用性のないものほど魅力的だ」というアンビバレントな特質がある。
貯金&新聞バッジ
骨董市で見つけました。どんなふうに使っていたのでしょうか。小学校の「貯金係」「新聞係」かな、なんて想像をめぐらすのも、楽しい時間。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
昔の学校で使われていたクラス委員のバッジも、かなり魅力的なアイテムである。
ほぼ絶対的に実用できないところに、古いものの完全性があるからだ(単なる無駄遣いか)。
女性の場合は、より実用的なアイテムの方を好むかもしれない。
アサヒビール&三ツ矢サイダーのコップ
骨董市で見つけたコップ。昔は居酒屋さんでビールを頼むと、びんビールと一緒にこんなコップが出てきました。そんな居酒屋、探さなくっちゃ。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
ノベルティのコップは、意外と深い「沼」なので注意が必要。
それにしても、昔のガラスコップは、チープなものほど安心感があっていい。
チープなレトロ雑貨の中に、貴重なコレクティブルを発見。
オールドパイレックス
パイレックスの製品は今でもありますが、「オールドパイレックス」は、1920~1960年代製のもの。こちらは「スノーフレーク」という模様。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
オールドパイレックスを普段使いできるようになったら、本物のコレクターだと思う。
「美品ほど使えない」という葛藤は、誰でも一度は経験しているのではないだろうか。
道産子としては、北海道ローカルが気になる。
小熊のプーチャン バター飴
北海道のスーベニールといえば、バターあめです。千秋庵のバターあめは、ソフトであっさりめの味。1粒1粒がクマの形になっているんです! それにしても、チェロを奏でるプーチャンが描かれたレトロな青い缶、可愛すぎます!(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
インバウンドの外国人観光客にも、バター飴の味が分かるのだろうか。
千秋庵の「小熊のプーチャン バター飴」は、かわいいデザイン缶が大人気。
小熊が大自然の中で、空に浮かびながらウッドベースを奏でるイラスト入りの缶が大人気。当初、大缶のみの販売でしたが、子供が遠足に持っていける大きさの缶も用意したいと考え、手ごろなサイズをあれこれと模索し小缶が誕生。(『千秋庵』公式サイト「パッケージの歴史」)
小熊が演奏しているのは「チェロ」ではなく「ウッドベース」らしい。
千秋庵には「山親爺(やまおやじ)」というロングセラー商品もある。
山親爺
「山親爺」とはクマのこと。クマがスキーをはき、サケを背負ったイラストが可愛い、洋風せんべいです。キュートなクマのおまけつき!(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
バターとミルクを使った洋風煎餅「山親爺」は、1930年(昭和5年)発売。
ライバルの帯広「六花亭」も出てくる。
なにしろ、六花亭の始まりは「帯広千秋庵」だった(1933年)。
六花亭のチョコ
マルセイバターサンドで有名な北海道のお菓子メーカー。バターサンドも大好きなのですが、ここで作られるチョコレートがお気に入り。白地に古めかしい花の絵が描かれていて、とても清楚。「アーモンドヤッホー」(何てキュートな名前!)も気になっています。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
北海道の山野草を使った花柄包装紙は、画家・坂本直行のデザイン。
六花亭といえばホワイトチョコレートで、1968年(昭和43年)に日本で初めてホワイトチョコレートを発売したことでも有名。
文化系としては、カルチャーなものにも注目したい。
ウディ・アレンの映画『ラジオ・デイズ』は、1987年(昭和62年)公開。
ラジオ・デイズ
ウディ・アレンの映画は何度見ても新しい発見があって、大好き。この作品は、古き良きアメリカの、ラジオが人々の暮らしの中心にあったころの日常を描いたもの。懐かしいあれこれが詰まっていて、胸がキュンとなります!(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
ウディ・アレンの映画は、オリーブ少女の時代から、文化系女子の人気が高かった。
もちろん、雑誌『Olive』を忘れることはできない。
Olive
少女のころ、発売日を指折り数えていました。そして、とっくに少女じゃなくなったころもずっと読んでいた乙女な雑誌。休刊は本当に残念です。神保町の古本屋さんでバックナンバーを見つけました。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
80年代の『オリーブ』もいいけれど、「渋谷系の王子様」小沢健二が連載を持っていた90年代『オリーブ』も楽しい。
コミックでは、みつはしちかこ『小さな恋のものがたり』が登場。
チッチとサリー
みつはしちかこ著の『小さな恋のものがたり』(立風書房)に登場する男の子と女の子。サリーを想う、チッチの乙女心に共感して、読むたび、胸がキュンとなります。(佐々木ルリ子「レトロなつかしダイアリー」)
連載開始は、なんと、1962年(昭和37年)の『美しい十代』で、60年代から70年代の少女たちは、チッチとサリーに大きな影響を受けた(らしい)。
男の子たちは、チッチの作る「大きなおむすび」に憧れたという(笑)
作者が同世代のためか、共感できるアイテムが、本書には多い。
格式張ったアンティークではなく、チープな雑貨が中心となっているところも、本書を高く評価したい部分である。
ヤフオクやメルカリでガツガツ蒐集する、というよりは、スーパーマーケットやコンビニでの出会いを大切にする。
そんな楽しみ方もあるのもしれない。
書名:レトロなつかしダイアリー
著者:佐々木ルリ子
発行:2005/12/30
出版社:河出書房新社