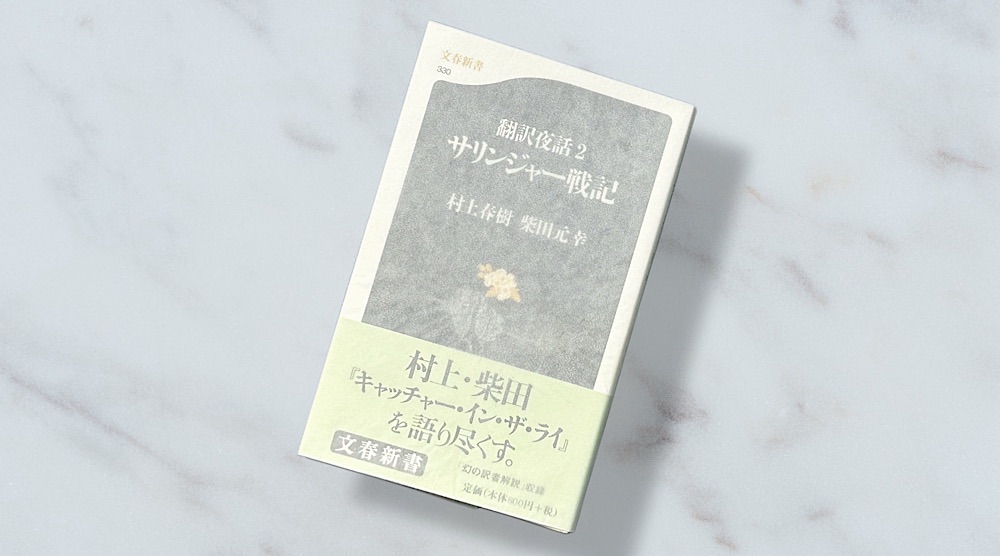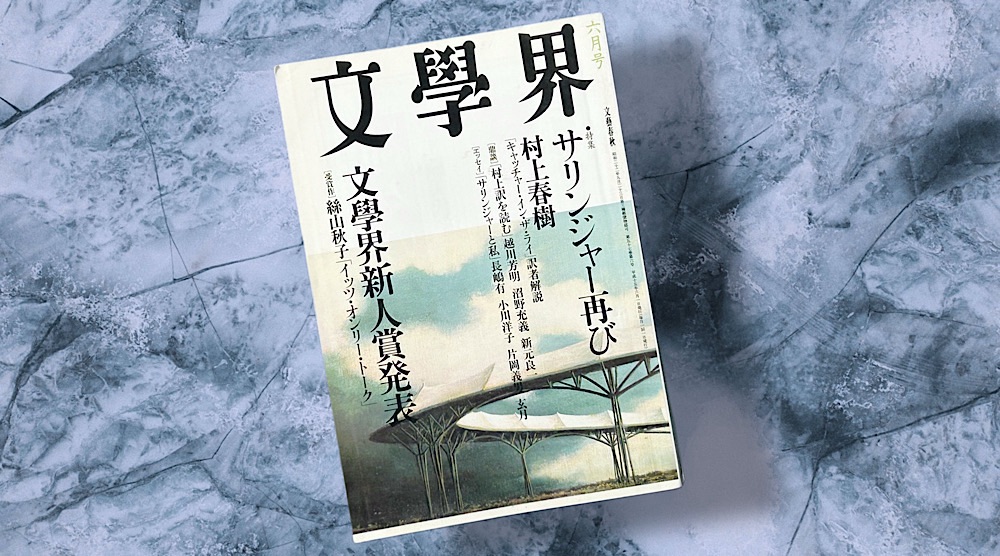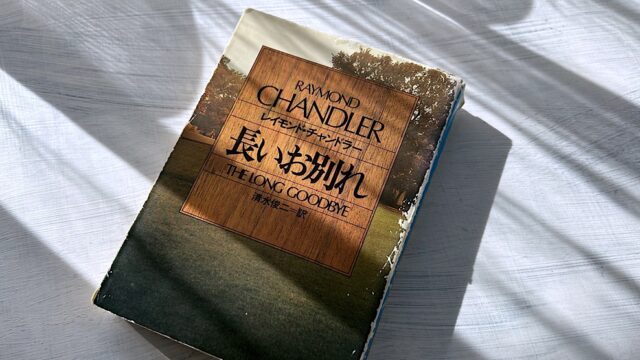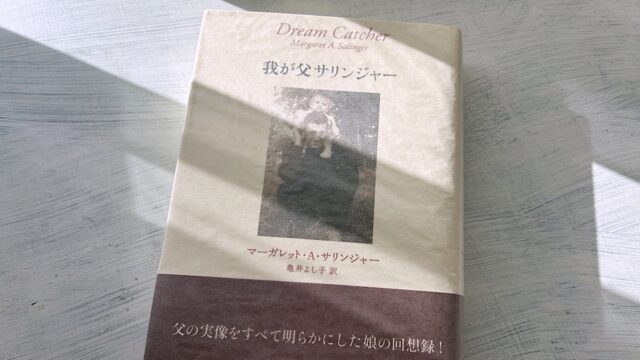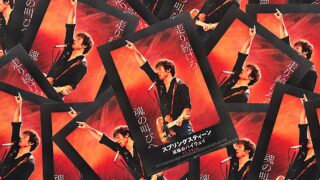村上春樹・柴田元幸『翻訳夜話2 サリンジャー戦記』読了。
本作『翻訳夜話2 サリンジャー戦記』は、2003年(平成15年)7月に文藝春秋から刊行された対談集である。
この年、村上春樹は54歳、柴田元幸は49歳だった。
何が言いたいのか、意味がわからない
サリンジャーの代表作『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(ライ麦畑でつかまえて)を読んで、「何が言いたいのか」「意味がわからない」などと、戸惑う読者も少なくない。
なぜなら、『キャッチャー』は(最初から)正解のない文学作品だったからだ。
2003年(平成15年)に、村上春樹・訳の『キャッチャー』が出版されたとき、この古典的名作に再び光が当てられた。
2003年(平成15年)6月『文学界』は「サリンジャー再び」という特集を組み、村上春樹による「『キャッチャー・イン・ザ・ライ』訳者解説」のほか、「村上訳を読む」という(3人の識者による)対談や、「サリンジャーと私」と題する(4名の作家による)エッセイを掲載した。
さらに、村上春樹は、翻訳協力者でもある柴田元幸と『キャッチャー』をテーマとする対談を二度に渡って行い、その内容を一冊の新書としてまとめた。
それが、本作『翻訳夜話2 サリンジャー戦記』である。
村上春樹と柴田元幸は、サリンジャーの『キャッチャー・イン・ザ・ライ』について、深く考察していく。
村上 本当はこの小説の中心的な意味あいは、ホールデン・コールフィールドという一人の男の子の内面的葛藤というか、「自己存在をどこにもっていくか」という個人的な闘いぶりにあったんじゃなかったのかということなんです。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
古い翻訳である『ライ麦畑でつかまえて』(野崎孝・訳)は、「社会性の偽善性に反抗するホールデン・コールフィールドの物語」という読み方が主流だった。
しかし、新たな訳者(村上春樹)は、「少年対社会」の物語ではなく、「自分自身の意識状況とのせめぎあい」の物語だったと指摘する。
村上 ひとつの考え方としては、「君」というのが自分自身の純粋な投影であってもおかしくないということです。それがオルターエゴ(もうひとつの自我)的なものであってもおかしくない。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
つまり、本作『キャッチャー・イン・ザ・ライ』は、ホールデン・コールフィールドという一人の少年による「(自分の中の)自分との闘い」を描いた物語だった、ということである。
村上 単純に言ってしまえば、もう完全なサリンジャー自身のオートバイオグラフィー(自伝)的なものですよね。(略)本の中にいろんなやつが出てきますよね。(略)でもそういう人々って、注意深く読んでみると、明らかに多かれ少なかれサリンジャー自身の投影でもあるんですよね。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
村上春樹によると、作者(サリンジャー)は『キャッチャー』の中に、様々な自分自身を投影していたらしい。
村上 それから、DBとかフィービー、アリー、そういうホールデンの兄弟姉妹に関して言えば、これはもう完全に自己の分身的な存在ですよね。(略)翻訳者としてはあまり分析的になりたくはないんだけど。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
フィービー(妹)は幼児的イノセンスがもっとも強く、理想的なかたちで結晶した生身の姿であり、アリー(死んだ弟)は、博物館のガラスケースに入れられたイノセンスである。
そして、DB(兄)は、職業作家になっているサリンジャー自身が、いくぶん戯画化されたかたちで投影されたものだと、村上春樹は分析しているのだ。
それどころか、ストラドレイターやアックリーといった寮生活の「嫌な連中」さえ、あるいは、自分自身の反映だったかもしれない。
村上 若いときって、みんな多かれ少なかれそうなんですよ。結局、自己の憧れの投影と、自己のコンプレックスの投影みたいなもののミクスチャーの中で、うだうだと行きつ惑いつ生きているんですね。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
主人公(ホールデン・コールフィールド)がさまようニューヨークの街は、彼自身の「心の闇」である。
村上 結局この話は、ホールデンがニューヨークに出てからは、一種の地獄めぐりみたいな構成になってますよね。でも、その地獄というのは、巨大都市という現実的な地獄でありながら、そのままホールデンの、そしてつまりはサリンジャーの、魂の暗闇でもあります。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
複雑な物語は(答えのない物語は)「意味不明」だと混乱する読者がいる。
しかし、小説にとって「意味」は、それほど重要ではないと、村上春樹は言う。
村上 極端なことを言ってしまえば、小説にとって意味性というのは、多くの人が考えているほど、そんなに重要なものじゃないんじゃないかな。というか、より大事なのは、意味性と意味性がどのように有機的に呼応し合うかだと思うんです。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
言葉では言い表すことのできないものがある。
人間の耳では聴きとることのできない「倍音」や、普通のお風呂よりも体が温まる「温泉」のように、理屈ではなくてフィジカルで感じるもの。
村上 温泉のお湯につかっていると身体が温まりやすいのと同じで、倍音の込められている音というのは身体に長く残るんですよ、フィジカルに。でも、それがなぜ残るかというのを言葉でもって説明するのは、ほとんど不可能に近いんです。それが物語という機能の特徴なんです。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
むしろ、「これは、こういう物語だよ」とひと言で済まされるような作品は、小説としてはつまらないということだ。
村上 すぐれた物語というのは、人の心に入り込んできて、そこにしっかりと残るんだけど、それがすぐれてない物語と機能的に、構造的にどう違うかというのは、言葉では簡単にわかりやすく説明できない。(略)『キャッチャー』というのは、だれがなんといっても、実にしっかりと残る本なんです。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
言葉で表現することができないものを強引に言葉でまとめてしまうと、「社会に反抗する無垢な少年の物語」のように、単純な話になってしまいかねない。
ひと言では説明できないところに、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』という物語の「深さ」がある。
多くの読者が『キャッチャー』に魅了され、『キャッチャー』がどのように素晴らしい小説であるかと説明しようとしてきた。
しかし、多くの場合、その試みは失敗することになる。
そもそも「きちんとした体系」みたいなものは、この小説には最初からなかったのだ(「何もかも、とっちらかったままなんです」)。
村上 だからこそ、この小説は非常に捉えにくいんですよね。そういう文脈で知的な人に嫌われるところがあります。知的というか、論理的な考え方、整合的な読み方をする人に、ということです。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
大切なことは、自分なりの「意味」を、自分自身の感性によって「新たに発見する」ことだろう。
なにしろ、「正解」なんてものは、最初から用意されていないのだから(この『キャッチャー』という小説の場合は)。
訳者の村上春樹は、『キャッチャー』は「怖い本」だと考察している。
『キャッチャー』が、なぜ「怖い本」なのか?
村上 何度も繰り返すようだけど、この本はかなり怖い本です。ちゃらちゃらしたブルジョアの坊ちゃんの神経症的なうだうだ話というのではないし、イノセントな若者が偽善的な社会に反抗するというのでもない。自己というものを、この世界のどこにどのように据えればいいのかという命題を、真剣に探究している本だと思います。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
「自分探し」をしているのは、ホールデン・コールフィールドであり、作者のサリンジャー自身でもある。
あるいは、多くの読者が、『キャッチャー』という小説を通した「自分探しゲーム」に参加していたのかもしれない。
例えば、ジョン・レノンを射殺したチャップマンや、レーガンを狙撃したヒンクリーたちも。
そして、彼らの見つけた「答え」は、「インチキな世の中を破壊する」ことだった。
村上 なんというか、もともと深い問題を抱えた人が即決的な解答を求めるところがまずいんであって(笑)、根本的な問題のない人は、そんなに安易には解答を求めないんですよね。だから『キャッチャー』のいちばんいい読者というのは、そこに意味やら解答やらを求めない人なんじゃないかな。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読んで「意味がわからない」と感じる感覚は、決して間違いではない。
この物語を読んで、何かを感じたかどうか。
理屈ではなく身体で感じることも、読書にとってはひとつの楽しみ方なのかもしれない。
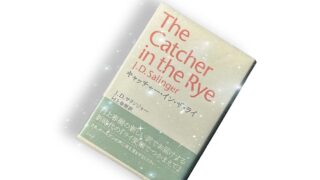
正解のない『キャッチャー』を読み解く
本作『翻訳夜話2 サリンジャー戦記』では、小説家(村上春樹)と、東京大学の英文学教授(柴田元幸)の二人が、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』について、激論を交わしていく。
なにしろ、テーマは「『キャッチャー』は謎に満ちている」なのだ。
答えのない問題に、いい歳をした大人たちが(しかもすごい人たちが)、必死になって取り組んでいる。
こういう対談を読むと「『キャッチャー』はどのような読み方をしたっていい小説なんだ」という、無暗な勇気を与えられてしまう。
『文藝春秋』の特集「サリンジャー再び」に発表した「サリンジャーにおける愛と死──『ライ麦畑でつかまえて』はアメリカでどう読まれてきたか」の中で、都甲幸治は、エドウィン・ハヴィランド・ミラーの「アリー・コールフィールドを悼んで」(1982)を紹介している。
ホールデンの人生は一九四六年七月十八日、アリーが死んだ日の十三歳のまま止まっている。死んだアリーのことを徐々に忘れてしまう他の人々と違って、ホールデンの心は常にアリーとともにあって、彼を愛し続けている。当然ながら、生を前提としている日常世界では、ホールデンは上手く生きられない。(都甲幸治「サリンジャーにおける愛と死──『ライ麦畑でつかまえて』はアメリカでどう読まれてきたか」)
第二次世界大戦中に育まれ、朝鮮戦争の最中に出版され、ベトナム戦争中に広まった『ライ麦畑でつかまえて』を「銃弾が一発も発射されない戦争小説である」と指摘したのはジョン・スィリー「博物館のホールデン」(1991)だった。
サリンジャーが偽装された戦争後小説を書いたのだとしたら。彼は死んだ仲間のことが忘れられない。アックリーだって、ストラドレイターだって、今となってはかけがえのない仲間だった。でも死んだ仲間との連帯だけでは、戦後の日常は生きていけない。(都甲幸治「サリンジャーにおける愛と死──『ライ麦畑でつかまえて』はアメリカでどう読まれてきたか」)
戦争によって傷ついた作者(作中のホールデン・コールフィールド)は、フィービーという瑞々しい命を持った存在によって癒されていく。
それは、サリンジャーの名作短篇『エズミに捧ぐ──』に登場するX軍曹とエズミとの関係にも似ていたかもしれない(作品集『ナイン・ストーリーズ』所収)。

とにかく、いろいろな(すごい)人たちが、いろいろな読み方をした。
正解のない『キャッチャー』は、いろいろな読み方ができてしまう小説なのだ。
この物語の本当にすごいところは、この「難しい小説」が、分かりやすい簡単な文章によって構成されているということである。
村上 だから、僕はよく言うんだけど、簡単な言葉で有効に語られる深い、暗い内容というのは、優れた物語にとってのひとつの大きな資格であると思うんですよ。でも、文壇文学というか、純文学というのは、むずかしい文学言語のようなものを使って、むしろ簡単なことをむずかしく書くというのが、一種の制度的スタイルみたいになっているところがあるわけです。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
高校生の独白によって語られる『キャッチャー』は、極めて平易な言葉によって組み立てられている。
文章としては中高生にもお薦めできる、分かりやすい物語である。
ストーリーが入り組んでいるわけでもない。
行き場をなくした家出少年が、クリスマスの街を徘徊するだけの物語と言ってしまってもいい。
それでも、なお、その内容はとても深くて、どこにもたどり着くことはできない。
村上春樹と柴田元幸という二人の「すごい人たち」も、結論の出ない難問に(真剣な姿勢で)延々と取り組んでいく。
柴田 少なくとも小説に関しては、アメリカほどイノセンスに重きを置くところ、大人になることに重きを置かないところはないと思うので、『キャッチャー』はアメリカのイノセンス崇拝症候群の典型的症状である、と片づけてしまうことだってできる。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
『キャッチャー』の主人公(ホールデン・コールフィールド)は、成長しない主人公である(「この話の最初と終わりで、ホールデンという人間が変化したかというと、したとも言えないんですよ」)。
村上 だから僕は、ホールデンがギャツビーのことが好きだという気持ち、なんとなくわかるんです。ギャツビーはある意味では成長しない人だから。社会システムからはずれて、自分の夢みたいなものを後生大事に護っている。(略)とにかくイノセントなんですね。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
それは、成熟年齢が遅くなっていく現代社会とも重ねることができる。
村上 昔は二十歳が成人の目安だったけど、今はだいたい三十歳くらいでしょう。(略)つまりそれだけ「思春期」が長くなっているんですね。そういう意味で『キャッチャー』は成熟先送りシンドロームの走りと言っていいのかもしれない。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
切り口を変えながら、物語の考察はどんどん深まっていく(ただし、決して答えは出ない!)。
村上 そういうところがこの本の含んでいる、多義的な物語の不気味さじゃないかと。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
「多義的な物語」とは、いろいろなとらえ方をすることができる物語、ということである。
「奥が深い」という世界を越える「底の知れない」不気味さが『キャッチャー』にはあった。
どこまで読んでも、どれだけ読んでも、決して「読み尽くす」ことはできない。
村上 つまり僕の感覚からいえば、フィービーというのは、正確な意味での肉親じゃないんですよ。(略)自己の一部なんですよ。鏡に映った別の姿。過去から抜け出てきたひとつの仮説。もっと穏やかに言って、幻影的なもの。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
村上春樹の短編小説「鏡」を読んだ人には分かるかもしれない。
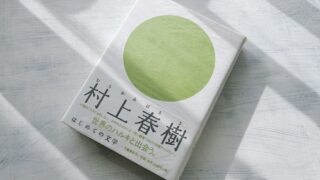
『キャッチャー』には、様々な形で作者(サリンジャー)が反映されていると、訳者(村上春樹)は踏んでいる。
村上 そういう意味では、『キャッチャー』を読むと、これは彼自身による自己のトラウマの分析と、その治療の道を見つけるための自助的な試みなんだな、というふうに僕は捉えるわけです。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
サリンジャーの戦争体験について理解していないと、このあたりの説明は分かりにくいかもしれない。
映画『ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー』(2017)にも描かれているとおり、第二次大戦に従軍したサリンジャーは、ヨーロッパ戦線でひどい戦争を経験している。
戦後のサリンジャーは戦争によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱えていて、それが彼の小説には反映されていると考える評論家は多い。
村上 お兄さんのDBが、療養中のホールデンをサナトリウムに訪ねてきますよね。あのDBはもちろん自分の名前JDの言い換えですね。だから、考えようよっては、彼はみずからを訪ねていっているということにもなるわけですよ。そのあたりはちょっと怖いなという気がします。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
サリンジャーの人生について詳しい人は、主人公(ホールデン)に作者(サリンジャー)の姿を見つけることだろう。
村上 それに実際、ホールデンは精神病というわけではありませんよね。彼はかなり神経症的ではあるけれど、精神病を患っているわけじゃありません。戦争直後のサリンジャー自身がそうであったのと同じように。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
もちろん、作者(サリンジャー)と主人公(ホールデン)を、必ずしも同一視する必要性はまったくない。
むしろ、同時代的に『キャッチャー』を読んだ人々は、作者(サリンジャー)の人生のことなんか、全然考えなかったかもしれない(それほど有名な作家ではなかったから)。
それでも、やはり『キャッチャー』はおもしろい小説だった。
村上 この本は本質的にはやはりそうとう暗い話だと思うんです。前にも言ったように、地獄めぐりみたいなところが、次から次へと出てきます。ホールデンが自己意識の中を、真っ暗闇の中を、手探りで、あちこちつまずきながら進んでいく。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
なぜ、多くの読者は、ホールデン・コールフィールドに共感するのだろうか?
それは、ホールデン・コールフィールドにとって世の中が完璧なものではなかったように、多くの人にとっても人生は完璧なものではなかったからである(という仮説)。
村上 何はともあれホールデンがその時点で求めているのは、自分を絶対的に受け入れてくれる高位者じゃないかと僕は思うんです。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)
「キャッチャー」とは、ライ麦畑の崖っぷちから落ちそうになっている子どもたちを、さっと助けてくれる「救世主」のことだ。
「ライ麦畑のキャッチャーになりたい」と願いながら、本当に助けを求めていたのは、実は、ホールデン・コールフィールドの方だったのではないだろうか。
旧訳『ライ麦畑でつかまえて』というタイトルからは、「ライ麦畑でつかまえてほしい」という主人公の(祈りにも近い)「SOS」を読みとることができる。
もとより、生きることは厳しくて困難なものだった。
「人生の崖っぷち」に立ったからと言って、誰かが助けてくれるわけじゃない(それが人生だ)。
不安定な人生を生きる少年の不安は、我々自身の不安でもある。
みんな、心のどこかでは「誰かに助けてもらいたい」と思いながら、この世の中を必死で生きているのだ。
だからこそ、『キャッチャー』は、必死に生きる人たちに向かって響く小説だったのではないだろうか。
書名:翻訳夜話2 サリンジャー戦記
著者:村上春樹・柴田元幸
発行:2003/07/20
出版社:文春新書