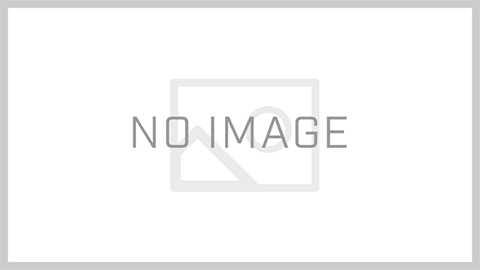伊藤ユキ子『紀行・アラン島のセーター』読了。
本作『紀行・アラン島のセーター』は、1993年(平成5年)11月に晶文社から刊行された旅行記である。
この年、著者は43歳だった。
アラン・セーターの伝説
アラン・セーターは、アイルランド発祥のニットウェアである。
英国の沿岸地方に伝わるフィッシャーズ・セーターとしては、ガンジー・セーターと並んで有名なアイテムとなっている。
かっちりとした風合いのガンジーは、よりの強い中細ほどの糸で表メリヤス編みの地に裏目で「錨」「旗」「はしご」などの模様をほどこしていく。一方のアランは、太めの糸で裏メリヤス編みの地に表目で模様を浮き彫りにしていく。アランの方がずっと立体的・装飾的で、目につきやすかったのかもしれない。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
多様な編み目デザインは、アラン・セーターの大きな魅力だ。
当時の(1980年前後の)イギリスでは、「スコッチハウス」などの専門店が、こぞってアラン・セーターをブリティッシュ・トラッドの代表選手のように扱っていたという。
ちょうど「フォークロア」とか「トラッド」とかの波が、英国調のセーターを流行へと押し上げていた時期である。(略)お金よりも手間暇かけたものに価値を見出すという折からの手づくりブームが、流行に拍車をかけたのかもしれない。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
本来、アラン・セーターは、アイルランド西方の小さな島、アラン島の男たちの労働着(ワーク・ウェア)だった。
半農半漁の男たちは、畑を耕すときも魚を獲るときもアラン・セーターを着込んで作業してらしい。
アラン・セーターの特徴である「乳白色の浮彫り模様」には、常にひとつの伝説がつきまとっていた。
一面にひろがる美しい浮き彫り模様。それらは、ただ模様というにとどまらず、家紋のような意味をもっていた。それぞれの家がそれぞれに、模様の組み合わせたパターンを代々受け継いでいたのだ。だから漁に出た男たちがよしんば怒り狂う海にのみこまれ、顔のない無残な溺死体で発見されたとしても、着ているセーターによってどこのだれかは確認することができる。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
浮彫りのデザインは「家紋」であり、海難事故があった場合には、セーターのデザインによって身元が判明する。
「家紋伝説」は日本でも幅広く受け入れられて、人々はロマンチックな夢と一緒にセーターを買った。
女たちは、波高い海原へ木の葉のような小舟で乗り出していく夫や息子のために、一目一目心をこめて編んだ。愛する人を守り抜こうとする想いとともに、毅然とした覚悟までを編みこんで、大切な人の漁支度を整えたにちがいない。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
アラン・セーターの模様は、アラン島の自然や風景、生活などを表現している。
デザインの一つ一つには、隠された意味があった。
ケーブル(縄編み)
・漁師の使うロープ、命綱
ハニーコム(蜂の巣)
・漁網を広げた風景(ミツバチは縁起の良い動物だった)
リンク(ダブルケーブル)
・家族との永遠のつながり
ダイヤモンド
・成功、富、宝物の象徴
トゥリー・オブ・ライフ(生命の木)
・不死身、不滅
バスケット(籠)
・漁師の使うかご(豊漁への祈り)
アイリッシュ・モス(かのこ編み)
・海草(海への感謝を意味する)
ジグザグ
・海岸の崖、あるいは稲妻
ダブルジグザグ
・結婚生活、山あり谷あり
トレリス(格子)
・石を積み上げた壁
トリニティ/ブラックベリー
・キリスト教の「三位一体」(神の加護)
アランセーターがもたらす「伝説」に、人々は魅了された。
アラン模様に精神的な奥行きさえ感じとってしまうのは、やはり、伝説を知ったせいなのだろうと思った。伝説を抱きしめて編んでいると、厳しい自然のなかで、男たちは男らしく、女たちは女らしく生きていた時代の気分にくるまれていく。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
著者(伊藤ユキ子)は、「アラン・セーターの伝説」を求めてアイルランドへと渡った。
彼女のアイルランド紀行は、伝説のアラン・セーターの歴史を解き明かす旅でもあったかもしれない。
しかし、彼女が現地で確かめたことは、「アラン・セーター伝説は伝説でしかない」という事実だった。
著者は、著者なりのアプローチによって、アラン・セーターの歴史を解き明かしていく。
アラン・セーターの歴史
アラン島にアラン・セーターが伝えられたのは、1847年以降だったと考えられる。
なんでも、キルマーヴィエ村に住むケーティ・ギルさんという方のおばあさんが、ゴルウェイ湾の南部、本土のクレア州の人から「ケーブル」や「ダイアモンド」「トレリス」などの模様を教わったのがアラン編みのはじまりだというのである。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
「一〇〇〇年以上の歴史を持つ」と伝えられていたアラン・セーターの歴史は、意外にも新しいものだった。
「少なくとも前世紀後半にはアランセーターの原形のようなものはあったと思う。それ以前のこと? 編み地はもっと平坦なものだったって聞いているわ。だから、模様が家紋のような意味をもっていただなんて私は信じていない。スコットランドのタータンチェックのような歴史は、残念ながらアラン編みにはないのよ」(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
「自分の母親が、アメリカからアラン編みの技法を持ち帰った」という、お年寄りの証言もあった。
「そう、私が生まれる四年前だから一九〇八年にまちがいない。アメリカからアラン編みの技法をもってこの島へ帰ってきたんだよ。そりゃ料理上手で編み物も達者でねえ。自慢の母さんだった」(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
いずれにしても、1900年前後からアラン・セーター編みは、アラン島の人々の間で広がり始めたらしい。
それでは、謎の「アラン・セーター伝説」は、どこから生まれたのだろうか?
きっかけは、1934年(昭和9年)に公開されたイギリス映画『アラン』(原作は J・M・シング)だったのではないかと、著者は推測している。
その頃、ナチス・ドイツから逃れてイギリスへ亡命中のハインツ・エドガー・キーヴァというユダヤ人実業家がいた。
1936年(昭和11年)、彼はダブリンの「カントリーワーカーズ」で、アラン島で編まれたというセーターを見つけた。
「ウィスカリー型の糸で編んだ「バイブリカル・ホワイト」のずんぐりしたセーター……、それは板のように固く、コプトの僧侶が着るシャツのように直線的で、ストーンヘンジのような雰囲気を漂わせていた」(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
ロンドンのブロンプトン・ロードで高級衣料品を経営していたキーヴァは、「バイブリカル・ホワイト」のフィッシャーズセーターに強く惹かれたらしい。
第二次大戦勃発後、オックスフォードで「アート・ニードルワーク・インダストリーズ」という手芸材料の会社を興したとき、キーヴァの頭にあったのは、ダブリンで見つけた、あのフィッシャーズセーターだった。
彼は、戦前にダブリンで観た映画『アラン』を思い出し、フィッシャーズセーターの歴史に、ひとつの仮説を立てた。
それには、一〇〇〇年以上にもおよぶ時の流れと、宗教色とが与えられていた。六世紀頃、アラン島で修業を積んでいた修道士たちによって編み出されたもの、と彼は推論したのである。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
しかし、1932年(昭和7)から1933年(昭和8年)にかけて、アラン島で撮影されたドキュメンタリー映画『アラン』に、乳白色のアラン・セーターは登場しない。
しかし、なにはさておいて意識の網を張っていたアランセーターは一度も見なかった。アラン島らしさにこだわって製作された映画の中に、あの乳白色の浮き彫り模様は、ついぞ登場しなかったのである。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
当時のアラン島では、アラン・セーターはまだ普及前だったのだろう。
あるいは、キーヴァは、映画『アラン』の原作者でもあるJ・M・シングの戯曲『海へ騎りゆく人々』にインスパイアされた可能性もある。
漁に出て行方不明となった兄(マイケル)の靴下が、妹(ノラ)のもとへと届けられる。
「これ、まちがいないわ、マイケルのよ。私、編み目を二〇×三つくって途中で四目落としたの。そう、これにまちがいない」(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
妹の手編みの靴下は、図らずも、死んだ漁師が自分の兄であることを教えてくれた。
ちなみに、岩波文庫版『海へ騎りゆく人々』(山本修二・訳)では、次のように訳されている。
ノーラ これは私が編んだ三足目の、後で手をつけた方だよ。私、編目を六十にして、四つだけ落したんだよ。(ジョン・ミリングトン・シング「海へ騎りゆく人々」山本修二・訳)
編目を数えた姉(カスリーン)は「ちょうど、数が合ってるわね」と、大声で叫ぶ。
兄(バートレイ)は漁師だった。
カスリーン 海へ出掛けて行くというのが、若い男の暮しなんだよ。それに年寄りのお婆さんが、一つ事をくどくどと、繰り返して言ってるのを、聴いてる人があるものかね?(ジョン・ミリングトン・シング「海へ騎りゆく人々」山本修二・訳)
バートレイが海へ出かけていくのを、母親(モーリヤ)だけが嘆き悲しんでいる(「お前も、他の息子と一緒に、溺れ死にでもしてしまった日には、みんなどんなに苦労するだろうね」)。
やがて、届けられた兄(マイケル)の遺品を見て、姉妹は泣き崩れる(「ドネゴールで溺れ死にしていた男の人の肌身についていたシャツと無地の靴下だとさ」)。
ノーラ あんなに立派な漕ぎ手で、あんなに立派な漁夫だった人の名残りが、僅か古びたシャツ一枚と、無地の靴下の片足だなんて、情無い話じゃないかね?(ジョン・ミリングトン・シング「海へ騎りゆく人々」山本修二・訳)
無地の靴下の編み目の数から、ノーラは、それが自分の編んだ兄(バートレイ)の靴下であることを理解する。
この悲劇が、商売人(キーヴァ)の創作によって「アラン・セーターの伝説」へと生まれ変わったのだ(という推測が成り立つ)。
1943年(昭和18年)、キーヴァからアラン・セーターの情報を仕入れたロンドン在住のファッション・ジャーナリスト(メアリー・トーマス)は、『メアリー・トーマスのニットパターン集』の中で、アラン・セーターを紹介する。
「交差のモチーフの素晴らしいお手本です。代々受け継がれてきたという複雑で伝統的な模様。このセーターは、アラン諸島の漁師たちによって着用されています」(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
もちろん、アラン・セーターは「代々受け継がれてきた模様」ではないし、漁師たちの労働着(ワークウェア)でもなかった。
そう、乳白色ではなかった。それは深みのある紺色だった。「仕事するのに白いものなんか着られるもんかい。そうだろ?」(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
同じ頃、商売人(キーヴァ)は、スコットランド西方のヘブリデーズ諸島(アウター・ヘブリデーズ)で、ウィスカリー型の糸が紡がれていることを発見する。
戦後、多くのアラン・セーターが、この島の「ハリス・ツイード紡績」の糸を使用して編まれ、世界中へと広められていった。
アラン島では、多くの女性たちが優秀なニッターとして活躍するようになっていた。
1900年代初頭、極度の貧困生活から逃れるために、彼女たちは編み物を始めたのだ。
しかし、その貧困のなかで、アラン編みは稼ぎ仕事として普及していった。そして、手から手へと受け継がれ、その見事な技はいまなお生きている。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
大飢饉による恐慌の中から生まれてきた土地改革(土地戦争)と民族独立運動の時代。
ニットを編む女たちが祈っていたものは「海へ出る男たちの命」ではなく、「明日の食い扶持を得ること」だったのだ。
羊毛の色をそのまま生かすということはなく、すべて鉄色や紺色、深緑といった濃くてくすんだ色に染めたものらしい。それも、紡いだ毛糸を、ではなく、編み上げた作品を染めていたのだそうだ。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
やがて、詩人(ウィリアム・バトラー・イエーツ)や戯曲家(J・M・シング)らは、アイルランドに眠る古い伝説や民話、神話、妖精物語などを、次々と発掘していく。
民族の誇りを目覚めさせたアイルランド・ルネッサンスは、人々の「非英国化」を促し、新たなアイルランドの伝説を生み始めていく。
「貧民周密地域局」がアラン島の人々に奨励したセーターづくりも、後を追いかけてできる伝説も、そんな時代の気分にぴたりとハマったのだと思う。そして、いまで言う「村おこし」の目玉がアランセーターではなかったかと、私は見ている。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
戦後、多くの(アイルランド系)アメリカ人がアイルランドを訪れ、アラン・セーターを買っていった。
アランセーターの製造・販売に尽力したのは、もちろん、キーヴァの経営する「アート・ニードル・インダストリーズ」である。
そういえば、アイルランドを旅するアメリカ人のなかには、ルーツ探しを目的とする人がたいへん多い。かつて絶望的な現状から逃れ、新天地アメリカへと渡った移民の子孫たちが、わが出自を確かめるためにやって来るのである。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
「1000年の歴史を持つ」アラン・セーターは、故郷アイルランドの象徴にさえなっていたかもしれない。
やがて、アメリカン・トラッドの波と一緒に、アラン・セーターは日本へと輸入されてきた(もちろん、あの「伝説」と一緒に)。
当時の『編物ヴォーグ・スタイル一〇〇〇集』に見つけた特集の序文には、こんな言葉が綴られていた。「一〇〇〇年の歴史をもつといわれるアラン模様は、英国アラン島の漁師のセーターとして生まれ……」(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
ファッション雑誌などでアラン・セーターの特集を見かけるようになったのは、1968年(昭和43年)~1969年(昭和44年)のことだったと、著者は回想している。
何度かのトラッド・ブームを経て、アラン・セーターはすっかりと定着したらしい(流行の波はあるとしても)。
アイルランドは、アラン・セーター発祥の地として知られる。
アランセーターに興味があると言ったら、コピーした簡単なチラシをくれた。(略)「そうね……、でも、私は何百年説なんて信じていませんわ。ましてや千年だなんて」(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
アラン・セーター伝説が、商業上の創作だったことは、既に定説となっている。
それでも、複雑なアラン編みのセーターを買うとき、我々は、あの「伝説」をも一緒に買い求めているのではないだろうか。
昔のアランセーターは、未脱脂、つまり、脂分を含んだままの毛糸で編んだため、ベタベタするうえ鼻をつまみたくなるほど羊くさかったものだそうだ。そんな話をたまたまパブで隣り合わせになった人から聞いてはいた。だが、いまどきそんなことがあるのだろうか。だいいち、羊の臭いとも純毛が放つ臭いともちがう。倉庫のような店のこと、あるいはネズミのオシッコが……。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
未脱脂の(脂分を含んだままの)毛糸で編まれたセーター(ピュアニューウール)のセーターは、現在でも入手可能である。
以前、アイルランドにあるニットウェアのファクトリーブランド「Kerry Woollen Mills(ケリーウーレンミルズ)」のアラン・セーターを(オンラインで)購入したことがあるが、届けられたセーターの臭いには、さすがにびっくりした。
上記の引用文に「ネズミのオシッコが」とあるとおり、あの臭いは、まさしく、子どもが小さかった頃に我が家で買っていた「ハムスター(のオシッコ)の臭い」だった。
いくらスノッブなアイテムが好きと言っても、さすがに、あの臭い(のセーター)を着る気にはどうしてもなれなかった。
いろいろなニットウェアを買ったけれど、強烈な印象という意味では、ケリーウーレンミルズに勝るものは(今に至るまで)ない。
本書『紀行・アラン島のセーター』が刊行されたのは、バブル景気崩壊直後の1993年(平成5年)である。
そういえば、ここのところ手編みがブームだという。(略)DCブランドに夢中だった若い層が、「私だけのブランド」に価値を見出しはじめたせいなのかもしれない。(伊藤ユキ子「紀行・アラン島のセーター」)
あれから30年。
日本では、久し振りの「編み物ブーム」が到来しているらしい。
「1000年の歴史を持つ」と言われた「伝説のアラン・セーター」に注目が集まることもあるだろうか。
書名:紀行・アラン島のセーター
著者:伊藤ユキ子
発行:1993/11/30
出版社:晶文社

(2026/03/01 21:41:33時点 楽天市場調べ-詳細)