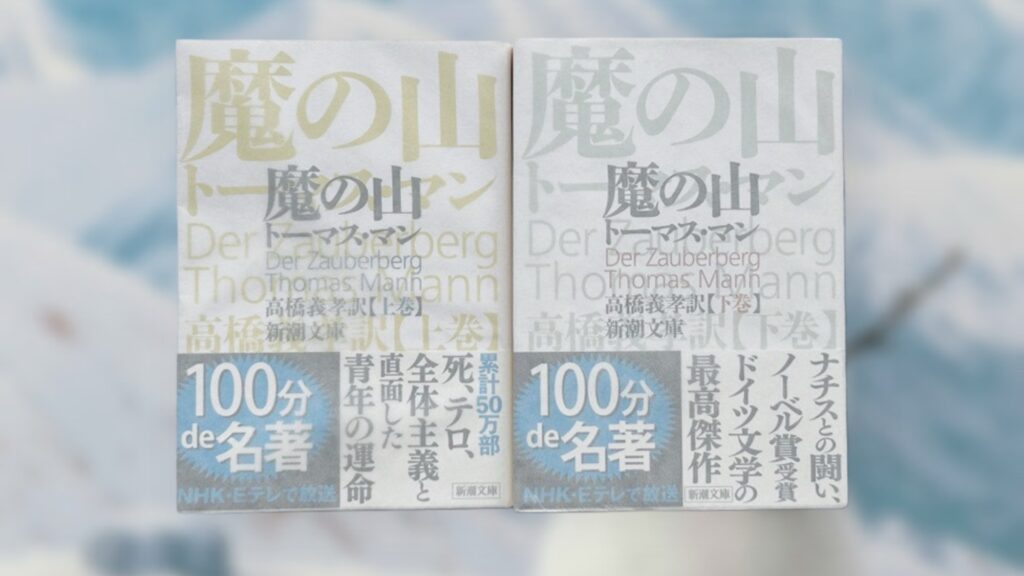フランツ・シューベルト『冬の旅』鑑賞。
バリトンは、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ。
ピアノは、ジェラルド・ムーア。
史上最強の『冬の旅』ペアによる、1962年(昭和37年)のレコーディング版である。
シューベルトと『冬の旅』
街に雪が降り始めると、シューベルト『冬の旅』の季節である。
一八二七年、二八年のシューベルトは、自分の寿命を知っているかのように、精力的な創作活動を続けていた。(略)なかでも、一八二七年二月からとりかかった『冬の旅』の作曲には、シューベルト自身、大きな精力を費し、そうとうに消耗したらしい。(村田千尋『シューベルト(作曲家・人と作品シリーズ)』)
フランツ・シューベルトは、1828年11月19日に腸チフスで亡くなっているから、『冬の旅』は、まさしく最晩年の作品だった。
もっとも、この年、シューベルトは31歳で、あまりにも若すぎる死であったことに間違いはない。
直接の死因はチフスであったが、一八二三年以来、彼の体は梅毒に蝕まれ、体力は低下していた。(村田千尋『シューベルト(作曲家・人と作品シリーズ)』)
シューベルトのリート(歌曲)の中でも『代表作』のひとつに数えられる『冬の旅』(第1部)は、亡くなる年の1月に発表され、続編となる『冬の旅』(第2部)は、彼の死後、12月30日に発表された。
11月21日に葬儀、12月23日には追悼会が行われているから、『冬の旅』(第2部)はまさしく追悼出版だったと言える。
陰惨で重苦しい『冬の旅』は、「永遠の冬の旅」へと旅立つシューベルト自身を送るレクイエムとなった。
なにかに取り憑かれ、消耗して見えるシューベルトを気遣う友人たちに対し、彼は『冬の旅』第一部十二曲を感動した声でみずから歌って聴かせたという。しかし、物語のあまりの陰惨さ、音楽語法の斬新さについていくことができず、ほとんどだれも理解、共感を示さなかったらしい。(村田千尋『シューベルト(作曲家・人と作品シリーズ)』)
『冬の旅』が受け容れなかったことについて、松下たえ子は「シューベルトの音楽の新しさが人々に理解されなかったから」と指摘している。
しかしシューベルトが彼の「冬の旅」を初めて披露した時、聴衆の反応は冷たかった。彼らはその音楽の暗さにただ唖然とした。(略)シューベルトの音楽の新しさ──その独創性と特殊性──とが人々に理解されなかったからである。(松下たえ子『ヴィルヘルム・ミュラー読本』)
シューベルトの音楽が新しかったように、作詞をしたミュラーの詩もまた新しすぎた。
つまり、『冬の旅』の持つ意味とその新しさを理解した読者は同時代の文学者の中にはいなかった。そんななか、音楽家シューベルトはそれを発見した。そして大いなる共感と感銘を彼の音楽に移したのである。(松下たえ子『ヴィルヘルム・ミュラー読本』)
『冬の旅』の新しさは、その作品が時代を超えて、200年以上も愛され続けていることからも理解できる。
そもそも『冬の旅』は、ドイツの詩人(ヴィルヘルム・ミュラー)によって、1822年に12篇、1823年に10篇が雑誌に発表された作品である。
1824年には『旅する角笛吹きの遺稿詩集(第二巻)』に収録、出版された。
それを目にしたのが、ウィーンの作曲家(シューベルト)である。
シューベルトは雑誌『ウラニア』(一八二三年)に載ったミュラーの「冬の旅」一二篇を読んだ。偶然の出会いであった。彼の目線と同じような世界観と、同じような鋭い風刺に魅せられ、何週間かで付曲した。しかしその完成後ほどなく『旅する角笛吹きの遺稿詩集 第二巻』を手にした。(松下たえ子『ヴィルヘルム・ミュラー読本』)
シューベルトは1797年生まれ、ミュラーは1794年生まれ。
『旅する角笛吹きの遺稿詩集(第二巻)』が出版された1824年には、シューベルトが27歳、ミュラーが30歳という、同世代の芸術家同士だった(そして、どちらも30代前半で早逝する)。
「歌曲王」と呼ばれたシューベルトは、多くの詩人の作品に作曲をした。
シューベルトは、詩をたいして吟味もせずに手当たりしだいにとりあげており、文学的なセンスに欠けるのではないかといわれることがある。(略)彼の詩人リストにはまったく知られていない名が多数並んでおり、これが、「手当たりしだいに詩をとりあげる」といわれる理由となっている。(村田千尋『シューベルト(作曲家・人と作品シリーズ)』)
ミュラーは、ゲーテ、マイルホーファーに次いで、シューベルトが採りあげた詩人としては三番目に多い詩人となっている(『美しき水車小屋の娘』『冬の旅』『岩の上の羊飼』)。
同時代を生きたドイツの詩人であるゲーテやハイネと比べて、ミュラーの名前は決して著名とは言えない。
ミュラーの名前は、シューベルトの作曲した『美しき水車小屋の娘』や『冬の旅』の作詞者として、後世まで知られることになったのである。
これはしかし日本だけの話ではなく、ミュラーの母国ドイツでも事情は似たりよったりのようで、二〇世紀末から再び出版されることになったミュラーの詩の解説者や伝記作家もほとんど例外なく、歌曲「冬の旅」や「美しき水車小屋の娘」でヴィルヘルム・ミュラーに出会い、関心を持つようになったと記している。(松下たえ子『ヴィルヘルム・ミュラー読本』)
そのため、ミュラーの詩は、大抵の場合、音楽の世界において語られることとなった。
日本において「ヴィルヘルム・ミュラー」の名前を最もよく見かけるのは、『美しき水車小屋の娘』や『冬の旅』を収録したCDの解説である。
ここには「水車小屋」の ”物語” も、牧歌的な背景もない。灰色の冬の野が私たちの視界をとざし、その中でただひとりの ”私” の独白が、どこまでも続いてゆく。「冬の旅」の最大の特徴は、この均質な情感の異様な持続である。(西野茂雄「歌曲集『冬の旅』全曲 D.911」)
専門書を探しても、歌曲となった『美しき水車小屋の娘』や『冬の旅』の解説書はあるものの、ドイツ文学としてのヴィルヘルム・ミュラーの詩集は、日本では出版されていないようである。
つまり、ミュラーは「シューベルトのミュラー」として受容されているということである。
ヴィルヘルム・ミュラー(一七九四~一八二七)は、一八二〇年代ドイツ文学界では注目を浴びた詩人であり、文筆家であった。しかし彼の作家活動は三十三歳になる誕生日直前の急逝までの一〇年余でしかない。(松下たえ子『ヴィルヘルム・ミュラー読本』)
ミュラーの作品は、シューベルトのほか、ブラームスやヴォルフ、レーヴェ、マイヤーベーアなど、多くの作曲家によって付曲された。
全783作の詩のうち、123作の詩に241名の作曲家が付曲し、作品数としては530曲にもなるという。
そして、その頂点にあるとも言える作品が、シューベルトの作曲した『冬の旅』だったのである。
ドイツ文学としての『冬の旅』
ドイツの作家(トーマス・マン)の代表作『魔の山』に『冬の旅』が登場している。
なんとしたことだ、彼は歌を歌っている。凍てついたような、頭のしびれるような興奮のさなかに、それとは気づかず茫然と口ずさむように、彼は切れぎれの息づかいをしていながら、低い声で『菩提樹(リンデンバウム)』を歌っている。(トーマス・マン「魔の山」高橋義孝・訳)
戦場で、主人公(ハンス・カストルプ)が最後に歌っていたのは、結核療養所のドイツ製蓄音機で聴いていたドイツ歌曲、シューベルトの「菩提樹」だった。
彼は立ちあがり、泥だらけの重い靴を引きずり、跛をひきながらふたたび蹌踉として前進を続けて、われ知らず口ずさんだ。「枝はそよぎぬ、いざなう如く──」(トーマス・マン「魔の山」高橋義孝・訳)
『冬の旅』の中で「菩提樹」は、日本においても最も良く知られた作品となっている。
すると菩提樹の枝がざわざわと音を立てる
ぼくに呼びかけるように
おいで お若いの
おまえの安らぎの場はここだよ
(ヴィルヘルム・ミュラー「菩提樹」松下たえ子・訳)
本作『冬の旅』は、死に場所を求めてさすらう若者の物語である。
疲れ果ててたどりついた「市門の前の泉のほとり」に、一本の菩提樹があった。
疲れ果てた主人公に、菩提樹は優しく語りかける(「おいで お若いの、おまえの安らぎの場はここだよ」)。
しかし、彼は菩提樹の誘惑を振り切って旅を続けた。
今やあの場所から
遠く離れたところにいるのに
ざわざわという音がずっと耳に残っている
おまえの安息の場はあそこなのにと
(ヴィルヘルム・ミュラー「菩提樹」松下たえ子・訳)
本作『冬の旅』は、生きにくい時代を生きる若者の「自分探し」の物語である。
自分の「安息の場所」を探して、彼は旅を続けるが、彼の「居場所」は見つからない。
菩提樹に呼びかけられた「安息」さえ、彼の居場所ではなかった。
そもそも、物語は、彼が旅へと出発する場面から始まる。
来た時ぼくはよそ者で
去り行く今もよそ者だ
旅立ちの時は
選べない
この暗闇の中
自分で探すしかない道程だ
(ヴィルヘルム・ミュラー「おやすみ」松下たえ子・訳)
彼が探すのは、自分が生きていく「道」である。
人生を生きる若者の戸惑いと不安が、恋愛物語(というか失恋物語)の形をとって描かれていく。
雪の中 むなしく探す
彼女の足跡
ここはふたりで
歩き回った緑の野原
花はどこだ
緑の草はどこにある
花々は枯れ果て
芝生もすっかり色あせた
(ヴィルヘルム・ミュラー「凍結」松下たえ子・訳)
絶望の中で彷徨う若者の心は、今にも凍死しそうなほどに冷たい。
そのときにたどりついた場所が、あの「菩提樹」だった(「おいで お若いの、おまえの安らぎの場はここだよ」)。
菩提樹の誘惑から逃れて、若者の旅は続く。
夕焼けから夜明けまでに
白髪になることもままあるそうだ
そんなこと信じられるか それにぼくの頭は
こんな長旅をしていてもそうはならなかった
(ヴィルヘルム・ミュラー「白髪の頭」松下たえ子・訳)
なぜ、それほどまでに、彼は苦しんでいたのだろうか?
それは、彼が「新しい時代」を生きようとしているためだった。
ほかの旅人が行く道を
なぜ避ける
雪に埋もれた岩山の
隠れた小径をなぜ探す
(ヴィルヘルム・ミュラー「道しるべ」松下たえ子・訳)
「ほかの旅人が行く道」を避けながら、彼は生きていた。
そこに、彼の苦悩がある。
やがて若者は、自分の死に場所となるべき「旅籠」へとたどりつく。
なんとこの宿の
部屋はすべて塞がっているというのか
ぼくは疲れ果て倒れんばかりで
死にそうな傷を負っているというのに
ああ なんと無慈悲な旅籠だ
そうか ぼくを追い返すのか
よかろう 先を行こう ただ先だ
なあ わが忠実な旅の杖
(ヴィルヘルム・ミュラー「旅籠」松下たえ子・訳)
しかし、その「旅籠」に、彼のための部屋(死に場所)はなかった。
死ぬこともできないで、彼は、この社会を生き続けていかなくてはならない。
そのことに気がついたとき、彼の再生は始まる。
道に迷うのは慣れっこだ
どの道だろうと目的地には着くもんだ
人の喜び 苦しみは
すべては鬼火の戯れだ
どんな川もいつかは海に注ぎ
どんな悩みもいつかは墓場にたどりつく
(ヴィルヘルム・ミュラー「鬼火」松下たえ子・訳)
少しずつ、彼の心は勇気を取り戻していく。
休もうと身を横たえた今
初めて気付いた この疲れ
険しい道のりも
歩いてさえいれば元気だったのに
(ヴィルヘルム・ミュラー「休息」松下たえ子・訳)
彼が気づいたのは「歩き続けていくこと」の意味である。
確かに ぼくにも最近まで三つの太陽があった
でも最良の二つは沈んでしまった
三番目も後を追って沈んでくれればいい
暗いところがぼくの気分にあっていそうなんだ
(ヴィルヘルム・ミュラー「幻の太陽」松下たえ子・訳)
大切なことは、最後の一つの太陽が、彼にはまだ残されているということである。
絶望の崖っぷちを歩きながら、彼はまだ生き抜いていたのだ。
心が何を言おうと聞いてはやらぬ
聞く耳など持つもんか
心が何を嘆こうと知るもんか
嘆くなど愚か者のすることだ
陽気に世の中へ繰り出そう
雨も風もなんのその
神が地上にいないなら
我ら自身が神々だ
(ヴィルヘルム・ミュラー「勇気」松下たえ子・訳)
やがて、「勇気」が彼を励ます(「心が何を嘆こうと知るもんか、嘆くなど愚か者のすることだ」)。
そして、彼は決意するのだ。
この生きにくい時代を(疎外感を抱えながらも)生き続けていくことを。
ずっとむこうの村はずれに
ライアーマンが立っている
かじかんだ指で
懸命にライアーを回している
誰も聞こうとしない
誰も見向きもしない
ただ犬どもが唸っている
その老人をとりまいて
それでもなすがまま
あるがまま
ライアーを回す ライアーは
鳴りやむことがない
風変りな老人よ
お供しようか
わが歌に合わせて
ライアーを回してくれるか
(ヴィルヘルム・ミュラー「辻芸人」松下たえ子・訳)
「かじかんだ指で、懸命にライアーを回している」辻芸人は、彼自身の姿である。
生き続けていくことを決心した若者の心は、「それでもなすがまま、あるがまま、ライアーを回す、ライアーは鳴りやむことがない」と、むしろ疾走感さえ感じさせる。
長い冬の旅の中で彼が見つけたものは「生きる希望」だった。
最後に置かれた「辻芸人(ライアーマン)」で、彼は初めて他者に語りかける。ライアーを回す乞食のような老人である。このライアーは(略)差別的な意味合いを持っており、乞食や旅芸人の楽器にされていた。(松下たえ子『ヴィルヘルム・ミュラー読本』)
アウトローとして生きる辻芸人は、最初の「おやすみ」に登場する主人公と同じように、現代社会の「よそ者」である(「来た時ぼくはよそ者で、去り行く今もよそ者だ」)。
「よそ者」である辻芸人が生き続けていく姿に、主人公は自分自身の未来をも投影したのだ。
本作『冬の旅』の通奏低音となっているのは、生きにくさを抱えて生きる若者の「疎外感」である(「よそ者である、馴染まない、見捨てられた、救いがない」といった感情)。
「菩提樹」の誘惑は、『魔の山』の主人公(ハンス・カストルプ)を「死」へと導く呪文でもあった(なぜなら、彼は戦争の時代を生きていたから)。
そして、現代社会を生きる我々もまた、疎外感を抱えながら生きる「冬の旅人」である。
「菩提樹」の誘惑を断ち切って、我々もまた生き続けていかなくてはならないのだ。
残りの「ひとつの太陽」が輝いているかぎり──。