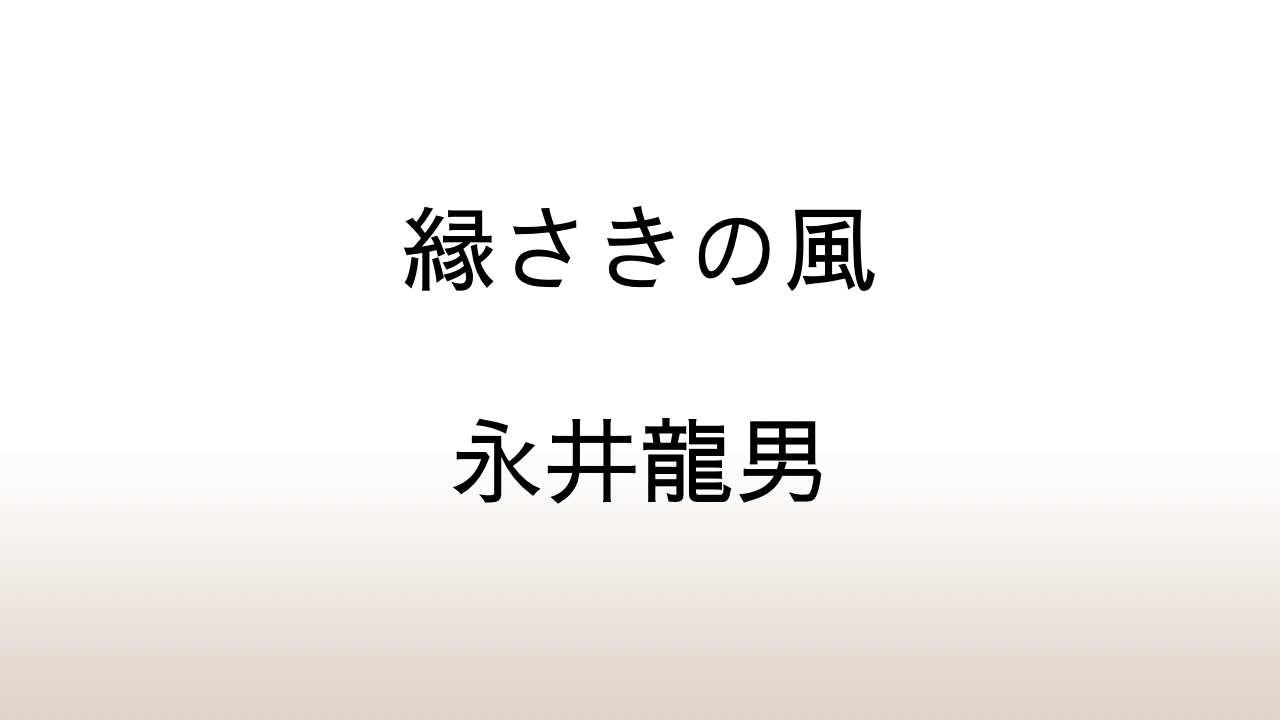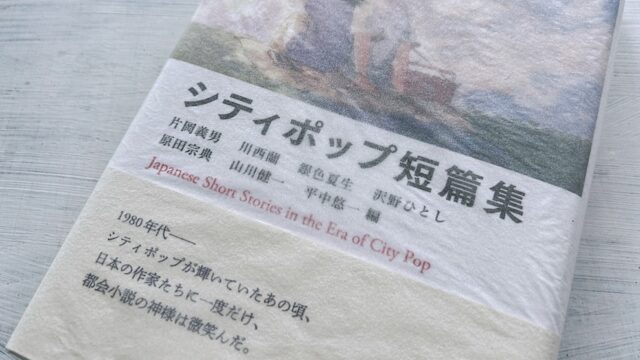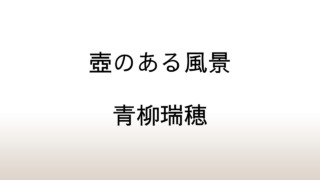永井龍男「縁さきの風」読了。
本書は、昭和五十八年に刊行された雑文集(いわゆる随筆集)である。
日常の買い物から遠い日を回想する
全体の構成は大きく「四季雑記」「応答一束」「鎌倉つれづれ」「追憶の人」「全集の校正を終って」に分類されている。
「四季雑記」は季節の移り変わりを背景とした身辺雑記で、ひとつひとつの作品から立ち上る季節の香りが豊潤である。
例えば、僕は「夏帽子」という作品を気に入っているが、新しい夏帽子を買うために、著者は鎌倉から東京まで出かけていく。
銀座通りの専門店でお気に入りの帽子を買った後、著者はフルーツ・パーラーでサンドイッチと冷たいコーヒーを注文するのだが、その店を訪ねるのは実に四十年ぶりのことであった。
いや、少し待ってくれと、私は舗道に立ち止まる。ちょうどあの方角から、海の匂いがしてきたことがあったろう。あれも戦争前の、ある初夏のことだった。その時、お前は云ったではないか。海の匂いが、東京の汐の匂いがしてきたと、ちょうどこの辺に立ち止ってお前は独り言を云ったものだ。なつかしい汐の香であった。そうだ、そんなことがたしかにあった。あの頃、銀座に赤や黄や青を縞にした日除けが流行したが、そういう一軒の店の前で、東京湾の方向へ向いて立っていたものだ。(永井龍男「夏帽子」)
日常のちょっとした買い物から遠い日を回想する文章の流れは、本当に素晴らしいものだと思う。
「越前大野から永平寺へ」は、越前大野を旅したときの旅行記だが、土地の人の会話を巧みに引用しているところがいい。
手打ちそばの昼食を食べながら、紅葉はいつ頃かと訊ねると、案内人は「もう水霜が来ていますから、十日か二週間というところでしょう」と答えるのだが、著者は「水霜とは寒い土地柄をしのばせるよい言葉と感心する」と、敏感な反応を示している。
続けて引用されている「初雪らしい初雪は、やはり十二月に入ってからですが、雪催いの日には、雪の匂いがします。雪に匂いがあるとは嘘のようですが、われわれ土地の者には匂います。同じように、残雪が消えてゆくにしたがって、まず春の来る匂いがします。ほんとうに匂ってきます」という案内人の言葉にも旅愁が感じられる。
旅行記というよりも、もはや聞き書き小説と言ってよいくらいに、濃密な文章だ。
これは、随筆の中でも特に旅行記を、僕が好んで読んでいるということによるのかもしれないが。
「しろき・くろき」では、昔の東京の酒場風景が偲ばれている。
「神田神保町という所は、古本屋の町とも云われている。その一軒で本を売り、その銭を握って、夜店の外れに屋台店のおでん屋がのれんを下げているのに入る。そういうことを覚えて十八九から酒はうまいものと思った」とか「浅草は、盆正月が書入れ時であった。田原町から雷門にかけて、電車通りの片側に屋台店がズラリと並んでいるので、焼鳥屋やすし屋で一日分の空腹を癒しホロ酔いで帰る。浅草には電気ブランや、五色の酒というのを呑ませる有名な店があったが、酔いの早いのを用心して一度も呑んだことはなかった」など、古き良き時代の東京が酒を通して描かれている。
読書の楽しみを綴ったのが「再び、切る楽しさ」。
よい本に出逢った悦びは、何事にも比べることが出来ない。徹夜をしても読み明かすのは若いうちの情熱である。年を取ると、一気に読み進むのが惜しまれて、明日のために枕もとの灯を消すかも知れない。(永井龍男「再び、切る楽しさ」)
読書に夢中になっているうちに夜を明かしてしまう楽しさは、文学好きの人ならば誰でも経験をしていることだろう。
そんな読書の楽しみを共感できる作品である。
文学生活の他は無力だった横光利一
「横光利一展に寄せて」の中に楽しい話があった。
同人雑誌の仲間で野球の試合をした時、横光利一は自身の結婚式のために新調したモーニングとエナメル靴で登場したという。
「仕様がない」という言葉を「しょむない」と発音する癖のあった横光は、「僕は、これより他に洋服と靴を持たんから、しょむない」と言いながら、上着とチョッキを脱ぎ捨ててグラブを手にした。
普段は和服姿で過ごしている横光が結婚したばかりの頃のエピソードらしいが、「横光さんという人は、幼児のように世事に疎く、文学生活のほかは実に無力な、痛々しいまでに不器用な人柄」と、著者は回想している。
結局、この生活能力の無さが祟って、横光は終戦直後の混乱を乗り切ることができず、栄養失調で死んでいったという話は、この後の「全集の校正を終って」の中でも触れられている。
本書を「雑文集」と言ってしまえばつまらないが、鎌倉文士が綴った雑文には、やはり鎌倉文士らしい面影が浮かんでくるものである。
「最後の鎌倉文士」と呼ばれた作家のエッセンスを楽しむには、こんな雑文集が一番ではないだろうか。
書名:縁さきの風
著者:永井龍男
発行:1983/5/20
出版社:講談社
文芸エッセイの世界をより深く知りたい方へ
大人の随筆の世界をもっと知りたい!という方に、おすすめの記事を用意しました。
アナクロで粋な昭和エッセイの世界を極めてみませんか?
大人のための随筆(エッセイ)案内
昭和文学を中心に、大人のための随筆(エッセイ)を集めました。
教養ある「粋」な大人になりたい方に、超おすすめのマニアックな文芸世界です。
▶ 大人のための随筆(エッセイ)案内|教養ある大人が嗜むべき名作の歩き方ガイド