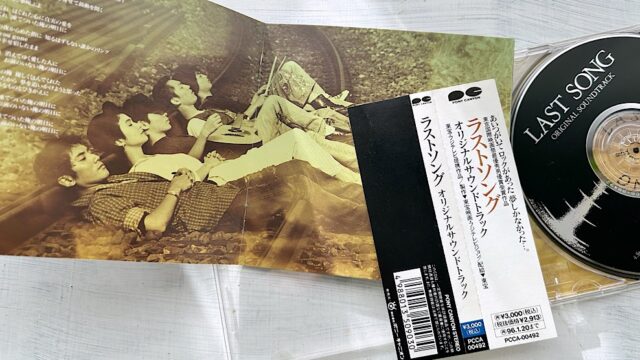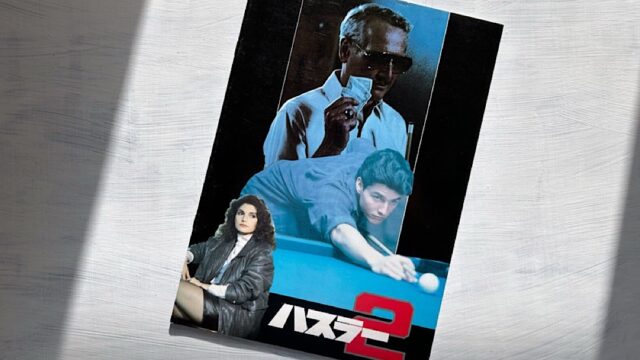杉元伶一「就職戦線異状なし」読了。
本作「就職戦線異状なし」は、1990年(平成2年)3月に講談社から刊行された長篇小説である。
杉元伶一のデビュー作だった。
1991年(平成3年)には、織田裕二主演で映画化もされている。主題歌は槇原敬之「どんなときも。」。
バブル絶頂期、超売り手市場の就職活動
その夏、早稲田大学・本格文芸倶楽部からは4名の学生が就職戦線に参加していた。
セックスマニアの<大原>、就職活動マニアの<立川>、小説家志望の<糸町>、スマートな優等生<南野>。
後輩たちは「就職内定獲得レース運営委員会」を立ち上げて、誰が大手マスコミに就職することができるか、賭けている。
時代は折りしもバブル景気絶頂期で、空前の超売り手市場と呼ばれた時代だった。
糸町は舞い落ちてくる会社案内を蹴散らし、踏みにじった。「自分から頭を下げ、貴社に入れて下さいと頼むのは死んでも願い下げだ。だが、これだけ多くの企業が小社や弊社に来て下さいと俺の前に這いつくばっているんだぜ」(杉元伶一「就職戦線異状なし」)
しかし、どんなに就職活動が大学生に有利とは言っても、大手マスコミに入社することが難関であることに変わりはなかった。
NHK、日本テレビ、新潮社、文藝春秋、講談社、朝日新聞、光文社、主婦の友社、マガジンハウス、、、
彼らは、次々と就職戦線に散っていく。
1989年から1991年まで、大学卒の求人倍率は2.5倍を超えた。空前の超売り手市場と呼ばれた時代である。
頼りにしていた先輩をOB訪問で訪ねたときには、既に退職した後だった。
「なりゆきさ。それ以外にない。街を歩いているサラリーマンを捕まえて片っ端から聞いてみろ。お前はなんだって今の仕事を選んだってな。張り倒されるぜ。どいつもこいつも後悔してるに違いないんだ」(杉元伶一「就職戦線異状なし」)
「たまたま受けてたまたま受かった会社で文句を言わずに働いて、結果たまたま幸福になれば良し、往々にして不幸になったら運がなかったと思って諦めな」「よっぽど嫌なら転職すればいい。俺みたいにさ」と、ボイラーマンをしている先輩は言った。
それでも、彼らは、大手マスコミへの就職を目指して前進を続ける、、、
ちなみに、映画では仙道敦子演じる<毬子>が重要な役回りを担っているが、これは映画オリジナルで、小説には登場しない。
バブル時代の就職活動も、決して気楽なものじゃなかった
本作のテーマは、人は何を基準に就職先を選ぶのか?ということである。
現に出版社で働く<古宮>は、「大体、金目当てで仕事を選んだら必ず後悔することになる。君はそんなことも解らないのか?」と、軽蔑したような声で言った。
ナンパな大原にとって、就職先は愛情の付加価値だった。
「一流企業に勤めている大原さん」と紹介することができれば、彼女の母親も安心するし、彼女も友だちに胸を張って自慢することができる。
だから、彼にとって就職は、彼女への愛情の付加価値に過ぎないものだったのだ。
「今はこうやって遊んであげてるけど、それはあたしがまだ二十一だし、結婚とか全然考えてないからだわ。大原さん、二十四よね? あたしが二十四くらいになって遊ぶのに飽きてきて、落ち着いちゃおうかなって考えだしたら、今からきっぱり言っとくけど、絶対に大原さんみたいな安定性に欠けて、先の見込みのない男には指一本触れさせないからね」(杉元伶一「就職戦線異状なし」)
こうした大原の就職観は、女性たちによって育まれたものだと言っていい。
就職観というのは、そのくらいに曖昧で、就職先の会社を選ぶ基準なんて、いかにも頼りないものだった。
就職戦線で幾多の敗北を繰り返すうち、彼らは現実と直視し始める。
「ガキが大人になったかどうかの目安は、職業選択の幅がどれだけ狭まってしまったかなんだろうな」「なりたいものなんてのがあるうちはまだまだガキなんだよ」(杉元伶一「就職戦線異状なし」)
就職先を選択するのは自分たちではなく、企業側なんだと気が付いたとき、彼らは、大人への第一歩を踏み出していたのだ(切ないけれど)。
そう考えると、就職活動期というのは、大学生から社会人へと変わる過渡期のようなものなのかもしれない。
至るところ、ふざけた表現で埋め尽くされている冗談のような小説だが、冗談でも言って笑っていなければやってられない——それが、彼らの本音だったのではないだろうか。
バブル時代の就職活動も、決して気楽なものじゃなかったんだなあ。
書名:就職戦線異状なし
著者:杉元伶一
発行:1992/5/15
出版社:講談社文庫