大久保房男「戦前の文士と戦後の文士」読了。
本書は、昭和30年代に「群像」編集長を務めた著者による、文壇エッセイ集である。
<第三の新人>と「群像」長編一挙掲載の企画
私は第三の新人より年長と書かれているけれど、第三の新人の中心的作家の一人である庄野潤三氏と同年だから、第三の新人とは全く同じ世代である。(大久保房男「戦前の文士と戦後の文士」)
<第三の新人>と同世代の編集者ということもあるのか、戦前戦後の文壇を回想した本書の中でも、<第三の新人>に対する記述は少なくない。
第三の新人を世の中の余計者の立場から小説を書く流派としては、安岡章太郎、吉行淳之介、庄野潤三の三氏を私はその中心人物と考えていた。流派の第三の新人も交遊グループの第三の新人も、文壇の評価は極めて低く、序数としての第三が三等列車のように等級を表すような使われ方もしていたから、同世代の私は応援団のような気持になり、何とかして文壇の評価を変えてもらおうと考えていた。(大久保房男「戦前の文士と戦後の文士」)
当時、<第三の新人>の前には戦後派があり、後には派手な新人が登場していたから、<第三の新人>は、その狭間で消えてなくなるだろう、とさえ言われていた。
そこで、著者は、<第三の新人>の一人である遠藤周作に、「第三の新人に対する文壇の評価が不当に低いのは、これと言った長編小説を書いていないからだ」「戦後の文壇ではこれといった長編小説を持っていないと尊重されない傾向があるから、第三の新人は是非力の籠った長編小説を書くべきだ」と説得する。
評価の低い第三の新人にはどこの雑誌も連載を頼む気がしないだろうけど、ぼくは先ず流派としての第三の新人の中心の安岡、吉行、庄野の三氏に長篇を書くようにすすめ、書き上げた作品を編集部でよく検討し、これでいけるとなったらそれがどんなに長くても一挙に掲載する、そんなことを考えているんだ、と言ったら、遠藤君は、それを聞いたらみんな喜びますわ、早速話してやって下さいよ、と言って、自分で安岡、吉行、庄野の三氏に電話をかけ、新橋駅で会うことになった。(大久保房男「戦前の文士と戦後の文士」)
「群像」の長編一挙掲載の企画は、その後、紆余曲折を経て、昭和33年4月号に安岡章太郎の『舌出し天使』が掲載され、9月号に吉行淳之介の『男と女の子』が掲載された。
さらに、昭和34年6月号に、庄野潤三の『静物』が一挙掲載され、この作品は新潮社文学賞を受賞した。
「群像」の編集部では、今度の号はこの新人の力作で打って出るという時は、発売のずっと前から原稿を書いてもらい、それを編集部でよく読んで、感想を述べて手を入れてもらってから掲載した。先般亡くなられた庄野潤三氏の『静物』の場合も、長編の掲載と考えていたのに、手を入れてもらったら短くなって、中篇になってしまった。それが新潮社文学賞を受賞した。(大久保房男「戦前の文士と戦後の文士」)
もっとも、手を入れると短くなったのは<第三の新人>までで、それ以後の新人は、大体において長くなったらしい。
ちなみに、安岡章太郎、吉行淳之介、庄野潤三の三人は、昭和28年から29年にかけて芥川賞を受賞したメンバーで、いずれも佐藤春夫の門下生だった。
選考員の佐藤春夫が、自分の門下生に次々と芥川賞を受賞させたというので、当時の新聞が「売れ残りの卒業生をいいところに嫁がせるために強引な売り込みをする女学校の校長みたいだ」と批判したこともあったという。
文藝手帖を捨てなかった庄野潤三
最後に、庄野さんの話をもうひとつ。
文士の作品の中には「文壇史」「盛衰史」「回想記」「交遊録」などと題したものがたくさんあるが、そういう作品の中には、事実や日時に誤ったものも少なくないという。
私が第三の新人の中心人物と見て来た安岡、吉行、庄野の三氏の中では庄野さんのものが一番誤りがない。庄野さんは出版社から毎年贈られる文藝手帖を捨てずにとっておいて、過去のことはそれに当って書いている。(大久保房男「戦前の文士と戦後の文士」)
日記を作品にすることの多かった、庄野さんらしいエピソードである。
何だか、<第三の新人>の話ばかりで終わってしまったが、本書では、戦前から戦後にかけて文壇で活躍した文士たちの回想が、幅広く綴られている。
むしろ、<第三の新人>の話は、全体のごく一部に過ぎないので、念のため。
書名:戦前の文士と戦後の文士
著者:大久保房男
発行:2012/5/8
出版社:紅書房

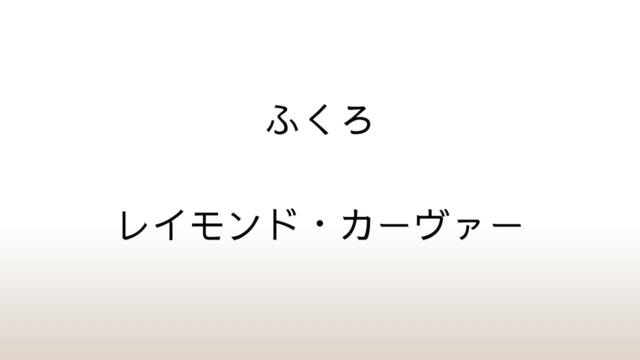




-150x150.jpg)









