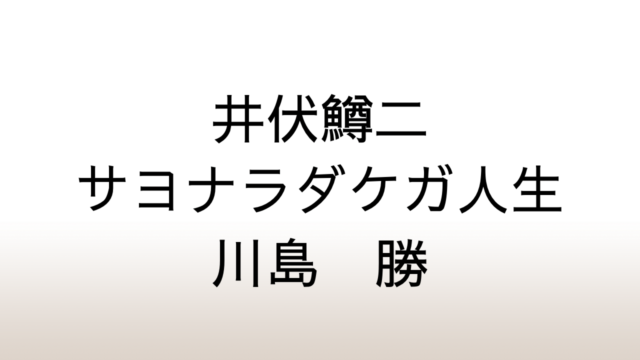阿川弘之「カレーライスの唄」読了。
本作「カレーライスの唄」は、1961年(昭和36年)、北日本新聞などに連載されたユーモア青春小説である。
単行本は、1962年(昭和37年)3月に、新潮社から刊行されている。
この年、著者の阿川弘之は42歳だった。
戦争を知らない世代が、戦争について考えることのできるエンタメ小説
本作の根底を流れているものは、「貧乏しているときに食べたカレーライスはおいしい」という、ひとつの単純な信念である。
「この間の川武サンタ・アンナのカレーライスといい、このコーヒーといい、心のくたびれた時にごちそうになるものの味は、本当にええなあ」(阿川弘之『カレーライスの唄』)
作中、こうしたフレーズは何度も登場してきて、物語に通底する基本的な哲学となっていることが分かる。
「ああ、うまいなあ。紅茶もうまいなあ。貧乏して、失業して、ごちそうになるものは、カレーライスでもトーストでもほんとにうまいよ」(阿川弘之『カレーライスの唄』)
そして、主人公<桜田六助>のこうした信念の大きな背景となっているものが、ひとつとして、戦後、中国で戦犯として処刑された父親の存在、もうひとつが、郷里・広島を襲った原子爆弾による惨劇だろう。
本作は、出版社の倒産に伴い失業した若い男女が、神武景気や岩戸景気などと呼ばれる高度経済成長下でブームとなっている株式投資により資金を蓄え、二人でカレーライス屋さんを開業するという、昭和のサクセスストーリーだが、根底を流れる「貧乏しているときに食べたカレーライスはおいしい」という思想が、この小説を浮わついたものとすることなく、しっかりと下支えしている。
もちろん、著者(阿川弘之)の専門分野とも言える戦争文学らしさが顔を出している場面も少なくないが、こうした戦争論は、本作の大きな性格となっているユーモア小説としてのエンターテイメント性を損なわない範囲で、スパイスとしての効能を果たしているに過ぎない。
むしろ、娯楽小説の中に「日本の戦争体験」という辛口のスパイスをさりげなく混ぜ込むことよって、本作『カレーライスの唄』は、甘さと辛さの絶妙なバランスを保った大人向けの味のエンタメ小説として、完成されたものとなっているのではないだろうか。
原爆当時のことを思えば、広島の町も大した復興をしたものだ。道は広く、りっぱに舗装され、高い新しいビルディングが立ち並び、人々の服装もきれいである。ほんとうは、町のどこかにまだたくさん、ふた目と見られないような顔をした原爆被害者が、そっとかくれて暮らしており、原爆の後遺症が出て、今ごろになって突然死んでゆく人も跡をたたないらしいのだが、町のにぎわいだけ見ていると、そんな話がまるでうそのようだ。(阿川弘之『カレーライスの唄』)
本作の連載が開始された1961年(昭和36年)という時代背景を考えたとき、高度経済成長に浮かれる日本に向けて、著者は今一度、戦争の戒めのようなものを提示したかったのではなかったか、という推測も浮かぶ。
それは、戦争責任と呼ばれるような大上段なものでなく、「貧乏しているときに食べたカレーライスはおいしい」という、敗戦国・日本の誰もが感覚的に覚えている、リアルな戦争体験である。
本作における「出版社の倒産と失業」を「太平洋戦争と敗戦」に、「株式投資とカレーライス屋の開業」を「高度経済成長と戦後社会の復興」に置き換えてみると、案外、この小説は
戦後日本の復興に向けた未来予想図と考えることもできるような気がする。
そして、敗戦国・日本の復興を支えたのも、物語の中の若き失業者たちを支えたのも、結局は、回りの人々の優しさだったというところに、日本の強みが描かれているのではないだろうか。
時代は昭和から平成、平成から令和へと変わったが、敗戦国・日本の教訓は決して失われたわけではない。
むしろ、現在のような時代にこそ、我々は、あのときに食べた「カレーライスの味」を思い出すべきではないだろうか。
戦争を知らない世代が、戦争について考えることのできる、そんなエンタメ小説だと思った。
爽やかでおしゃれな鈴木英人のイラスト
ところで、我が家の書棚にある『カレーライスの唄』は、講談社文庫(上下巻)で、その表紙の装画は、鈴木英人が担当している。
まるで、山下達郎や片岡義男を連想させるような、爽やかでおしゃれな鈴木英人のイラストと、阿川弘之の『カレーライスの唄』とは、どう考えてもマッチしないような気がするんだけれど、、、。
講談社文庫版の刊行は1982年(昭和57年)。
1962年(昭和37年)の単行本刊行から20年が経過する中で、日本もずいぶん豊かになったということなのかもしれないね。
書名:カレーライスの唄
著者:阿川弘之
発行:1982/9/15
出版社:講談社文庫