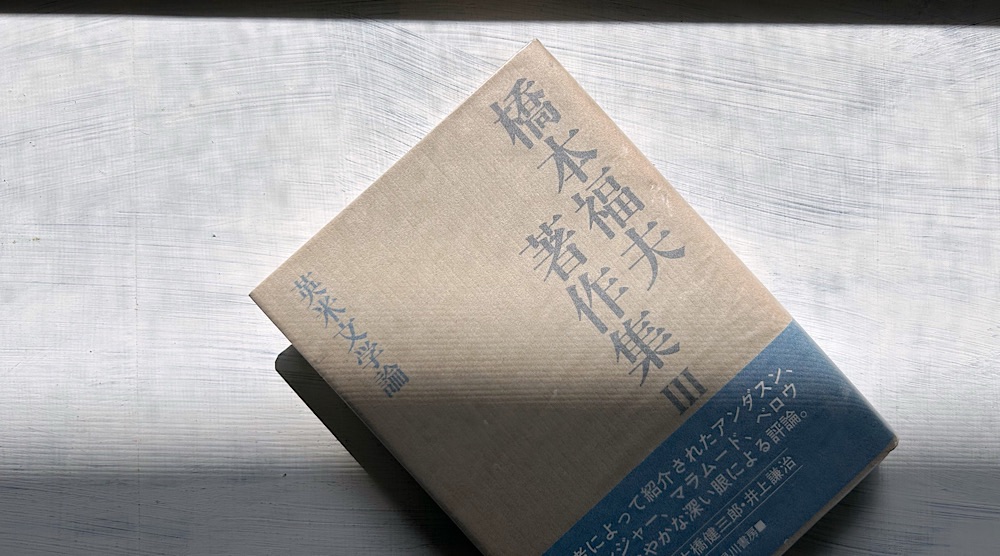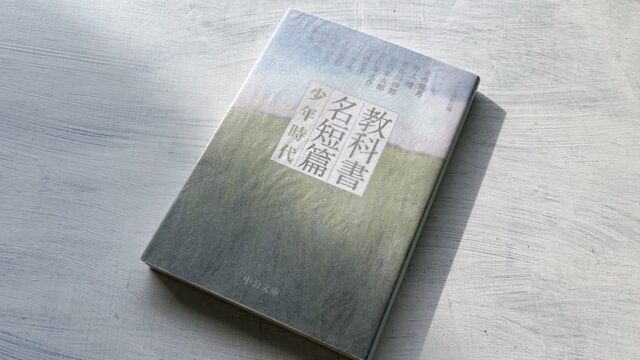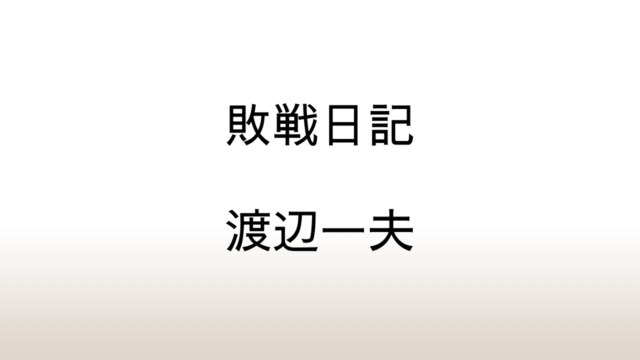J.D.サリンガー『危険な年齢』読了。
本作『危険な年齢』は、1951年(昭和26年)7月にリトル・ブラウン社から出版された長篇小説である。
原題は「The Catcher in the Rye」。
この年、作者は32歳だった。
日本最初の『ライ麦畑でつかまえて』
J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」には、三つの日本語訳がある。
・危険な年齢(橋本福夫)ダヴィッド社/1952年
・ライ麦畑でつかまえて(野崎孝)白水社/1964年
・キャッチャー・イン・ザ・ライ(村上春樹)白水社/2003年
このうち最も有名なのが、野崎孝訳の『ライ麦畑でつかまえて』で、最も新しいものが村上春樹訳の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』である。
橋本福夫の訳した『危険な年齢』は、さしずめ、最も古く、最も知られていない『ライ麦畑』ということになるかもしれない。
本国アメリカにおける『ライ麦畑』の刊行は1951年(昭和26年)7月だから、1952年(昭和27年)12月にダヴィッド社から刊行された『危険な年齢』の翻訳は、ほぼリアルタイムなものだったと言っていい。
「危険な年齢」は昨年(1951年)に出版されたものであり、わたしがこの書を初めて読んだのはちょうど一年前の昨年の十二月頃であった。「ハーパース・マガジン」の書評でこの書のことを知り、期待して読んだのだったが、はたして期待に背かないものであると思った。(J.D.サリンガー「危険な年齢」あとがき:橋本福夫)
サリンジャーは、当時、日本では、まだ普通に知られる作家ではなかった。
著者名が「J.D.サリンガー」とされていることからも、それが伝わってくる。
作者J.D.サリンガーはまだ若い人であり(1919年生まれである)、長篇小説はこれが処女作であって、今迄は短篇小説をいろんな雑誌に載せていたということだけれども、わたしはまだ残念ながらそれらの短篇小説を読んでいない。(J.D.サリンガー「危険な年齢」あとがき:橋本福夫)
訳者にとって、サリンガーは「未知数の作家」だった。
もちろん、本国アメリカで『The Catcher』は発売直後からベストセラー作品になっていて、『危険な年齢』のあとがきにも、「映画嫌いなホールデン・コールフィールドには皮肉な話だが、映画化されるそうである」と綴られている(実際に映画化されることはなかった)。
訳者としては、「アメリカの生んだ戦後(アプレゲール)らしい戦後小説」として、この物語を日本へ紹介するつもりだったのだろう(なにしろ、この文学作品が永遠の古典となることを、当時は誰も知らない)。
タイトル「危険な年齢」については、「出版社であるダヴィッド社におまかせした次第であった」とある。
直訳すれば「ライ麦畑でとらまえる者」となるこの作品名を、どのような形で日本語に翻訳することが正解なのか、判断が難しかったはずだ(現代の村上春樹でさえ、日本語に置き換えることはあきらめた)。
「危険な年齢」は多少漠然としているが、「ライ麦畑でとらまえる者」は戦後のアメリカの若い人達の持つ空虚感を表明した言葉であった。(略)要するに、「ライ麦畑でとらまえる者」とは、現実の虚偽、気取り、無神経、野蛮、グロテスクに絶望して、現実的な、実際的なことがらのすべてへの興味も希望も喪失した若いひとを、象徴しているわけである。(J.D.サリンガー「危険な年齢」あとがき:橋本福夫)
アプレゲール(戦後)という文脈から読んだとき、『危険な年齢』は、若者たちの虚無感を象徴した物語ということになる。
そして、戦争が終わって、まだ6~7年しか経っていない時代にあっては、そのような読み方が最も自然だったはずで、「危険な年齢」という日本語タイトルには、戦争直後という時代背景が含まれていたことに注意しなければならない。
ちなみに、この時代、日本の文壇に登場してきたのは、安岡章太郎や吉行淳之介、小島信夫、庄野潤三といった、いわゆる「第三の新人」世代だった(サリンジャーが1919年生まれ、安岡章太郎が1920年生まれ、庄野潤三が1921年生まれ)。
さらに、1956年(昭和31年)には、石原慎太郎『太陽の季節』がベストセラーとなって、戦後の新しい若者たちの代表として「太陽族」が登場する。
こうした時代背景を考えると、当時の『危険な年齢』は、戦後に登場した新しい世代を象徴する作品として、日本の読者にも受け止められていた可能性は大きい。
本作『危険な年齢』は、戦後を生きる若者たちの喪失感に主眼が置かれた青春小説だったのだ(少なくとも当時の日本社会としては)。
そして、神格化された『ライ麦畑でつかまえて』と違って『危険な年齢』は、純粋に物語を観賞することができる、素直な翻訳となっている。
村上春樹の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読んだけれど、イマイチ意味不明だったという人は、橋本福夫訳の『危険な年齢』も読み比べてみるといい。
新しい発見が、きっと、そこにはある。
喪失感を抱えた若者による自分探しの物語
日本国内において、70年以上も読み継がれてきた『The catcher(ライ麦畑)』だが「何が言いたいのか分からない」という読後感は、未だに後を絶たない。
既に、古典とさえ言える『ライ麦畑』は、どうして理解が難しいのだろうか。
ストーリーとして、この物語は、全寮制の高校を中退した孤独な少年(ホールデン・コールフィールド)が、クリスマス前のニューヨークの街をフラフラとさまよい、実家に戻って妹(フィービー)と再会するというシンプルな内容になっている。
あらすじとしてシンプル過ぎるからこそ、一見「オチ」のない結末に、読者は戸惑ってしまうのかもしれない。
実際、『危険な年齢』は、表面的なストーリーを追いかけるだけでは理解することが難しい、深い文学作品だ。
なぜなら『危険な年齢』は、暗示性に富んだ小説となっているからである。
その代表が、主人公(ホールデン・コールフィールド)の被っていた「赤い帽子」である。
ついでその朝ニューヨークで買った帽子をかぶってみた。やけに長いひさしのついている赤い鳥打帽子なんだ。(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
耳垂れの付いた「赤い鳥打帽子」は、物語の中で「ホールデン自身」として機能している。
僕は鳥打帽子を、僕の好きなようにひさしをうしろにまわしてかぶり、ついで、あらん限りの声をはり上げてどなってやった。「眠りほうけろ、この低能めら!」(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
赤い帽子を後ろへ回しているところに、ホールデンの解放された感情が示されている。
妹(フィービー)の小遣いをもらった兄(ホールデン)が泣き止んだとき、彼は、赤い鳥打帽子をフィービへ渡す。
それから僕はオーバーのポケットから例の鳥打帽子をとり出して、彼女にやった。フィービはこういうへんちくりんな帽子が好きなんだ。(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
フィービーが好きなのは、もちろん、(へんちくりんな)兄(ホールデン)自身である。
さらに、回転木馬の場面(ラストシーン)では、フィービーが、ホールデンの頭に、赤い鳥打帽子を乗せる。
すると彼女はどうしたかというと──僕はまいらされたんだけど──僕のオーバーのポケットに手をつっこんで、僕の赤い鳥打帽子を取出し、僕の頭にかぶせてくれたんだ。「きみはいらないのかい?」と僕は言った。「すこしのあいだ、兄さんがかぶってていいわ」(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
兄の頭に帽子を乗せる行為は、傷ついた兄の心に寄り添う妹の気持ちを投影している。
こうした鳥打帽子の描写は、アントリーニ先生の「君は自分の真実の尺度を知り、それに応じた帽子を自分の頭にかぶらせられるようになる」という言葉に呼応したものだろう。
つまり、鳥打帽子そのものが、ホールデン自身だったのだ。
セントラルパークの小さな湖にいるアヒルも、ホールデンにとって大きな関心事だった。
「ねえ、君、ホリッヅ君」と僕は言った。「君は中央公園の中の湖(ラグーン)のそばを通ったことがないかい? 中央公園の近くのさ」「あそこのなんです?」「池。あの小さな湖みたいなやつさ。ほら、アヒルがいたりする」(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
湖が凍ってしまう冬の間、アヒルは、どこへ行ってしまうのだろうか?
アヒルは、もちろん、ホールデンの化身であり、アヒルの謎は、ホールデン自身の居場所探しでもある。
つまり、この物語では、様々な描写に、ホールデン自身の姿が投影されているのだ。
みんなが廊下をバタバタと駆け出し、階段を走り降りて行くので、僕もバスローブをひっかけて駆け降りてみると、ジェイムズ・キャスルが石段の上に横たわっていた。死んでしまっていて、歯や血がそこらに散らばっており、誰もそばへ寄ってみる者もなかった。キャスルは僕の貸してやった丸首のスエーターを着ていた。(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
ホールデンのセーターを着て自殺したジェイムズ・キャスルも、また、ホールデンの分身として読むことができる。
こうした主人公の投影は、『危険な年齢』という物語を読み解く上で、非常に重要な要素と言えるだろう(投影探し)。
ホールデンの反社会的スラングの多用は、あくまでも表面的な仕掛けであって、随所に織り込まれた暗示性を、どのように読み解くかというところに、この物語の「深さ」がある。
『危険な年齢』は「投影探し」をしながら掘り進めていくことで、おもしろさを見つけることができる小説なのだ。
村上春樹は、この投影を「言い換え」と表現している。
代表作『キャッチャー・イン・ザ・ライ』もかたちとしては一応長編小説にはなっていますが、よく読み込んでいくと、正確な意味での長編小説とは言えないような気がだんだんしてくる。ひとつのヴォイスによるものごとのさまざまな「言い換え」を、時間順に、並列的にならべているだけではないのかと。(村上春樹「短編小説はどんな風に書けばいいのか」)
泥酔したホールデンは、喧嘩別れしたばかりのサリーの自宅に、真夜中の電話をかける。
「サリイかい? きみんところのクリスマス・ツリーの飾りつけに行くぜ。いいかい? ねえ、いいかい?」「もうわかったわよ。さっさとおやすみ。いまどこにいるの? 誰といっしょなの?」「誰とでもないんだ。おれと僕自身と僕とだ」(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
「誰とでもないんだ。おれと僕自身と僕とだ」というホールデンの言葉は、この物語が、多くのホールデンの分身によって構成されていることを示唆している。
社会を嫌悪するホールデンの嫌悪感は、ある意味での自己嫌悪であり、社会に傷つくホールデンの姿は、自分自身に傷ついている少年の姿なのだ。
ホールデンが「インチキ」と呼んだ現代社会は、実は、ホールデン自身の中に潜む「インチキ」であり、フィービーが持つイノセンスは、ホールデン自身が持つイノセンスでもある。
『危険な年齢』という、この物語まるごと全部が、つまりは、ホールデン・コールフィールドという少年自身だった。
そして、作品タイトルと深く関わってくるロバート・バーンズの「Comin Thro’ The Rye(カミン・スルー・ザ・ライ)」。
最初に、この歌が登場するのは、教会から出てきた子どもが、車道を歩きながら歌っている場面である。
僕は何を歌っているのか聞きたいと思って、いっそう近寄ってみた。その子供は「だれとだれとが麦ばたけで」という歌を歌っているのだった。(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
少年は歩道ではなく車道を歩いているが、彼らの両親は、子どもに注意を払うこともなく、前を歩いていく。
彼と細君とはおたがいに話しながら歩いていて、子供のことには全然注意をはらっていなかった。ところがその子供がすばらしかったんだ。彼は歩道ではなく車道のほうを歩いているのだったが、それでもふち石のすぐそばを歩いていた。(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
「ふち石のすぐそばを歩いていた」というフレーズが、後の「ライ麦の中のとらまえる者になりたい」という、ホールデンの告白につながっていく。
このとき、ホールデンに勇気を与えてくれたのが「だれとだれとが麦ばたけで」だった。
ホールデン・コールフィールドは、自分の居場所を見つけたのだ。
「僕が何になりたいか知ってるかい?」と、ホールデンはフィービーに訊ねる。
「なによ? えらそうなことを言って」と、フィービーは兄を突き放す(『危険な年齢』のフィービは、クールな男前でかっこいい)。
「とにかく、僕には、ひろいライ麦畑のなかかなんかで、小さな子供たちが遊んでいる様子が頭に浮んでくるんだ。何千人もの小さな子供がね。そしてあたりには僕よりほかには誰も──おとなはだよ──いないんだ。僕は断崖のふちに立っている。僕のしなきゃならないことは、子供たちが断崖から転げ落ちそうになったら、つかまえることなんだ。子供たちがわき目もふらずに夢中で走ってきたりしたら、僕がどこからか飛び出してきて、つかまえてやるんだ。一日じゅうそんなことばかりをしているんだ。そういうライ麦の中のとらまえる者になら、僕はなってみたいな」(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
ライ麦畑の中で遊ぶ子どもたちは、ホールデンの中に潜むイノセンスを投影したものだったかもしれない。
変わることを恐れるホールデンは、自分自身の変化を(成長を)何よりも恐れていた。
成長とはイノセンスを失ってしまうことだと、ホールデンは知っていたからだ。
そして、イノセンスの喪失は、ホールデンにとって、社会における自身の居場所の喪失をも意味していたのである。
ホールデン・コールフィールドの愛読書には、フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』(1925)があった。
僕はD・Bに、リング・ラードナーのものや「グレート・ギャッビイ」のような作品なら、僕は今でも愛読できるんだから、と言ってやった。事実そうなんだからね。僕は「グレート・ギャッビイ」には夢中になっていたんだ。ギャッビイ。愉快な男だな。あの男には僕もまいったよ。(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
ホールデンの中の「ギャツビー」は、イノセントを抱えたまま死んでいった30歳の男である(なにしろ、初恋の相手デイジーへの純愛はすごい)。

あるいは、変わらずに成長することの一つのモデルを、ホールデンは「ギャツビー」の中に見出していたのかもしれない。
長い物語の(わずか三日間の物語だが)随所に登場するSOSは、ホールデン自身のSOSである。
「僕は何からも何ひとつ得られない人間なんだ。僕自身が狂ってきているんだ。へんてこになってきているんだ」(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
ガールフレンド(サリー・ヘイズ)とうまく意思疎通できないホールデンは、突然、「二人で山小舎か何かで暮そうじゃないか」と提案する。
都会願望の強い(つまり俗物の)サリーは、ホールデンの申し出を当然拒否するが、現状からの逃避を願うホールデンの言動は、この物語の大きな主題となっている。
高校の寄宿舎を飛び出して、真夜中のニューヨークをさまよい、田舎暮らしを提案するホールデンの行動を支えているものは、現状への不満によって育まれた、現実世界からの逃避願望である。
自己認識と現実社会との価値観のズレが、ホールデンを現実社会からの逃避へと駆り立てていた。
ホールデンの反社会性は、現実社会と折り合うことのできない自身の疎外感に裏打ちされていたのだ。
むしろ、ホールデンは、自分が生きている社会の現実に、常に傷付き続けているのであり、盛んに「気がめいる」という言葉を連発しているのも、その表れだったのだろう。
正直に言うと、性欲よりも気がめいってくるほうが強かった。彼女そのものが僕の気持をめいらせるんだ。押入れにかけた緑色のドレスやなんかがね。(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
ホールデンは、とにかくいろいろなものに傷ついているが、彼を一番傷つける存在は、最愛の妹フィービー(10歳)だった。
その時、僕は不意に泣き出してしまった。泣かずにはおれなかったんだ。誰にも聞きつけられないように気をつけたけれど、泣いたことは事実なんだ。僕が泣き出すと、フィービがすっかりおびえてしまい、そばへ来てなぐさめようとしてくれたけれど、一度泣き出すと、どうにも止められるものじゃないよ。(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
フィービーからクリスマスの小遣いをもらったホールデンが号泣する場面は、この物語の中でも、とりわけ切ない場面だ。
フィービーの優しさが、ホールデンを傷つけるのであり、フィービーの持つイノセンスが、ホールデンをまた傷付けるからだ。
ホールデンは、変わることを恐れる少年だった。
今あるがままのすがたでとどめておきたいものもある。そうしたものは、あの大きな硝子のケースの一つに納めて、そうっとしておきたいのだ。そんなことは不可能だということは僕も知ってはいるけれど、それではひどすぎる気がする。(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
イノセントなフィービーも、やがては俗世間の中へ解き放たれて変わってしまうだろう。
そのことを知っているからこそ、ホールデンは、フィービーの持つイノセンスにも傷ついていたのだ。
街の女の子たちを眺めながら「この女の子たちみんなに、これからどんなことが起るだろう」と考え、「いずれは大部分の者が馬鹿な男たちと結婚するにきまっている」と妄想して、自ら傷つくホールデンである。
フィービーの変化(成長)には、とても耐えられそうもない(そこに「喪失感」の予感がある)。
「アリイ、僕の姿を消さないでおくれ。アリイ、僕の姿を消さないでおくれ。アリイ、僕の姿を消さないでおくれ。おねがいだからね、アリイ」(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
弟(アリイ)が死んだとき、13歳だったホールデンは、ガレージの窓ガラスを、拳ですべて叩き壊してしまう。
変わることの恐怖が(失われてしまうことの恐怖が)、ホールデンを精神的に追いつめたのだ。
それでも、傷つきやすいホールデンの心を癒してくれるのも、やはり、フィービーの持つイノセンスだった。
土砂降りの中、回転木馬に乗っているフィービーを見て、ホールデンは幸福な気持ちになる。
だが僕は気にもかけなかった。僕は急にむやみに幸福な気持がしてきたんだ。フィービがくるくる廻っているのを眺めているとね。正直に言うと、大声を上げそうになるほど、むやみに幸福な気持がしてきたんだよ。なぜだか知らないがね。(J.D.サリンガー「危険な年齢」橋本福夫・訳)
回転木馬は、フィービーの持つイノセンスの永続性を象徴したものだろう。
少なくとも、ホールデンは、フィービーを乗せて回り続ける回転木馬に、未来への希望を見たのだ。
だから、この物語は、喪失感を抱えた若者の、自分探しの物語として読むことができる。
答えは見つからないまでも生きるヒントはある、的な。
戦場でトラウマを抱えた元アメリカ兵も、現代社会を生きる若者たちも、それぞれの喪失感を抱えて生きていた。
本作『危険な年齢』は、そんな我々に、未来への希望を与えてくれる物語だったのだ。
今、橋本福夫・訳の『危険な年齢』を読むことは難しい。
しかし、『キャッチャー』の持つ時代背景を考えたとき、『危険な年齢』は失われてしまうには惜しい翻訳作品だと思う。
「翻訳には賞味期限がある」と、村上春樹は言った。
だからこそ、古い翻訳には、その時代にしか表現することのできない空気感が反映されているのではないだろうか。
書名:危険な年齢
著者:J.D.サリンガー
訳者:橋本福夫
発行:1952/12/20
出版社:ダヴィッド社