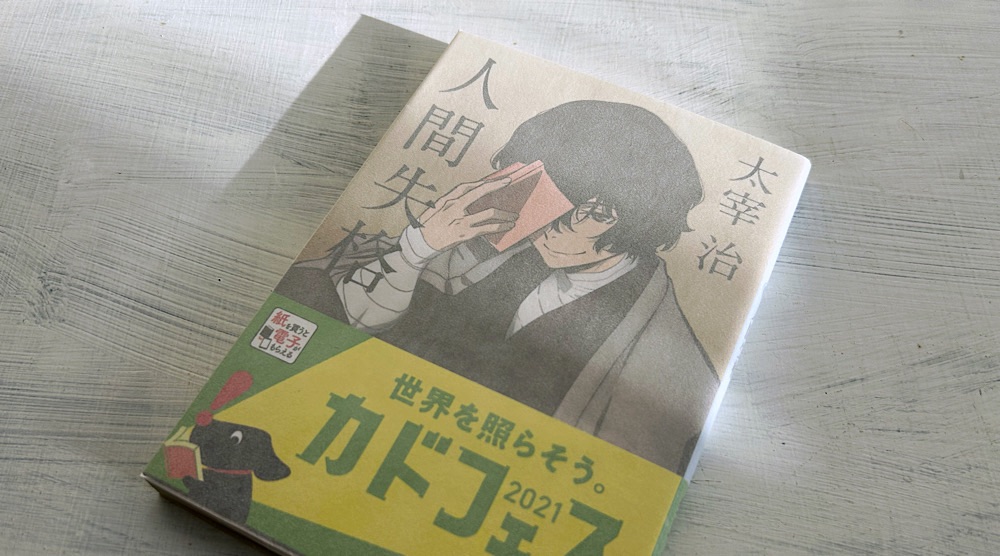太宰治「人間失格」読了。
本作「人間失格」は、1948年(昭和23年)6月から8月まで『展望』に連載された長編小説である。
著者の太宰治は、この年の6月13日に入水自殺(39歳だった)。
単行本は、1948年(昭和23年)7月、筑摩書房から刊行されている。
「人間失格」というタイトルの意味
太宰治の『人間失格』は、「人間失格」というタイトルがいい。
漢字四文字でインパクトを与えるし、しかも分かりやすい。
キャッチフレーズの得意だった太宰の中でも、とりわけ出来の良いキャッチフレーズ。
ところが、どうして、この小説が「人間失格」なのか?という、作品タイトルの意味になると、突然に難しくなってくる。
本作『人間失格』は、酒と女に溺れたクズな男が、自殺未遂を繰り返した挙句に麻薬中毒となり、最後には精神病院へ強制入院させられてしまうという、ストーリーとしては、全然分かりやすい物語である。
ただし、「クズな男だから人間失格だ」とか、「精神病院へ入院したから人間失格だ」とか、そういうシンプルな解釈をすると、どうにも落ち着かない。
そんなことを言えば、「人間に失格している人間」なんて、世の中にいくらでもいるということになる。
問題は、「人間に合格する」とはどういうことで、「人間に失格する」とはどういうことなのか。
そこに、この物語のテーマが込められている。
主人公<大庭葉蔵>は、人間が嫌いだった。
人間が嫌いというよりも、人間を恐れていたのだ。
自分は、実は、ひとりでは、電車に乗ると車掌がおそろしく、歌舞伎座へはいりたくても、あの正面玄関の緋の絨緞が敷かれてある階段の両側に並んで立っている案内嬢たちがおそろしく、レストランへはいると、自分の背後にひっそり立って、皿のあくのを待っている給仕のボーイがおそろしく、殊にも勘定を払う時、ああ、ぎごちない自分の手つき、自分は買い物をしてお金を手渡す時には、吝嗇ゆえでなく、あまりの緊張、あまりの恥ずかしさ、あまりの不安、恐怖に、くらくら目まいして、世界が真暗になり、ほとんど半狂乱の気持になってしまって、、、(以下略)(太宰治「人間失格」)
人間恐怖症。
人間恐怖症の人間が生きる道は二つあって、一つは、人間との交流を一切断絶してしまうこと。
もう一つは、自分をごまかしながら、なんとか人間と交流をしていくことである。
人間との交流を断つことは、人間社会から弾き出されることを意味しているが、葉蔵は、人間社会から弾き出されることをも恐れている。
彼が選んだ道は、自分を偽りながら「道化者」として生きていくことだった。
自分に嘘を生き続けて生きる、そんな彼の仮面を見破った者は、過去に二人あった。
学校時代の同級生<竹一>と、心中事件を起こしたときに自分を取り調べた<検事>の二人である。
このとき、彼は我を忘れてパニックになる。
「ほんとうかい?」ものしずかな微笑でした。冷汗三斗、いいえ、いま思い出しても、きりきり舞いをしたくなります。中学時代に、あの馬鹿の竹一から、ワザ、ワザ、と言われて背中を突かれ、地獄に蹴落とされた、その時の思い以上と言っても、決して過言では無い気持です。あれと、これと、二つ、自分の生涯に於ける演技の大失敗の記録です。(太宰治「人間失格」)
仮面は、要蔵にとって、人間社会で生きるための生命線だったから、嘘を見破られることは、人間社会で生きていく資格を失うことになる
これが「人間失格」だ。
結局、要蔵は、人間社会で生きていくために自分を偽って世の中を欺きながら、最後にはすべてが破綻して、精神病院に入院させられてしまう。
おそらく、太宰治には、何が「人間の合格」で、何が「人間の失格」なのかという、根本的な疑問があったに違いない。
言い換えると「生きるってことの正解は何か?」ということである。
世の中と自分の価値観とのズレを感じながら、太宰治もやはりまた「生きにくさ」を抱えた作家だったのかもしれない。
小説「人間失格」が伝えたかったこと
太宰治の『人間失格』は、非常に人気のある文学作品だけれど、決して楽しい物語ではない。
むしろ、読み終えた後に自己嫌悪感を覚えて塞いでしまうことさえあるくらいだ。
それでも、この小説は、強い人気を保ち続けている。
なぜか?
それは、主人公・要蔵に共感する気持ち、「人間失格になりたくないという気持ち」を、誰もが持ち続けているからだろう。
本作「人間失格」は、「人間に失格したくない」と脅え続ける男の物語である。
(それは世間が、ゆるさない)(世間じゃない。あなたが、ゆるさないのでしょう?)(そんな事をすると、世間からひどいめに逢うぞ)(世間じゃない。あなたでしょう?)(いまに世間から葬られる)(世間じゃない。葬むるのは、あなたでしょう?)(太宰治「人間失格」)
要蔵が恐怖していた人間とは「世間(社会)」のことであり、「人間失格」とは、人間社会から締め出されてしまうことである。
もしも、最初から隠遁者のような生活を送ってしまえば(つまり、最初から「人間失格」であれば)恐れるものは何もない。
かりそめにも「人間社会の中で、うまく生きていきたい」という希望を持つから、「人間に失格してしまう」ことを恐れてしまうのである。
ここに、大庭葉蔵(あるいは太宰治)という男の「生きにくさ」がある。
そして、そんな「生きにくさ」(社会と自分との違和感)を感じながら生きている人は、世の中にきっと、他にもたくさんいるはずだ。
結局、それは「繊細か鈍感か」とか「器用か不器用か」とかいう問題に収斂されていくような気がする。
「他人のことを気にせずに生きていけるマイペースな人(本作では<ヒラメ>とか<堀木>といった存在)は幸せだよね」というメッセージが、そこからは受け取ることができる。
そう考えると、本作が今もって人気の理由が分かるような気がする。
本作「人間失格」は、生きにくさを抱えて生きる繊細な人々に向けられた応援のメッセージだったのだ。
堀木のあの不思議な美しい微笑に自分は泣き、判断も抵抗も忘れて自動車に乗り、そうしてここに連れて来られて、狂人という事になりました。いまに、ここから出ても、自分はやっぱり狂人、いや、癈人という刻印を額に打たれる事でしょう。人間、失格。もはや、自分は、完全に、人間で無くなりました。(太宰治「人間失格」)
本作『人間失格』を書き終えて、太宰治は、山崎富栄とともに玉川上水で入水自殺してしまう。
だから、「この作品は遺書のようなものだ」と、長く伝えられ続けているけれど、もしかすると、太宰治はもっと生き続けたかったんじゃないだろうか。
「もはや、自分は、完全に、人間で無くなりました」とあるけれど、それは、人生の終わりを意味するものではない。
人間失格でも廃人でも何でもいいから、とにかくしぶとく生きてやる。
人間に失格した以上、怖いものなんて何もないぞ。
そんな呪いのような言葉が、この後には続いていくような気がするのだ。
恥の多い生涯を送って来ました──
恥、上等。
恥でも人間失格でも、とにかく生きていることが大切なんだから。
書名:人間失格
著者:太宰治
発行:2021/04/30 改版
出版社:角川文庫