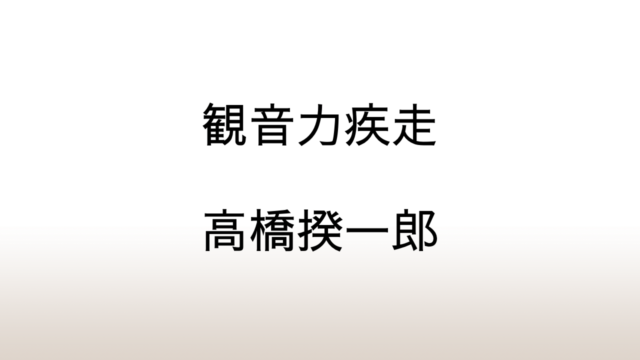アントン・チェーホフ「ワーニカ」読了。
本作「ワーニカ」は、1886年(明治19年)12月25日『ペテルブルグ新聞』の「降誕祭物語」欄に発表された短篇小説である。
この年、著者は26歳だった。
児童虐待からの救いを求める少年の叫び
本作「ワーニカ」は、トルストイから「一級作品」と絶賛されるとともに、チェーホフ存命中にヨーロッパ諸国で翻訳紹介された名作短篇である。
クリスマス・イブの夜、9歳の少年が、故郷の祖父に宛てて手紙を書いている。
「おじいちゃんに、お手がみをかきます。こうたん祭(クリスマス)おめでとうございます。おじいさまが、神さまからいいことをたくさん、たくさん、していただけるよう、お祈りします。ボクには、お父さんもお母さんもいない、おじいちゃん、たったひとりだけ」(アントン・チェーホフ「ワーニカ」児島宏子・訳)
両親を亡くしたワーニカは、9歳にして、モスクワにある靴職人の親方のところへ見習い奉公に出されていて、この靴屋でひどい虐待を受けていた。
靴職人一家が夜中のミサへ出かけた隙に、ワーニカはこっそりと救いを求める手紙をしたためていたのである。
「大すきなおじいちゃん、おねがいだから、ボクをうちにつれかえってください。村につれてって。ボクはもうがまんできない……おじいちゃん、おねがい、ほんとうにおねがい。神さまにずっとおいのりします。ボクをここからつれ出して、じゃないとしんじゃう……」(アントン・チェーホフ「ワーニカ」児島宏子・訳)
ワーニカは、書き上げた手紙を封筒に入れて、夜中のポストへ投函する。
もうすぐ、おじいちゃんが助けに来てくれると、ワーニカは安心して眠りにつくのだが、宛て先の住所もなく、切手も貼られていない手紙が、故郷のおじいちゃんのところへ届くことは、おそらく難しいだろう。
救いのない結末に愕然とするが、クリスマスの新聞に掲載されたこの物語そのものが、あるいは、子どもたちの悲痛な叫びを届ける、ひとつの手紙だったのかもしれない。
おじいちゃんなんてものが、本当には存在しなかったのだとしても、ワーニカの手紙は世界中へと届けられた。
そうでも考えないと、この物語は、本当に救いようのない物語ということになってしまう。
世界中にワーニカがいる
本作「ワーニカ」は、クリスマスに発表された、クリスマスのための短篇小説である。
クリスマス・シーズンが舞台になっているから、随所に出てくるクリスマスの描写が素晴らしい。
「なつかしいおじいちゃん、ご主人さまのところでプレゼントのついたヨールカ(クリスマスツリー)をかざったら、金色のクルミを取って、みどり色の長もちにかくしておいて。おじょうさまのオリガ・イグナーチエヴナに、ワーニカのためにってたのんでください」(アントン・チェーホフ「ワーニカ」児島宏子・訳)
ワーニカの中で思い出されるクリスマスの思い出は、楽しい思い出ばかりだ。
おじいさんと一緒にヨールカ(クリスマスツリー)のイェリ(トウヒ)の木を取りに、森へ行ったときのことや、多くの子どもたちで降誕祭に星を持って歩いたこと。
美しい思い出は、大人になった読者すべての思い出でもある。
地方から都会へ出て働いている大人たちは、この物語のクリスマスの描写に、大きな共感を覚えたに違いない。
そして、懐かしい故郷のクリスマスとは対照的に、ひどい虐待を受けているモスクワのクリスマス。
クリスマス・イブの夜に救いの手紙を綴っている少年の姿は切なくて、なんとかしてあげたいと多くの読者は考えるが、著者のチェーホフはハッピーエンドを用意していない。
なぜなら、少年ワーニカを救うことができるのは、作家その人ではなく、この物語を読んでいるすべての読者だったからだ。
物語の中で少年を救っても、現実に苦しんでいる子どもたちにとっては、何らの解決策にもならない。
この物語からは、偽善的なクリスマス物語に対する強い怒りを感じるし、すべての児童虐待を放置している現代社会に対する無言の抗議の声を聴くこともできる。
真っ暗な夜というのに、白い屋根や煙突からたなびく煙も、きらめく銀色の樹氷や雪のふきだまりもふくめ、村全体が一望に見渡せます。ハミングしてきらめく無数の星が空一杯にちりばめられ、天の川は、祭りの前に雪でみがいて洗われたよう……。(アントン・チェーホフ「ワーニカ」児島宏子・訳)
そして、この物語は、決して昔の物語ではない。
子どもたちを巡る問題は、いつの時代にも、大人たちに与えられた大きな課題であり続けるからだ。
ただ、少なくとも、こういう物語が忘れられないうちは、世界もまだまだ捨てたもんじゃないなとは思う。
現代のワーニカの叫びを、我々は聞き漏らしてはいないだろうか。
書名:ワーニカ
著者:アントン・チェーホフ
訳者:児島宏子
発行:2012/02/15
出版社:未知谷