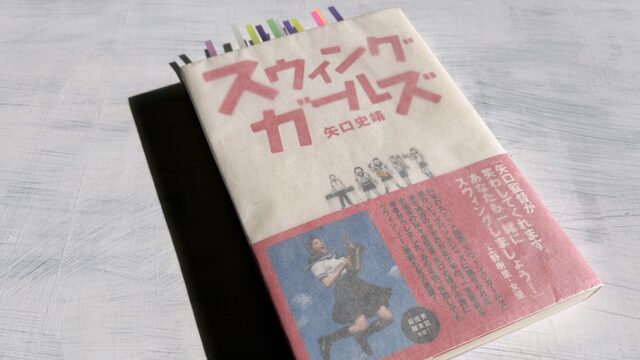佐藤春夫「詩文半世紀」読了。
本作「詩文半世紀」は、1963年(昭和38年)8月に読売新聞社から刊行された回想録である。
この年、著者は71歳だった(昭和39年5月、72歳で死亡)。
話すような言葉で書かれた自叙伝
本書で「詩文半世紀」とともに併録されている「うぬぼれかがみ」の終わりに、次のような言葉がある。
僕はどう見えてもよい。僕は見えのために生きて来たのではなかった。僕自身のために生きて生涯七十年を歌い暮したのしい人生を語りつづけた。僕には書きさえすれば憂鬱でさえも十分に楽しいものであった。(佐藤春夫「うぬぼれかがみ」)
本書『詩文半世紀』では、そんな<楽しい人生>が、<しゃべるように書かれた文体>で綴られている。
人生の総決算という意図を有していたのか、時に感情的に、歯に衣を着せない言葉で文壇を総括している。
例えば「うぬぼれかがみ」では、自作に批判的な論評を発表していた中村光男に対して、攻撃的な言葉で反論している。
僕が感情的になるのは当然ではないだろうか。君は最初から僕に対して悪意を持って対していたのである。それを生憎と僕はすぐ感じた。第三者には君の隠し持った匕首が見えなかったらしい。そうして僕が先に感情的になったと思っているらしい。(佐藤春夫「うぬぼれかがみ」)
この「うぬぼれかがみ」は、中村光男に反論する形で、自作の創作過程を詳細に振り返っているから、作品理解を深める上でも参考となる随想文である。
感情的であるのは、中村光男に対してだけではなくて、師と慕った永井荷風に対する舌鋒も興味深いものがある。
仲違いの原因は、佐藤春夫が監修した『永井荷風読本』の印税の半分を、佐藤春夫が持っていってしまったことにあったらしい。
こう考えて来ると、彼に憎まれるということはかつて一度愛されたということの証拠みたいでさえある。彼は後輩が一人前となって世に通用することに対して、妙な嫉みを持つ人でもあった。(佐藤春夫「詩文半世紀」)
荷風は『永井荷風読本』の印税を独り占めできると思っていたところ、思わず弟子の佐藤春夫との折半になってしまったので、そこに不服があったのかもしれない。
身近に暮らした弟子だからこそ綴ることのできる、文壇のちょっとした内幕だろう。
門弟三千──多くの仲間たちに囲まれた文学人生
本作『詩文半世紀』では、佐藤春夫の人生を振り返る形で、日本の近代文学の歴史をも振り返っている。
近代文学論的な考察は、確かに参考となるものだが、ゴシップ好きとしては、文壇の些細な内輪ネタみたいなものの方が楽しい。
そのころ東郷青児は今東光と友人で、わたくしも今東光とは知り合いであったため、自然東郷とも知り合ったが、今、東郷のこの両才人はかげでは互いに「奴はゆだんのならない大悪党ですよ」と言い合いながら、共犯のように仲良くしていたものであった。(佐藤春夫「詩文半世紀」)
東郷青児や今東光に関する記述は、ほんのわずかにしても、見逃せないものがある。
室生犀星とは、彼が仲間内から「室生のダラ」(あほんだら)と呼ばれていた頃からの、古い知り合いだった。
犀星の文学は教養などでできたものではなく、直接に人生そのものから汲み取って成ったもので、そこに彼の文学は独特の味があるのではないか。(佐藤春夫「詩文半世紀」)
作中、佐藤春夫は、室生犀星と生田春月という二人の友人を並べて回想しているが、文学的教養のあった春月よりも、人生で多くを学んだ犀星の方に惹かれていたらしい。
石川啄木については、ほとんど記憶がないらしく、「啄木は天才的な詩人ではなく、むしろ目先の利いた鋭い批評家」などの言葉があるくらいである。
佐藤春夫が芥川龍之介の友人であったことは有名な話で、芥川の死後、菊池寛が芥川龍之介賞を創設したとき、芥川の友人であった佐藤春夫も、選考委員の一人として名前を連ねている。
芥川竜之介はある時ある人に「フランス語を知らず、音楽を解しないのは、佐藤にとって気の毒だなあ」と語ったと伝聞した──芥川はわれわれ野人と違ってそんなことは決して直言しない人であったが。(佐藤春夫「詩文半世紀」)
芥川賞の選考委員となったことで、佐藤春夫は太宰治から絡まれることになるのだが、本書において太宰治の話はまったく登場しない。
三田塾の恩師だった馬場孤蝶の最期に触れた話は胸を打つ。
この達人は、遺言らしいことをはっきり、りっぱに言った。それでも辞去しようとすると「いつまでもそばにいてもらいたい気もするが」と、さすがに声をうるませたのは悲しかった。(佐藤春夫「詩文半世紀」)
このとき、見舞いに同席していたのは、三田塾で同期生だった詩人の堀口大学だった。
さすがに、文壇の中枢で半世紀も活躍してきた文人の回想録は、隅々まで内容が濃い。
中でも印象に残ったのは「坂ありて旧居跡なし春の雪」の句を詠んだときのエピソードだ。
「都会の憂鬱」の舞台となった幽霊坂の暮らしは、「生涯で一番わびしくみじめであった」が、「わが人生の旅の宿で、思い出して一番なつかしいような気がする」ものでもあった。
一度曲がり角を間違えそうになってすぐ気がつき、幽霊坂の土地は見つけたが、家は全く跡形もなく、そこは近代風なビルになっていたのを注意してみると、思いきや、このビルは角川書店であった。(佐藤春夫「詩文半世紀」)
このとき詠んだ俳句が「来てみれば旧居跡なし春の雪」で、後に「坂ありて旧居跡なし春の雪」と推敲された。
細い道で自動車の切り返しに苦労する運転手に「僕の生涯もここでこの程度に行きなやんでいたものでしたよ」と語りかける場面がいい。
多くの名言が並ぶ本書にあって、最も心に残る言葉だったかもしれない。
つまり、人生には、行き悩むときというものが、誰しもあるということなのだ。
それが、どのように素晴らしい功績を残した文豪の人生であったとしても。
書名:詩文半世紀
著者:佐藤春夫
発行:1963/08/20
出版社:読売新聞社