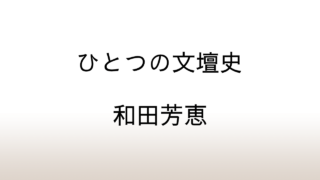庄野潤三の随筆集を読む。
それは、心の日向ぼっこをしているように温かい読書だ。
日常の些事に疲れた心の緊張が、少しずつ解けていくのが分かる。
あるいは、それを、心の日光浴と呼ぶのかもしれない。
庄野潤三とエッセイの関係
庄野潤三は多くの随筆集を残した小説家である。
まるで随筆のような小説を書く人だったから、小説と同じように随筆を書くことも好きだったのだろう。
庄野さんの随筆を語る上で、忘れてはいけない人が二人いる。
一人は、名作『エリア随筆』を遺したイギリスのエッセイスト、チャールズ・ラムである。
庄野文学の源泉とも言えるチャールズ・ラムのことは、庄野さんの作品の中で繰り返し触れられている。
おそらく、庄野文学にとって、小説か随筆かというジャンル分けは、あまり意味のないものだった。
長いものが小説で、短いものが随筆。
日常生活を題材とする庄野さんは、そのくらいの感覚で文章を書いていたのではないだろうか。
そういう意味で、庄野さんの作家スタイルは、師と慕った井伏鱒二と似ているかもしれない。
庄野さんの随筆に大きな影響を与えたもう一人は、英文学者かつエッセイストとして名を馳せた福原麟太郎である。
アメリカ・ガンビア州にあるケニオン・カレッジへの留学体験を『ガンビア滞在記』にまとめた庄野さんは、福原麟太郎にもこの著作を贈った。
これを福原さんが絶賛したところから、年齢の離れた二人の交流が始まる。
福原麟太郎のエッセイを、庄野さんは、こよなく愛していたことは、これも、随筆を始めとする庄野さんの著作の中で、繰り返し語られているところである。
イギリス・エッセイを敬愛する福原麟太郎のエッセイに、庄野さんは自身の源泉を見たような気持ちになったのかもしれない。
庄野さんの随筆を読んでいると、チャールズ・ラムと福原麟太郎の二人が、庄野さんにとっていかに特別な存在であったかということが分かる。
そして、日英二人の高名なエッセイストの後に続くように、多くの随筆を書き続けたのが、庄野潤三という作家だった。
庄野さんには、全部で9冊の随筆集がある。
『自分の羽根』(1968)、『クロッカスの花』(1970)、『庭の山の木』(1973)、『イソップとひよどり』(1976)、『御代の稲妻』(1979)、『ぎぼしの花』(1985)、『誕生日のラムケーキ』(1991)、『散歩道から』(1995)、『野菜讃歌』(1998)、『孫の結婚式』(2002)の9冊である。
これに「自選随筆集」だった『子供の盗賊』(1984)を加えると、庄野さんには全部で10冊の随筆集があることになる。
庄野さんの随筆集は、最初に日常の報告があり、次に文学に関するものがあり、最後に交流のあった人たちの話がある。
大体、そんな構成になっている。
あるいは、チャールズ・ラムと福原麟太郎の伝説のように、古い随筆集から新しい随筆集まで、繰り返し語られる物語がある。
庄野さんは、流行に流されない作家だった。
庄野潤三の全随筆集解説
以下、簡単に、それぞれの随筆集のポイントを紹介しておこう。
自分の羽根(1968)
1968年(昭和43年)に講談社から刊行された第一随筆集。
この年、庄野さんは47歳だった。
既に代表作『夕べの雲』(1965)を発表しており、小説家としてのスタイルを確立しつつある時期だった。
本作『自分の羽根』には、デビュー直後から雑誌や新聞などに発表した随筆が収録されている。
あとがきに「はじめの方の『たつたの川』で小学三年生であった私の長女が、この随筆集の校正刷が出る少し前に、成人式を迎えた」とある。
当時から既に、庄野さんの作品は、子どもたちの成長を一つの基点として語られていたのだ。
私は短い文章を読むのが好きで、短ければ短いほど気に入るという性質がある。それで、この本にも出来るだけ枚数の短いものを拾い上げるようにした。おが屑みたいなものがまじっているが、お許し頂きたい。(庄野潤三「自分の羽根」あとがき)
この随筆集には、庄野文学を語る上で重要な表題作「自分の羽根」がある。
私は自分の経験したことだけを書きたいと思う。徹底的にそうしたいと考える。但し、この経験は直接私がしたことだけを指すのではなく、人から聞いたことでも、何かで読んだことでも、それが私の生活感情に強くふれ、自分にとって痛切に感じられることは、私の経験の中に含める。(庄野潤三「自分の羽根」)
小学五年生の長女と羽根つきをやりながら、庄野さんは「私は自分の前に飛んで来る羽根だけを打ち返したい」と考える。
この随筆で表明された庄野文学のスタイルは、生涯徹底された。
▶『自分の羽根』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
クロッカスの花(1970)
1970年(昭和45年)に冬樹社から刊行された第二随筆集。
この年、庄野さんは49歳だった。
『紺野機業場』により芸術選奨を受賞したのも、同じ1970年(昭和45年)のことである。
あとがきに「求められて、何か書きとめておく。もしその時、書きとめておかなかったら、一生のうち、二度とそういう機会は来ないかもしれない」とある。
名作中篇「絵合せ」が『群像』に発表されるのが、1970年(昭和45年)12月のこと。
明らかに、庄野さんは「書きとめておかなかったら、一生のうち、二度とそういう機会は来ないかもしれない」ものを、意識していたのだろう。
『夕べの雲』の家族が随所に登場するこの随筆集は、庄野家の一番いい時期をスケッチしていたのかもしれない。
「父のいびき」のようにわずか四行(センテンスで3つ)という短いものもあれば、「豆腐屋」のように、この時期の短編集に収録されていてもおかしくない作品もある。
毎日、同じような生活をしていると、今日は昨日と大体のところで変りはなかったように、明日も今日と大体のところで変りはないという風に考える。それでも、何かしら、思いがけないいいことがあるかもしれない。ちょっとしたことでも、いいことがあると嬉しい。何といってもそれは思いがけないことであるから、不意うちのよろこびがある。(庄野潤三「日常生活の旅」)
何気ない日常を描き続けた庄野さんらしさが、この随筆集の中にもある。
▶『クロッカスの花』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
庭の山の木(1973)
1973年(昭和48年)5月に冬樹社から刊行された第三随筆集。
この年、庄野さんは52歳だった。
庄野文学の歴史としては、『絵合せ』(1971)や『明夫と良二』(1972)など、長女が結婚して家を出ていく時期の様子を描いた名作が次々と発表され、文学賞を受賞していた充実期にあたる。
作家としての業績により日本芸術院賞を受賞するのも、1973年(昭和48年)。
アンコウという魚は海底で眠ったようにしていて、頭の真上に小魚が来た時だけ、大きく口を開いて吸い込むそうだが、私はどちらかというとアンコウ的な作家の方が好きである。(庄野潤三「私の取材法」)
「アンコウ的な作家」とあるのは、「自分の前に飛んできた羽根だけを打ち返す作家」ということと同じ意味だろう。
「子供の本と私」の中の「変らない景色というものはない。いつまでも、身のまわりの世界が同じであるということは、あり得ない」というフレーズは、多くの作品に通底する「庄野哲学」を感じさせる。
子供の本を書いてみたいという気持と、五、六年前に私が味わった、そのうちに消えて無くなる筈の、男の子の黄色い帽子を名残惜しく思った気持との間に、もしかすると何かつながりがあるのかも知れない。(庄野潤三「子供の本と私」)
古い家族アルバムの写真を眺めるような懐かしさが、庄野さんの随筆にはある。
▶『庭の山の木』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
イソップとひよどり(1976)
1976年(昭和51年)6月に冬樹社から刊行された第四随筆集。
この年、庄野さんは55歳だった。
文藝春秋から『鍛冶屋の馬』を刊行したのも、同じく1976年(昭和51年)のことである。
「日を重ねて」に「私の家族が川崎市の北部、いまは多摩区の生田へ来てから、十四年目になる」とある。
庄野さんの起点は、常に生田で暮らし始めたときからであり、生田での暮らしを指折り数えながら前へと進むのが、庄野さんという作家の生涯変わらぬ姿勢だった。
私たちは、越して来た最初からこの生田という土地が気に入っていた。それで、三年たてば三年たったでよろこび、五年たてば五年たったでよろこび、このようにして、自分たちが住みついた年の数を数える度に、次第にこの地に根づいてゆくことを祝福したのであった。(庄野潤三「日を重ねて」)
「生田小学校の金木犀」は「多摩丘陵のひとつである生田の丘へ越して来てから、十五年になる」という一文から始まる。
庄野文学は、まさしく「生田文学」とでも呼ぶべきものであった。
▶『イソップとひよどり』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
御代の稲妻(1979)
1979年(昭和54年)4月に講談社から刊行された第五随筆集。
この年から、庄野さんの随筆集は講談社が担当することになる(最後まで変わらなかった)。
この年、庄野さんは57歳だった。
『引潮』(1977)や『水の都』(1978)など、力のこもった逞しい仕事をこなしていた時期である。
この年12月、芸術院会員となった。
あとがきに「目次を作っていて、ラムやチェーホフ、伊東静雄がどこかに入っているのが分ると、たとえほんの僅かな分量のものであっても心賑やかになる」とあるのは、処女随筆集『自分の羽根』から、庄野さんのスタンスが変わっていない証拠だ。
かつて、3人の子どもたちが主役だった日常は、長女の孫が主役へと変わりつつある。
表題ともなっている「御代の稲妻」とは、朝顔の種類の名前のことで、花に稲妻のような白い筋が入るらしいが、庄野家の「御代の稲妻」には、白い筋がなかった。
「稲妻なしの御代だけ」だったらしい。
「エリア随筆──本との出会い」に、庄野さんらしい文章がある。
「私は生れつき、新規なことには臆病なのである」(戸川秋骨訳・岩波文庫)。これは「除夜」のはじめの方に出て来る言葉だが、ラムがこんなふうにいうと、頼もしく聞える。有力な味方を得たような心持になる。(庄野潤三「エリア随筆──本との出会い」)
庄野さんにとって、チャールズ・ラムは、福原麟太郎の思い出へとつながる架け橋のような存在でもあった。
▶『御代の稲妻』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
ぎぼしの花(1985)
1985年(昭和60年)4月に講談社から刊行された第六随筆集。
この年、庄野さんは64歳だった。
前作『御代の稲妻』まで外函に入っていた本が、この『ぎぼしの花』から外函なしになっている。
この年の11月、庄野さんは脳内出血で入院(闘病記『世をへだてて』に詳しい)しているから、本作『ぎぼしの花』には、病気で倒れる以前の随筆が収録されていることになる。
『御代の稲妻』を出して貰ったのが昭和五十四年四月で、今度の『ぎぼしの花』までに六年たったことになる。この間、文芸雑誌の仕事をいつも何かしら抱えていて、ほかの原稿を書く機会がどうしても少なくなりがちであったためだが、随筆、短文という文学の形式に対する尊重、親愛の念は変らない。(庄野潤三「ぎぼしの花」あとがき)
「随筆、短文という文学の形式に対する尊重、親愛の念は変らない」というところが庄野さんらしい。
当時、庄野さんは、『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』(1984)や『サヴォイ・オペラ』(1986)などの大作に、集中的に取り組んでいる時期であった。
1972年(昭和47年)に刊行された『明夫と良二』を回想した文章がいい。
空想の世界を外に求めるかわりに、ふだんの通りの生活の中に、私たちをよろばせ、楽しませてくれるような何かが、見つかりはしないだろうか。いつでも身のまわりにあるために、ついその面白みに気が附かないでいることはないだろうか。もしそういうものがあるとすれば、できるだけ詳しく書きとめてみたい。日常の詩にふれたい。これが作者の願いです。(庄野潤三「『明夫と良二』」)
「日常の詩にふれたい」とあるのは、庄野文学に通底する「作者の願い」だろう。
出典に「岩波文庫版『明夫と良二』」とあるのは、「岩波少年文庫版『明夫と良二』」の誤りである。
▶『ぎぼしの花』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
誕生日のラムケーキ(1991)
1991年(平成3年)4月に講談社から刊行された第七随筆集。
この年、庄野さんは70歳だった。
大病から復帰後は、『インド綿の服』(1988)や『エイヴォン記』(1989)など、後期の家族物へと執筆の軸足が移されている。
「途中、一度躓きはしたけれども、幸いに健康に恵まれて、仕事を続けることが出来て、新しい随筆集を出せるようになって嬉しい」とあとがきにあるのが、当時の庄野さんの偽らざる心境だったのだろう。
冒頭の「おるす番」と「たき火」で、<三歳になる孫娘>として<フーちゃん>が登場しているから、夫婦の晩年シリーズで庄野文学のファンになったという人は、随筆集では、この『誕生日のラムケーキ』から読み始めるといいかもしれない。
「長女の宅急便」や「誕生日のラムケーキ」「大きな犬」など、夫婦の晩年シリーズの落穂拾い的な作品が、この頃から目立つようになる。
福原麟太郎を偲んだ「童心」と「文章の力」がいい。
福原さんがイギリスの文学についてお書きになる。それを読むと、イギリスのその作者も作中人物も俄に身近な、親しい存在になるから不思議だ。何しろ福原さんが興味を持っておられることが分かっただけで、これは面白そうだと思ってしまう。そうして、もっと詳しくそれについて知りたくなる。大それたことといわねばならない。(庄野潤三「文章の力」)
福原麟太郎が亡くなったのは、1981年(昭和56年)1月18日のことである。
この随筆「文章の力」は、『福原麟太郎自選随想集・野方閑居の記』(1988年復刊版)の栞に掲載された。
▶『誕生日のラムケーキ』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
散歩道から(1995)
1995年(平成7年)9月に講談社から刊行された第八随筆集。
この年、庄野さんは74歳だった。
中学の同期生の会報に載せた近況のように短いものも含めるようになったが、私はもともと短く書かれた文章を読むのが好きなので、こんなふうになった、ここに収められた中でも、例えば「有美ちゃんのおみやげ」のように短い随筆が、書名にとり上げたかったほど気に入っている。(庄野潤三「散歩道から」あとがき)
短い作品が好きだという庄野さんの姿勢は、第一随筆集『自分の羽根』のときから変わっていない。
「じいたんのハーモニカ」「ミッキーマウス・マーチ」「梅見のお弁当」「孫娘の学習机」など、本編とリンクするような作品がたくさん入っているのも楽しい。
この時期、庄野さんは、夫婦の晩年シリーズ最初の作品となる長編「貝がらと海の音」を『新潮45』に連載していたから、いよいよ本編と随筆が繋がり始めたのだろう。
「旅さきの井伏さん」「井伏さんを偲ぶ」「井伏さんの本」など、井伏鱒二を偲ぶ随筆が並んでいる。
敬愛する井伏鱒二が亡くなったのは、1993年(平成5年)7月10日の午前11時40分。
95歳の大往生だった。
▶『散歩道から』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
野菜讃歌(1998)
1998年(平成10年)10月に講談社から刊行された第九随筆集。
この年、庄野さんは77歳だった。
庄野文学の晩年を象徴する「夫婦の晩年シリーズ」は、『貝がらと海の音』(1996)、『ピアノの音』(1997)、『せきれい』(1998)と、既に著作を重ねていた。
本書にも「うさぎのミミリー」のように、後の単行本タイトルとなるような随筆が収録されている。
この「お祝いの絨毯」の委員長格の長女は、はじめて「群像」に載った「舞踏」のなかでは、頼りないお父さんに「ちょうちょ、とってえ」とせがむ三歳の女の子であったことに今、気が附いた。(庄野潤三「お祝いの絨毯の話──『ピアノの音』」)
庄野文学は、まさしく時間の積み重ねによって生まれた地層のような文学世界だと思う。
掘り返したところには、必ず、過去の作品に描かれた家族の姿があるのだ。
本書で特筆すべきは、日本経済新聞に連載された「私の履歴書」が収録されていることだろう。
小沼丹を偲ぶ「小沼とのつきあい」も切ない。
庄野さんにとって生涯の盟友だった小沼丹が亡くなったのは、 1996年(平成8年)11月8日のこと。
かねて病気療養中で、訃報を知らせてくれたのは、同じく旧友の吉岡達夫だった。
庄野さんの長篇小説『つむぎ唄』に登場する三人の中年男性は、庄野潤三・小沼丹・吉岡達夫の三人がモデルになっていたという。
▶『野菜讃歌』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
孫の結婚式(2002)
2002年(平成14年)9月に講談社から刊行された第十随筆集。
庄野さんにとって、最後の随筆集である。
この年、庄野さんは81歳だった。
『庭のつるばら』(1999)、『鳥の水浴び』(2000)、『山田さんの鈴虫』(2001)、『うさぎのミミリー』(2002)と連載が続いており、「随筆の切抜きがたまらなかった」と、庄野さんはあとがきに綴っている。
この年も『庭の小さなばら』(2003)を『群像』に連載中で、いわゆる「静かな庄野潤三ブーム」の時代だった。
夫婦の晩年シリーズの連載は、この後も、『メジロの来る庭』(2004)、『けい子ちゃんのゆかた』(2005)、『星に願いを』(2006)と続いていく。
表題作「孫の結婚式」は、<足柄の長女の次男の良雄の結婚式>のことを綴ったもので、孫娘のフーちゃんは、この時、中学一年生になっていた。
孫の結婚式に出席するのは、これが二度目だが、若い二人の晴姿を見るのは悪くない。私には三人の子供と八人の孫がいる。これから何人の孫の結婚式に招かれて出席することができるだろう?(庄野潤三「孫の結婚式」)
最初の結婚式は、長女の長男・和雄と聡子ちゃんとの結婚式だった。
「夕食まで」や「私の週刊食卓日記」など、日常の食べ物の話が多いのは、静かなブームを支えている読者のニーズに応えてのものだったのだろう。
私の家は多摩丘陵のひとつの生田の丘の上にあります。丘の上で風当たりが強いものですから、風よけの木をいっぱい植えたのが大きくなり、四十年たった今では、植木溜のような庭になりました。(庄野潤三「『うさぎのミミリー』のこと」)
生田の丘における庄野家の歴史も、とうとう四十年になってしまったが、この短い随筆「『うさぎのミミリー』のこと」は、「新潮社テレフォンサービス『著者は語る』」の原稿だったものらしい。
庄野さんの声を聴くことができる貴重な機会だったわけで、録音データが残っているなら、ぜひ聴いてみたいものだと思う。
本書の巻末には、江國香織との対談「静かな日々」が収録されている。
▶『孫の結婚式』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
子供の盗賊(1984)
おまけとして『子供の盗賊』についても触れておく。
本作『子供の盗賊』は、1984年(昭和59年)12月に牧羊社から刊行された自選随筆集である。
この年、庄野さんは63歳だった。
四十何年前、学校にいた時分に初めて読んだ『エリア随筆』の作者チャールズ・ラムとその姉メアリイの暮しぶりを二人が生れ育った街にあって偲ぶロンドン十日の旅──『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』(文藝春秋)を書き終り、次の仕事はどうしたものかと思案している時、文筆生活に入った最初の頃からの友人で昭和三十五年には作品集『静物』を担当してくれた牧羊社の川島勝さんからラムのことを書いたこの機会に自選随筆集を作ってみませんかという誘いを受けた。(庄野潤三「子供の盗賊」あとがき)
つまり、本作『子供の盗賊』は、庄野さんにとっての『エリア随筆』だったわけだ。
題名の「子供の盗賊」では小学三年生であった私の長女が、「一枚のレコード」まで来ると縁先で子供を遊ばせながら洗濯をする母親になっている。(庄野潤三「子供の盗賊」あとがき)
時間の経過を測る物差しは、ここでもやはり長女の成長だった。
庄野さんお気に入りの随筆だけが(それも初期のものが)精選されているので、これから庄野さんの古い随筆集を読んでみたいという方に、最初の一冊としておすすめ。
表題作「子供の盗賊」は、小学三年生だった長女の学校へ、学芸会を観に行ったときの話を綴ったものである。
▶『子供の盗賊』を今すぐ読む(文庫/Kindle/Audible)
まとめ
以上、庄野潤三の随筆集計10冊(9冊+1冊)について、簡単にご紹介した。
要約すると、『ぎぼしの花』までの前期と、『誕生日のラムケーキ』以降の後期とに分けて考えることができるが、前期と後期を区分しているのは、1985年に入院した庄野さんの大病だ。
病気をした後の庄野さんは、晩年の家族ものに取り組むようになるから、「静かなブーム」の庄野潤三が好きな人は、後期の作品から読んでいくと入りやすいだろう。
自分としては『クロッカスの花』や『庭の山の木』あたりがお気に入りだが、これは小説作品でいうと『絵合せ』や『明夫と良二』の頃の五人家族物語が好きだという個人的な理由によるものである。
僕の読書ライフは、庄野さんの影響によるところが極めて大きかった。
庄野さんの随筆に出てくる本は、ほとんど自分でも読んでしまったし、それも、できるだけ庄野さんが読んだものと同じ本で読むように心がけた。
庄野さんのお気に入りだった本を集めるのは、僕の古本蒐集の一つのテーマとなっている。
▶ 庄野潤三について詳しく知りたい方は「完全ガイド」をご覧ください