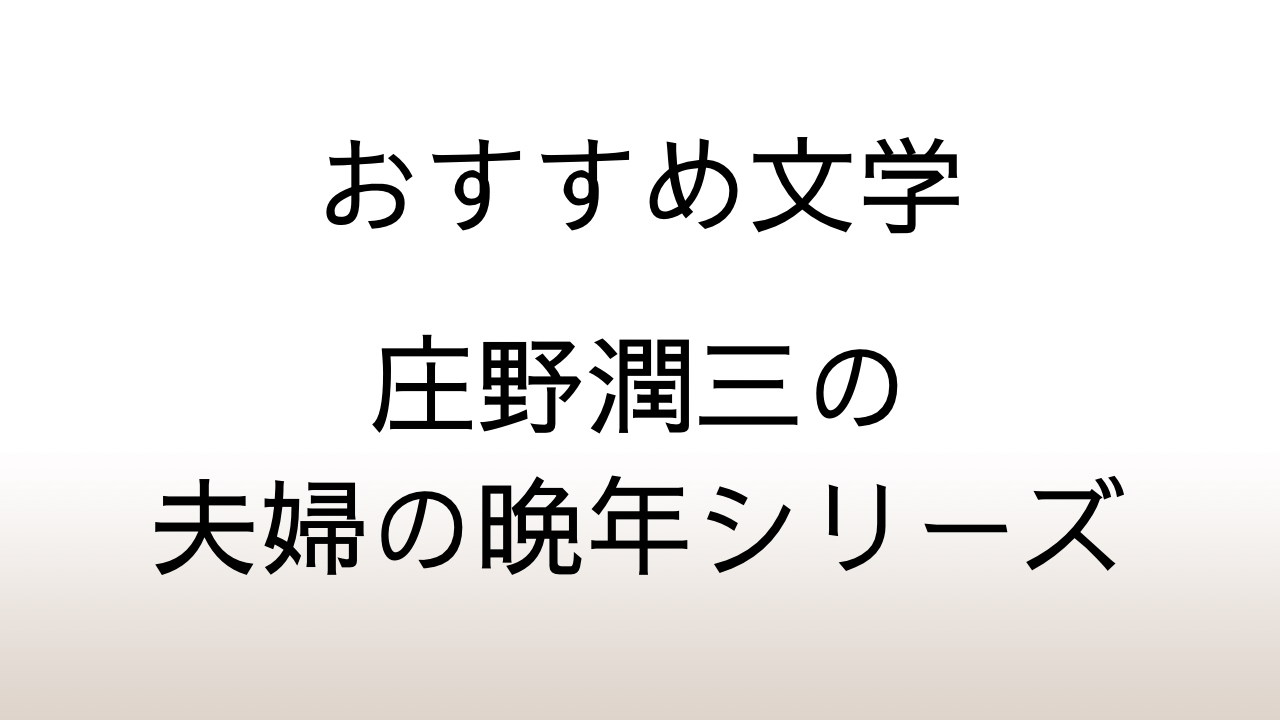まだ『アンアン』の増刊号だった『クウネル』(2002年11月15日)に、庄野潤三のインタビューが掲載されている。
「夫婦の日常の風景を、端的な言葉で綴った小説『うさぎのミミリー』が、若い女性たちの間で、静かな人気を呼んでいる」とあるように、庄野潤三の小説は当時、若い女性の間でちょっとしたブームとなっていた。

ここで紹介されている『うさぎのミミリー』は、『貝がらと海の音』から続くシリーズの最新作(第7作目)で、最終的に、このシリーズは2006年の『星に願いを』まで、通算10年間、計11作品を刊行するまで続くことになる。
著者本人の言葉によると、このシリーズは「夫婦の晩年を描いた物語」だった。
子供らがみな大きくなり、結婚して、家に二人きり残された夫婦が、いったいどんなことをよろこび、どんなことを楽しみにして生きているかを描く小説を私は、ずっと書き続けている。つまり、夫婦の晩年をテーマとした連作を文芸誌に書き続けている。(庄野潤三「星に願いを」)
もっとも、シリーズ最初の作品『貝がらと海の音』のあとがきには「もうすぐ結婚五十年を迎えようとしている夫婦がどんな日常生活を送っているかを書いてみたい」とあって、「そんな夫婦がどんなことをよろこび、どんなことを楽しんで毎日を送っているかを書いてみたい」という内容に変わったのは、シリーズ5作目『鳥の水浴び』のあとがきからだった。
最初は「老夫婦の日常生活」だったシリーズのテーマが、5作目からは「老夫婦の喜びや楽しみ」へと、より凝縮されたものとなっていることが分かるが、そもそも、庄野さんが自身の家族を題材とした作品を書くのは、このシリーズが初めてのことではない。
庄野さん自身が代表作と認める『夕べの雲』は、生田の丘へ引っ越してきた5人家族の日常生活を題材とするものだったし、その後も『絵合せ』『明夫と良二』『野鴨』など、実際の庄野一家をモデルとする一連の(そして、極めて質の高い)作品は、これまでにも多数発表されていた。

子どもたちが大きくなった後、庄野さんは一時期家族小説を離れ、スケールの大きな作品に精力的に取り組むようになるが、家族に支えられながら大病から復帰する様子を描いた闘病記『世をへだてて』に続いて、南足柄市に住む長女からの手紙を中心とした『インド綿の服』を発表するなど、庄野文学の原点とも言うべき家族小説に立ち戻ることになる。
さらに、初めての孫娘であるフーちゃん(次男の長女)誕生後には、『エイヴォン記』『鉛筆印のトレーナー』『さくらんぼジャム』の、いわゆる「フーちゃん三部作」を発表しており、この流れが、夫婦の晩年シリーズの第一作目となる『貝がらと海の音』へと直接的につながっていった。

そして、これら壮大な家族物語の中に共通して認められる特徴は、今書きとめておかなければ、いつか忘れられてしまうだろう日常の些細なことにこそ、作家は注目していたということだろう。
一般に庄野文学では「まるで随筆みたいな小説」とか「特別のストーリーがない小説」などといった評価が散見されるが、それは、我々の人生こそ、特別の物語のない小説のようなものであり、そんな我々の人生を飾り立てることなくスケッチした作品が、庄野さんの小説だったということを意味している。
夫婦の晩年シリーズの作品総数は計11作品。
1996年(平成8年)から2006年(平成18年)まで、毎年1冊の単行本が刊行されており、シリーズの全作品タイトルは次のとおりとなっている。
①貝がらと海の音(1996)
②ピアノの音(1997)
③せきれい(1998)
④庭のつるばら(1999)
⑤鳥の水浴び(2000)
⑥山田さんの鈴虫(2001)
⑦うさぎのミミリー(2002)
⑧庭の小さなバラ(2003)
⑨メジロの来る庭(2004)
⑩けい子ちゃんのゆかた(2005)
⑪星に願いを(2006)
作品タイトルにかかわらず、すべての作品は、庄野夫妻の日常生活をスケッチしたものであり、シリーズ全体では、1994年(平成6年)9月から2004年(平成16年)6月までの庄野家の様子が、ほぼ通算して描かれている。
つまり、夫婦の晩年シリーズは、庄野夫妻の晩年を網羅した記録小説ということになるが、この記録小説には、原則として、作品テーマのとおり「楽しいこと」や「嬉しいこと」しか登場してこない。
著者の庄野さんは、2005年(平成17年)『星に願いを』の連載を最後にシリーズを終了し、執筆活動最後の一年で自伝的長編小説『ワシントンのうた』を連載して、作家生活にも区切りを付けた。
老衰で亡くなったのは、2009年(平成21年)9月21日。
享年88歳の幸福な生涯だったと思われる。
以下、夫婦の晩年シリーズ全作品の概略を、それぞれご紹介したい。
貝がらと海の音(1996)
本作『貝がらと海の音』は、1995年(平成7年)1月から12月まで『新潮45』に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは74歳だった。
単行本は、1996年(平成8年)4月に新潮社から刊行されている。
作品では、1994年(平成6年)9月から1995年(平成7年)6月までの日常生活が描かれていて、クリスマスに妻からハーモニカをプレゼントされたことや、小学2年生のフーちゃんをはじめとする孫たちとの交流の様子などが紹介されている。
いつも坐る席のうしろの壁に、大きな井伏さんのお顔のポスターが懸っているから、驚いた。かおるちゃんと信子ちゃんの話を聞くと、今度、井伏さんの郷里の福山の美術館で「井伏鱒二の世界」という展覧会がある。その展覧会に所蔵の軸などを出品することになった小沼丹が、このポスターを持って来てくれたのだそうだ。(庄野潤三「貝がらと海の音」)
1995年(平成7年)1月17日の阪神・淡路大震災で被災した知人の様子が詳しく綴られていることも、本作の大きな特徴となっている。
ピアノの音(1997)
本作『ピアノの音』は、1996年(平成8年)1月から1997年(平成9年)1月まで『群像』に連載された長篇小説である。
連載開始の年、庄野さんは75歳だった。
単行本は、1997年(平成9年)4月に講談社から刊行されている。
作品では、前作『貝がらと海の音』に続く1995年(平成7年)8月から1996年(平成8年)5月までの日常生活が描かれているが、作品タイトル「ピアノの音」は、ピアノ教室へ通う庄野夫人のピアノの練習曲のことを示している。
「今から十年くらいたって、まだ元気でいられたら」と考える。「八十いくつになった私は、散歩に外へ出て行く代りに庭のこちら側の木の混み合っていないところを、行きつ戻りつして歩いているかも知れないな」(庄野潤三「ピアノの音」)
孫娘フーちゃんは、小学3年生の女の子として登場。
せきれい(1998)
本作『せきれい』は、1997年(平成9年)1月から12月まで『文学界』に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは76歳だった。
作品では、前作『ピアノの音』に続く1996年(平成8年)8月から1997年(平成9年)4月までの日常生活が描かれているが、特に大きな出来事として、盟友・小沼丹の病死をあげることができる。
夕方、吉岡達夫から電話かかり、「小沼が昨日のお昼、十二時半に病院で肺炎で亡くなった。家族だけで葬儀をすませて、小沼はもうお骨になって家に帰った。さっき、奥さんから電話があった」という。(庄野潤三「せきれい」)
以降、小沼さんの死は、本シリーズの中で繰り返し語られるエピソードとなる。
庭のつるばら(1999)
本作『庭のつるばら』は、1998年(平成10年)1月から12月まで『新潮』に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは77歳だった。
単行本は、1999年(平成11年)4月に新潮社から刊行されている。
作品では、前作『せきれい』に続く1997年(平成9年)5月から10月までの日常生活が描かれているが、特筆すべきことは、「フーちゃん三部作」からレギュラーメンバーとして登場していた<清水さん>が急死したことだろう。
清水さんのお通夜。五時すぎに家を出て、バスで生田へ。送迎バスの出る橋のたもとで待つうちに、お通夜へ行くらしい喪服の婦人が来る。この二人連れは送迎バスを待たずに歩いていく。バスは満員になり、発車。「デニーズ」向いの坂道を上って行く。途中でさっき歩いて行った婦人の二人連れを追い越す。春秋苑の門を入ってからが長かった。(庄野潤三「庭のつるばら」)
一方で、孫の和雄(長女の長男)が婚約するという、うれしい話もあった。
庄野さんの「喜寿(かぞえ)」のお祝いで、四家族揃って伊良湖ビューホテルへ二泊旅行に出かけるのも、この作品である。
鳥の水浴び(2000)
本作『鳥の水浴び』は、1999年(平成11年)1月から12月まで『群像』に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは78歳だった。
単行本は、2000年(平成12年)4月に講談社から刊行されている。
作品では、前作『庭のつるばら』に続く1997年(平成9年)10月から1998年(平成10年)9月までの日常生活が描かれている。
夜のハーモニカは、昨日から二日続けて「故郷」を吹く。「うさぎ追いしかの山」の「故郷」。妻がこの唱歌をうたうとき、「いかにおわす父母」のところでぐっと胸に来るものがある。「いかにおわす」と問いたくても、そのちちもははもとっくにこの世にいないからである。(庄野潤三「鳥の水浴び」)
日本経済新聞に「私の履歴書」を連載するなど、充実した作家活動が目立つ。
山田さんの鈴虫(2001)
本作『山田さんの鈴虫』は、2000年(平成12年)1月から12月まで『文学界』に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは79歳だった。
単行本は、2001年(平成13年)4月に文藝春秋から刊行されている。
作品では、前作『鳥の水浴び』に続く1998年(平成10年)10月から1999年(平成11年)8月までの日常生活が描かれている。
シリーズ当初から登場回数の多い孫娘フーちゃんは、本作において西生田小学校を卒業し、西生田中学校へ入学した。
ちくまの会は、筑摩書房の井伏鱒二全集が別巻二巻を残してあらかた刊行を終ったのを記念して、監修、編集に名を連ねた人たちを招いてのお祝いの会である。(略)全集の監修は、河盛好蔵、飯田龍太、小沼丹、安岡章太郎、三浦哲郎と私の六人。このうち小沼は残念なことに亡くなり、今日の会には体調を崩されたという飯田龍太さんのほか皆さん出席(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)
長男(たつさん)のマイホーム購入や、良雄(長女なつ子の次男)の結婚式など、大きなライフイベントが相次いでいることも、本作の特徴と言えるだろう。
うさぎのミミリー(2002)
本作『うさぎのミミリー』は、2001年(平成13年)1月から12月まで『波』に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは80歳だった。
単行本は、2002年(平成14年)4月に新潮社から刊行されている。
作品では、前作『山田さんの鈴虫』に続く1999年(平成11年)8月から2000年(平成12年)5月までの日常生活が描かれている。
世の中的には、2000年のミレニアムに話題が集中した時期だったが、作品の中では、庄野さんの「かぞえ80歳の誕生日」が印象的。
次男は家から白のペンキと筆を持って来て、玄関の郵便受に「庄野」と書いてくれる。この前来たとき、郵便受に黄色のペンキを塗ってくれた。そのとき、名前を入れてくれるよう頼んでおいたのである。(庄野潤三「うさぎのミミリー」)
良雄の結婚式や正雄(長女なつ子の四男)の西湘高校入学、龍太(長男たつさんの長男)の長沢小学校入学など、次々世代の大きなライフイベントが目立つ。
庭の小さなばら(2003)
本作『庭の小さなばら』は、2002年(平成14年)1月から12月まで『群像』に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは81歳だった。
単行本は、2003年(平成15年)4月に講談社から刊行されている。
作品では、前作『うさぎのミミリー』に続く2000年(平成12年)5月から2001年(平成13年)1月までの日常生活が描かれている。
井伏鱒二や小沼丹とも通った大久保の居酒屋「くろがね」で「くろがねの会(おじいちゃん八十歳おめでとうの会)」が開催されている(かぞえで80歳のお祝い)。
また、長女と三人で日光へ旅行に出かけたり、長女の案内で小田原の鰻屋「柏又」で食事をしたり、安岡章太郎『鏡川』の出版祝いの会に出席したりするなど、かぞえ80歳を迎えてなお元気な様子が確認できる。
次男一家がインド洋のモルジブ島への旅から無事元気で帰国したのを祝う会をひらくことにして、五時半に近くのすし屋の増膳に集まる。会席料理というものをまだ食べたことのない長男と次男に、この機会に食べさせてやりましょうという会でもある。(庄野潤三「庭の小さなばら」)
個人的には、『明夫と良二』時代の作品に繰り返し登場していた「図書室のベッド」(長男が子どもの頃に使っていたもの)の解体が印象に残るエピソードだった。
メジロの来る庭(2004)
本作『メジロの来る庭』は、2003年(平成15年)1月から12月まで『文学界』に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは82歳だった。
単行本は、2004年(平成16年)4月に文藝春秋から刊行されている。
作品では、前作『庭の小さなばら』に続く2001年1月(平成13年)から始まっており、『波』に「うさぎのミミリー」の連載が始まったことや、2月9日に80歳の誕生日を迎えたことなどが綴られている。
ところが、4月になると、フーちゃんが生田高校へ入学したり、新潮社から『うさぎのミミリー』の単行本が刊行されたりと、2002年(平成14年)4月にあったはずの出来事が描かれるようになる(作品鑑賞に大きな影響はないが)。
夕食を前に図書室のソファーで本棚からとり出した本を読む。今日の読書タイムは『明夫と良二』(岩波書店)を読む。長女が結婚した年の結婚式を迎える前の私たち一家の様子が詳しく書きとめられている。(庄野潤三「メジロの来る庭」)
5月には、良雄のところに長女(萌花)が誕生、庄野さんにとっての初孫となった。
2002年(平成14年)9月までの日常生活が描かれている。
けい子ちゃんのゆかた(2005)
本作「けい子ちゃんのゆかた」は、2004年(平成16年)1月から12月まで『波』に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは83歳だった。
単行本は、2005年(平成17年)4月に新潮社から刊行されている。
作品では、前作『メジロの来る庭』に続く2002年(平成14年)9月から2003年(平成15年)3月までの日常生活が描かれている。
フーちゃんが加入している生田高校吹奏楽部の演奏会を観に行く話などもあるが、柿生のだるま市など、長年の年中行事以外のイベントは目立たないようになった。
どのくらい長生きしたのだろう? とにかく、多摩丘陵の一つのこの生田の山で生れて、原稿を書いて暮しているこの家の主人の庭先で四季を送り、最期は安らかにこの庭で息を引きとった四十雀であった。(庄野潤三「けい子ちゃんのゆかた」)
庭で死んでいる四十雀を見つけた話は、本シリーズとしては珍しく象徴的な書き方となっている。
星に願いを(2006)
本作『星に願いを』は、2005年(平成17年)1月から11月まで『群像』に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは84歳だった。
単行本は、2006年(平成18年)3月に講談社から刊行されている。
「夫婦の晩年」シリーズ最後の作品となった本作では、前作『けい子ちゃんのゆかた』から一年後となる2004年(平成16年)3月から6月までの日常生活が描かれている(フーちゃんは、おそらく高校3年生になっている)。
4月に『メジロの来る庭』(2004年4年)が刊行されたエピソードが登場しているし、6月には『小沼丹全集』(2004年6月)も刊行されている。
物語の期間としては4か月程度だが、日常生活の様子よりも、全体に昔の思い出話が誌面を占めており、作家として限界まで連載を続けていた様子が伝わってくるような気がした。
「くろがね」が出来るまでは、新宿西口で待合せて地下の小さなビアホールで二人で生ビールを飲む。海老の串やきをとって、これを食べながら、ジョッキを傾けた。二人とも海老の串やきが気に入っていた。(庄野潤三「星に願いを」)
亡き友・小沼丹への追想は、最後まで絶えることはなかった。
まとめ
年末年始の休暇を活用して、庄野さんの「夫婦の晩年シリーズ」全11作を、最初の『貝がらと海の音』から最後の『星に願いを』まで、一気に通読してみた。
印象的だったことは、『せきれい』で小沼丹の訃報に接する場面と、『庭のつるばら』で清水さんの葬儀に参列する場面で、涙が出そうなくらい切ない気持ちになったことである。
「特別のドラマがない」と言われる物語の中の登場人物の「死」に、なぜ、これほどまでに心を揺さぶられたのだろうか。
それは、親しい人間の「死」は、我々にとって避けがたい宿命であることを、自分自身が痛感したからに他ならない。
「夫婦の晩年シリーズ」は、老夫婦の喜びや楽しみを綴った人生讃歌の物語だが、この人生讃歌には、親しい人々の「死」という悲しい現実が最初からセットになっている。
当時のインタビューで、庄野さんは「不愉快なことや嫌だと感じたことは書かない」と語っていて、それを作品中で徹底しているが、身近な人間の死は、生きていく上で避けることのできない事件だった。
むしろ、こうした親しい人々の「死」こそが、老夫婦の喜びや楽しみを陰で支えていると言っても過言ではないだろう。
つまり、どのように楽しい毎日も永遠ではない、だからこそ、今この瞬間の人生を大切に生きなくてはならないというメッセージ性こそが、この「夫婦の晩年シリーズ」全体を構造的に支えている文学観なのだ。
愛着のある庭で花や野鳥を眺めたり、好きな宝塚の観劇に出かけたり、墓参りのために故郷大阪を訪れたり、あるいは、子どもたちの家族と交流したり、庄野夫妻の喜びは些細なことの積み重ねに過ぎないように見える。
しかし、人生の満足度を測る尺度は、実際に生きる人それぞれの問題であって、そのことを庄野さんは、この長いシリーズの中で実践することによって可視化してみせたのだ。
本当の幸せは、背伸びをして飾られた暮らしの中にあるのではない。
おそらく、そうした人生の真実に気づいた若い世代が、庄野潤三の作品世界に共鳴し、「静かなブーム」を支えた人々だったのではないだろうか。
庄野潤三の「夫婦の晩年シリーズ」は、一過性のブームで終わるものではない。
2021年の「生誕100年」を紹介する読売新聞の見出しには、「静かなブーム」の文字があった。
既に『クウネル』(2002)の頃から、庄野潤三の小説は「静かなブーム」であり続けたのである。
それは、「夫婦の晩年シリーズ」が、既に多くの世代の中で「隠れたスタンダード」として定着していることを意味してはいないだろうか。
幸いに多くの作品は、講談社文芸文庫や小学館「P+D BOOKS」で入手することができる。
時代は移り変わっても、庄野さんの「夫婦の晩年シリーズ」は、普遍的な人生の物語として、いつまでも読み継がれていくことだろう。