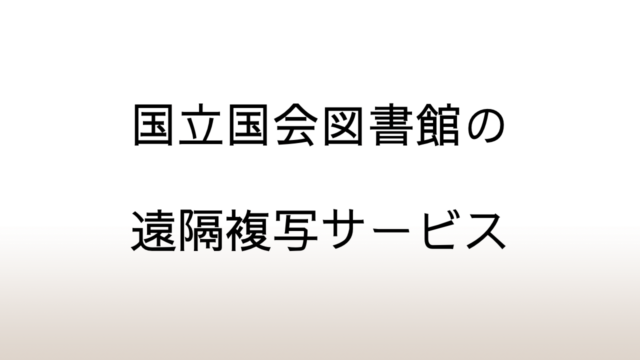庄野潤三「明夫と良二」読了。
本作「明夫と良二」は、1972年(昭和47年)4月に岩波書店から刊行された長篇小説である。
この年、著者は51歳だった。
1972年(昭和47年)、第26回「毎日出版文化賞」受賞。
1972年(昭和47年)、第2回「赤い鳥文化賞」受賞。

濃密な家族間コミュニケーション
 「岩波少年少女の本 16」庄野潤三『明夫と良二』
「岩波少年少女の本 16」庄野潤三『明夫と良二』庄野潤三の代表作を一つだけ選ぶとしたら、僕は『明夫と良二』を選びたい。
この小説は、『夕べの雲』に代表される「五人家族の物語」の最後の作品となったからだ。
「瀬戸物屋が来る。こうしてあの小さな家へ、どんどん品物が運び込まれる。何だか『アリババと四十人の盗賊』に出て来る、あのかくれがの岩屋みたいではないか。金や銀や目もまばゆい細工物なんか無い代り、お玉杓子だってフライパンだってある。よく切れる包丁も米櫃もある」(庄野潤三『明夫と良二』より「荷物運び」)
短篇小説『絵合せ』で、娘を嫁に出す父親の不安を綴った庄野さんは、本作『明夫と良二』で、長女(和子)を明るく送り出した。
「五人家族の物語」が、「四人家族の物語」へと発展したのだ。
本作『明夫と良二』は、岩波書店の「岩波少年少女の本 16」として刊行された児童小説である。
これは、どこの港からも船に乗らず、従って海のまっただ中で怖ろしいあらしに出会うこともなく、無人島に流されもしない、自分の家でふだんの通りに暮らしている五人の家族の物語であります。(庄野潤三「明夫と良二」あとがき)
「五人家族の物語」は、庄野文学にとって大きな柱となるテーマだった。
庄野家から片道3キロばかりの(黍坂)に新居を構えた長女(和子)は、引き続き、物語の中に登場するが、この作品の主役は、やはり、長男(明夫、予備校生)と次男(良二、中学三年生)である。
「仕様がないなあ」と明夫はいった。「だから、お前はグズなんだ」「は」「もっと素早くしないと駄目じゃないか」「は」「かなぶんって、すぐに汁を出すんだよ」「は」(庄野潤三『明夫と良二』より「かなぶん」)
中学生の良二に対して、予備校生の明夫が、何かとマウントを取りたがる姿は、傍から見ていて滑稽でもあり、楽しくもある。
「お前につき合って、一緒に走ってやったり、そんなことをおれがすると思ったら、大間違いだよ」「思いません」「そんな考えは、甘いよ。おれが自転車でのろのろお前のそばについて走って行くなんて、思うな」「思いません」「おれは普通に走るよ。お前に関係なしにどんどん先へ行ってしまうけど、それで文句いったって知らないよ」「いいません」(庄野潤三『明夫と良二』より「黍坂まで」)
厳しい上下関係の中で、濃密なコミュニケーションが育まれている(仲良すぎだろ、と思う)。
両親(井村夫妻)は、いつでも末っ子(良二)の味方だ。
練習に出かける前に、一時間くらい、昼寝の時間がある。廊下の床の上にパンツ一枚で寝ている良二を見て、細君は、「ラマ僧の小僧そっくり」という。頭を短く刈って、顔も手足も日に焼けて黒くなっている。断食しているわけではないが、細長い。上から下まで同じ幅で、出入りというのがない。(庄野潤三『明夫と良二』より「リレー式練習法」)
この物語を支えているのは、家族間の濃密なコミュニケーションである。
「この分では、明日は危いな」「雨になりそうですか」「どうも何だか、おかしくなって来たぞ」(略)「やっぱり降りそうですか」「いや、それは明日になってみないことには分らない。しかし、この空模様ではどうもよくないな」「明日までもたせるのは、無理ですか」「無理だな」(庄野潤三『明夫と良二』より「結婚式の天気」)
長女の結婚式を翌日に控えて、天気の心配をする夫婦の会話ものんびりしている(結局、真夏のように暑い好天となった)。
庄野潤三の長女(夏子)が、井伏鱒二夫人の紹介で今村邦雄と結婚したのは、1970年(昭和45年)5月のことだった。
この物語は、1970年(昭和45年)の5月から8月にかけての、庄野家の日常をスケッチした物語と言っていい。
全部で三十あるエピソードが、「何だかちょっと変わったところ」も見られる五人家族の様子を伝えている。
「あと一曲きくと遅くなりますね」といいながら、細君は、次にかけるレコードをどれにするか、考えた。もう十一時になっていた。歌劇の中から主だった曲を抜き出したのがあって、その一枚を取り出した。音楽が鳴り出してから、「全部きくと遅くなる」と井村はいった。「途中までにしよう」「そうね。『手紙のデュエット』までにしましょうか」(庄野潤三『明夫と良二』より「『手紙のデュエット』」)
複雑な言い回しや面倒な説明がなくて、シンプルな会話文や短いセンテンスの文章が多いのは、児童向けの小説だからではなく、それが、庄野文学の本質だったからだろう。
書き込むことではなく、省くことにこそ、庄野文学の余韻があったのだ(ちょっと俳句に似ている)。
明夫が笑っている。「どうしたんだ」「あのね」と明夫はいった。「いま、良二が『埴生の宿』をうたっていたの。それで僕が、それ、あるって聞いた」「それ、あるって、なんの意味だ」「うん。だから、良二も何の意味か分らなくて、なに?といったの」(庄野潤三『明夫と良二』より「たわむれ」)
庄野文学には、とりとめのないエピソードが数多く登場するが、その中でも、本作『明夫と良二』では、殊更に他愛ない話が多い。
「今日は、ざんねん、食わしてやる」と言うと、良二はラジオを放り出して「うれしーい」と叫んだ。
夕食に「ざんねん」をすることになった。豚肉の水だきの時に、おかずはおかずとして食べるが、頃合をみて、御飯の上に塩を少しふりかけ、海苔をちぎったのをのせておいて、鍋の中のスープをかける。そうすると、おいしくて、いくらでも食べられる。もっと食べたいが、もうこれ以上入らない、残念だというので、ざんねん雑炊という名前が附いている。(庄野潤三『明夫と良二』より「ざんねん」)
あえて、とりとめのないエピソードだけを精選して、物語を構成しているのではないかと、考えたくなるくらいだ。
しかし、我々の日常のほとんどは、他愛ないエピソードによって綴られている(それが、平穏な生活であるほどに)。
黙って見過ごしてしまえば忘れてしまうようなエピソードを、物語の中へ組み込むことによって、庄野さんは、長女が結婚して家を出たばかりの庄野家の夏を、記録(記憶)しようとしていたのかもしれない。
仲良し家族の幸福の断片
 庄野潤三『明夫と良二』岩波少年文庫
庄野潤三『明夫と良二』岩波少年文庫『明夫と良二』が発表された1972年(昭和47年)前後、庄野さんは、作家としての絶頂期にあった。
1971年(昭和46年)に『絵合せ』で野間文芸賞、1972年(昭和47年)に『明夫と良二』で毎日出版文化賞と赤い鳥文学賞を受賞、1973年(昭和48年)には、作家としての業績が認められて日本芸術院賞を受賞し、川崎市文化賞までもらった(まさに受賞ラッシュである)。
それは、『夕べの雲』に始まった「山の上の文学」が、広く社会一般に評価された、ということに他ならない。
ここは山の上なので、朝晩はかなり冷える。(彼の家族は、最初のころの面影がすっかり無くなったいまでも、まだ丘といわないで、山と呼んでいる)(庄野潤三『明夫と良二』より「とび上る二人」)
彼ら(井村一家)が、「山の上の家」で暮らし始めたのは、1961年(昭和36年)4月のことだ。
九年前にこの一家が引越して来たころには、ここは春さきに春蘭の蕾のいっぱい見つかる赤松の林、桃畑や柿畑、夏になるとかぶと虫が集まって来る櫟林、杉林の谷間のある山であった。(庄野潤三『明夫と良二』より「つつじの花」)
九年前に引っ越してきたばかりの頃の暮らしについては、長篇『夕べの雲』に詳しい。

生田の「山の上の暮らし」は、『夕べの雲』から連綿と受け継がれてきたものなのだ。
この山椒の木は、九年前の春、彼等がここへ引越して来て間もないころに、大学でフランス語を教えている井村の知人が、自分の家の庭から持って来てくれたものである。(庄野潤三『明夫と良二』より「揚羽の幼虫」)
当時、長女(夏子)は中学二年生だったが、長男(龍也)は小学四年生、次男(和也)に至っては、幼稚園に入ったばかりの子どもだった。
しかも、次男の幼稚園は、電車に乗って通園するところにあったから、山の上から駅までの往復だけでも、両親にとっては相当の負担感があったらしい。
井村の細君は、ときどき、不意に、胃の痛みで苦しむようになった。
彼等が東京から多摩丘陵のひとつであるこの丘の上へ引越して来た年のことだが、井村の細君が身体の具合を悪くして、肉や卵、それに油を使った料理を一切食べられなくなったことがある。(庄野潤三『明夫と良二』より「つつじの花」)
それでなくても、山の上の過酷な環境である。
最初の冬は、井村の家では石油ストーブひとつで過した。そこへ肉も卵もいけない、油を使った料理は禁物というのだから(胃ではなく、胆嚢だということが分ったので)、「寒くて寒くて仕様がなかった」と、あとで振り返って細君がいうのも無理はない。(庄野潤三『明夫と良二』より「つつじの花」)
このとき、大阪にいる井村の兄(悠二伯父ちゃん)が、蜂蜜の缶を送ってくれた(悠二伯父ちゃんは「馬追う子」で登場する)。
井村家のあった山の周りは、間もなく切り崩されていく。
ところが、三年くらいたつと、大きな工事が始まって、この山が削り取られて、舗装道路にかこまれた新しい住宅町が出来上った。井村の家はほんの僅か外れていたために、もとの山の続きに──崖の上に取り残されたようになってしまった。(庄野潤三『明夫と良二』より「つつじの花」)
「山の上の家」は、小田急電鉄小田原線「生田駅」から、西三田団地の長い坂を上ったところにあるが、庄野さんは、作品の中で、界隈の移り変わりを描き続けた。
はじめは、そこの崖にいい小松林があった。奥の方へ行くと山の雑木林になっていた。中へ一歩でも入り込むと、鳴き交わす鳥の声しか聞えなかった。まるで別世界のようであった。ところが、下の方に宅地をつくることになって、ブルドーザーが崖を削ってしまった。(庄野潤三『明夫と良二』より「おなか叩き」)
高校生だった長女が、短大を卒業した後で船の会社に就職することは、前作『絵合せ』にも書かれているとおりだ。

船の会社に二年間勤めて、つい十日前にやめたのだが、前の年の秋、明夫の高校の体育祭の日には、ちょうど南米へ向けて出港する船があり、仕事の関係で横浜へ行かなくてはいけないことになった。(庄野潤三『明夫と良二』より「つつじの花」)
結婚して家を出た長女は、実家からほど近い(黍坂)に家を借りた。
黍坂というところに、和子たちの入る借家がある。バスは、昼間は一時間に一本くらいしか通らない代りに、もし利用する気なら、なかなかこれで役に立つ。(庄野潤三『明夫と良二』より「凧」)
黍坂は、長沢近くにある(餅坂、餅井坂)がモデルとなっているが、長女の結婚によって、庄野文学の舞台が広がったことは、その後の作品世界でも知られている(『野鴨』『おもちゃ屋』『鍛冶屋の馬』など)。

日常生活の中に、さりげなく、亡くなった両親の思い出話が入る。
明夫の方はもう長い間、大阪へ行ったことがない。小学一年の夏休みに井村が連れて行ってから、一度も行かない。(略)井村の母が亡くなる二月前に生まれた良二は、まだ一度も父母の生家を見たことがない。(庄野潤三『明夫と良二』より「やぶかんぞう」)
遠い故郷は、井村一家が、すっかりと関東に根付いたことを示している。
黒御影の石の天辺にたまった水を見るのを忘れるな、空の雲がそこに映っているから(もし雲が浮んでいたとすれば)。うらに刻まれている言葉は、井村のいちばん上の兄が、義姉と二人の小さな姪(下の方は生まれたばかりの赤ん坊であった)を残して死んだ時に、お前のお祖父さんが書いたもので、是非それを読むようにといった。(庄野潤三『明夫と良二』より「やぶかんぞう」)
家族を代表して、大阪まで墓参りへ行く明夫に、父(井村)が「黒御影の石の天辺にたまった水を見るのを忘れるな」と教える場面は、短篇「蒼天」を思い出させる(作品集『丘の明り』所収)。

日常スケッチの中に、庄野家の歴史が織り込まれているのだ。
逆説的に言えば、現在の平穏な日常生活は、様々な歴史の上に培われたものだということだろう。
子ども向けの物語の中で、庄野さんは、そのような人間の営みを、決して説教くさくなることなく、極めて自然体で盛り込んでいる。
長女が結婚したお祝いに「ひじきとじゃこと鰹節」をどっさりと贈ってくれたのは、房州の海岸町で暮らす、井村の友人だった。
この気前のいい友達は、井村の家族が東京へ引越して来たその翌年の夏に、みんなで泳ぎに来るようにといって、彼の町から汽車でひとつ先の駅に近い、小さい宿屋を紹介してくれた。和子は小学一年生、明夫は三つ、良二はまだ生まれていなかった。(庄野潤三『明夫と良二』より「姉と弟」)
本作『明夫と良二』は、『夕べの雲』から続く「五人家族の物語」の総決算的な位置付けの作品ではなかっただろうか。
海水浴にちょうどいい宿屋を紹介してくれた「房州の海岸町で暮らす友人」は、小説家・近藤啓太郎で、家族で海水浴へ行った話は、短篇『蟹』という作品にもなった。
積み重ねられた家族の歴史が、まるでミルフィーユのように、日常生活の他愛ないエピソードの中で顔を出している。
庄野文学の深さは、培われた歴史の深さでもある。
長女の結婚を機に、庄野さんは、家族の歴史物語を『明夫と良二』という児童向け文学作品の中に織り込んで綴った。
メインは、あくまでも、明夫と良二の兄弟を主人公とする日常スケッチという体裁を取りながら。
むしろ、児童文学という枠の中で書かれた作品だったからこそ、『明夫と良二』は、肩の力が抜けて、良い意味で気軽に読める物語となっている(次作長篇『野鴨』は文学作品という趣が強い)。
本作『明夫と良二』は、何度読んでも楽しい物語である。
というよりも、何度も読まずにはいられない物語だ。
大きな事件があるわけではなく、感動の名場面があるわけでもない。
どこの家庭にもありそうな、他愛ない暮らしを描いた作品だからこそ、安心して何度も読みたいと思えるのだ。
それは、家族がみんな元気で仲良しだった時代の、ある意味で「おとぎ話」かもしれない。
しかし、かけがえのない幸福感が、この物語の中にはある。
仲良し家族の幸福の断片に触れながら、僕たちは、あの懐かしくも遠い昭和の日本を旅しているのだろう。
書名:明夫と良二
著者:庄野潤三
発行:2019/02/07
出版社:講談社文芸文庫