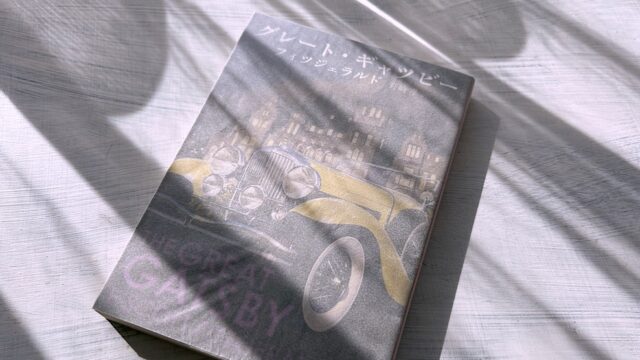トマス・ヒューズ「トム・ブラウンの学校生活」読了。
本作「トム・ブラウンの学校生活」は、1857年にイギリスで刊行された長篇小説である。
この年、著者は35歳だった。
原題は「Tom Brown’s School Days」。
やんちゃなトム・ブラウンの少年成長物語
庄野潤三の『エイヴォン記』に、次のような庄野さんの台詞がある。
「エイヴォン? エイヴォンといえばイギリスの田舎を流れている川の名前だ。ほら、『トム・ブラウンの学校生活』のなかで、トムが学校の規則を破って釣りをする川が出て来るが、あの川の名がエイヴォンだよ」(庄野潤三「エイヴォン記」)
近所の<清水さん>からもらったバラの名前が「エイヴォン」だったことで、庄野さんは、トマス・ヒューズの『トム・ブラウンの学校生活』を思い出す。
つまり、『エイヴォン記』という作品タイトルには、バラの名前である「エイヴォン」と、『トム・ブラウンの学校生活』に登場する川の名前である「エイヴォン」とが重ね合わせられているわけだ。
そして、『エイヴォン記』の中の「エイヴォンの岸辺」において、『トム・ブラウンの学校生活』は詳しく語られることになる。
『トム・ブラウンの学校生活』は、1830年代のパブリックスクール<ラグビー校>を舞台に、やんちゃな少年だったトム・ブラウンが立派な大人の男性へと成長していく過程を描いた、少年成長物語である。
学校の規則を破って、エイヴォン川で魚釣りをするトム・ブラウンは、もちろん、やんちゃな時代のトム・ブラウンだ。
エイヴォン川も、ラグビーを通る辺は、ゆるやかな流れになっていて、あまりきれいではない。うぐい、あかはら、その他の下等な魚が多い(あるいは、多かったというべきか)。それに小かますがちらほら見うけられる。だが釣や食物にするほどの魚は全くない。しかしこの川は水泳にはあつらえ向きである。(トマス・ヒューズ「トム・ブラウンの学校生活」前川俊一・訳)
活発なトム・ブラウンにとって、学校の教師は敵であり、学校の規則を破ることは、教師との戦いでもあった。
もとより、トム・ブラウンは、社会的な規律を守ることのできない、無軌道な少年だったわけではない。
階級にかかわりなく、村(白馬ヶ渓)の子どもたちと一緒に遊んで成長したトム・ブラウンは、上層階級の少年に似合わず、村の子どもたちが持つ「上層階級に劣らず男らしく、正直で、そして純真さの点ではかえってかれらに優っていた」性質を、しっかりと身に付けていた。
親友アーサーに「君はここで何をしたいと思い、何を得ようと思ってあるのかい」と訊かれたとき、トム・ブラウンは次のように答えている。
トムは一寸考えた。「僕はクリケット、フットボール、その他あらゆるゲームの第一人者になりたいよ。そして紳士と俗人とを問わず、腕づくでは何人にもひけを取らぬようになりたい。学校を去る前に六級に進んで校長を喜ばしたい。それから、外聞の悪くない程度の成績で、オクスフォードに進学出来るだけのラテン語とギリシャ語を修得したい。さあ、若いの、こんな事これまで考えて見たことはないが、数え立てれば先ずこんなところだ」(トマス・ヒューズ「トム・ブラウンの学校生活」前川俊一・訳)
そのとき、トムは、「しかし、一つ忘れていたよ。僕がこの学校に置土産として残したいものを」を言って、次の言葉を付け加える。
「それは、下級生を一度もいじめたこともなし、上級生に対しても決して後を見せたことのない人間の名前だよ」
この正義感こそ、つまり、トム・ブラウンという少年の人間的な魅力だった。
そのことを知っていたからこそ、アーノルド校長は、トムとイーストという二人の少年のヤンチャぶりに手を焼きながら、簡単に彼らを放校処分にすることなく、自らの手で厳しい指導を与え続けたのである。
アーノルド校長とキリスト教の素晴らしさを伝える
やんちゃなトムとイーストの学校生活を改めさせるために、アーノルド校長の取った作戦は、「面倒を見てやるような幼い生徒をつけてやる」ことだった。
そして、ひ弱で信心深い転入生<ジョージ・アーサー>の世話役に任命されたトムは、アーサーが寮生たちにいじめられることがないよう、身を挺してアーサーを守る。
このアーサーとの出会いこそが、ラグビー校におけるトム・ブラウンの大きな成長のきっかけとなったのであり、それは、アーノルド校長の作戦が見事に功を奏したことを意味している。
本作『トム・ブラウンの学校生活』は、1830年代のパブリックスクール<ラグビー校>の様子を克明に再現した作品として有名だが、そこで描かれているものは、アーノルド校長の素晴らしさであり、キリスト教の偉大さである。
もともと、この作品のタイトルは『一同窓生の描けるトム・ブラウンの学校生活』となっていて、ラグビー校の卒業生が、トム・ブラウン時代のラグビー校を回想する構成の小説となっている。
トム・ブラウンの成長ぶりを通して語られているのは、ラグビー校に実在したという<アーノルド校長>の素晴らしさだ。
この偉大なる校長は、六級生を教え、全校を支配し、指導し、古典を編纂し、歴史の著述をするかたわらに、この忙しい数年間、トムのような人間とその仲よし連中と──そして、疑いもなく、それと同時に他の五十人の生徒たちの足どり──を見守るだけの時間を見出したのである。(トマス・ヒューズ「トム・ブラウンの学校生活」前川俊一・訳)
しかも、校長は、「これらすべてを自分の功に帰することなど全然なく、また自分が特にある少年のことを心配してやっているということを、自分でも気づかず、他人にも一切知らせないで」いるらしい。
卒業を目前に控えたとき、トムは、アーノルド校長の偉大な教育者ぶりを初めて正しく理解して、改めてアーノルド校長を尊敬する。
ここに、『トム・ブラウンの学校生活』という物語の、大きなポイントがある。
念のため記しておくと、<ラグビースクール>は、イギリスのウォリックシャー州にある実在のパブリックスクールで、小沼丹もイギリス滞在時に、この学校を訪れている(「ラグビイの先生」~『藁屋根』に収録)。
そして、もう一つのポイントは、ひ弱で信心深い少年アーサーを通して描かれる、キリスト教の偉大さだ。
「君のアーサーに対する友情以上に大きな喜びを覚えさせられたものはないね」と先生は言葉を続けた。「あれが君ら両人の今日をつくり上げたのだよ」「少なくとも私をつくり上げてくれましたよ」とトムは答えた。「アーサーがいなかったら、今頃はこの学校にはいますまい。かれがラグビー校にはいって、私の同室者になったのは、私にとっては最大の幸運事でした」(トマス・ヒューズ「トム・ブラウンの学校生活」前川俊一・訳)
アーサーとトムが同室になったのは、もちろん偶然ではない。
それが、校長による教育的な配慮だったことを先生から伝えられて、トムは自分の無理解を恥じる。
そして、校長に対する尊敬を新たにするのだが、それほどまでに、ラグビー校において、アーサーがトムに与えた影響は大きかった。
そのアーサーを支えているものがキリスト教であり(アーサーの父親は献身的な牧師だった)、トムは、アーサーを通して宗教の素晴らしさを、正しく理解するようになる。
エンタメ小説というよりは、教育と宗教を語るための物語だから、時に説教臭い部分が鼻につくこともあるが、それも含めて、『トム・ブラウンの学校生活』は、1830年代のイギリスのパブリックスクールの空気感というものを再現しているのだろう。
細かい部分では、作品の随所に登場する食事の場面がいい。
父親と二人で訪れた<孔雀軒>の食事(ステーキとオイスター・ソースと黒ビール)。
ラグビー校へ向かう途中に寄った宿屋の朝食(鳩パイ、ハム、巨牛の腿肉のコールド・ボイルド・ビーフ、木盤に乗せた家庭用パンの大きな塊、透いて見えるくらい薄く切ったベーコン、落とし卵、バタートースト、コーヒーと茶)。
到着したばかりの寮で食べたおやつ(焼いたじゃがいもとソーセージ)。
200年前のイギリスの食事が、現代より美味しかったかどうか分からないけれど、『トム・ブラウンの学校生活』に登場する食べ物は、どれも美味しそうだ。
そんなところにも、1830年代のイギリスのさりげない魅力があるのかもしれない。
不満があるとすれば、この作品が、現代日本では入手困難になっている、という事実だ。
邦訳としては、1952年(昭和27年)に岩波文庫から出たものが定番だが、常に在庫なし。
稀少文庫ということで古書価も高く、とても気軽に読めるような作品ではない。
何とかならないものですかね、岩波文庫さん。
なお、訳者による解題は、「上巻」の巻末に収録されているので、参考までに。
書名:トム・ブラウンの学校生活(上・下)
著者:トマス・ヒューズ
訳者:前川俊一
発行:1952/07/25
出版社:岩波文庫