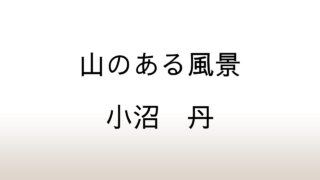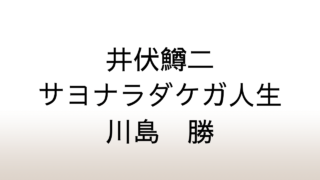森田たま「石狩少女」読了。
本作「石狩少女」は、1940年(昭和15年)7月に実業之日本社から刊行された長篇小説である。
この年、著者は40歳だった。
敬愛する恩師の言葉に支えられて
森田たまの『石狩少女(おとめ)』が、ちくま文庫から復刊された。
帯には「本読む少女はいきづらい」「少女小説の傑作」と書かれているから、現代向きの小説と判断されたのだろうか。
主人公<野村悠紀子>は、明治末期を生きる女学生である。
前にも記したように、国木田独歩が湘南の病院で死んだのはその年の初夏であったが、同じ初夏の頃に、川上眉山が自殺した事も感じやすい少女の胸をゆすぶった出来事の一つであった。前の年の十四歳は運よく女学校へ入学したよろこびと、同時に年長者ばかりのあいだに交って、一所懸命背のびをしているような苦痛とで無我夢中にすごしてしまい、学校以外の事には何一つ心の向く余裕もなかったのが、ようやく二年生になってすこしずつ心の落ち着きを取戻すとともに、回覧雑誌をこしらえてみようとおもいたつほど、学課のほかに何か求める気もちが動いてきたのであった。(森田たま「石狩少女」)
やがて、「現代の清少納言」とまで称されることになる女性作家の少女時代が、この物語には描かれている。
文学を志して生きることが、いかに大変な時代であったか。
強い自我を持つ誇り高い女学生だった悠紀子にとってさえ、生きることは簡単ではなかった。
なにしろ、姉(美和子)とのいさかいが多い。
姉びいきの母親からは、露骨に邪魔者扱いされる。
姉が病気で死んだときには、「お前が死ねばよかったのに」と言われる。
生意気な生徒だから、学校でも当然に浮いている。
病気になって長期欠席したときも、クラスメートたちは停学になっていたものと思い込んでいたくらいだ。
そんな世の中で悠紀子を理解していてくれたのが、教頭の土屋先生だった。
夕暮れの大通公園で、土屋先生は「私は実はいま、あの夕陽をみてふと思ったのです。あの夕陽、あの夕陽こそ野村悠紀子の姿ではないかと」と言った。
「野村さん、あなたはね、こんなちいさな町──いや、札幌というところはなかなかよいところですが、しかしあなたはこの町で平凡にお嫁にいって、平凡に人妻として一生を終るべき人じゃない。かならずあの太陽のように、日本の上にかがやく人だと思うのです」(森田たま「石狩少女」)
この作品で著者が書きたかったもの、それは、このときの土屋先生の言葉がすべてだったのではないだろうか。
その他の文章は、土屋先生の言葉を輝かせるために存在していると言ってもよいくらいだ。
「ねえ、あなたもああいう生涯をおくるのですよ。いいですか。どんなに辛くとも苦しくとも、途中でくじけてしまってはいけない」
悠紀子は、このときの土屋先生の言葉を道標として、文学者への道を歩んでいくことになる。
「北海道出身者として初めて」と言われる女性作家の青春の日の輝きが、そこにはあった。
こういう理解ある先生が、近くにいるかどうかということで、変わってしまう人生というものもあるのかもしれない。
明治末期の札幌情緒が美しい
本作『石狩少女』で著者が描きたかったものが、もう一つある。
それは、故郷・札幌の美しさである。
札幌中心部に生まれ、札幌の女学校へ通った森田たまは、生涯、札幌を愛し続けたという。
そこはかとなく、かすかに牧草の匂いがする。町の中に牧草の干してあるところはない筈だけれど、ひょっと大通りのあたりを牧草のくるまが通り、その匂いが夕風にのってきたのかもしれなかった。それともまた、半町ほどさきの町角にゆったりと根を張った楡の大樹の、早くも散りそめた落葉の匂いかもしれなかった。(森田たま「石狩少女」)
何気ない文章に、明治末期の札幌情緒が描かれている。
長い薄暮であった。太陽は疾うに手稲山の左肩へ没し去ったにもかかわらず、夕やけの余映は西の空一面にひろがりひろがって、紅に朱に橙に、やがてうす紫の淡い色から、空の浅黄にとけかけている。(森田たま「石狩少女」)
札幌の夏の薄暮は長い。
太陽が沈んでからも、長い夕闇が続く。
それは、北欧の白夜を思い出させる。
手稲山とか藻岩山とか豊平川とか札幌近郊の林檎畑とか中島公園とか狸小路とか銭函とか、いかにも観光案内的にローカルな地理以上に、札幌で生きた人間にしか分からないだろう、微妙な情景描写が、この小説にはある。
決して、ベストセラーとは言えない、この作品が、札幌の地で長く愛されてきたという理由が分かるような気がした。
札幌を「詩の都」と呼んだ石川啄木が札幌に滞在するのは、1907年(明治40年)。
作中に登場する国木田独歩の死は1908年(明治41年)だから、まさに、『石狩少女』と同じ時代の札幌を、石川啄木は見ていたわけだ(啄木にも『札幌』という小説あり)。
後半、悠紀子は、秋田へお嫁(の下見)にゆくのだが、繊細な札幌の描写と異なって、秋田の情景にはほとんど触れられていない。
これもまた、故郷・札幌を描くために、この小説が書かれているということなのだろう。
キシキシとひしめくようにかたく葉をまいたキャベツのやまが、台所の隅にかさなり合い、みがき鰊がごしごしと洗われる。大こんの水漬、キャベツの塩漬、それから鰊漬、なた漬、たくあんと、つぎからつぎへ重石をのせた四斗樽が、漬物小屋の中へならんでゆく。あまった野菜は土室に貯え、土室のない家では台所の炉の下の土を掘って、そこへ大根も人じんもごぼうもしまっておく。(森田たま「石狩少女」)
敬愛する土屋先生の思い出と、懐かしき札幌での暮らし。
それが、この物語のすべてだと言っていい。
生きづらさを抱える文学少女の青春を支えたものこそ、この小説の大きなテーマとなっているのだから。
なお、学友<白井千鶴子>として、片脚の女性作家として知られる素木しずが、ささやかに登場している。
そして、僕の好きな登場人物は、泣き虫の叔母さんだ。
書名:石狩少女
著者:森田たま
発行:2024/01/10
出版社:ちくま文庫