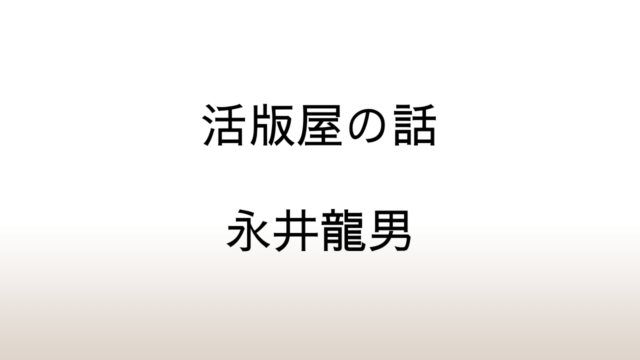庄野潤三「秋風と二人の男」読了。
本作は、1965年(昭和40年)11月、「群像」に発表された短編小説である。
この年、著者は44歳だった。
作品集としては、1967年(昭和42年)12月に筑摩書房から刊行された『丘の明り』に収録されている。
▶ 庄野潤三について詳しく知りたい方は「完全ガイド」をご覧ください

変わらないものに惹かれてしまうこと
物語は「巻きずしというのは、うまそうなものだな」という、主人公「蓬田」の言葉から始まる。
そのとき、蓬田は出かける用意をして、まだ時間が少し早いので、台所で細君が夕食の巻きずしを作っている様子を眺めているのだ。
蓬田は細君が巻きずしをこしらえる手順を詳細に観察しながら、「死んだいちばん上の兄は好きだったな」と、早世した長男の思い出を妻に話す。
学校の水泳部にいた時分、兄はどこかへ出かけて、夜、帰って来るとき、駅前の寿司屋で太巻を一本買って、まるごと食べながら合宿へ戻ったのだそうだ。
これから「芝原」と待ち合わせをしている蓬田は、「これを芝原に食べさせてやりたい」と考えるが、この巻きずしをどこで食べるかということを考えると、飲みに出かけるときに巻きずしを持っていくのも躊躇される。
蓬田の友人である芝原は、二年前に細君を亡くして、いまは高校三年の女の子と二人きりで暮らしているのだが、いくら、女の子が料理をしてくれるといっても、巻きずしを作ったりはしないだろう。
結局、蓬田は巻きずしを持って、待ち合わせの場所へ出かける。
蓬田と芝原は、こうして時々二人で会っていたが、特別な用件というものがあるわけではなく、ただ酒を飲みながら、他愛もない話をするというだけのことだった。
歩き出してから、半袖シャツの蓬田は秋風が少し冷たいことに気がつくが、今さら山の上にある自宅まで上着を取りに戻る気にもなれない。
「何も冷蔵庫の中へ入りに行くんじゃないんだ」と、蓬田は自分に言い聞かせる。
蓬田と芝原は、ターミナルのすぐそばの百貨店の地階のビア・レストランで、料理を食べながら酒を飲む。
芝原は固いフランスパンを食べているときに、入れ歯(ブリッジ)が取れてしまったことを話し、蓬田は家族で海水浴に行った漁村で、神社にお参りをしたことを話した。
「あそこへ行く途中の景色が、いつも変らないんだ」と、蓬田は言う。
「それを見ると、有難いなあという気がして、たまらなくなる。最初に来た時から、ちっともその景色が変らないんだ。それが、何かあり得ないことのような気がしてね。ふだんわれわれは、世の中に変らないものはない、いつまでもそのままで残っているものはないんだという気持で暮しているだろう。そういう風に自分と自分のまわりをみているだろう。一種の覚悟というかな。それがもうしみ込んでしまっている。だから、去年みたのと同じ景色が見えて来ると、思わず見入ってしまうんだ」(庄野潤三「秋風と二人の男」)
芝原は、ふうんと言って、二人はまた酒を飲んだ。
ビールだった酒は、もう熱燗に変わっていた。
庄野文学らしさが流れている名作短篇
ここで書かれている物語は、特別の物語ではない。
ストーリーとしては、主人公である蓬田が、妻が巻きずしをこしらえる様子を眺め、友人と会って酒を飲む、というだけの話である。
小説というよりも、エッセイの趣に近い。
実際、この物語は、庄野さん自身の体験を素材としたもので、「亡くなった上の兄」は、長男・鷗一のことだし、「蓬田」は庄野さん自身、「芝原」は作家で友人の小沼丹のことである。
当時、二人は時々こうして会って、海老の串焼きを食べながらビールを飲んだ。
小沼丹に「のんびりした話」というエッセイがある。
先日、庄野潤三と飲んでいたら、今度新宿の小田急デパアトの下にニュウ・トウキョウが出来て感じがいいから行こうと云う。早速出掛けて、エビの串焼とか鶏の塩焼とか注文して酒を飲み、たいへんのんびりした。(小沼丹「のんびりした話」/『小さな手袋』所収)
小沼丹とは早稲田大学で同僚だった横田瑞穂の回想にも、本作品が登場している。
七時半に講義が終ると、そろって新宿のビヤホールへ行き、ジョッキーを傾けながら夕飯をとる。それから行きつけの飲み屋をまわって雑談する。(略)その頃のことは庄野君の好短編「秋風と二人の男」に描かれている。(横田瑞穂「小沼丹君のこと」/『山桃』所収)
「秋風と二人の男」の姉妹編として「鉄の串」という短篇小説があるが、こちらは、横田瑞穂を加えて三人の男たちが飲みにいく話となっている(作品集『絵合せ』所収)。
何ということのない日常生活の一部を、三人称の小説仕立てにしたのが、この「秋風と二人の男」という作品だが、本作は現在も庄野さんが遺した名作短篇として、多くの読者に愛されている。
妻の作る巻きずし、死んだ兄の思い出、秋風の冷たさ、海老の串焼き、海水浴の思い出、どのエピソードも、根底に庄野文学らしさが流れている。
海水浴へ出かける蓬田が語る「ふだんわれわれは、世の中に変らないものはない、いつまでもそのままで残っているものはないんだという気持で暮しているだろう。そういう風に自分と自分のまわりをみているだろう。一種の覚悟というかな」という言葉は、まさしくこの短篇小説の核心となっているものだろう。
作品:秋風と二人の男
著者:庄野潤三
初出:群像(1965年11月)