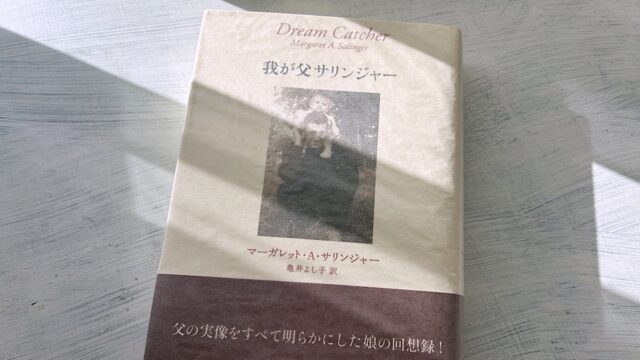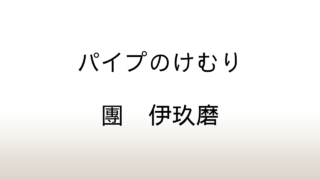小島信夫「アメリカン・スクール」読了。
本作「アメリカン・スクール」は、『文學界』1954年(昭和29年)9月号に発表された短編小説である。
この年、著者は、39歳だった。
本作によって、小島信夫は、翌年の1955年(昭和30年)に芥川賞を受賞(庄野潤三「プールサイド小景」とのダブル受賞だった)。
単行本では、1954年(昭和29年)に刊行された『アメリカン・スクール』に収録されている。
敗戦国・日本の劣等感を自虐的に明るく描く
同じ時に芥川賞を同時受賞した庄野潤三の「プールサイド小景」に比べて、小島信夫の「アメリカン・スクール」は明るい小説である。
その明るさは、敗戦国・日本の劣等感をあからさまに曝け出した、自虐的とも言える明るさだろう。
言ってみれば、逆切れみたいに小島信夫は、戦争に負けた自国民を卑屈に描いてみせる。
ここに登場する英語教師たちは、いずれも敗戦国民の象徴みたいな人たちだ。
最も極端で滑稽な存在が、英会話を得意とする自信家の<山田>である。
彼は、得意の英会話を生かして、何とか自分の存在価値を認めてもらおうと、あくせく動き回るが、心の中では、戦勝国アメリカに対する尊敬の気持ちを微塵も抱いていない。
「実はこんなこと云って何ですが、将校の時、だいぶん試し斬りもやりましたよ」「首をきるのはなかなかむつかしいでしょう?」「いや、それは腕ですし、何といっても真剣をもって斬って見なけりゃね」「何人ぐらいやりましたか」「ざっと」彼はあたりを見廻しながら云った。「二十人ぐらい。その半分は捕虜ですがね」(小島信夫「アメリカン・スクール」)
戦時中に、日本刀で捕虜の首を何人も斬り落としたと自慢するところなどは、人間として醜悪すぎるくらいだ。
一方で、英会話の不得手な<伊佐>は、英会話をできないことが発覚するのを恐れて、日本語さえ喋ろうとしない。
彼はグッド・モーニング、エブリボディと生徒に向って思いきって二、三回は授業の初めに云ったことはあった。血がすーとのぼってその時ほんとに彼は谷底へおちて行くような気がしたのだ。(おれが別のにんげんになってしまう。おれはそれだけはいやだ!)(小島信夫「アメリカン・スクール」)
日本国民の誇りとプライドを一切棄て去った伊佐の姿もまた、敗戦国民の劣等感を端的に表現するものだっただろう。
そして、山田と伊佐の間に挟まれた紅一点の女性教師<ミチ子>もまた、劣等感を抱えた日本人の一人である。
彼女は英会話が得意であるが故に、英語を話すことによって日本国民としての存在意義を失ってしまうのではないかとの恐怖を感じている。
ミチ子は英語で「彼」というと何か伊佐の陰口を云ってもそれほど苦にならないことを知って、伊佐のあれほど英語を話すのを嫌う気持もわかるような気がした。たしかに英語を話す時には何かもう自分ではなくなる。そして外国語で話した喜びと昂奮が支配してしまう。ミチ子は、山田のそばをはなれなくてはと思った。(小島信夫「アメリカン・スクール」)
この三人を中心に、物語は日本人の滑稽な姿を曝け出しながら、ゆっくりと進められてゆく。
英語は、アメリカ人に媚びを売るための道具でしかない
この物語に出てくる「英語」は、国際共通語としての英語ではない。
敗戦国民である日本人が、戦勝国民であるアメリカ人とコミュニケーションを取るために必要な言語のことである。
その日、集められた日本の英語教師30人は、田舎の県庁からアメリカ村にあるアメリカン・スクールまで、6キロメートルの道のりを徒歩で移動する。
彼らが黙々と歩き続ける横を、占領軍のジープが次々と追い抜いていく。
アメリカン・スクールの見学にあたっては、清潔な服装をすることや、弁当を持参することなどの約束事が、事前に言い渡されていた。
日本人の誰もが貧しく、腹を空かせている時代に、アメリカン・スクールを訪問する彼らは、アメリカ村で暮らす人々に見られて恥ずかしくない格好を求められたのである。
言葉は、対等な関係性があってこそ共通語になり得る。
素晴らしいアメリカン・スクールの施設を見て、伊佐は愕然とする。
「何故こんなに恥ずかしいめをしなければならんのでしょう?」「恥ずかしいめって? ハダシになったこと?」「いいや、こんな美しいものを見れば見るほど」(小島信夫「アメリカン・スクール」)
ミチ子が、わざわざハイヒールを持参してきて、運動靴から履き替えるところも、日本人の劣等意識の表れだったのだろう。
そのような環境の中、戦争に負けた日本人にとって、アメリカ人と英語を話すことは、誇りでも自慢でもなかった。
犬が尾を振るのと同じ程度に、英語は、アメリカ人に媚びを売るための道具でしかなかった。
少なくとも、アメリカとの戦争に負けた日本の英語教師にとっては。
戦争っていうのは、始めた以上、決して負けてはいけないものなんだと思った。
作品名:アメリカン・スクール
著者:小島信夫
書名:アメリカン・スクール
発行:2008/1/1 改版
出版社:新潮文庫