車谷長吉「文士の魂」読了。
本書は、1998年から2001年にかけて、雑誌『波』に発表された「意地ッ張り文学誌」を書籍化した文学エッセイである。
テーマに沿って、二~三冊程度の文学作品を紹介
毎回、何らかのテーマに沿って、二~三冊程度の文学作品を紹介している。
例えば、「青春小説」で紹介されているのは、夏目漱石の『三四郎』と森鴎外の『青年』という、いずれも明治の文豪による青春小説である。
「青春とは多くの可能性と期待に満ちた時である。と同時に、お先真ッ暗で、何をどうすればよいのかまったく分からない、闇の中に頭を突っ込んでいる時代でもある」という文章から始まり、そのような青春の時期に、著者は夏目漱石の『三四郎』に出会ったとある。
「三四郎」というこの小説の通奏低音は、この図書館の場面がそうであるように、新鮮な発見の驚きである。三四郎が広田先生に、上京の汽車の中ではじめて出逢った時もそうであるし、東京という都市の動きにはじめて触れた時の驚きもそうである。(略)この新鮮な「驚き」が、この青春小説を生気のあるものにしている。(車谷長吉「文士の魂」)
鷗外の『青年』と比較した後で、著者は「こうして二つの作品を見て来ると、漱石の天才であるのに較べて、鷗外は刻苦勉励の人ではあるけれど、小説家としての才能は凡庸な人だったことがよく分かる」と、締めくくっている。
「伝記小説」では、文学作品の紹介以上に、歌人・持田鋼一郎の言葉が印象に残る。
それは、著者が初めての作品集『鹽壺の匙』の出版記念会でのこと。
曰く、「車谷、これできみも処女小説集を出したわけだが、問題は第二作品集で、第一作品集をいかに超えるかだ。人はともすればマナリスム(自己模倣)に陥りがちだね。俵万智の歌など、その典型だろう。一篇うまく行ったら、そのうまく行った自分の作品を、次ぎの作品で、も一篇なぞるんだ」(車谷長吉「文士の魂」)
この言葉は、過去の自分を乗り越えることの難しさを、一般の読者には<自己模倣>を期待する気持ちもあるから、作家というのは難しいものだと思った。
この後、持田鋼一郎は、「小説家の場合、もう書くことがなくなったら、だいたい苦し紛れに伝記小説に手を出すね。高井有一が立原正秋の伝記を書いたのなど、その一番よい例だ」と持論を展開している。
『立原正秋』(1991)は、ある意味で高井有一の代表作の一つともなっているから、伝記小説を書くことは、特別に悪いこともないんじゃないだろうか。
庄野潤三「さまよい歩く二人」は小説なのか
さて、本書で特筆しておきたいことは、庄野潤三の「さまよい歩く二人」という短篇小説が紹介されていることである。
「さまよい歩く二人」は、1970年の『文藝』に発表された作品で、現在は、講談社文芸文庫の『絵合せ』で読むことができる。
著者は、この小説を「大阪曽根崎新地(北新地)の料理屋「柚香里」の下働きをしている時に、タコ部屋で読んだ」そうである。
物語の語り手である<彼>の二人の子どもたちが、東京上野の美術館へ十七世紀オランダの画家の展覧会を観に行き、その後、動物園へ行って、鳩に餌をやったり、猿山を眺めたりして帰ってくる。
子どもたちから聞いた、そんな話が、一篇の短篇小説としてまとめられているが、この作品の、どこが小説なのか?と疑問に感じる人も少なくないかもしれない。
実は、「新鮮な驚き」というタイトルの、この章は、<小説とは何か?>ということについて考察する内容になっていて、はじめに、石川桂郎の『剃刀日記』を長々と引用した後で、著者は「「小説になる」には、「非日常的な時間」を創り出すことが大事だ」と結論を導いている。
そして、庄野さんの「さまよい歩く二人」は、そうした「小説とは何か?」という流れの中で登場してくる。
この何の変哲もない日常的な光景が、なぜ「小説になる」のかを考えれば、それは上野公園をふらふらしているだけの二人に「さまよい歩く二人」という物々しい題を付け、つまりそういう基本概念(コンセプト)で括ったところに、庄野の才能があるのだった。なるほど、こういう具合にすれば「小説になる」のか、と私は新鮮な驚きを覚えた。(車谷長吉「文士の魂」)
庄野さんの「さまよい歩く二人」は、上野公園をフラフラしている姉弟の話が、グリム童話の「水牛の革の長靴」や「金の毛が三本はえているおに」という作品へと展開していく場面がおもしろい。
現代の日常生活と古い童話との親和性を見出したところにこそ、この作品の味わいがあるのではないだろうか。
書名:文士の魂
著者:車谷長吉
発行:2001/11/20
出版社:新潮社



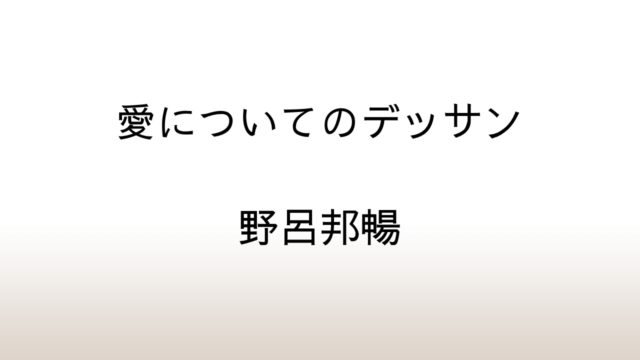


-150x150.jpg)









