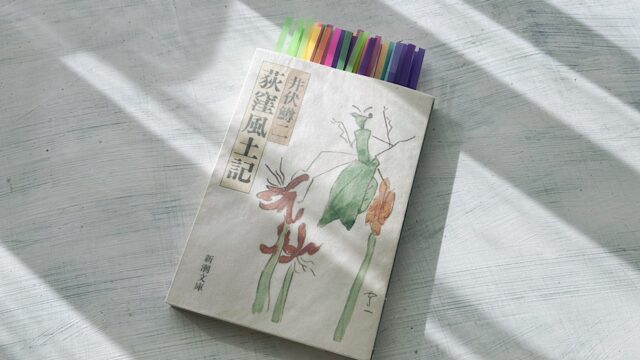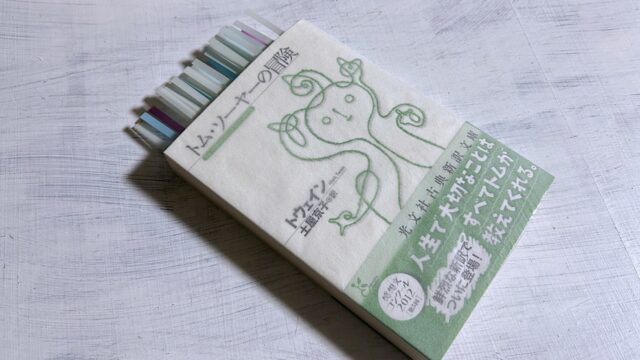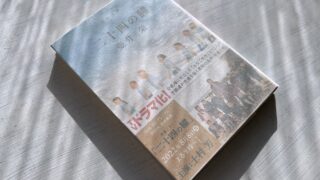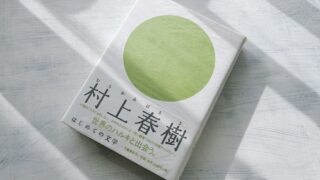今回の青春ベストバイは、秋元治先生の『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の「第8巻」です。
おすすめは、ずばり、初登場のチャーリー小林。
甲斐バンドのパロディだった「チャーリー小林と安全バンド」は、今読んでも笑えます。
チャーリー小林の初登場は「ひな祭りロック」
なんとなくチャーリー小林を読みたくなって、ブックオフで『こち亀』第8巻を購入。
チャーリー小林の初登場は「ひな祭りロック」だったんだよね、確か。
ジャンプコミックスの発売は、1979年(昭和54年)6月だから、僕は小学6年生だったということになる。
しっかり意識して『こち亀』を読むようになったのは、確かこの頃からで、買い揃えたコミックスの背表紙には「山上たつひこ」という作者名が書かれていた(第7巻以降は秋本治に変更された)。
その後、シリーズ化される両さんの誕生日だけれど、誕生日が「3月3日」だったという事実が明かされるのは、実は、この回が初めてだった(寺井さんは5月5日)。
初期レギュラーでヒロイン格だった<たばこ屋の洋子ちゃん>に誘われて、派出所メンバーでひな祭りパーティーに参加しているところ、人気ロックミュージシャン「チャーリー小林と安全バンド」を乗せたトラックが交通事故を起こすという話で、何十年ぶりかで読み返してみても、やっぱり楽しかった。
自分の中のイメージで、チャーリー小林のモデルは、『東大一直線』の小林よしのりと甲斐バンドの甲斐よしひろの2人ということになる。
小林よしのりと甲斐よしひろは同じ福岡出身の幼なじみで、『少年ジャンプ』でギャグ漫画を連載していた小林よしのりと秋本治との交友関係が、秋本先生と甲斐先生のつながりへと発展していったんじゃなかっただろうか(ちなみに、甲斐よしひろを「甲斐先生」と呼んでいたのは中島みゆき)。
だから、チャーリー小林のビジュアルは小林よしのりで、音楽的な要素は甲斐バンドだったんだろうなって、今も僕は考えているわけだ。
例えば、チャーリー小林の新曲『〆切ノイローゼ』は、明らかに甲斐バンドのシングル曲『テレフォン・ノイローゼ』がモデルになっている。
ひな祭りパーティーでは、何気に中川さんが歌っている『ブラッディマリー』も、実は甲斐バンドの曲だから、初期『こち亀』で、甲斐バンドが果たす役割は、すごく大きかったんじゃないだろうか。
そして、僕が甲斐バンドの音楽に触れるようになったのも、実はチャーリー小林がきっかけだったのかもしれないな(冗談みたいな話だけれど)。
「こち亀」は僕らのタイムカプセルだ
もっとも、『こち亀』の場合、音楽面では太田裕美の影響も大きくて、チャーリー小林の『アイデアが風をひいた日』は、太田裕美のアルバム『心が風をひいた日』がモデルになっている。
『時には〆切日がない方がいい』は、カルメン・マキの『時には母のない子のように』のパロディだと思うけれど、『ベタぬり天使』は、甲斐バンドの『そばかすの天使』だったのかな。
それにしても、『〆切ノイローゼ』も『アイデアが風をひいた日』も『時には〆切日がない方がいい』も「ベタぬり天使」も、チャーリー小林の曲名は本当にいい。
当時の『こち亀』は、こういうパロディ的な要素が、すごく楽しかった。
やっぱり、秋本先生のセンスはすごい。
次にチャーリー小林が登場するのは『安全バンド再び!』(ジャンプ・コミックス10巻)。
ロックバンドのコンサートの仕事と聞いた中川さんが「すると、昔、学校の保健委員だった人がいるという甲斐バンドですか?」と発言している。
「ぜひ、八っちゃんとチャーリー小林と一しょに『ポテトチップスをほおばって』をうたってもらいたい!」と言ったのは両さん(『ポップコーンをほおばって』のパロディ)。
コンサート会場に貼ってあるポスターは『マイ・ジェネレーション』のパロディで、両さんが持っているシングルレコード『カンナ』は『安奈』のパロディ。
とにかく、初期の『こち亀』は文字が多くて、細かいところまでびっしりとギャグが書き込まれていた。
ライブ会場でチャーリー小林が乗った飛行機からぶら下がっている垂れ幕は、「安全バンド・サーカス&サーカス」だった。
『サーカス&サーカス』というのは、1978年(昭和53年)に発売された甲斐バンドのライブ・アルバムだから、当時、甲斐バンドファンだった人たちは、きっとかなり楽しかったんじゃないだろうか。
チャーリー小林は、『愛があれば……』にも登場している(ジャンプ・コミックス10巻)。
1日署長にやってきたチャーリー小林が、警察官の制服を着て仕事をするという話で、「音楽に国境はありません。ことばもいらない。歌ですべてが通じあうのです。ビートルズが、私たちに教えてくれました」と、静かに語りかける(『ビートルズが教えてくれた』は吉田拓郎)。
ここでチャーリー小林が歌うのは、ピートー・シーガー(またはジョーン・バエズ)『ウィシャルオーバーカム(勝利を我らに)』と、岡林信康『友よ』。
もっとも、両さんには、まったくどちらも通用しないというところが楽しい(「あの人は歌以前に心がゆがんでいる」)。
パトロール先のレコード店は「チャーリー小林 フェスティバル中」で、『ジャイアント馬場に耳をふさいで』が流れている(『ダニーボーイに耳をふさいで』のパロディ)。
壁に「甲斐バンド 真夏のコンサート」のポスターがあったりするのもいい。
このとき、子どもが万引きしたレコードが、チャーリー小林のソロアルバム『翼ないもの』だった(甲斐よしひろ『翼あるもの』のパロディ)。
時代が変わると、こういう流行り物を採り入れたネタというのは、理解されにくくなってしまうけれど、僕は別にそれでもいいと思う。
長期連載だった『こち亀』という漫画自体、タイムマシンのようなものだし、僕にとっての『こち亀』は、あの頃を懐かしく振り返ることのできるタイムカプセルのようなものだから。
ちなみに、80年代のバンドブーム時代に再登場したチャーリー小林は、もはや甲斐よしひろではなかった。
チャーリー小林って、あくまでも絶頂期の甲斐バンドがあってこそのキャラクターだったんだよなあ。